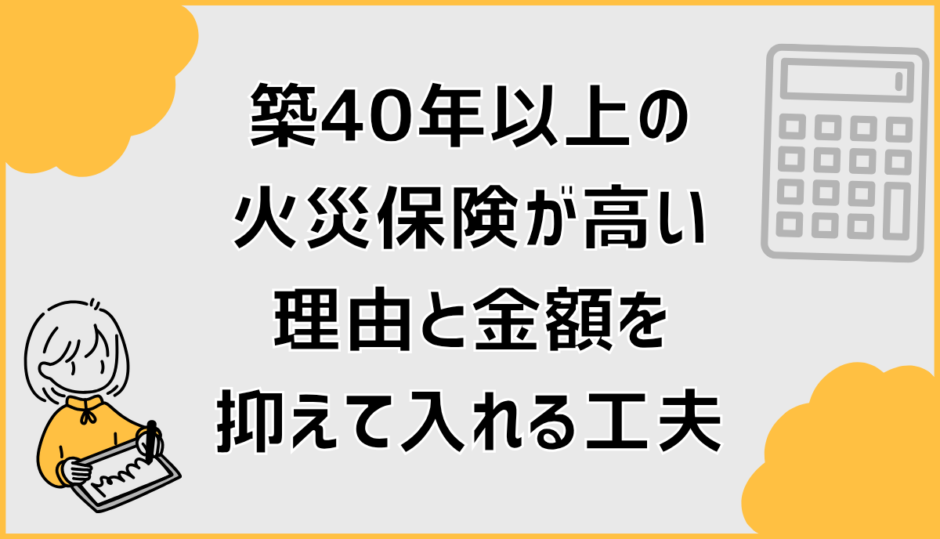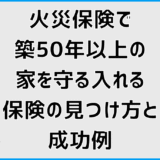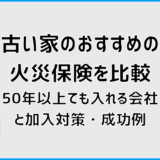この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
築40年以上の火災保険の金額について調べているあなたは、築年数が古い家の火災保険の仕組みや、なぜ保険料が上がりやすいのかという理由、さらに加入できるのかどうかという不安を抱えているのではないでしょうか。
特に、更新のときに急に保険料が上がって驚いたり、見積もりが予想以上に高くて戸惑ったり、場合によっては加入を断られた経験があるという声もよく聞きます。
築40年以上の住宅には、火災保険に関するよくある悩みがいくつもあり、どこから対策を始めれば良いのか迷ってしまうこともあると思います。
ここでは、火災保険の金額の考え方を整理しながら、築古住宅でも入れるのかという疑問への答え、保険料を抑えるためにできる現実的な対策、複数社の比較で見えてくる選択肢、そして判断に迷うときに役立つよくある質問まで順番に解説していきます。
正しい情報を知ることで、不要な不安に振り回されず、納得して選べる状態に近づけることができると思います。築40年以上だからといって諦める必要はありません。
一緒に整理しながら、より安心して備えられる方法を見つけていきましょう。
- 築40年以上の家で火災保険に入れるのかどうかの判断基準
- 火災保険の金額が高くなる理由と背景
- 保険料を抑えるために実践できる対策と見直し方法
- 複数社の比較で失敗を防ぐ考え方とよくある質問への具体的な理解
本記事は、保険会社の公式情報や各種調査データ、利用者の体験談を参考に筆者が独自に編集・構成しています。
口コミは個人差があり、内容の正確性や最新性を保証するものではありません。最終判断は公式情報や専門家への相談を前提としてください。

築40年以上の家を持っていると、「火災保険の金額はいったいいくらになるのか」「年数が古いだけで高くなるのでは」と不安を抱える方が多いようです。
実際、築年数の影響で保険料が上昇しやすくなることはありますが、その理由は単に古いというだけではなく、老朽化や災害リスク、保険会社ごとの評価の違いなど、複数の要素が関係しています。
また、更新時の大幅な値上げや加入断りといった悩みも増えており、どう対応すべきか迷う場面もあるかもしれませんね。
ここでは、築40年以上の火災保険の金額の目安、保険料が高くなりやすい背景、そして実際によくある悩みとその考え方を、分かりやすく整理していきます。正しい情報を知り、落ち着いて対策を進めることが、安心につながる一歩になります。
築40年以上の家の火災保険について、「だいたいどのくらいが普通なのか」が分からないと、不安だけが先に立ってしまいやすいと思います。
実際のところ、築年数が進むほど保険料は上がりやすい傾向がありますが、構造や地域、補償内容の組み合わせで金額は大きく変わります。ここでは、あくまで一般的な目安としてどの程度の金額帯になりやすいかを整理しておきます。
戸建て住宅全体で見ると、建物のみを対象にした火災保険料は、一般的な例として年間5〜9万円程度と紹介されることが多いです。ここに地震保険を付けると、さらに数万円ほど上乗せされるケースがよく見られます。
ただし、これは「木造か鉄骨か」「オール電化かどうか」「水災補償を付けるか」などの条件で大きく変わるため、あくまで参考の幅だと考えてください。
自宅の見積もりがこの幅よりかなり高い場合、過剰な補償や特約が付いていないか、免責が低すぎないかなどを確認すると、調整のヒントを見つけやすくなります。
一方で、相場より極端に安い場合は、いざというときに必要な補償が抜けていないかをチェックした方が安心です。正確な保険料や条件は、必ず各保険会社や代理店の公式資料で確認し、最終的な判断は専門家にも相談するようにしてください。
まず全体の相場と比較ポイントを整理したい方は、こちらの記事でまとめていますので、全体像がつかみやすくなります。参考にしてみてください。
築40年以上の住宅では、同じ保険金額・同じ補償内容でも、新築時と比べて保険料が1.3〜2倍程度に開く例が紹介されることがあります。
例えば「木造・延床100㎡前後・保険金額2000万円・水災補償あり」という条件で見ると、築40年のケースで年間6万円前後となる試算が示されることもあります。もちろん、これはあくまで一例であり、すべての住宅に当てはまるわけではありません。
イメージしやすいように、一般的な目安として紹介されるケースを簡単に整理すると、次のような関係になることが多いです。
| 条件の例 | 年間保険料の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 新築木造・水災あり | 3〜4万円前後 | 条件次第で変動 |
| 築40年木造・水災あり | 5〜7万円前後 | 新築より割高になりやすい |
| 築50年以上木造・水災あり | 6〜9万円前後 | 加入条件が付く場合もある |
これらはあくまでも一般的な紹介例であり、実際の金額は保険会社ごとの料率や割引、地域区分で大きく変わります。
したがって、自宅の適正な金額を把握するうえでは、同じ条件を固定して複数社から見積もりを取り、数字の並びを比較することが欠かせません。
築40年を超えたあたりから、保険会社によっては「築年数区分」が一段階上がり、保険料がじわりと高くなる例があります。
さらに築50年以上になると、割増率がもう一段階上がったり、水災補償を付けられなかったり、長期契約が不可となるなどの制限が増えるケースが見られます。これは建物の老朽化リスクが高まるという判断に基づいていると説明されています。
とはいえ、築50年以上だからといって一律に加入できないわけではありません。状態の良い住宅であれば、補修履歴や写真を提出することで、通常に近い条件で契約できることもあります。
築40年と築50年以上で評価が変わりやすいことを知っておくと、「まだ40年台のうちに見直しを進めておく」「リフォーム後にあらためて相談する」といった対策を取りやすくなります。
年数だけで諦めるのではなく、自宅の状態と希望する補償を整理したうえで、複数社に相談していく姿勢が大切です。
築40年を超えた建物で保険料が上がりやすいのは、「古いから」という一言で片付けられるものではありません。
保険会社は統計データや過去の事故事例をもとに、損害が起こる確率や被害額を評価しています。その結果として、老朽化や耐震性の違い、自然災害リスクの高まりなどが、築古住宅の保険料に反映されていると考えられます。
築40年を過ぎると、給排水管や電気配線、屋根や外壁など、住宅のさまざまな部分で経年劣化が目に見えて現れやすくなります。
配管の腐食や継ぎ目の緩みから水漏れが発生したり、古い配線やコンセントからの漏電が火災につながったりするリスクが高まるとされています。
こうした設備起因の事故は修繕費が大きくなりやすく、保険会社にとっても支払いリスクが重くなるため、築年数が進むほど料率が高めに設定される傾向があります。
一方で、老朽化の状況を自分でも把握し、必要な部分から計画的に補修していくことで、保険会社に対して「管理された建物である」ことを示しやすくなります。
点検記録やリフォーム履歴を残しておくことは、見積もりや審査の場面で有利に働く場合があるため、早めに意識しておくと良いと思います。
日本では1981年に建築基準法の耐震基準が大きく見直され、それ以前に建てられた住宅は「旧耐震基準」の建物とされています。
築40年以上の多くはこの旧基準に該当するため、地震や台風などの自然災害に対する耐性が相対的に低いと評価されるケースが少なくありません。その結果、災害リスクの高い地域では保険料が上乗せされる要因の一つになっています。
とはいえ、旧耐震だからといって必ずしも危険というわけではなく、実際には地盤や構造、補強状況など個別の条件によって耐震性は大きく変わります。
耐震診断を受けて現状を把握し、必要に応じて耐震改修や屋根の軽量化などを行うことで、損害リスクを下げることは十分可能です。診断書や改修報告書を保管しておけば、保険会社への説明材料にもなります。
築40年以上で申し込みをした際、「築年数が古いので難しい」と言われることがありますが、実際には雨漏りが放置されていたり、基礎に大きなひび割れがあったりと、建物の状態そのものが問題になっている場合も多いとされています。
つまり、年数そのものというより、長年の間にどのように維持管理されてきたかが問われているというイメージに近いです。
加入を断られた場合でも、建物診断を受けて状態を確認したり、屋根や外壁の補修を行ったりすることで、あらためて契約できた例も紹介されています。
断られた理由をきちんと確認し、写真や診断書などの資料を準備したうえで別の保険会社や代理店に相談すると、選択肢が広がる可能性があります。
火災保険の評価基準は、保険会社によって少しずつ違います。インターネット完結型の商品では、築25〜30年程度までを自動見積もりの上限とし、それ以上は「問い合わせが必要」「加入不可」としている例が多く見られます。
一方で、代理店経由の商品や共済では、築40年以上でも個別に状況を確認し、柔軟に契約可否を判断してくれるケースがあります。
同じ建物でも、ある会社では「対象外」とされ、別の会社では条件付きで契約できることも珍しくありません。したがって、一社の回答だけで「うちの家はもう入れない」と決めつけてしまうのは早計です。
建物状態が分かる資料を整えたうえで、複数のルートに相談してみることが、築古住宅での火災保険選びの大きなポイントになります。
築40年以上の家を所有している方からは、「急に保険料が高くなった」「更新が難しいと言われた」「実家の契約をどう引き継げばいいか分からない」など、さまざまな悩みが寄せられています。
ここでは、特に相談が多いパターンを整理しながら、どのような考え方や準備をしておくとスムーズかを解説します。
最近は、更新のタイミングで保険料が大きく上がるケースが増えています。背景には、自然災害の増加に伴う料率改定や、築年数区分の見直しがあります。
特に築30年、40年といった節目で区分が変わると、それまでよりも割増率が大きくなることがあります。その結果として、「同じ補償なのに更新後は2倍近い金額になった」と感じる方も少なくありません。
このようなときに、保険料だけを見て大きく補償を削ってしまうと、いざというときに必要な支えが足りなくなる危険があります。
値上げの理由を確認しつつ、補償の優先順位を整理し、他社の見積もりも取って比較することで、無理のないラインを探るやり方が現実的です。
新たに火災保険を申し込んだり、保険会社を切り替えようとしたりしたときに、「築年数や建物状態の理由でお引き受けできません」と言われることがあります。
しかし、1社で断られたからといって、すべての会社で同じ結果になるとは限りません。基準や審査方針はそれぞれ異なり、特に代理店型の商品では現場を確認したうえで判断してくれる場合もあります。
断られた際には、その理由をできるだけ具体的に聞き取ることが大切です。屋根の劣化なのか、雨漏りなのか、基礎のひび割れなのかによって、取るべき対策は変わります。
そのうえで、建物の写真や診断書、補修見積もりなどを準備し、別の保険会社や共済、代理店に相談すると、契約にこぎつけられる場合があります。
加入を断られて不安を感じている方は、こちらの記事で、古い家におすすめの火災保険をまとめていますので、参考にしてみてください。
親世代が高齢になり、実家の管理を子ども世代が担うケースが増えています。火災保険についても、「名義は親のままだけれど、支払いは自分がしている」「相続を見据えて名義を変えた方がいいのか」といった悩みがよく聞かれます。
保険会社によって細かなルールは異なりますが、所有者や居住者との関係が整理されていれば、名義の変更や代理人による契約・支払いが認められる例は多くあります。
こうした手続きを進めるうえでは、誰が家をどう利用しているのか、今後どのように管理していくのかを家族で話し合っておくことが欠かせません。
負担の分担や名義の整理ができていないと、更新のタイミングで慌ただしく決めることになりがちです。早めに話し合い、必要であれば専門家にも相談しておくと安心です。
築40年以上の住宅は、空き家として放置されるケースも増えています。
人が住んでいない家は、火災の発見が遅れやすい、放火や不法侵入のリスクが高まりやすいなどの理由から、居住中の住宅よりも保険料が高くなったり、そもそも引き受け対象外とされることがあります。
また、「別荘扱い」「賃貸用」「物置」といった用途によっても、必要な補償や商品が変わってきます。
空き家について火災保険を検討する場合は、「今後住む予定があるのか」「売却予定なのか」「貸家として活用したいのか」といった方向性を整理することが第一歩になります。
そのうえで、管理状況(定期的な見回りや清掃の有無など)を説明しながら保険会社や代理店に相談すると、現実的な提案を受けやすくなります。場合によっては、空き家管理サービスや活用策とセットで検討することも選択肢に入ってきます。

築40年以上の家でも、火災保険に加入できるケースは多くあります。ただ、申し込みや更新のタイミングで「保険料が想像以上に高くなった」「断られてしまった」という声もよく聞かれます。
年数が古いからといって諦める必要はなく、建物の状態を整えたり、補償内容を工夫したり、複数社を比較することで、現実的な選択肢を見つけやすくなります。
まずは、加入できる可能性と費用を抑えるための具体的な方法を整理し、迷わず進められる準備をしていきましょう。ここでは、加入のポイント、保険料の調整方法、比較の重要性、そしてよくある疑問への回答をまとめていきます。
築40年以上の家を持っていると、「もう火災保険には入れないのでは」と心配になる方もいますが、実際には加入できている例は数多くあります。
ポイントになるのは、築年数そのものよりも、現在の建物状態と、状態を説明できる資料をどこまで用意できるかという点です。ここでは、加入しやすい典型例と、断られたときに見直したいポイントを整理します。
築40年以上でも、屋根や外壁に大きな損傷がなく、雨漏りや傾きといった深刻な不具合が見られない住宅は、火災保険の加入が認められる場合が多くあります。
また、過去に給排水設備の更新や屋根の葺き替え、外壁塗装などを行っていると、保険会社にとってもリスクが把握しやすくなります。
申し込みの際には、建物全体が分かる外観写真や、補修工事の領収書・報告書などを用意しておくと、審査がスムーズに進みやすくなります。複数社に同じ資料を提出し、条件を比べることで、自宅にとって現実的な選択肢を見つけやすくなります。
もし一度申し込みをして断られてしまった場合でも、そこで終わりと考える必要はありません。重要なのは、「なぜ断られたのか」をできるだけ具体的に把握することです。
例えば「屋根の劣化が進んでいる」「雨漏りがある」「基礎のひび割れが大きい」など、理由によって取るべき対策は違います。
原因が分かれば、必要な補修を行ったり、専門家の診断書を取得したりして、あらためて別の保険会社に申し込むことができます。写真や工事報告書を添えて再審査を依頼すると、評価が変わるケースもあります。行動を積み重ねていくことで、加入の可能性は着実に広がっていきます。
築40年以上の住宅では、すでに住宅ローンを完済している場合も多いと思います。ローン返済中は、金融機関の条件として保険金額や補償内容が指定されていることがあり、自由度があまり高くありません。
一方で、完済後は保険金額や補償範囲を自分たちの判断で見直しやすくなります。
例えば、建物の評価額が大きく下がっているのに、昔のまま高額な保険金額で契約していると、保険料だけが過大になっている可能性があります。
再調達価格や時価の考え方を確認しながら、現在の家計やライフプランに合う水準に調整していくことで、無理のない保険料に近づけていくことができます。
具体的なプラン設計の考え方については、こちらの記事でで詳しく解説しています。参考にしてみてください。
築古住宅になると、保険会社の評価は厳しくなりがちです。ただし、その分だけリフォームや耐震補強の有無が大きな意味を持ちます。
例えば、配管を一新している、屋根材を軽量なものに変えている、耐震補強工事を実施しているといった実績があれば、同じ築年数でも評価は大きく変わります。
こうした改善実績は、工事内容を示す書類や写真とセットで保管しておくと、保険の申し込み時に強い説得材料になります。
築年数が進んでいるほど、計画的なリフォームと火災保険の見直しを組み合わせて考えることが、選択肢を増やすポイントになります。
リフォームによって審査を突破したい方は、こちらの記事にまとめていますので、参考にしてみてください。
築40年以上の住宅では、どうしても保険料が高めに出やすくなりますが、だからといって「高いから仕方ない」と受け入れる必要はありません。
大事なのは、守りたいポイントの優先順位を整理し、そこから外れる部分を丁寧に削っていくことです。この過程を踏むことで、補償を大きく落とさずに負担を抑えられる場合があります。
まず考えておきたいのは、「この家で何を守りたいのか」という点です。持ち家として長く住み続けたいのか、将来的に売却や賃貸も視野に入れているのかによって、必要な補償は変わってきます。
建物の再建費用をきちんと確保したいのか、ある程度の修繕費が出れば良いのかといった考え方も整理しておくと、契約内容を決めやすくなります。
感情的に「すべて心配だから全部付けておきたい」と考えると、保険料はどうしても膨らみます。家族の暮らし方や貯蓄状況も踏まえながら、必要な補償とそうでない補償を分けていくことが、節約の第一歩になります。
火災保険には、破損・汚損、類焼損害、個人賠償責任など、さまざまな特約が用意されています。これらは暮らしに合っていれば心強いものですが、すべてを付ける必要があるとは限りません。
例えば、家具や家電が少ない家で高額な家財補償を付けている場合、実態以上の保険金額になっているかもしれません。
一つひとつの特約について、「この家の状況で本当に必要か」「別の保険でカバーされていないか」を確認し、外しても支障がないと判断できる部分から見直していくと、保険料が下がる余地が見えてきます。
ただし、外すかどうか迷う補償については、安易に削らず、専門家にも相談しながら判断することをおすすめします。
保険料を抑えるためのもう一つの方法が、免責金額や契約期間の調整です。免責金額とは、「この金額までは自己負担にする」というラインで、この金額を高めに設定すると保険料が下がる商品が多く見られます。
例えば、10万円まで自己負担と決めておけば、小さな修繕は自費で賄い、大きな被害のときだけ保険を使うという考え方になります。
また、商品によっては長期契約や一括払いによって、トータルの保険料が割り引かれる場合があります。
ただし、築古住宅では長期契約が選べないこともあるため、利用できるかどうかは事前に確認が必要です。正確な条件は必ず各社の公式資料で確かめ、分からない点は担当者に質問しながら検討してください。
火災保険の見直しでは、損害保険会社の保険だけでなく、共済や地震保険との組み合わせも検討の余地があります。共済は、運営主体や地域によって仕組みが異なりますが、築年数に対して比較的柔軟に対応していると紹介されることもあります。
一方で、補償範囲や自己負担額の考え方が保険会社の商品とは違うため、内容を丁寧に比較することが欠かせません。
地震保険についても、付ける・付けないの二択ではなく、建物と家財のどちらにどの程度付けるかといった調整の余地があります。
損保・共済・地震保険を含めて全体像を整理し、自宅に合ったバランスを探っていくことが、安心と負担の両立につながります。
迷ったときは、加入可否の判断ポイントや事例を詳しく整理していますので、こちらの記事を参考にしてみてください。
築40年以上の住宅では、火災保険の評価が保険会社ごとにばらつきやすくなります。
そのため、「たまたま最初に相談した会社の条件だけで決めてしまう」と、本来より高い保険料を払い続けることになったり、別の会社なら付けられた補償を諦めたりする可能性があります。ここでは、なぜ比較が欠かせないのかを整理しておきます。
築年数に対する考え方は、保険会社ごとに少しずつ異なります。
ある会社では「築40年以上は原則として新規引き受け不可」としている一方で、別の会社では「建物状態に問題がなければ個別に判断する」としていることがあります。
つまり、築年数に対する線引きが違うため、1社で難しいと言われても、他社では受け入れられる可能性があります。
比較をせずに最初の回答だけで諦めてしまうと、本来利用できたはずの選択肢を見逃してしまいます。複数社から話を聞くこと自体が、一種のリスク回避策だと考えるとイメージしやすいかもしれません。
築50年以上で加入が難しいことについて、入れる保険の見つけ方と成功例をまとめていますので、参考にしてみてください。
火災保険の保険料は、「建物の構造」「所在地」「保険金額」「補償内容」などの条件を同じにしても、会社ごとに結果が変わることがあります。
築40年以上の住宅では、特に割増率の設定や水災補償の扱いに違いが出やすく、年間で数万円の差になることもあります。
見積もりを比較するときは、各社バラバラの条件で試算するのではなく、「建物2000万円」「火災・風災・水災あり」といった具合に条件をそろえたうえで数字を並べると、純粋な金額差を把握しやすくなります。
そのうえで、補償内容やサービス面まで含めて総合的に判断することが大切です。
火災保険には、大まかに分けて「ネット型」「代理店型」「共済」といった形があります。
ネット型は手続きが簡単で保険料も抑えやすい一方、築年数に制限を設けている商品が多く、築40年以上では自動見積もりの対象外となることがよくあります。
代理店型は、担当者が建物状態を確認したうえで提案してくれるため、築古住宅でも柔軟な対応を期待しやすい面があります。
共済は、地域や職域ごとに運営主体が異なり、料金体系や補償内容もそれぞれ特色があります。
築年数に対して比較的広く受け入れている例も紹介されていますが、一方で加入資格や地域の条件があるため、内容を細かく確認する必要があります。自宅の状態や希望する補償に合わせて、これらの選択肢をバランスよく比較してみてください。
比較を進める際は、まず自宅の基本情報(所在地、構造、延床面積、築年数)と、希望する補償内容(火災・風災・水災・家財の有無など)を整理するところから始めます。
そのうえで、同じ条件を複数社に伝え、見積もりを出してもらうと、結果を横並びで比較しやすくなります。
比較の途中で分からない用語や違いが出てきた場合は、そのまま進めずに必ず説明を受けてください。
費用や補償の情報は人生や財産に関わるため、あいまいな理解のまま決めてしまうのは避けたいところです。正確な情報は各社の公式サイトやパンフレットで確認し、最終的な判断は専門家にも意見を聞きながら進めることをおすすめします。
実際に比較を進めたい方は、こちらの記事で火災保険の一括見積もりのメリット・デメリットをまとめていますので、参考にしてみてください。
最後に、築40年以上の住宅に関する火災保険の相談で、特によく寄せられる質問をまとめておきます。ここで概要を押さえておくと、どの章を読み返せばよいかが分かりやすくなるはずです。
築40年以上という理由だけで、一律に加入できなくなるわけではありません。多くの場合、雨漏りや傾きなど建物状態の問題や、メンテナンス不足が引き受けの可否に影響していると考えられます。
加入を目指す場合は、建物の状態を整理し、写真や診断書、補修計画などを用意したうえで複数社に相談することが大切です。
リフォームや耐震補強を行った場合、その内容が分かる書類や写真を保険会社に提示すると、評価が変わる可能性があります。
特に、耐震性や防水性能、配管の更新などは、損害リスクの低下につながる要素として扱われることがあります。工事内容を記録しておき、申し込みの際にきちんと説明することが、より良い条件につながる一歩になります。
住宅ローン完済後は、保険金額や補償内容を自由に見直しやすくなるタイミングです。ローン中は金融機関の条件に合わせていた場合でも、完済後は家計やライフプランに沿った設計に調整できます。
補償を減らすかどうかは慎重に判断する必要がありますが、無理のない範囲に整える良い機会といえます。
実家の火災保険を子どもが契約者として引き継ぐことは、多くの保険会社で可能とされています。所有者や居住者との関係が適切に整理されていれば、名義変更や代理人による契約手続きを進められるケースが一般的です。
具体的な条件や必要書類は会社ごとに異なるため、事前に窓口で確認し、家族で方針を話し合ったうえで進めるとスムーズです。
火災保険や住宅の情報は、統計や制度の改定によって変化していく側面があります。
最新の数値や制度については、総務省統計局の住宅・土地統計調査などの公的データ(出典:総務省統計局「住宅・土地統計調査」 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.html)や、各保険会社の公式サイトで確認し、最終的な判断は専門家と相談しながら進めるようにしてください。
どうでしたか?ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます。
築40年以上の家を持っていると、火災保険の金額がどれくらいになるのか、入れるのか、更新で急に高くならないかなど、不安や迷いを抱える方が多いと感じています。
ですが、年数が古いからといって諦める必要はありません。状態の確認や補修、補償内容の整理、そして複数社の比較によって、納得できる選択肢に近づくことは十分可能です。
今回の記事では、築40年以上の家で火災保険の金額が高くなりやすい理由や、よくある悩みへの考え方、現実的に進める対策を整理しました。ポイントをまとめると、次のようになります。
- 築年数だけで加入できないわけではなく、建物状態の説明が鍵になる
- 保険料は補償内容や免責、特約の調整で抑えられる可能性がある
- 比較することで金額差や条件の違いが明確になる
- 不安な点は資料を整え、専門家や代理店へ相談して検討する
焦らず、一つずつ確認していくことで、必要な補償と家計のバランスを守る道が見えてきます。
最後に紹介させてください。
もっと具体的に知りたい場合や、次に何をすればいいか迷ったときは、以下の記事が参考になると思います。目的に合った内容から読んでみてください。
プランの違いが知りたい方へ
続けるか考え方を知りたい方へ
住宅ローン完済後の火災保険は続ける?見直し判断と手続き完全ガイド
加入例や入れる保険を参考にしたい方へ
火災保険で築50年以上の家を守る入れる保険の見つけ方と成功例
通るための改善点などを知りたい方へ
あなたの家にとって最適な選択となりますように。そして、この記事がその一歩になればうれしく思います。