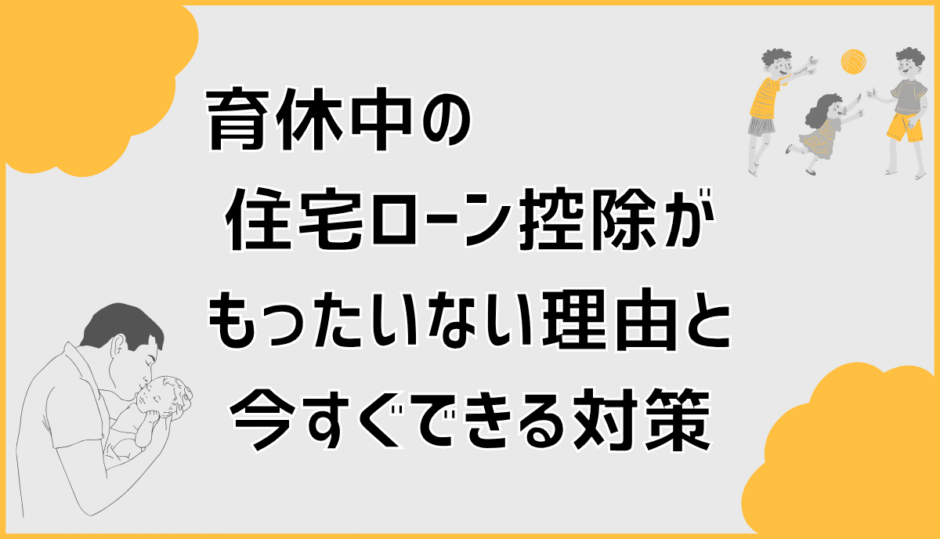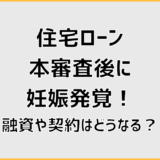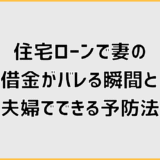この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
育休に入ってから、ふと住宅ローン控除のことが気になったことはありませんか。毎月の返済は続くのに、収入は減り、控除が十分に受けられずもったいないと感じる人が少なくありません。
特に住宅ローン控除と育休が重なるともったいないと感じる最大の理由は、育休中に所得税が減ることで控除の一部が消えてしまう仕組みにあります。
さらに、育休中の書類提出のタイミングを誤ったり、公務員で育休中に勤務先が年末調整してくれないケースなど、知らないうちに控除を逃してしまう人もいます。
ペアローンを利用している育休中の家庭では、夫婦どちらの名義で控除を受けるかによって節税効果が大きく変わります。
加えて、育休中の住宅ローン控除2年目には、確定申告で育休中に収入がない場合でも手続きが必要になることがあり、見落としやすいポイントです。
また、育休中の住民税の支払い方法や軽減策を事前に理解しておくことも欠かせません。
ここでは、住宅ローン控除と育休でもったいない状況を防ぎ、育休明けにも安心して控除を活かすための実践的な対策をわかりやすく解説します。
家計がきついと感じる時期こそ、制度を正しく理解し、無理のない形で賢く乗り切っていきましょう。
- 育休中に住宅ローン控除を使い切れず、もったいない状況になる理由とその仕組み
- 育休中や育休明けに必要な確定申告・年末調整などの手続きの流れ
- 公務員やペアローン利用時など、立場や状況別に注意すべき住宅ローン控除のポイント
- 育休中の住民税の支払い方法や、家計がきつい時の負担軽減策

育休と住宅ローン控除が重なると、思わぬ「損」をしてしまうことがあります。育休中は給与が支給されず、所得税が少なくなることで控除を十分に受けられない場合があるためです。
制度の仕組みを知らないまま過ごすと、本来受け取れるはずの還付金が戻らずに終わるケースも少なくありません。
ここでは、育休中に起こりがちな控除の「もったいない」状況を防ぐために、控除が減る理由や確定申告の基本、公務員やペアローン利用時の注意点、そして住民税や申告の実務までをわかりやすく解説します。
住宅ローン控除は、マイホームを購入した人が毎年の所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。年末時点のローン残高に控除率を掛け、その金額を税金から差し引く仕組みになっています。
2022年以降の制度改正により控除率は0.7%に引き下げられましたが、対象期間は最長13年(新築住宅)とされ、環境性能の高い住宅ほど長く恩恵を受けられるようになっています(出典:国税庁「住宅借入金等特別控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm)。
しかし、育休中は給与の支給がなくなったり、手当が非課税扱いとなるため、所得税額そのものが大きく減少します。住宅ローン控除は、あくまで支払う税金(所得税)を上限として差し引かれる制度です。
そのため、収入が減って税額が小さくなると、計算上の控除額を使い切れないことが起こります。
控除を使い切れない部分は自動的に住民税側へ振り替えられますが、住民税の控除には上限があるため、それを超えた分は消えてしまいます。
これが「育休中に住宅ローン控除を使い切れず、損をしてしまう」状態です。
住民税の控除上限は、原則として課税総所得金額の5%かつ上限97,500円(一定の条件下では7%・上限136,500円)に制限されています。
つまり、所得税で控除しきれなかった分を住民税で補うにも限度があるということです。未控除分は翌年以降へ繰り越せないため、結果的に控除の一部が無駄になってしまうケースが多く見られます。
育児休業給付金は雇用保険から支給されるものであり、非課税所得として扱われます。
課税対象にならないという点は一見ありがたいように見えますが、実際には所得税の控除を受ける上で「課税所得の減少=控除を受けられる余地が少なくなる」ことにつながります。
この仕組みを理解していないと、育休を取った年に予想外に控除が減る結果となり、損をしたように感じる人も少なくありません(出典:厚生労働省「育児休業等給付」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html)。
たとえば、年末残高が4,500万円の住宅ローンを抱えている場合、控除率0.7%を掛けた控除額は315,000円になります。
ところが、その年の所得税が120,000円しかなければ、控除はその金額までしか適用されません。
残りの195,000円は住民税から引ける可能性がありますが、上限が97,500円であれば、最終的に97,500円分は差し引けず消滅します。
育休中は収入が減るため、このような「取りこぼし」が起こりやすいのです。
| 区分 | 控除の対象となる税金 | 上限の考え方 | 翌年への繰越 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | その年の所得税額 | 各年の限度額の範囲で税額まで | 不可 |
| 住民税 (所得税で控除しきれなかった分) | 翌年度の個人住民税(所得割) | 課税総所得金額の5%(上限97,500円)または7%(上限136,500円) | 不可 |
育休に入る時期が住宅ローン控除の初年度や中盤に重なると、この影響が特に大きくなります。
家計にゆとりがあるうちに控除額を最大限活用するためには、夫婦での控除の分担や、育休を取るタイミングの調整を検討することも効果的です。
育休中は勤務先から給与が支給されないため、年末調整の対象外になるケースがほとんどです。その場合、住宅ローン控除の申請は自分で確定申告を行う必要があります。
育休と住宅ローン控除のタイミングが重なる場合、この確定申告の手続きを正しく理解しておくことが大切です。
提出時期は翌年の1月1日から5年間までとされており、早めに申告を済ませるほど還付金の振り込みも早くなります。
申請の際は、住宅ローンの年末残高証明書、登記事項証明書、売買契約書(または請負契約書)の写し、そして確定申告書Bや住宅借入金等特別控除明細書などの提出が必要です。
特に初年度の申告は、提出書類が多いため、年明け早々の準備がスムーズな手続きにつながります。
2年目以降は通常、勤務先で年末調整によって自動的に控除が適用されますが、育休中で給与の支給がない場合は、引き続き確定申告での対応が必要になります。
この手続きの有無を見落とすと、控除が適用されず、返ってくるはずの税金が戻らないままになるため注意が必要です。
育休を取得する時期が年度末に近い場合は、年内に給与が出ないため、確定申告でしか控除を受けられないケースもあります。
確定申告のタイミングを逃さないよう、カレンダーやメモアプリなどでスケジュール管理をしておくことが賢明です。
育児休業給付金は非課税であるため、税金の計算には反映されません。たとえ毎月給付金が入っていても、所得税や住民税の控除額を左右することはないのです。
そのため、育休中は所得が少なく、結果として控除を使い切れないケースが多発しています。これを防ぐには、住宅ローン控除の適用時期を確認し、可能であれば夫婦のどちらが控除を受けるかを見直すのも一つの方法です。
夫婦共有名義の場合は、所得のある方に控除を集中させることで、無駄を減らすことができます。
公務員が育児休業を取得する場合、育休中は原則として給与の支給が停止されます。
月の途中で育休に入る場合は、出勤日数に応じて日割りで支給されることもありますが、ほとんどのケースでは年末に給与支給がなく、年末調整の対象外になります。
そのため、公務員の育休中は確定申告で住宅ローン控除を受けるのが基本的な流れとなります(出典:人事院「育児休業 常勤職員向けQ&A」https://www.jinji.go.jp/seisaku/kinmu/ryouritu/ikuzikyugyou_joukin_qa.html)。
民間企業と異なるのは、給与体系やボーナス支給が厳格なルールに基づいており、勤務実績がない場合は自動的に支給が止まる点です。
特に、期末・勤勉手当は基準日に在職していないと支給対象にならないため、所得税の課税額が極端に少なくなります。この影響で、住宅ローン控除の一部が適用されないことも珍しくありません。
一方で、公務員の育休中にも雇用保険の育児休業給付金が支給されますが、これは非課税収入であるため、控除に影響を与えません。
その結果、育休中に住宅ローン控除を受ける場合は、所得税が発生しない可能性を見越して手続きを進める必要があります。収入が減ることで控除を十分に活かせないリスクがあるからこそ、事前の準備が大切になります。
育児休業を取得する年度に入居し、住宅ローンを利用した公務員は、初年度に確定申告を行って控除を申請します。
翌年以降、給与支給が再開した年は勤務先で年末調整により控除を受けることができますが、再度育休に入って給与がない場合には、再び確定申告を行う必要があります。
確定申告の手続きでは、住宅ローン残高証明書、登記事項証明書、売買契約書などを準備し、申告書に添付して提出します。
特に年度の切り替わり前後に育休が重なる場合は、提出期限に余裕を持つことがポイントです。
育休中は仕事も家事も育児も忙しく、つい税金の手続きを後回しにしてしまいがちです。
しかし、住宅ローン控除は10年〜13年にわたり続く長期的な制度であり、1年分の取りこぼしが積み重なると大きな差になります。確定申告を行えば、育休中であっても適用のチャンスをしっかり活かせます。
ゆとりのあるスケジュール管理を意識し、家族で協力して手続きを進めることが、将来的な節税効果を最大化する鍵になります。
育休を取得する時期と住宅ローン控除の関係は、見落とすと大きな損失につながる重要なポイントです。
育休によって課税所得が減ると、控除の「受け皿」となる所得税額が小さくなり、控除しきれない部分が出てしまうことがあります。
そのため、ペアローンを組む際には、どちらの名義でどの程度借入を行うかを慎重に設計することが欠かせません。
ペアローンは、夫婦それぞれが独立したローン契約を結び、互いが連帯保証人となる仕組みです。この構造により、住宅ローン控除も各自が個別に受けることになります。
しかし、育休期間中は収入が減少するため、育休を取る側に控除枠を多く持たせても、控除しきれず「使い残し」が出やすいのが現実です。
反対に、課税所得が安定している側へ借入を多く配分すれば、同じ世帯全体でも控除を最大限活用できます。
また、建物の持分割合は、資金の実際の負担割合と一致させることが原則です。
もし片方の持分が実際の負担よりも大きいと、贈与とみなされるリスクが生じます。名義、返済、資金の出し方が自然に整合していることが、税務上の安全性を保つ基本です。
住宅ローン控除の額は、年末残高に控除率を掛けて算出されます。ただし、その年に納める所得税の範囲内でしか差し引けません。
たとえば、育休に入った妻が控除額を持っていても、所得税がほとんどない場合は控除を生かしきれません。
その一方で、夫が安定的に課税所得を維持しているなら、その分を多く借入に充てるほうが、控除を余さず活かせるのです。
| 配分パターン | 控除の活かしやすさ | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| 夫100対妻0 | 最も効率的。未控除リスクが少ない | 妻が将来高所得化した際のバランス再考が必要 |
| 夫75対妻25 | バランス型。夫中心で控除活用しつつ妻にも恩恵 | 妻の復職時期が遅れると控除ロスが出る可能性 |
| 夫50対妻50 | 対等型。共働き安定時は有効 | 育休期間中に妻の控除が使い切れず非効率になりがち |
育休と住宅ローン控除の関係を意識するなら、借入の比率だけでなく、復職時期や課税見通しを事前に確認しておくことがポイントです。
控除額は翌年以降に繰り越せないため、年度ごとに確実に使い切れるよう、あらかじめ設計しておくことが重要です。
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、たとえ今年が育休であっても、前年に給与所得があれば翌年に住民税の支払いが発生します。
この仕組みを理解していないと、育休中に突然届く納付書に戸惑うことが少なくありません。
育休期間中は給与が支給されないため、通常の給与天引き(特別徴収)ができず、市区町村から送付される納付書をもとに自分で支払う「普通徴収」に切り替わります。
多くの自治体では、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付する仕組みを採用しています。支払いのタイミングを把握しておくことで、急な出費に慌てず、育児と家計の両立がしやすくなります。
住民税の金額や免除の可否は自治体によって異なりますが、育休中の所得減少が著しい場合は、納付猶予や減免申請を検討できます。
これらは自動的に適用されるものではなく、申請書と証明書類を提出して審査を受ける必要があります。納期限の直前ではなく、余裕を持って役所に相談することが大切です。
| 項目 | 基本の仕組み | 実務でのポイント |
|---|---|---|
| 課税対象 | 前年の所得を基準に翌年課税 | 当年育休でも前年に所得があれば課税される |
| 納付方法 | 特別徴収または普通徴収 | 給与が止まると普通徴収に切り替えられる |
| 納付スケジュール | 年4回の分割払い | 納付日を家計カレンダーに記録して管理 |
| 負担軽減制度 | 猶予・分割・減免制度 | 事前申請が必要。審査期間も考慮して行動 |
育児休業給付金は非課税所得とされており、住民税を押し上げることはありません。そのため、育休期間中の住民税額は、ほぼ前年の収入状況に左右されます。
復職後の課税再開も、前年の所得が基準となるため、カレンダーに合わせて資金準備を計画しておくと安心です。
住宅ローン控除は、制度上、初年度に必ず確定申告で手続きを行う必要があります。
会社員でも例外ではなく、確定申告を経て控除を開始し、翌年以降は勤務先による年末調整で引き継がれるのが一般的です。
しかし、育休中で給与が支給されない年は、年末調整の対象外となるため、2年目以降であっても自分で確定申告をする必要があります。
確定申告の準備には、金融機関から送付される年末残高証明書、登記事項証明書、売買契約書または請負契約書の写しなどの書類が必要です。
これらを事前に揃えておくことで、スムーズに申告書を作成できます。申告書はe-Taxを使えば自宅で完結でき、育児中でも手続きの負担を軽くできます。
確定申告の受付は、還付申告であれば翌年1月1日から5年間有効です。育児や家事で忙しくても、期限内であれば焦らずに進められます。
確定申告を行っておくことで、たとえその年に所得税の納税がなかったとしても、住宅ローン控除の適用履歴が登録され、翌年以降の年末調整で自動的に引き継がれます。
これにより、控除漏れを防ぎ、長期的な減税効果を確実に得ることができます。
住宅ローン控除制度の詳細や必要書類、提出先などは、国税庁の案内ページに詳しく掲載されています(出典:国税庁 住宅借入金等特別控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm)。

育休中は収入が一時的に減るため、住宅ローンの返済や税金の控除手続きに不安を感じる方も多いものです。
特に年末調整が行われない場合や、控除の2年目以降に育休が重なる場合には、思わぬ控除漏れが起こることもあります。また、収入減によってローン返済が負担に感じるケースも少なくありません。
ここでは、育休中に年末調整がされないときの対応から、控除手続きの注意点、返済負担を軽くするための方法、さらに育休明けに控除を最大限に活かすための実践策までを、わかりやすく解説します。
育休に入ると給与の支払いがなくなるため、勤務先で年末調整が行われないことがあります。
この場合は自分で確定申告を行うことで、住宅ローン控除を適用する流れになります。慌てず一つひとつ進めれば難しい手続きではありません。
まず押さえておきたいのは、住宅ローン控除の適用は「年末時点で住宅ローンの残高があり、居住していること」が条件になるという点です。
年末調整がない年は、自分で確定申告をして控除を申請します。初年度はもちろん、2年目以降でも育休中に給与がない場合は同様に確定申告が必要です。
申告は税務署の窓口に直接提出するほか、郵送やオンライン申請(e-Tax)でも可能です。
特にe-Taxは自宅で手続きが完結できるため、小さな子どもの育児中でも負担が少なく済みます。準備する書類を整理しておくと、スムーズに進められます。
必要な書類は次のようなものです。住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送付されるもの)、登記事項証明書、売買契約書または請負契約書の写し、本人確認書類、源泉徴収票(該当する場合)などです。
これらの書類を揃えた上で、住宅借入金等特別控除の計算明細書と確定申告書を作成します。還付申告は翌年の1月1日から5年間提出できるため、育児が落ち着いた時期に余裕をもって進めることもできます。
次の表は、年末調整がない年に確定申告で住宅ローン控除を行う際の流れを整理したものです。
| ステージ | 対応内容 | 注意点・つまずきやすいポイント |
|---|---|---|
| 書類準備 | 年末残高証明書・登記事項証明書・契約書の写しを用意 | 証明書の発行時期が遅れる場合があるため、早めの確認が安心 |
| 申告書作成 | 計算明細書と確定申告書を記入(e-Tax利用も可) | 入居日や住所の記載漏れに注意。システムの案内を見ながら落ち着いて進める |
| 提出 | e-Tax送信、または窓口・郵送で提出 | 添付書類の入れ忘れや控えの保管忘れが起こりやすいので注意 |
| 還付確認 | 指定口座への入金と住民税の控除反映を確認 | 入金口座の誤りに注意。住民税の通知で反映状況をチェック |
住宅ローン控除に関する正式な案内は、国税庁の公式サイトにわかりやすく掲載されています(出典:国税庁 住宅借入金等特別控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm)。
住宅ローン控除の2年目以降は、通常は勤務先の年末調整で控除を受ける流れになります。しかし、育休中で年内に給与がない場合は年末調整の対象外となるため、自分で確定申告を行う必要があります。
この切り替えの判断を誤ると控除を逃してしまうことがあるため、早めの確認が大切です。
給与が発生する年は勤務先で年末調整を行い、住宅借入金等特別控除証明書と金融機関から届く年末残高証明書を提出します。
一方で給与がない年は、確定申告書に住宅借入金等特別控除の計算明細書と残高証明書を添付して申告します。どちらの場合も、入居を継続しており、借入条件を満たしていることが前提になります。
また、所得税で控除しきれない場合は、翌年度の住民税から一部が差し引かれる制度があります。これを適用するためには、必ずその年の所得税申告が完了していることが条件です。
確定申告を忘れると、住民税での控除も受けられず、減税の機会を失う可能性があるため注意が必要です。
次の表は、2年目以降の典型的な手続きパターンをまとめたものです。
| 状況 | 手続き先 | 主な提出書類 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 年内に 給与あり | 勤務先 (年末調整) | 年末調整用住宅借入金等特別控除証明書・年末残高証明書 | 締切が早い場合が多いため、提出期限を必ず確認する |
| 年内に 給与なし | 税務署 (確定申告) | 計算明細書・年末残高証明書・契約書写しなど | 還付申告は翌年1月1日から5年間可能。育休中でも後から対応できる |
このように、2年目以降は「給与があるか・ないか」によって手続きの窓口が変わります。年ごとにどちらの方法を取るかを見極め、早めに準備しておくことで控除の取りこぼしを防げます。
育休中は収入が減少する一方で、住宅ローンの支払いは継続するため、家計に負担を感じやすくなります。このようなときは無理をせず、冷静に現状を整理して対応策を考えることが大切です。
まず検討したいのは、金融機関への早めの相談です。多くの金融機関では、一時的な返済見直し制度が整備されており、育休や出産などライフイベントに伴う収入減に柔軟に対応してもらえることがあります。
担当者に状況を正直に説明し、利用できる選択肢を聞いてみましょう。
代表的な見直し策としては、返済期間の延長、一定期間の元金据え置き、ボーナス返済の停止や減額、金利タイプの変更などがあります。
返済総額が増えるケースもありますが、短期的な家計の安定を優先することも現実的な判断です。状況に応じて、将来の返済計画を再構築していく姿勢が求められます。
また、支出の見直しも大きな助けになります。育休中は通勤費や外食費が減る一方で、生活費や育児用品の支出が増えやすくなります。
家計簿アプリなどを活用して現金収支を可視化し、固定費を一時的に下げる工夫をしてみましょう。保険料や通信費、サブスクリプションなどを一時的に削減するだけでも効果があります。
返済が難しくなりそうな兆しが見えた時点で、早めに相談や手続きを始めることが最も大切です。延滞が発生してしまうと選択肢が限られるため、早期の行動が家計を守る鍵になります。
家計再建の専門家やファイナンシャルプランナーに相談するのも有効です。安心して育休期間を過ごすためにも、無理のない返済プランを立て、必要なサポートを早めに受ける姿勢を持ちましょう。
育休が明けて給与が再開すると、住宅ローン控除の年末調整が再び可能になります。復職直後は仕事や育児で忙しくなるため、控除に関する手続きは早めの準備が欠かせません。
住宅借入金等特別控除証明書や金融機関からの年末残高証明書は、勤務先の提出期限を事前に確認し、余裕を持って用意しておきましょう。
控除の再適用をスムーズに行うためには、復職時期と給与支給のタイミングにも注意が必要です。
年末までに給与が支払われる場合は勤務先で年末調整が可能ですが、支払いが翌年以降になる場合は確定申告を行う必要があります。
自分の給与スケジュールを把握しておくと、手続きを迷わず進められます。
また、住宅ローン控除は10年以上続く長期の制度であるため、毎年の残高や所得税額を確認し、控除額を把握しておくことが安心につながります。
夫婦でペアローンを組んでいる場合は、それぞれの所得に応じた控除額を比較しておくと、家計全体で控除効果を最大化できます。
次の表は、復職後の控除計画を立てる際の目安を示しています。
| 年度 | 年末残高の目安 | 控除率 | 想定所得税額 | 控除見込み | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 4,300万円 | 0.7% | 約18万円 | 住民税での調整あり | 復職初年度は要確認 |
| 来年 | 4,100万円 | 0.7% | 約22万円 | 当年で吸収可能 | 収入増により控除拡大見込み |
| 再来年 | 3,900万円 | 0.7% | 約24万円 | 余剰なし | 安定期に入る年 |
| 4年後 | 3,700万円 | 0.7% | 約25万円 | 控除完了見込み | 家計の安定期 |
住宅ローン控除は短期で完結する制度ではありません。焦らず、確実に申告と提出を積み重ねていくことが、結果的に最も効果的な節税になります。
復職の時期に合わせて控除の流れを整理し、年ごとの確認を怠らないようにしておくことが、将来的な安心につながります。
育休中と住宅ローン控除の関係は、一見複雑に感じられますが、制度の仕組みを理解し、早めに準備をすることで、無駄を減らし家計の安心を守ることができます。
育休によって収入が減ると、控除を最大限に活かせず損をしてしまうケースがありますが、対策を取ることで十分に回避可能です。ここで、記事の要点を整理しておきましょう。
育休と住宅ローン控除を活かすための4つのポイント
- 確定申告のタイミングを逃さないこと
育休中は年末調整がされないケースが多いため、自分で確定申告を行う必要があります。初年度だけでなく、2年目以降でも給与がない年は忘れずに手続きを行いましょう。 - ペアローンの控除配分を最適化すること
夫婦でペアローンを組む場合、育休を取る側に控除枠を多く持たせると控除を活かしきれないことがあります。安定した収入のある側に配分を調整することで、控除効果を最大化できます。 - 育休中の住民税を理解しておくこと
育休期間中も前年の所得に基づいて住民税の支払いが発生します。普通徴収に切り替わることが多いため、納付スケジュールを把握して計画的に対応しましょう。 - 育休明けに控除を再適用する準備をすること
復職後は年末調整が再開されます。提出書類の準備やスケジュールを確認し、控除の再適用をスムーズに行うことが大切です。
住宅ローン控除は長期にわたって家計を支える制度です。
育休というライフイベントの時期こそ、焦らず制度の仕組みを正しく理解し、確実に手続きを進めることが大きな節税効果につながります。
家族の未来を見据え、無理のない家計運営を続けながら、賢く住宅ローン控除を活かしていきましょう。