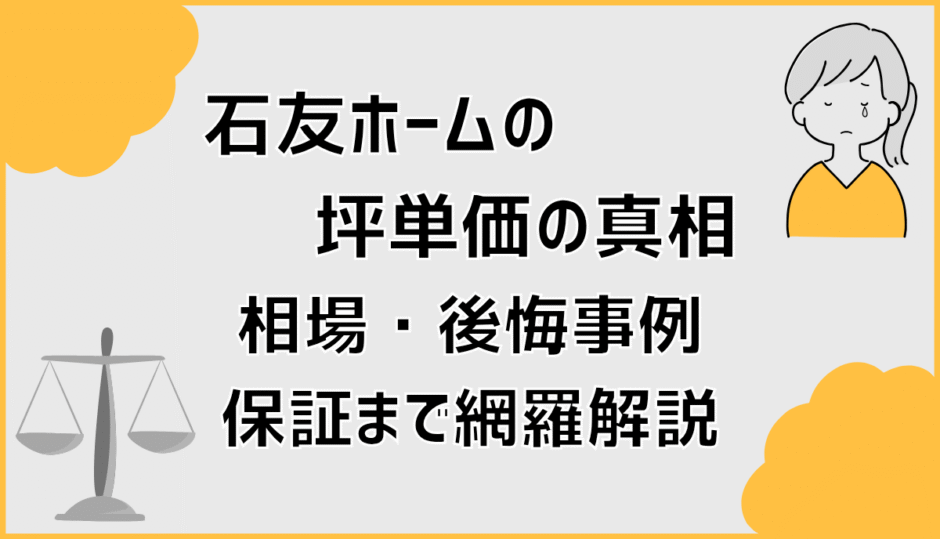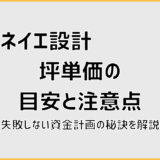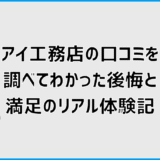この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
家づくりを考えるとき、多くの人が最初に気にするのが石友ホームの坪単価です。けれども数字の大小だけを追いかけると、本当に大切な部分を見失う危険もあります。
口コミに表れる評価を見れば、高断熱や耐震性といった強みに安心感を覚える声がある一方で、費用説明の不足が後悔につながったという経験も耳にします。
だからこそ、標準仕様の範囲や付帯工事の有無を丁寧に確認し、将来の建築費用や変動要因を理解しておくことが欠かせません。
さらに、10年後の定期点検や延長保証がどのように暮らしを支えてくれるのかを知ることは、長期的な安心を得るための大切な視点となります。
他社メーカーと比較することで見えてくる違いもあり、相場の背景を整理することは資金計画を立てるうえで有効です。
ここでは、よくある質問とともに石友ホームの坪単価を多角的に解説し、後悔を減らしつつ自分に合った選択肢を見つける手助けをしていきます。
- 坪単価の相場や建築費用の算出方法を理解できる
- 標準仕様の内容や変動要因を把握できる
- 口コミや評価から後悔を防ぐ視点を学べる
- 点検や延長保証の仕組みを確認できる
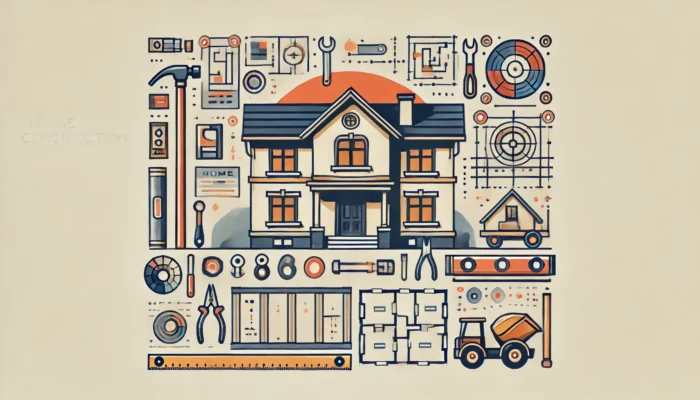
家づくりを検討する際に気になる指標のひとつが「坪単価」です。
石友ホームは北陸を中心に実績を重ねてきたハウスメーカーであり、その坪単価には地域特性や高気密高断熱の性能、自由度の高い設計力などが反映されています。
ただ金額だけを切り取って比較すると本質を見誤ることもあるため、相場の目安や標準仕様の範囲、さらには他社との違いを理解しておくことが大切です。
ここでは、石友ホームの強みや坪単価の相場、費用算出の仕組み、仕様内容、変動要因、さらには競合他社との比較までを網羅的に整理し、読者が納得して判断できるための情報を丁寧に解説していきます。
石友ホームは、北陸の多湿・多雪、そして寒暖差が大きい気候風土に根ざした家づくりを続けてきました。
こうした厳しい自然条件のもとで培われた技術は、快適さと耐久性を同時に実現することを目的としています。
たとえば冬の冷え込みや夏の湿気といった日常の暮らしに直結する課題に向き合い、家族が安心して過ごせる環境を整える工夫が随所に盛り込まれています。
中心となるのが、木造在来工法に高性能断熱・気密パネルを組み合わせて六面体を一体化する「HI-PAIR工法」です。
この工法は室内の温度差を抑え、冷暖房の効率を高めることで、光熱費の軽減や一年を通した快適な居住環境につながります。
さらに外壁通気構造を取り入れることで壁内の湿気を逃がし、結露を防ぐ効果も期待でき、北陸特有の湿潤な環境でも性能が長く維持されやすい点が特徴です。
屋根や基礎部分の断熱性能を高める設計も標準的に採用されており、全体として省エネ性と居心地の良さを兼ね備えた住まいづくりが可能となっています。
耐震・制震面でも安心感を高める工夫が施されています。
石友ホームの住宅はすべて構造計算に基づき耐震等級3で設計されており、加えて住友ゴム工業の制震ダンパー「MIRAIE」が標準搭載とされています。
この装置は地震のエネルギーを吸収して揺れを和らげ、繰り返し発生する余震や長周期地震動にも対応できるとされています。
そのため、構造材の損傷リスクを抑え、室内の安全性を高めることにつながります。
耐震で建物自体を強くし、制震で揺れを逃すという二重の備えが、雪国特有の荷重条件と相まって大きな安心をもたらしているのです。
断熱・省エネ性能については、断熱等級7を満たす仕様が選択可能で、最新の基準にも対応しています。
住宅性能表示制度に基づく等級は第三者から見ても比較しやすい客観的な指標となっており、家づくりを検討する際の信頼性が高まります。
断熱性が高い住宅は暖房や冷房にかかる負担を減らす効果が期待され、省エネ性が高いほど環境負荷の軽減にもつながります。
これにより快適さだけでなく、家計や環境に配慮した暮らしが実現しやすくなります(出典:国土交通省 住宅性能表示制度 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html)。
また、建材の供給体制にも強みがあります。石友ホームはAQ認証を取得した自社プレカット工場を持ち、グループ内で一貫した体制を築いています。
これにより木材を安定的に調達でき、加工精度を一定水準以上に保ちながら施工までつなげることが可能です。
材料の無駄を減らし、設計通りの性能を発揮しやすい体制は、長期的な住まいの価値を守るうえで大きな役割を果たします。
将来的にリフォームや修繕を行う際にも、標準化された工程や一貫した品質管理が安心につながります。
さらに、引き渡し後のアフターサポートも整備されています。
1年・3年・10年の定期点検を通じて住まいの状態を確認し、必要に応じて補修を行える仕組みがあるため、住んでからの不安を減らすことができます。
所定のメンテナンスを受けることで保証期間を延長でき、構造躯体・防水・防蟻に関しては最長で60年まで保証が続く仕組みとなっています。
このような長期保証の体制は、家族が将来を見据えて安心して暮らせる大きな後ろ盾といえるでしょう。
こうした北陸の気候に根差した設計思想や耐震・制震の工夫、そして長期保証までを含めた総合力が、多くの人に石友ホームが選ばれる理由となっています。
坪単価は「本体価格÷延床面積(坪)」で算出されますが、このとき本体に含まれる範囲や、延床面積と施工床面積のどちらを基準とするかによって数値は大きく変わります。
そのため、坪単価を比較する際には条件をそろえて判断することが欠かせません。例えば、地盤改良や屋外給排水工事を本体に含める会社もあれば、別途計上する会社もあります。
こうした違いが見かけ上の坪単価に影響を与えるため、注意が必要です。
各種調査や実際の見積事例をもとにすると、石友ホームの坪単価はおおむね60万~90万円程度とされています。
特に30~40坪の住宅で平均すると71.5万円前後、全体の平均は66.9万円ほどというデータもあります。
さらに高性能仕様を選んだ場合には、83万~86万円程度まで上がるケースも確認されています。
数値の幅が大きいのは、延床面積や導入する仕様、含まれる工事内容によって条件が異なるためです。
下表に、条件ごとの目安を整理しました。
| 前提条件 | 想定面積帯 | 坪単価の目安 |
|---|---|---|
| 回答者全体平均 | 全体混在 | 約66.9万円 |
| 主流面積帯の平均 | 30~40坪 | 約71.5万円 |
| 高性能仕様の見立て | 30~40坪 | 約83~86万円 |
| 公称レンジ | 30~50坪 | 60~90万円 |
数字のばらつきには建物の形や設備仕様も大きく影響しています。
総二階でシンプルな形の建物は外皮面積が小さく抑えられるためコスト効率が良く、坪単価が下がりやすくなります。
逆に、大開口や吹き抜けを多く採用したデザイン性の高い建物は外皮面積が増し、結果として坪単価が高くなる傾向があります。
さらに、照明やカーテン、外構工事などを本体価格に含めるかどうかでも数値は変わるため、必ず見積の範囲を確認して比較する必要があります。
全体を整理すると、石友ホームの坪単価は標準仕様で70万円前後、高性能やデザイン性を重視すると80万円台、さらにこだわりを積み重ねると100万円に近づくケースもあると考えられます。
このため、資金計画を立てる際は自分たちがどのレベルの仕様を望むのかを明確にしておくことが大切です。
家づくりを進める最初のステップとして、坪単価をもとにおおまかな資金計画を描く方法は有効です。
住宅建築は数千万円に及ぶ大きな投資となるため、最初に規模感を把握することは金融機関との相談やライフプランの設計にもつながります。
計算方法はシンプルで、以下の式を用います。
本体価格 = 坪単価 × 延床面積(坪)
総費用 = 本体価格 + 付帯工事費(本体の2~3割目安)+ 諸費用
延床面積を坪に換算する際には、1坪=約3.30578㎡(1㎡=約0.3025坪)を目安にします。
たとえば延床120㎡のプランで坪単価80万円の場合、坪換算は約36.3坪となり、本体価格は約2,900万円になります。
このように数値で確認できると、資金計画のイメージが具体的に描けるようになります。
下表では、30~40坪帯で坪単価を変えたときの概算費用を整理しています。
付帯・諸費は本体の25%を仮置きしていますが、実際には地盤の状況や外構の内容などによって変動します。
| 延床面積 | 前提坪単価 | 想定総費用 |
|---|---|---|
| 30坪 | 70万円 | 2,625万円 |
| 30坪 | 84万円 | 3,150万円 |
| 35坪 | 70万円 | 3,062.5万円 |
| 35坪 | 84万円 | 3,675万円 |
| 40坪 | 70万円 | 3,500万円 |
| 40坪 | 86万円 | 4,300万円 |
同じ面積でも形状が複雑になると外皮面積が増え、窓や外装材が増えることで本体価格に反映されます。
一方で、シンプルな総二階の形状にすれば外装の切り替えが少なく、コスト効率を高めやすくなります。
また、照明や造作収納、外構工事といった「別途」扱いになりやすい部分も積み上げれば大きな差額となるため、比較時には必ず内訳を揃えて確認することが欠かせません。
こうした試算を参考にすると、30坪では2,600万~3,200万円、35坪では3,000万~3,700万円、40坪では3,500万~4,300万円といった範囲が現実的な目安として考えられます。
ここに太陽光発電や蓄電池といった設備を追加すればさらに費用が増える一方で、長期的な光熱費削減に役立つ場合もあります。
資金計画の精度を高めるためには、坪単価だけにとらわれず、含まれる工事範囲やオプションの線引きを明確にした上で、複数の見積を横並びで検討することが大切です。
そうすることで、無理のない予算で理想に近い住まいを実現する道筋が見えてきます。
坪単価は、建物の本体価格を延床面積で割って算出するシンプルな指標ですが、その中に含まれる範囲をどのように定義するかで見かけの数字が大きく変わります。
ですから、家づくりを検討する際には、まず「標準仕様」と「別途工事」の境界をはっきりさせておくことが欠かせません。
これを曖昧にしたまま比較してしまうと、同じ坪単価でも実際の負担額に大きな差が出てしまう可能性があります。
一般的に標準仕様に含まれるのは、住宅の骨格を形づくる基礎や柱、梁といった構造体、断熱や防水、外壁通気を備えた外皮部分、そしてキッチンや浴室、洗面、トイレといった水まわり設備、さらに床や壁、天井などの室内仕上げです。
石友ホームの場合は、耐震性や断熱性、防蟻対策が標準段階からしっかりと組み込まれており、厳しい北陸の気候に適した安心感のある住まいを提供することを目指しています。
冬の寒さに備えた断熱仕様や、繰り返しの地震にも対応する制震装置の採用など、長く快適に住むための性能が初めから備わっているのが特徴です。
一方で、照明やカーテン、造作収納、外構工事、地盤改良、屋外給排水といった部分は、会社やプランごとに扱いが異なるため注意が必要です。
例えば、ある会社では外構が含まれるのに対し、別の会社ではすべてオプション扱いというケースもあります。
見積書を確認する際には、この境界をきちんと把握することが安心につながります。
| 項目区分 | 標準に含まれやすい内容 | 別途扱いになりやすい注意点 |
|---|---|---|
| 構造・外皮 | 基礎・構造体、断熱材、防水、外壁通気、サッシ | 高断熱サッシのグレードアップ、外壁材のデザイン変更 |
| 室内仕上げ | 床・壁・天井の仕上げ、建具、階段 | 造作家具、無垢材仕上げ、アクセント壁 |
| 設備 | キッチン・浴室・洗面・トイレの標準グレード | 食洗機や浴室乾燥機、タンクレストイレなどの追加 |
| 付帯・外構 | ― | 地盤改良、屋外給排水、カーポート、門柱・植栽 |
| 申請・諸費 | 建築確認申請、瑕疵保険 | 長期優良住宅申請、各種負担金 |
さらに、性能に関わる基準として、耐震等級や断熱等級といった公的指標が存在します。
これらは第三者から見ても比較可能な共通言語となり、住宅性能を客観的に把握するうえで信頼できるものです(出典:国土交通省 住宅性能表示制度 )。
同じ会社であっても、坪単価に幅が出るのは自然なことです。その背景には、延床面積、建物形状、選択する仕様、そして工事範囲の違いが大きく関わっています。
加えて、地域特有の気候条件や行政の建築規制、職人の人件費などもじわじわと影響を与えるため、単純に数値だけで比較するのは危険です。
延床面積が大きくなると総額は当然増えますが、1坪あたりの単価は逓減しやすくなります。これは、設備や申請費といった固定費部分が面積に比例しないためです。
ある程度大きな建物では基礎や屋根の比率が下がり、施工効率も高まるため、単価は安定しやすい傾向にあります。
建物の形状も見逃せません。総二階の矩形プランであれば外皮面積が抑えられ、材料や手間が減ることでコストが落ち着きます。
一方で、大きな吹き抜けや複雑な凹凸、大開口を採用すると施工の手間や外皮量が増え、坪単価が上がる要因になります。
特に屋根の谷部や外壁の切り替えは施工リスクが高まり、結果的に追加費用につながる場合も少なくありません。
仕様の選択も坪単価を大きく左右します。サッシをトリプルガラスに変更したり、無垢材を使ったりすれば、住み心地は豊かになりますがコストは上振れします。
さらに、太陽光発電や蓄電池を導入するなど、ZEH基準を満たすような高性能住宅を目指すと初期費用は一段と増加します。
ただし、長期的には光熱費削減や補助金活用によって、将来の負担を軽減できる可能性があります。
また、工事範囲の取り扱いも坪単価に直結します。
地盤改良や外構、屋外給排水の工事は、土地条件や会社の見積定義によって扱いが変わり、金額の差も数十万円単位に広がることがあります。
金融機関が融資対象とする範囲や、自治体の助成金制度なども確認することで、より現実的な資金計画を立てやすくなります。
こうした要因を整理すると、坪単価は単なる数字ではなく、敷地条件やライフスタイル、将来を見据えた全体設計の結果として捉えることが自然です。
背景を丁寧に読み解くほど、選択の基準がより明確になり、自分たちに合った住まいが見えてきます。
坪単価を比較することの本当の目的は、安さや高さを判断することではなく、自分たちが望む暮らしをどの水準で実現できるかを見極めることにあります。
そのためには、価格に加えて性能や設計自由度、保証体制などを含めて総合的に評価する視点が求められます。
坪単価だけに注目してしまうと、快適性や長寿命、将来のメンテナンス費用といった要素を軽視してしまいがちです。
石友ホームの相場は60万~90万円程度で、性能を高めれば80万円台に届くこともあります。
大手メーカーは70万~130万円ほどのレンジに収まり、外皮性能や設備標準、長期保証に強みがあります。
一方で中堅やローコストメーカーは50万~90万円ほどが一般的で、標準仕様はシンプルながらオプションを積み上げると価格が上がりやすい傾向があります。
| メーカー分類 | 目安坪単価 | 性能・設計の傾向 |
|---|---|---|
| 石友ホーム | 60~90万円 (主流帯は70万円前後) | 北陸の気候に適応した断熱・気密性能と制震技術。自由度が高く二世帯住宅や大開口設計も柔軟に対応可能 |
| 大手 (例:住友林業・一条工務店・セキスイハイム等) | 70~130万円 | 外皮性能や設備標準の厚みが強み。意匠や保証が充実しており、仕様を積み重ねると高額化しやすい |
| 中堅・ローコスト (例:タマホーム・アイフルホーム等) | 50~90万円 | シンプルな総二階設計でコスト効率を重視。オプション追加により価格が変動しやすい |
比較を進める際には、断熱等級や耐震等級、サッシや外構の扱いといった具体的な条件をそろえて照合することが大切です。
さらに、保証期間の長さやアフターサポートの体制、地域気候への適合度も見極めに役立ちます。
これらを踏まえると、どの価格帯が自分たちの価値観やライフプランに合うのかが、自然に浮かび上がってくるはずです。

石友ホームの坪単価は、実際に建てた人の評価や将来的な住まいの安心感と密接に関わっています。
口コミには高断熱・高気密による快適性や地域に根差した設計力を評価する声がある一方で、費用説明やアフター対応に課題を感じたという意見も存在します。
こうした体験談に加え、10年後の点検や保証制度がどのように暮らしを支えるのかを理解することは、将来の安心につながります。
ここでは、坪単価にまつわる評判や後悔の事例、定期点検と保証の仕組み、さらによくある質問を通じて、石友ホームでの家づくりを検討するうえで押さえておきたい視点を丁寧に整理していきます。
価格に対する評価は、暮らし心地やサポート体制への納得感と結びついて語られることが多いです。
石友ホームでは、断熱・気密の高さや耐震性を意識した設計により、季節を問わず快適に過ごせる点が高く評価されています。
家のどこにいても温度差が少なく、冬でも素足で過ごしやすい体感を評価する声や、吹き抜け・大開口・二世帯といった要望を柔軟に反映してくれる設計力を支持する意見が目立ちます。
また、北陸特有の豪雪や湿気に配慮した施工技術が安心感を与え、長期的な住まいの耐久性につながると実感される方も少なくありません。
さらに、施工中の現場見学で感じる整理整頓された環境や、営業担当の親身な対応も、安心材料として口コミに現れています。
一方で、工事中や引き渡し後の連絡スピード、現場スタッフの対応、費用の内訳説明に関しては改善を望む声もあります。
特に、標準仕様とオプションの境界が曖昧なまま進んでしまうと、最終見積が想定より上振れしたように感じやすくなります。
これは他社でも起こり得る“見積の定義のズレ”によるもので、早い段階で費用項目を同じ条件で比較することが、誤解を防ぐ大切なポイントになります。
また、担当者変更時の引き継ぎ不足やアフター対応の遅れに対する不満も散見され、情報の正確さやスピードが満足度に影響を与えることが明らかになっています。
総じて、良い評価は「寒暖差の少なさ・静けさ・提案力・地域に根ざした設計力」へ、厳しい評価は「説明の細やかさ・段取り・アフター対応」へ集中する傾向があります。
単なる数値比較ではなく、住み心地や施工中の安心感を含めて総合的に判断すると、坪単価の本質がより鮮明に見えてきます。
家づくりの後悔は、完成後に突如として現れるというよりも、打ち合わせ段階の小さな誤解や確認不足が積み重なって形になることが多いです。
よく挙がる理由としては、追加費用の発生に関する説明不足、現場清掃や近隣配慮への不満、そして「できない理由」の伝え方に納得が得られなかったという点があります。
とりわけ、難しい要望に対して代替案が提示されない場合や、法規制を理由に断られただけでは不安が残りやすい傾向にあります。
さらに、施工中の細部変更や図面と完成形の違いに説明が不足したと感じたケースも見受けられます。こうした小さな違和感が積み重なると、最終的に大きな後悔につながるのです。
費用に関する後悔では、地盤改良や給排水工事、外構など、当初の坪単価に含まれていなかった項目が土地条件によって必要となる場合が典型例です。
契約時の説明が不足していると、追加費用が突然の負担として感じられてしまいます。また、キッチンや浴室などの仕様を打ち合わせの途中でグレードアップしていくと、合計金額が予算を超えてしまったという声も少なくありません。
さらに、照明・収納・コンセント追加など細かな調整が積み重なり、最終的に百万円単位の差となるケースもあります。
資金計画が融資や補助金のスケジュールに追いつかず、ストレスとなったという声も耳にします。
このような後悔を減らすためには、標準仕様とオプションを最初に文書で明確にしておくこと、付帯工事の想定費用を共有することが有効です。
さらに、工事途中での変更や追加が発生した場合には、その都度見積もりを提示してもらい記録を残すことで、後の誤解を防げます。
最終的には、暮らし方の優先順位をあらかじめ家族で共有しておくことで、判断に迷ったときの道しるべとなります。
要するに、情報の鮮度と密度を高めるほど、安心した家づくりに近づけるということです。
長く安心して住むためには、引き渡し後の定期点検と適切なメンテナンスが不可欠です。
石友ホームでは、1年、3年、10年といった節目ごとに点検を実施し、その結果に基づいて必要なメンテナンスを行うことで保証を延長する仕組みを整えています。
特に、屋根や外壁、防水部分、そして基礎や構造部分は早めの対応が後々の大きな修繕を防ぐことにつながります。
また、給排水設備や換気システムといった設備も、定期的な確認で不具合を未然に防げることが多いです。
下記の表は、一般的な点検時期とチェック内容の目安です。
契約内容や仕様によって異なる場合がありますので、詳細は必ず個別の書面で確認する必要があります。
| タイミング | 主なチェックの観点 | 補足メモ |
|---|---|---|
| 1年目 | クロスや建具の調整、雨仕舞の初期確認 | 四季を一巡した後に現れる細かな不具合を調整すると安定しやすい |
| 3年目 | 外装シーリングの劣化、設備の作動状態、基礎のクラック確認 | 早期対応により修繕費を大きく抑えられる |
| 10年目前後 | 屋根・外壁・防水の再点検、バルコニー防水、給湯器や換気の更新検討 | 有償メンテナンスの実施で保証延長の対象になる場合がある |
新築住宅の性能確保に関する基本的な仕組みは、公的制度でも定められています。
特に「住宅性能表示制度」などの制度を理解しておくと、保証や点検の位置づけを整理しやすくなります(出典:国土交通省 住宅性能表示制度 )。
要するに、点検は保険というより整える習慣に近いものであり、家の状態が良いうちに適切な手を加えることで、長く健やかな暮らしを維持しやすくなります。
初めての注文住宅づくりでは、用語や定義が会社ごとに異なるため、迷いが生じやすいものです。ここでは、特に問い合わせの多いテーマをQ&A形式で整理しました。
- 坪単価はいくらを見ておけばいいですか?
- 一般的には60~90万円の間で検討されることが多く、30~40坪の住宅では70万円前後という声が目立ちます。ただし、仕様や外構の有無によって幅が生じるため、早い段階で標準仕様と別途費用の境界を確認しておくと安心です。
- 見積の分母は延床と施工のどちらですか?
- 会社によって算出方法が異なり、延床面積で割る場合と施工面積で割る場合があります。同じ本体価格でも分母が異なれば坪単価が変わるため、必ず条件をそろえて比較する必要があります。
- 付帯工事はどこまで含まれますか?
- 地盤改良や屋外給排水、外構工事の範囲は会社ごとに扱いが分かれます。土地条件によっても変動するため、調査前に想定レンジを共有し、調査後に精査する流れが適切です。
- 大開口や吹き抜けはコストに響きますか?
- 外皮面積や施工手間が増えるためコスト増要因となります。ただし断熱性や日射制御、空調計画を組み合わせて検討すれば、快適性を保ちながらコストとのバランスをとることが可能です。
- 価格を抑える設計は可能ですか?
- 総二階建てや整形プランは外皮面積を抑えやすく、コスト効率に優れます。どこを優先し、どこを調整するかを事前に明確にしておくと、安心して進められます。
質問は暮らしの形に直結するものです。疑問が出たときは、図面や見積内訳を同じ条件で比較するだけでも答えが見えやすくなります。
柔らかなコミュニケーションを重ねることで、家づくりは自分たちのリズムに沿った安心感あるものへと近づいていきます。
石友ホームの坪単価は、単なる数字の比較ではなく、その背後にある性能やサポート体制、そして将来の暮らしの安心感と密接に結びついています。
口コミや評価では、高気密高断熱の快適性や地域に合わせた設計力に支持が集まる一方、説明やアフター対応に関する改善要望も見られました。
こうした声を理解することは、家づくりを検討する上で大切な判断材料となります。
また、坪単価の幅が大きいのは、延床面積や建物形状、選ぶ仕様、付帯工事の範囲などが影響しているためです。
資金計画を考える際には、以下のような点を整理しておくことが役立ちます。
- 標準仕様とオプションの境界を明確にする
- 見積の分母が延床面積か施工面積かを確認する
- 付帯工事や外構の範囲を早めに把握する
- 長期保証や定期点検の仕組みを理解する
さらに、石友ホームは10年後の点検や延長保証の制度を整えており、必要なメンテナンスを適切なタイミングで行うことで、家の寿命を延ばしやすくなっています。
こうした仕組みを活用することで、長期的に安心できる住まいを維持することが可能になります。
他社メーカーと比較した場合も、石友ホームは地域特性に強みを持ち、自由度の高い設計や堅実な性能を備えている点で注目されます。
相場としては60万~90万円前後ですが、選択する仕様によっては80万円台やそれ以上になるケースもあります。
したがって、坪単価の金額だけでなく、暮らし全体の質や将来にかかるコストまで含めて総合的に考えることが大切です。
要するに、石友ホームの坪単価を理解することは、家づくりの成功につながる第一歩です。
性能・仕様・保証を含めた全体像を整理し、自分たちの優先順位を明確にすることで、納得できる住まいづくりへと近づくことができます。
とはいえ、「自分たちに合うプランがまだ分からない」「複数社を比較しながら最適な資金計画を立てたい」と感じる方も多いはずです。
そんなときは、全国のハウスメーカーや工務店から一括で間取り提案や見積りが受け取れるタウンライフ家づくりを利用してみるのも賢い方法です。
無料で複数のプランを比較できるため、石友ホームの坪単価と合わせて他社との違いをより具体的に把握できます。
【PR】タウンライフ