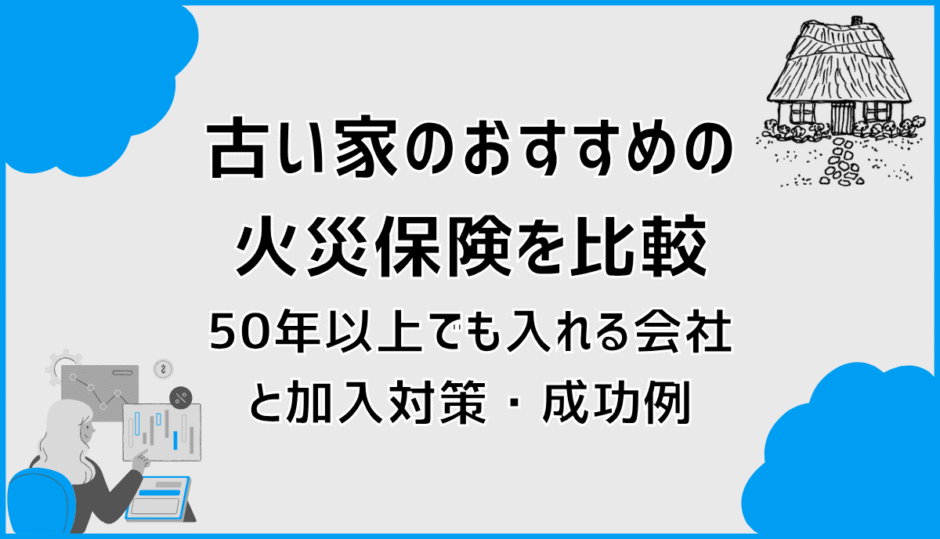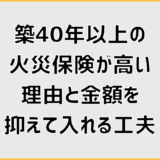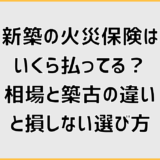この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
古い家に住んでいると、火災保険に入れるのか、あるいは入れないと言われてしまうのではと、不安を抱える方は多いようです。
築古の家は事故リスクが高いと見られがちで、加入審査の段階で理由や原因をはっきり説明してもらえず戸惑った経験のある方もいるかもしれませんね。一社で断られたことで、もう可能性がないのだと感じてしまう場合もあります。
しかし、実際には古い家でも加入に成功している例は多く、火災保険の扱いは会社によって大きく違います。同じ条件でも、比較する相手を変えるだけで結果が変わることは珍しくありません。
保険料が高くなる傾向はありますが、その差が生まれる理由を理解し、審査で評価されるポイントを押さえて準備すれば、選択肢は確実に広がります。
ここでは、古い家のおすすめの火災保険の情報を整理し、加入対策の考え方や成功のパターン、効率的な比較の方法までお伝えします。
古い家のおすすめの火災保険を探しているあなたが、最適な一社にたどり着けるよう、一緒に道筋を見つけていきましょう。焦らず、順番に整理していけば大丈夫です。
- 古い家が火災保険に入れないと言われる主な理由と加入審査で見られるポイント
- 築古物件でも加入に成功した具体的なパターンと対策
- 保険会社ごとのスタンスの違いとおすすめの比較方法
- 保険料を抑えながら納得できる契約に近づく考え方と手順
本記事は、保険会社の公式情報や比較データ、利用者の声などを参照し、筆者が独自に編集しています。
口コミや体験談は状況により感じ方が異なる場合があります。内容は一般的な情報であり、最終判断は各社の公式情報や専門家へご確認ください。

古い家に住んでいると、「うちも火災保険に入れるのかな」「築年数が古いと断られるかも」と不安を感じる方は多いようです。ネットの体験談や、保険会社で一度断られた経験があると、ますます心配が大きくなるかもしれませんね。
でも、実際には築50年以上の家でも加入できた例はあり、工夫次第で選択肢は広がります。火災保険の審査では、屋根や外壁、配線や水回りなどの状態、修繕履歴が重視されます。
情報不足や誤解で諦めてしまう前に、チェックポイントや成功例、もし入れないと言われたときの対処法を知っておくことで、安心して選べる道が見えてきます。ここでは、古い家の火災保険について、整理していきます。
古い家を所有していると「うちの築年数ではもう火災保険に入れないのでは」と感じる方が多いようです。しかし、火災保険の審査で見られているのは築年数そのものではなく、現在の建物状態や維持管理の状況です。
築50年以上の住宅でも、雨漏りや傾きがなく、基礎や柱が健全であれば、加入できている例は少なくありません。逆に、築浅でも放置されて劣化が進んでいる家は、リスクが高いと判断される場合があります。
加入のチャンスを広げるためには、まず自分の家の現状を整理することが大切です。
屋根や外壁に大きな破損がないか、配線が危険な状態になっていないか、長く放置された空き家になっていないかなど、保険会社が気にするポイントを先回りしてチェックしておくと、審査の印象が変わります。
軽微な不具合であれば、事前に補修してから申し込むことで「リスクを管理している家」と評価されやすくなります。
また、多くの保険会社では、申し込み時に建物の外観写真や、リフォーム歴の確認を求めています。ここでの情報提供が丁寧であればあるほど、審査担当者は状況を判断しやすくなります。
「いつ、どの部分を、どのように修繕したのか」を簡単にメモにまとめ、写真と一緒に提出するだけでも、印象はずいぶん違ってきます。
古い家だからといって、最初から無理だと決めつけてしまう必要はありません。築年数はあくまで目安であり、実際には建物の安全性や管理状態のほうが重視されています。
できる範囲でメンテナンスと情報整理を進めたうえで、複数の保険会社や共済に相談してみることが、加入の可能性を最大化する近道と言えます。
正確な条件や最新の取扱いは必ず各社の公式情報を確認し、最終的な判断は保険や不動産の専門家にも相談するようにしてください。
古い家の持ち主が火災保険に不安を感じやすい背景には、老朽化によるリスクと、ネット上の情報の影響があります。
築年数が進むほど、屋根や外壁、配線、給排水設備などにトラブルが起こりやすくなり、火災や水ぬれ事故の可能性が高まると考えられています。
そのため、保険会社は築古住宅を慎重に審査し、ときには引き受けを見送る判断をすることがあります。ここでは、よくある不安と断られる理由を整理しておきます。
築50年以上の家を所有していると、「年数だけで自動的に断られるのでは」と感じる方も多いようです。ただ、審査では必ずしも築年数だけで機械的に判断しているわけではありません。
構造のしっかりした木造や鉄骨、適切なリフォーム歴がある住宅は、築年が古くても前向きに検討されることがあります。心配な場合は、耐震診断や専門家の点検結果を用意しておくと、建物の安全性を客観的に示しやすくなります。
インターネット上には「築何年を超えると火災保険は絶対に無理」といった強い表現の記事も少なくありません。
こうした情報は一部の保険会社の条件だけを切り取って紹介している場合もあり、そのまま全体に当てはめてしまうと、必要以上に不安が大きくなります。
実際には、商品や会社ごとに審査の考え方は異なり、共済や空き家専用保険など、別の選択肢が用意されていることもあります。情報を読み取る際は、何年時点の情報か、特定の会社の条件ではないかを冷静に確認することが大切です。
一社に申し込んで断られると、「やはり古い家だからもう無理なのだ」と感じてしまいがちです。
ただ、火災保険は会社ごとにリスクの見方や商品設計が異なり、ある会社では厳しい条件でも、別の会社では受け入れ可能とされるケースも多くあります。
特に、代理店経由で複数社を取り扱っている窓口であれば、自宅の状況に合う会社を一緒に探してもらえることがあります。一度の審査結果だけであきらめるのではなく、情報と相談先を増やしていくことが、加入成功につながりやすい進め方です。
火災保険の審査では、築年数だけでなく、建物の外観や設備、過去の修繕状況など、複数の観点から総合的にリスクが評価されています。ここを理解しておくと、どこから手を付ければよいかが見えやすくなります。
特に、屋根や外壁の傷み、雨漏りや配線の劣化などは、事故につながりやすい要素として慎重に確認される項目です。事前に自分で点検し、必要に応じて専門業者に相談しておくと、審査の印象を改善しやすくなります。
屋根や外壁、基礎は、建物の安全性と耐久性を支える重要な部分です。瓦のずれや割れ、トタンやスレートの浮き、外壁の大きなひび割れ、基礎の欠けなどが放置されていると、台風や地震時の被害が大きくなると判断される可能性があります。
こうした損傷は、写真で見ても分かりやすいため、審査で注目されやすいポイントです。小規模な破損であれば、早めに補修を行い、その結果を写真で残しておくことで、「リスク箇所をきちんと管理している住宅」と評価されやすくなります。
雨漏りや電気設備、給排水は、火災や水ぬれ事故の直接の引き金になりやすい部分です。
屋根やサッシからの雨染みが残っている場合や、古い分電盤・コンセントがそのまま使われている場合、錆びた配管が放置されている場合などは、保険会社が特に慎重になります。
日頃から漏電ブレーカーの作動状況を確認したり、水道管の凍結防止対策を行ったりといった基本的な管理を行っておくとともに、気になる症状があれば早めに点検・修理を依頼することが、加入に近づく一歩になります。
長く住んでいる家ほど、何度かリフォームや補修を行っていることが多いはずです。こうした修繕履歴は、審査においてプラス評価につながる情報です。いつ、どの部分を、どの程度の工事で直したのかを簡単な一覧にしておくと、申し込み時の説明がスムーズになります。
外壁塗装、屋根の葺き替え、耐震補強工事など、建物の寿命を延ばす工事は特に評価されやすいと考えられます。
日頃の点検や清掃も含めて「きちんと手入れされている家」であることを伝えられれば、古い家でも審査が通りやすくなる傾向があります。
加入審査のチェック項目は会社ごとに異なり、補償範囲や保険料の考え方も大きく変わります。まずは全体像から整理したい場合は、火災保険の相場や選び方をまとめたガイド記事を参考にしてみてください。
築古住宅でも、工夫や準備によって火災保険の加入に成功している例は多くあります。ここでは、代表的なパターンを整理し、どのような行動が審査通過につながりやすいかを解説します。
大きな共通点は、建物の状態を放置せず、小さな補修と情報提供を積み重ねていること、そして一社だけでなく複数の会社に相談していることです。
築55年クラスの住宅でも、劣化が目立つ部分を先に補修し、そのビフォー・アフターの写真を提出することで、加入が認められたケースが報告されています。
例えば、割れた瓦の差し替えや、傷んだ雨樋の交換、ひび割れ部分への補修など、比較的短期間で行える工事でも、保険会社から見ると事故リスクを下げる大きな要因になります。
こうした改善を行ったうえで、「どこをどのように直したか」を写真と一緒に示すことで、築年数のハードルを乗り越えられる可能性が高まります。
なかには、現時点では劣化が残っているものの、具体的な修繕計画を提出することで仮承認となり、工事完了後に本契約へ移行できた例もあります。
ここでは、工事内容やスケジュール、見積書などをまとめた資料が重視されます。「屋根をいつまでに葺き替える」「耐震補強をどの範囲で行う」といった具体性があるほど、改善への意欲が伝わりやすくなります。
加入を目指す場合は、リフォーム会社と相談しつつ、計画書を作成して保険会社に提示する方法も検討の余地があります。
一社で断られても、別会社に申し込んだところ加入できた、という例は非常に多く見られます。会社ごとに、築年数の上限やリスクの取り方、評価の重点が異なるためです。
ある会社では築40年以上を新規で受け付けていなくても、別の会社や共済では、築50年超でも条件付きで受け入れている場合があります。
代理店や一括見積もりサービスを通じて複数社を比較することで、自宅の状態と相性の良い商品を見つけやすくなります。
以上のような成功例から分かるのは、築年数だけであきらめるのではなく、建物の改善と情報提供、相談先の選び方が加入可否を左右しているという点です。
慎重に準備しても、条件やタイミングによっては、通常の火災保険への加入が難しいと案内される場合があります。
ただ、その場合でも備えの手段が全くないわけではありません。共済の火災共済や空き家専用保険、修繕のうえでの再審査など、いくつかのルートが考えられます。ここでは主な選択肢と特徴を整理します。
| 対処法 | 特徴 | 検討のポイント |
|---|---|---|
| 共済の活用 | 築年数に比較的寛容な団体が多い | 地域や職域で加入条件が異なる |
| 空き家専用保険 | 無人の建物でも対象となる商品がある | 補償範囲や保険料の水準を確認する |
| 修繕して再審査 | 劣化箇所を改善して再チャレンジ | 修繕費と保険料のバランスを検討する |
民間の損害保険会社で難しいと判断された場合でも、都道府県民共済や全労済、JA共済などの火災共済は、築年数の条件が比較的緩やかなことがあります。
共済は相互扶助を目的とした制度で、営利性よりも組合員の生活保障を重視しているためです。ただし、補償額に上限が設けられている商品も多く、大きな住宅や高額な家財をすべてカバーできない場合があります。
掛金や補償内容は団体ごとに異なるため、必ず公式資料や窓口で詳細を確認し、必要に応じて専門家の意見も踏まえて判断してください。
共済は築古物件の強い味方ですが、選ぶ前に注意点も把握しておきたいところです。JA共済の特徴とデメリットを整理した記事も参考にしてみてください。
誰も住んでいない状態が続いている住宅は、通常の居住用火災保険では対象外とされることがあります。その場合、空き家専用の保険商品が選択肢になります。
空き家専用保険では、火災や風災、第三者への賠償責任など、空き家特有のリスクに焦点を当てた補償設計が行われています。一方で、地震による損害や細かな破損までは対象外となる場合もあり、補償範囲や免責金額の確認が欠かせません。
空き家の管理状況によって条件が変わることもあるため、見回り頻度や施錠・防犯対策など、日常の管理方法も併せて見直しておくと良いでしょう。
最初の審査で断られた場合でも、指摘されたリスク箇所を修繕したうえで、改めて審査を依頼すると結果が変わることがあります。屋根や外壁のひび割れ補修、古い分電盤の交換、漏水の修理などは、比較的分かりやすい改善ポイントです。
修繕後は、工事内容が分かる見積書や完了報告書、写真などを整理しておくと、保険会社にとって判断材料になりやすくなります。
修繕費用と保険料負担のバランスを考えながらも、必要最低限の安全性を確保しておくことは、火災保険の加入可否に関わらず大切な視点です。
最終的な決定にあたっては、保険会社や工務店などの専門家と相談しながら、無理のない範囲でリスク軽減を進めていくことが望ましいと考えられます。

古い家の火災保険を選ぶとき、「どこが受け入れてくれるのか」「保険料はどれくらい違うのか」「結局どの会社が安心なのか」と迷ってしまう方は少なくありません。
実際、築古住宅では保険会社ごとに審査の姿勢が大きく異なり、保険料の差も新しい家以上に開きやすい傾向があります。そのため、比較せずに一社だけで決めてしまうと、本来得られたはずの選択肢を逃してしまう可能性があります。
ここでは、築古に強い保険会社の比較表や記号の見方、審査基準の違い、条件付き承認の例まで整理し、ケース別にベストな選び方を解説します。
さらに、保険料を抑えるコツや見直しポイント、実際の見積もりへ進むためのステップも紹介します。古い家だからこそ、正しく比較して最適な一社を見つけていきましょう。
古い家の火災保険では、同じ築年数でも保険会社によって扱いがまったく違うことがあります。ある会社ではあっさり断られた条件でも、別の会社なら問題なく契約できるということも珍しくありません。
ここでは、築古物件へのスタンスごとに会社の傾向を整理し、比較しやすい形でまとめていきます。
まずは、実際の会社名も交えながら、種類ごとのおおまかな傾向を表にしてみます。ここでの評価は、あくまで一般的な傾向を整理したものであり、最終的な判断や条件は各社の最新の約款や公式情報で必ず確認してください。
| 保険会社 商品名 | 築30〜40年 (居住中) | 築40〜50年 (居住中) | 築50年以上 (居住中) | 空き家・ 相続物件 | 審査傾向・判断ポイント (※注釈) | スタンスの印象 (推定) | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいおいニッセイ同和損保 タフ・すまいの保険 | 加入事例が多い | 状態次第で検討される例 | 条件付きで引き受けの可能性あり (免責調整など) | 管理状態により要相談 | 公式で「築50年以上・築年不明は免責調整など条件付き引受」の記載あり | 慎重だが門戸あり | リフォーム済築古・状態が良い持ち家を維持 |
| 三井住友海上 GKすまいの保険 | 加入しやすい | 状態確認あり | 例として加入報告あり (リフォーム履歴重要) | 居住実態あれば相談可能 | 比較記事で「柔軟に対応例あり」と紹介多数 | 状態重視で前向き | 住み続ける築古戸建、相談しながら決めたい人 |
| 東京海上日動 トータルアシスト住まいの保険 | 補償手厚く安心 | 状態により可否分かれる | 本社審査など慎重という声多数 | 管理状態次第 | 保険料高め、審査慎重、優等管理物件向き | 補償重視 | 管理良好な築古、しっかり補償したい |
| 損保ジャパン THEすまいの保険 | 加入事例豊富 | 条件次第 | 審査厳格化報道あり | 状況により対応 | ダイヤモンド不動産研究所などで「築古は厳しめ」と紹介 | 標準〜慎重 | 大手ブランド継続希望 |
| ソニー損保 新ネット火災保険 | ネットで加入しやすい | 1980年築前後が判断ライン | 1980年以前新築は新規不可と案内あり | 使用状態により加入例あり | 公開情報「建築年1980年以前は対象外」 | 築古には弱い | 築30〜40年で費用を抑えたい |
| 日新火災 お家ドクター火災保険Web | 公式対象 | 対象外 (Web商品) | 対象外 | 空き家は不可 | 「築40年未満」「空家不可」と明記 | 審査明確 | 築浅や初めての火災保険 |
| 共済系 (全労済、県民共済、コープなど) | 加入しやすい傾向 | 同上 | 同上 | 空き家は内容による | 構造より状態重視。上限額は低め | 費用重視で有力 | 民間損保で断られた人 |
| 空き家向けカテゴリ (例:楽天損保「ホームアシスト」など) | – | – | 条件付き例あり | 比較記事で複数商品紹介 | 「住居として使用予定があるか」「家財常置」などが判断軸 | 空き家でも検討余地 | 相続など暫定空き家 |
この比較表は、築年数の区分ごとに、どの会社がどの段階まで加入相談に応じてくれる可能性があるかを整理したものです。各列の評価は、築年数の進行に対して、契約のハードルがどのように変化するかを把握するための目安として利用できます。
また、空き家・相続物件の欄は、居住実態の有無によって審査の方向性がどこまで変わるかを示しています。
併せて、審査傾向・判断ポイントの欄では、写真提出の必要性や修繕履歴の確認、免責金額の設定など、実際の承認につながりやすい条件の傾向をまとめています。
スタンスの印象では、加入が前向きに期待できるか、慎重姿勢なのかを把握することで、どの会社から優先して相談するべきか判断しやすくなります。
実際には、同じ共済であっても商品ごとに条件が異なり、同じ大手損保でも代理店の提案内容や内部審査の判断によって対応が変わることがあります。そのため、「絶対」ではなく、問い合わせ先を絞り込むための目安として使ってください。
築古住宅へのスタンスの違いは、各社が持つ引き受けポリシーとリスク管理の考え方から生まれています。例えば、全労済の住まいる共済では築年数や使用年数にかかわらず加入できると案内されており、老朽住宅でも受け皿になりやすいとされています。
ネット型損保は、ウェブ上の入力だけで完結させる仕組み上、築年数や構造で細かく条件分けをしにくいため、一定のラインを超えると一律で引き受け不可とする傾向があります。
逆に、代理店経由の大手損保や共済は、写真や補修計画などの追加情報をもとに個別判断してくれる余地があり、ここが柔軟性の差になってきます。
築古住宅で審査が通るかどうかは、「条件付き承認」をどこまで許容してくれるかにも左右されます。
典型的なパターンとしては、保険期間を1年に限定する、免責金額を高めに設定する、風災や水濡れなど一部の補償を外した上で火災・落雷・爆発のみを対象にする、といった調整があります。
また、外観写真や屋根・基礎部分の写真の提出を求められることも多く、過去に大規模なリフォームを行っていれば、その工事内容がわかる資料を添付することで印象が変わる場合があります。
耐震診断書やシロアリ被害の有無の報告などを求められるケースもあるため、築古の家ほど事前の点検と書類準備が肝心です。
築年数に厳格な上限を設けている会社は、ネット型損保や一部のダイレクト商品に多い傾向があります。これは、加入手続きが簡単な分、リスクを築年数や構造で機械的に線引きせざるをえないからだとされています。
具体的には「築40年超は新規契約不可」「築35年以上はネット申込み不可で、電話または代理店で要相談」といったルールが採用されている例が見られます。
こうした会社を避けるというより、築古住宅の場合は最初から「共済系」と「大手損保の代理店型」を軸に探しつつ、条件が合いそうならネット型も試す、という順番で動くと効率的です。
築年数制限が厳しい会社で断られても、その結果だけで「もうどこにも入れない」と考える必要はありません。タイプの違う会社にあたれば、同じ家でも評価が変わることは十分にあります。
より詳しく会社ごとの対応や審査の違いを知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。それぞれ実際に調査した内容をもとに、築古物件への姿勢や柔軟性を比べています。
古い家の火災保険では、保険料の差が新築以上に開きやすくなります。読者の方からも「どこも同じくらいだろうと思っていたら、会社によって数万円違っていて驚いた」という声がよく聞かれます。
同じ建物・同じ補償内容に近い条件でも、会社ごとにリスク評価の仕方が異なるため、比較をせずに一社だけで決めてしまうのはもったいない状況になりやすいと感じます。
築30年を超えるあたりから、多くの保険会社で火災リスクや水災リスクの評価がぐっとシビアになります。木造なら老朽化した配線や屋根の傷み、鉄骨造でも錆びや防水の劣化など、事故につながりやすい要素が増えるためです。
ただし、どこまでをどの程度のリスクと見るかは会社によってばらつきがあります。
ある会社は「築40年を境に料率が一段上がる」ような設計をしているのに対し、別の会社は築年数よりも立地や水害リスクのほうを重視しているといった違いがあります。
その結果、築古住宅では保険料のレンジが広がり、「A社では高いがB社では比較的抑えられる」といったケースが出やすくなります。このばらつきこそ、複数社を比べる価値が大きい理由です。
保険料を決める要素は、「建物の構造」「所在地」「築年数」「補償範囲」「保険期間」などです。例えば、木造は鉄筋コンクリート造に比べて火災時の損害が大きくなりがちとされるため、同じ築年数でも木造のほうが保険料が高くなるのが一般的です。
また、河川近くの低地や土砂災害警戒区域にある住宅は、水災リスクが高いと見なされ、該当する補償を付けると保険料が大きく増えることがあります。
さらに、近年は自然災害の増加を受けて、火災保険の保険期間が最長5年とされるのが一般的になりました。
築古の家で保険料を適正に比較するには、一社ずつ問い合わせるよりも、一括見積もりサービスや複数社を扱う代理店を活用するほうが現実的です。
自分で同じ条件を入力していっても、会社ごとに質問項目や構造区分の呼び方が微妙に違うため、完全に条件を揃えて比較するのはなかなか難しいからです。
一括見積もりサービスでは、建物の住所・構造・築年数などを一度入力すれば、対応可能な複数の会社からまとめて見積もりが届きます。
築40年超などハードルが高い条件でも、そもそも対応できる会社だけが候補として上がってくるため、「見積もりは取れたけれど結局断られた」という手戻りも減らせます。
ここで届いた見積もりをベースに、詳細を相談したい会社を2〜3社に絞り込むのが、時間と労力のバランスが良いと感じます。
火災保険の一括見積もりサイトの中でも、インズウェブは火災保険専用の比較サービスを長く運営していることで知られています。
複数社の料率改定や補償内容の違いを前提に設計されているため、築古物件でも対応可能な会社をピックアップしやすいのが特徴です。
利用するときのポイントは、できるだけ正確な建物情報を入力することです。登記簿や固定資産税の納税通知書で建築年や構造を確認し、増改築の有無も含めて事実に近い情報を反映させましょう。
また、気になる補償項目(例として水災の有無や家財の有無、地震保険の付帯など)をあらかじめ整理しておくと、各社の提案内容を比較しやすくなります。
保険料は同じ条件でも会社によって数万円単位で違うことがあります。だからこそ、まずは実際の見積もりを取って比較してみることが大切だと思います。
複数社を自分で回るのは大変ですが、一括見積もりなら負担なく選択肢を広げられます。手続きは簡単で、最短3分ほどで完了します。
築古住宅で保険料を抑えつつ、必要な備えを確保するには、補償内容の優先順位をはっきりさせることが肝心です。例えば、床上浸水のリスクがほとんどない高台の立地であれば、水災補償を外すことで保険料を下げる選択も考えられます。
一方で、古い屋根のある木造住宅では、風災・雪災の補償を削り過ぎると不安が残るため、むしろ免責金額を5万円や10万円に設定して、一定額までの小さな損害は自己負担にする方法が現実的です。
また、建物の保険金額を再調達価額と時価のどちらにするかで、保険料は大きく変わります。全焼時に建て替えを希望するのか、それとも解体撤去費と最低限の修繕費が出れば良いのかによって、必要な保険金額は違ってきます。
家財保険も同じで、実際に買い直す予定のあるものを中心に金額を設定することで、無駄な保険料を減らすことができます。最終的な条件は必ず各社の公式サイトや約款で確認し、不明点は担当者や専門家に相談しながら調整していきましょう。
同じ古い家といっても、築年数や住み方、相続しているかどうか、賃貸に出しているかなどで、選ぶべき火災保険は変わってきます。
ここからは、代表的なケースごとに、どのような会社や商品タイプを優先的に検討するとよいか、その考え方を整理していきます。
築30〜40年程度の家は、まだ多くの保険会社で通常の住宅として受け入れてもらえるゾーンです。
この築年数帯では、ネット型損保を含めた幅広い選択肢から比較できるため、補償内容と保険料のバランスを丁寧に見ていくことがポイントになります。
具体的には、まず現在の建物評価が適切かを確認しましょう。長く継続している契約だと、新築時の金額のまま更新され続けていることもあります。
再調達価額で契約を続けるのか、あるいは時価で保険料を抑えるのか、今後の建て替え予定も含めて検討するとよいと思います。
また、水災や破損・汚損などの特約をどうするかで保険料は変わるため、自宅のリスクに合った組み合わせを意識したいところです。
築40〜50年の家になると、ネット型損保の一部では新規契約を受け付けていないケースが増えてきます。ここでは、共済系や大手損保の代理店型商品が主な候補になりやすいです。この築年数帯で特に重視されるのが、修繕履歴や管理状況です。
過去に耐震補強工事を行っている、屋根や外壁を塗り替えた、配線を更新したといった履歴があれば、その記録を整理しておくと審査でプラス材料になります。
申込みの際に「何年にどのような工事をしたか」を伝えられるだけでも、築年数だけでは見えない安全性をアピールできます。写真を求められた時のために、屋根や基礎、室内の状態がわかる画像を撮っておくと安心です。
築40年以上になると、保険会社ごとの審査姿勢で結果が大きく変わります。損保ジャパンの対応が気になる場合は、実際に調査したこちらの記事も参考にしてみてください。
築50年を超える住宅になると、築年数そのものよりも「今の状態をどう証明するか」が鍵になります。
全労済の住まいる共済のように築年数を問わず加入できる商品もあれば、あいおいニッセイ同和損保や三井住友海上など、築年数制限を明示していない大手損保の商品を通じて個別判断をしてもらうルートもあります(出典:総務省統計局 住宅・土地統計調査 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.html)。
このクラスの築古住宅では、耐震診断書やリフォーム履歴、シロアリ点検結果など、第三者の評価があると大きな後押しになります。
外観だけで老朽化が進んでいると判断されると、補償を火災のみに絞られたり、免責金額を高く設定されたりすることもあります。どのレベルの補償を希望するのかを整理しつつ、複数の会社に条件を投げて比較する姿勢が大切です。
相続した実家が空き家になっているケースでは、通常の「居住用住宅」を対象とした火災保険にそのまま入れないことが多くなります。
総務省の住宅・土地統計調査によると、空き家数は900万戸、空き家率は13.8%と過去最高を記録しており(出典:総務省統計局 住宅・土地統計調査 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/)、空き家対策は全国的な課題になっています。
空き家の場合、大手損保では「一般物件」として契約する、あるいは空き家専用保険を利用するというルートが考えられます。
一般物件扱いは住宅用に比べて保険料が割高になりやすく、地震保険を付けられないなどの制約もありますが、何も掛けないよりはリスク低減につながります。
また、NPO法人が提供する空き家専用保険のように、空き家であることを前提に火災や解体費用、賠償責任をカバーする商品もあります。
現在も自分や家族が暮らしている古い家であれば、空き家よりも審査は通りやすくなります。人が住んでいることで放火リスクや発見の遅れが軽減されると見なされるためです。
この場合は、火災に加えて風災・水災・水濡れ・盗難といった日常的なリスクをどこまでカバーするかを検討の中心に置きます。
古い家では、水回りや配線のトラブルからくる水濡れ事故や漏電火災の可能性が高まると考えられるため、建物だけでなく家財への補償も含めて検討する価値があります。
また、地震時の倒壊リスクも新しい家より大きくなりやすいため、予算が許す範囲で地震保険を付けるかどうかも大きなテーマです。どこまで補償するか迷う場合は、最低限なくなると困る支出(解体費や当面の生活費など)から逆算する考え方も有効です。
古い家を賃貸として貸している、あるいはこれから貸す予定がある場合は、火災保険の役割が自宅利用のときとは少し変わってきます。
建物オーナーとしては、建物本体の損害に対する補償だけでなく、入居者とのトラブルに備えた賠償責任のカバーも意識する必要があります。
賃貸用住宅として契約する場合、保険会社は入居状況や管理体制を重視します。定期的に点検や清掃が行われているか、設備の修繕履歴があるかなどが評価ポイントになります。
また、入居者側にも家財保険と個人賠償責任保険への加入を勧めることで、賃貸借契約全体のリスクを下げることができます。
築古の賃貸では、建物の老朽化が原因の事故が起きた際の責任範囲が問題になることも多いため、保険だけでなく契約書や管理体制も含めて総合的に見直しておくと安心です。
築年数の古い家でも、事前に状態を整えておくことで、火災保険の審査が通りやすくなったり、条件が良くなったりすることがあります。ここでは、保険加入前にチェックしておきたい代表的なポイントを整理してみます。
築古住宅で真っ先に見直したいのが、屋根と電気配線です。強風や豪雨で被害を受けやすい屋根は、瓦のずれやトタンの浮き、コーキングの劣化などが放置されていると、台風のたびに被害が拡大しやすくなります。
保険会社にとっても、傷んだ屋根は風災リスクの象徴のような存在です。可能であれば、専門業者に点検を依頼し、必要な補修を済ませてから写真を撮っておくと、審査時の印象が変わります。
配線についても、築年数が古い家では、当時の基準で施工されたままになっているケースが少なくありません。
ブレーカーの容量に対してコンセントが増えすぎている、分電盤が旧式のまま、といった状態は、漏電火災のリスクを高める要因になります。
電気工事士にチェックを依頼し、必要に応じて分電盤の交換や配線の更新を行っておくことは、安全性の面でも火災保険の評価の面でも意味がある対策だと考えられます。
次に確認しておきたいのが、水回り設備です。キッチン、浴室、洗面所、トイレの給排水管は、経年劣化によってピンホールや亀裂が発生し、ある日突然の漏水につながることがあります。
特に、天井裏や壁の中を通っている配管は、普段目に見えないため、被害が出てから気づくことが多い部分です。
火災保険の水濡れ補償では、給排水設備の偶発的な事故による損害がカバーされることが一般的ですが、単なる老朽化や長年の管理不足と見なされると支払いの対象外になる場合もあります。
そのため、事前に水道業者に点検を依頼し、明らかな劣化や漏れの兆候があれば早めに補修しておくことが望ましいです。点検や修理の領収書や報告書は、保険加入時の説明や万一の事故後のやりとりでも役立ちます。
古い家の火災保険では、建物だけでなく家財や地震に対する備え方も見直しておきたいところです。家財保険は、家具や家電、衣類など、生活に欠かせないものが火災や水災などで被害を受けた際に補償してくれるものです。
築古住宅では、建物の価値が低く見積もられがちでも、家財を買い直す費用は現在の物価で発生します。世帯人数や持ち物の量に応じた適切な保険金額を設定することで、いざというときの生活再建がしやすくなります。
地震保険については、古い木造住宅ほど地震で大きな被害を受けるリスクが高いとされています。
地震保険は政府と民間保険会社が共同で運営する制度で、保険金額には上限があり、火災保険の保険金額の一定割合までしか加入できないなどのルールがあります。
細かな条件は必ず公式資料や保険会社の説明で確認する必要がありますが、全壊・半壊時に解体費や当面の生活費をカバーできるだけでも安心感は大きく変わります。
家財保険や地震保険を付けるかどうかは、家計とのバランスも含めた判断になりますが、「どこまで補償があれば生活を立て直せるか」を基準に考えてみると整理しやすくなります。
最終的な判断に迷うときは、保険会社や専門家に具体的なシミュレーションを依頼し、納得した上で契約内容を決めていくことをおすすめします。
具体的な見積もりを取って比較してみると、想像していたより大きな差が見えることもあります。
まずは負担なく情報を集めたい方には、一括見積もりサービスの活用が向いています。実際どうなの?と感じる場合は、一括見積もりのメリット・デメリットをまとめていますので参考にしてみてください。
どうでしたか?ここまで読んでくださり、ありがとうございます。
古い家の火災保険のおすすめを探していると、築年数が古い家は入れないのではと不安になってしまう方も多いと思います。
でも、築30年、40年、50年以上の家でも、加入審査のポイントを押さえ、建物の状態を整え、複数社を比較することで、保険に入れる可能性は十分残されています。
むしろ老朽化による事故リスクが高まりやすい古い家こそ、万一の備えが大切だと考えています。
改めて押さえておきたいポイントです。
- 築古でも入れる会社はあるため、築年数だけで諦めない
- 屋根や配線、水回りの点検が審査の印象を左右する
- 一社の否定で判断せず、別会社で成功する例が多い
- 保険料の差を理解し、複数の実見積もりで比較する
最終的には、机上の情報よりも、実際に見積もりを取ることが現実的な第一歩です。建物の状態や修繕履歴を伝えることで、各社の本当の対応が見えてきます。
一括見積もりや代理店を活用し、気になる数社から提案を受けてみてください。古い家でも納得の保険は必ず見つかります。
最後にひとつご紹介させてください。
古い家の火災保険のおすすめで迷っていると、どの会社がいいのか、保険料はどれくらいか。なかなか情報が集めにくいものです。
でも、複数社の条件を一度にまとめて比較できるインズウェブ火災保険なら、その手間がぐっと減ります。実際に利用した方のなかには「築年数がネックだったけど意外と条件が通った」「保険料が思ったより安くて驚いた」といった声も。
家の状態や築年数に不安がある方ほど、まずは見積もりでリアルな条件を確認しておくことが安心につながります。気になる方は、まずは軽い気持ちで比べてみるのもいいと思います。
築古住宅でも大丈夫!
インズウェブは、複数の大手保険会社の見積もりを一度に比較できるサービスとして、長く利用されてきたウェブサイトです。
運営はSBIグループの企業で、保険比較サービスの分野では大手として知られています。サービス内容に関しては、見積もり依頼が無料で、申込みを強制されることもありません。
入力した情報は見積もり作成のためだけに利用され、意図しない営業連絡が過度に行われるといった声も少ないようです。
利用者からは、自分で何社も調べる手間が省けた、保険料の違いが具体的に分かったなどの声が見られ、築年数が古い家の保険選びにも役立つと言われています。
安心して比較を進めたい方や、まずは状況を確認したい方にとって、落ち着いて判断できる選択肢のひとつとなるはずです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。