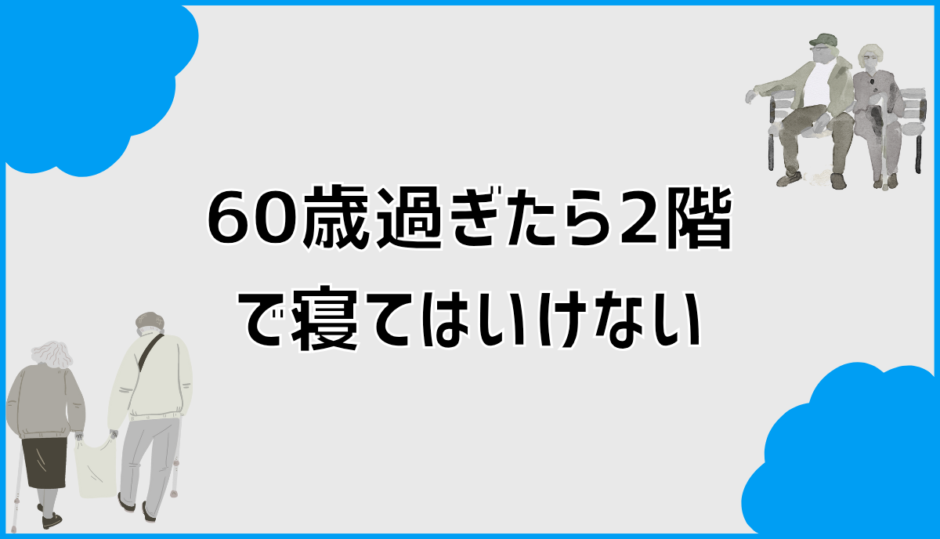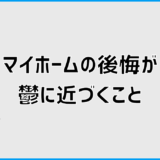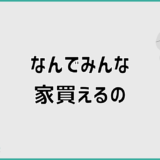この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
最近、60歳過ぎたら2階で寝てはいけないという言葉を目にして、少し気になった方も多いのではないでしょうか。今は問題なく過ごせていても、2階建ての家で年取ったらどうなるのか、寝室はそのままでいいのか、ふと立ち止まる瞬間がありますよね。
特に高齢者になると、階段が登れなくなる年齢はいつなのか、将来二階を使わない暮らしになるのか、不安が具体的になっていきます。
この悩みは、怖がりすぎでも気にしすぎでもありません。階段が登れない状態になったときの対策を、元気なうちから考えておくことで、後悔を減らせるからです。
ここでは、なぜ不安が生まれるのか、どんな条件でリスクが高まるのか、そして2階寝室が向く人・向かない人の違いを整理します。最終的には、あなた自身が納得できる判断軸を持てるよう、一緒に考えていきます。
- 60歳過ぎたら2階で寝てはいけないと言われる背景と不安の正体
- 階段が登れなくなる年齢を一律に決められない理由と考え方
- 2階寝室が向く人向かない人を分ける住まいと暮らしの条件
- 後悔を防ぐために今の検討段階で備えておきたい間取りの視点
- 自分に合う住宅会社が分からない…
- 土地・メーカー探し?何から始めたら?
- 注文住宅って予算的に大丈夫…?

こんなお悩みはありませんか?
LIFULL HOME’Sなら、日本最大級の住宅情報から住宅会社をまとめて比較。ハウスメーカーや工務店のカタログ・施工事例を無料でチェックできます。
「まだ何も決まっていない人」から家づくりを始められるLIFULL HOME’Sで家づくりを始めませんか?
※本記事では、メーカー公式情報や公的資料、各種レビューや体験談などを参考にしつつ、筆者の視点で整理・構成しています。口コミや体験談は感じ方に個人差がある点も踏まえてお読みください。

「60歳過ぎたら2階で寝てはいけない」と聞くと、少し極端に感じるかもしれません。
しかしこの言葉が気になり始める背景には、年齢そのものではなく、体の変化や暮らし方の変化があります。これまで当たり前に使っていた階段や寝室が、ある日を境に不安の対象へ変わることも珍しくありません。
ここでは、なぜ老後に2階寝室への違和感が生まれるのか、どんな条件でリスクが高まるのか、そして誰にとって2階寝室が向くのかを整理しながら、無理のない考え方を見つけていきます。
60歳を過ぎたら2階で寝ていいのだろうかと感じ始めるきっかけは、転倒などの大きな事故よりも、日常の小さな違和感であることが多いです。
夜中に目が覚めやすくなったり、階段で自然と手すりに手が伸びたり、以前より暗さや段差が気になったりと、体の変化が静かに表れます。
これは不安になったのではなく、これからの暮らしを体の変化に合わせて考え直す時期に入ったサインと捉えると整理しやすくなります。
不安が強くなる場面は、だいたい二つに集約されます。ひとつは夜間のトイレ移動。眠気が残る状態で、暗い階段を降りる。ここに急ぎたい目が慣れない足元が冷えるが重なると、日中と同じ身体感覚では動けません。
もうひとつは緊急時です。めまい、動悸、腹痛など、体調が急変したときに、2階から1階へ降りること自体がハードルになります。
救急要請や家族への連絡はできても、本人の移動が伴うと一気にリスクが増える。そう想像できるようになると、2階寝室が急に心細い場所に感じられます。
やっかいなのは、階段の負担が少しずつではなくある日、急に表面化することがある点です。睡眠の質が落ちる、薬の影響でふらつきやすい日が出る、膝や腰の痛みが一時的に強くなる。こうした要因は波があり、たまたま重なった日に転倒が起きてしまうケースがあります。
だからこそ、今の体力だけで判断して当分大丈夫と決め切るより、変化が起きたときの逃げ道を住まい側に用意しておくほうが、気持ちが安定します。違和感は、住まいの見直しを始める合図として受け止めると整理しやすいです。
ここで感じている不安は、何か決断を迫られているというより、家づくりを考え始める合図なのかもしれません。実際、多くの人が同じような違和感から検討を始めています。
もし、自分が今どの段階にいるのか整理したいなら、こちらの記事を参考にしてみてください。
2階寝室の論点は「2階=危険」と単純化することではありません。ポイントは、2階で寝ることに階段移動がセットで付いてくること、そしてその階段移動が夜間・季節・緊急時に弱いという構造です。ここを押さえると、必要な対策が見えやすくなります。
夜間は、視界が狭くなるだけでなく、脳も体も起動直後です。寝起きは血圧や心拍が安定しにくいとされ、立ち上がった瞬間にふらつく人もいます。そこに階段の段差、踏面の狭さ、手すりの握りにくさが重なると、事故の条件がそろってしまいます。
また、階段は一度バランスを崩すと連鎖的に転落しやすい場所です。居間の転倒と違い、衝撃が大きくなりがちなので、対策は階段を使う回数を減らす使うなら安全性を上げるの二方向で考えるのが現実的です。
冬は寝室が暖かくても、廊下や階段が冷えやすい家が多いです。
温度差が大きいと、体が急に縮こまり足が出にくくなったり、手すりを握る指先が冷えて力が入りにくくなったりします。入浴時のヒートショックが注目されがちですが、そもそも家の中の温度ムラは移動全般の負担を増やします。
夏は逆に2階が熱を持ちやすく、寝苦しさで睡眠が浅くなると夜間覚醒が増えることがあります。するとトイレ移動の回数が増え、階段利用も増える。
季節が変わるたびに住まいの弱点が表に出るので、寝室が2階の場合は冷暖房計画と照明計画をセットで見直すのが効果的です。
体調不良の日は、階段が普段の倍きつく感じることがあります。発熱、下痢、眩暈、薬の副作用など、理由はさまざまです。階段が唯一の上下移動手段だと、1階のトイレや玄関が遠い場所になります。
災害時も同様です。地震で家具が倒れ、階段の一部が塞がれる。停電で暗闇になる。火災で煙が上階に溜まる。こうした想定は極端に見えても、避難は最悪を想定して平時を整える領域です。
2階寝室なら、避難経路の確保や足元灯のバックアップなど、階段に依存しない備えが求められます。
何歳から2階はやめるべきかという問いはよくありますが、年齢だけで判断すると現実に合わないことが多いです。同じ年代でも、体力や生活習慣、持病、住まいの性能によって条件は大きく異なります。
重要なのは年齢ではなく、階段が使いにくくなったときに生活が行き詰まらないかどうかです。2階を続ける場合でも、1階へ切り替える場合でも、柔軟に対応できる仕組みを住まいに持たせておくことが安心につながります。
年齢基準に頼ると、まだ早いと先送りしがちです。ところが、住まいの変更は思い立ってすぐ実現できるとは限りません。部屋の片付け、家具の移動、リフォームの段取り、家族の調整など、時間も労力も必要です。
逆にもう年だからと早く決めすぎると、生活の楽しさが削られることもあります。たとえば、日当たりの良い2階の寝室を手放した結果、1階が暗くて落ち着かない。
こうした後悔も現実に起こります。数字だけではなく、生活の質と安全の両面を見て判断したいところです。
チェックしたいのは、派手な症状ではなく、生活の中での小さな変化です。たとえば、夜間にトイレで2回以上起きる日が増えた、階段で息が上がりやすくなった、片足立ちで靴下を履くのが不安になった、などです。
また、めまいが出やすい季節や、睡眠薬・血圧の薬の変更があった時期も注意が必要です。こうした変化は本人が慣れてしまい、危険のサインとして認識しにくいことがあります。家族と最近どう?と定期的に言語化するだけでも、判断材料が増えます。
階段がいつまで使えるかは人それぞれで、正解は一つではありません。だからこそ、今すぐ答えを出すより、選択肢を知っておくことが大切です。
もし、将来を見据えた家づくりをどう考え始めればいいか迷っているなら、こちらの記事を参考にしてみてください。
2階寝室が成り立つかどうかは、年齢だけでなく住まいの仕様と日々の暮らし方の組み合わせで決まります。2階で寝る前提のままでも、夜間動線や設備が整っていれば安心しやすい家もあります。
一方で、住環境や体調の変化によっては、早めに1階へ切り替えたほうが無理なく暮らせる場合もあります。重要なのは良し悪しを決めつけることではなく、自分の住まいがどちらに当てはまるかを冷静に見極めることです。
成り立ちやすい条件は、ざっくり言うと夜間の階段利用を減らせる階段が安全緊急時の手段があるの三点です。
具体例としては、2階にもトイレがあり夜間の上下移動がほぼ不要、階段が緩やかで踏面が広く、両側に握りやすい手すりがある、足元灯やセンサー照明で暗がりを作らない、といった状態です。
さらに、室温のムラが少ない家は、冬の廊下や階段が冷えにくく、移動の負担を抑えやすい傾向があります。
2階を使わなくなる典型は、体力や生活リズムの変化が重なり、これまで当たり前だった階段移動が負担に変わっていく流れです。
夜間のトイレ回数が増えることで上下移動がつらくなったり、膝や股関節の痛み、ふらつきから階段そのものに恐怖感を覚えたりするケースがあります。
さらに介助が必要な状態になると、2階での生活継続が難しくなり、1階に寝場所を移さざるを得ない状況が現実的になります。
また、夫婦のどちらかが先に体調を崩した場合、残る家族の介護負担や動線を考慮して生活機能を1階に集約する判断が取られることも少なくありません。
家族構成や役割が変わると、2階へ上がる理由そのものが減り、結果として空間は残っていても日常的に使わなくなるケースが多く見られます。
迷う場合は、今すぐ二択に決めてしまわないことが大切です。2階寝室を維持しながら、1階にも将来使える寝場所の候補を用意しておくと、判断に余裕が生まれます。
最初から白黒をつけないことで、「まだ早い」「もう遅い」といった極端な判断を避けやすくなります。
また2階が嫌なのか夜間の階段が不安なのかと不安の中身を整理すると、対策は現実的になります。
夜間移動が問題であれば、2階トイレの設置や照明・手すりの追加、寝室近くへの簡易トイレの導入など、暮らしを大きく変えずに取れる段階的な対応も選択肢に入ります。
ここまで読んで、自分は2階寝室が向いているのか、それとも将来切り替えたほうがいいのか、判断に迷っている方もいるかもしれません。実際には、住まいの考え方や情報の集め方によって、見える選択肢の深さは大きく変わります。
もし、住宅サービスの違いが判断を左右すると感じたら、こちらの記事も参考になります。「深さ」についてまとめていますので、参考にしてみてください。

「60歳過ぎたら2階で寝てはいけない」と感じたとき、本当に悩ましいのは正解が一つではない点です。本人は問題なくても家族が不安を抱えたり、将来を想定したつもりが思わぬ後悔につながったりすることもあります。
ここでは、判断が分かれやすい理由や設計段階で意識したい視点、実際に起こりやすい失敗例を整理しながら、後から困らないための備え方と、安心につながる考え方を丁寧に確認していきます。
寝室の階は、暮らしの中心に直結するので、家族の価値観がぶつかりやすいテーマです。本人は慣れているまだ動けると感じる一方で、家族は万が一の対応を先に想像します。どちらも自然な視点なので、ズレが起きるのは当然です。
家族の不安は、事故そのものよりも事故が起きた後の対応に向きやすい傾向があります。夜中に転倒した場合にすぐ気づけるのか、救急車を呼ぶ判断を本人が冷静にできるのか、階段で動けなくなったときに介助できるのか。
こうした想像は、日常では表に出にくいものの、家族側には常に引っかかりとして残ります。本人が元気であればあるほど、こうした不安は口にしづらくなりがちです。
一方で本人は、日中に問題なく階段を使えている感覚を基準に判断しやすく、「今できている=大丈夫」と考えます。この視点の違いが、2階寝室をめぐる認識のズレを生みやすい要因になります。
よくあるのは、体調を崩してからやっぱり1階に移そうとなり、片付けと工事の段取りが一気に発生するパターンです。急ぎの引っ越し同然になり、寝具の移動、収納の再配置、生活動線の作り直しで疲弊しやすくなります。
また、親世帯と子世帯で同居している場合、子ども部屋の配置や来客スペースの兼ね合いで、1階の空き部屋が確保できないこともあります。元気なうちから1階で寝る選択肢をどう残すかを話しておくほうが、後の負担が小さくなります。
話し合いでは危ないからやめてよりも、夜間に階段を使う回数を減らしたい緊急時に連絡できる仕組みが欲しいと条件に落とし込むのが有効です。
条件が共有できると、2階寝室を続ける場合でも対策が合意しやすくなります。反対に、1階へ移す場合もいつどの部屋をどう整えるかを段階的に決められます。感情のぶつけ合いではなく、生活設計として扱うのが近道です。
家族と話し合うとき、感覚的な不安だけでは話が噛み合わないこともあります。納得感を持って共有するためには、表面的な情報ではなく、条件や考え方まで整理された資料が役立ちます。
情報の深さという視点で住宅サービスを比べたい方は、こちらの記事にまとめていますので、参考にしてみてください。
家づくりで後悔を減らすためには、今の暮らしに最適かよりも将来の変化に対応しやすいかを軸に考えることが大切です。老後は誰にでも訪れますが、その時期や困り方は人それぞれで予測できません。
だからこそ、暮らし方が変わったときにも無理なく調整できる余地を、住まいにあらかじめ持たせておくことが安心につながります。
最初から寝室を1階に固定する方法は分かりやすい反面、日当たりやプライバシー、家族の生活動線に不満が出ることもあります。そこで現実的なのが、今は2階寝室を使いながら、将来に備えて1階に寝られる部屋を残しておく考え方です。
用途は客間や書斎、趣味室などで問題ありません。重要なのは、将来ベッドを置ける広さがあり、トイレまで無理のない距離であることです。
こうした余白があると、体調や生活の変化が起きても慌てずに対応しやすくなり、住まいに対する安心感も大きく変わってきます。
困りにくい間取りの共通点は、動線が短く単純であることです。寝室からトイレ、洗面、浴室までが近い。段差が少ない。廊下が暗くない。こうした条件は、年齢に関係なく毎日の負担を減らします。
扉は引き戸やレバー式にしておくと、握力が落ちたときに助かります。床材も、滑りにくさと掃除のしやすさのバランスがあると日常のストレスが減ります。将来の介助や車椅子を想定するなら、有効幅も早めに意識しておきたいポイントです。
最低ラインとして意識したいのは、1階に寝られる場所とトイレが無理のない距離で配置されていることです。完璧な介護仕様でなくても、寝起きの移動が階段を使わずに完結するだけで、転倒や体への負担は抑えやすくなります。
あわせて確認したいのが玄関までの動線です。老後は通院や訪問介護、買い物などで玄関を使う頻度が高まることもあります。寝場所から玄関までの経路に段差や狭さがなく、家具で塞がれないかは、間取り検討の段階で押さえておきたいポイントです。
将来の変更を難しくするのは、用途が固定された間取りです。たとえば1階がリビングのみで個室がなく、収納も不足していると、後から寝室へ転用することが難しくなります。
その結果、体調や生活の変化が起きた際に、無理な暮らし方を続けてしまうケースもあります。可能であれば、1階の一部を個室として使える余地を残しておくと安心です。
間仕切りしやすい構造や、配線・コンセントをベッド配置前提で計画しておくことで、将来の負担を抑えやすくなります。
2階寝室を続ける場合は、夜間にできるだけ階段を使わない使うなら安全性を最大限高めるという考え方が基本になります。
2階トイレが設けられない場合でも、寝室近くに簡易トイレやポータブルトイレを用意しておくことで、夜間の上下移動を減らすことができます。
あわせて重要なのが、体調急変時の連絡手段です。枕元にスマートフォンや呼び出しボタンを置き、家族と緊急時の対応ルールを共有しておくことで、万一の不安を軽減できます。
住まいの工夫と日常の運用を組み合わせることで、2階寝室でも現実的に安全性を高めやすくなります。
設計段階で特に効果が出やすいのが階段まわりの計画です。手すりは片側ではなく両側を前提にし、踏面に余裕を持たせ、必要に応じて踊り場を設けることで、将来の転倒リスクを抑えやすくなります。
照明も足元までしっかり届く配置にしておくと、夜間の不安が軽減されます。
あわせて、階段や廊下の温度差を小さくする断熱計画や、人感センサー付き照明など設備の力を活用することも有効です。高齢期の安全は一つの対策ではなく、細かな配慮を積み重ねることで確保しやすくなります。
工事をしなくても、日々の暮らし方を見直すことで安全性を高めることは可能です。夜間は廊下や階段を完全に暗くせず、足元が分かる明るさを保つこと、滑りにくい室内履きを用意すること、階段に物を置かないことは基本的な対策になります。
また、手すりを必ず握る習慣をつけるだけでも、転倒リスクは抑えやすくなります。
あわせて、寝る前の水分量を調整し、夜間のトイレ回数を減らす工夫も一案です。ただし脱水につながる可能性もあるため、体調管理については医療者の指示を優先し、無理のない範囲で取り入れることが前提となります。
ここまで読んで、間取りや会社は比べたほうがいいと感じた方も多いと思います。ただ、いきなり住宅会社に行くのはハードルが高いですよね。そんなときは、まず資料を見比べながら考えるところから始めても大丈夫です。
こちらの記事で、何も決まっていない人向けにおすすめの方法を整理していますので、参考にしてみてください。
寝室の階を巡る後悔は、安全を取りに行ったのに暮らしが窮屈になった切り替えるつもりが切り替えられなかった比較が足りず後から違和感が出たに集まりやすいです。失敗例を知っておくと、自分の計画に照らして予防できます。
1階に生活機能を集約しすぎた結果、リビングが窮屈になってしまうケースは少なくありません。
収納不足で動線が塞がれたり、来客時に落ち着いて過ごせる場所が確保できなかったりすると、安全性は高まっても暮らしの満足度が下がってしまいます。老後の備えでは、安全と快適さの両立が欠かせません。
そのためには、寝場所の候補を確保しつつ、普段は客間や趣味室など別用途で使える余白を残すことがポイントです。生活を縛りすぎない備えが、結果的に長く心地よく暮らせる住まいにつながります。
将来は1階に移すつもりだったのに、結局できなかったという後悔は少なくありません。主な理由は、1階に個室がなく転用できない、物が増えて部屋を空けられない、家族の部屋割りが固定化している、といった住まい側の制約です。
こうした問題は、体調が変化してから気づいてもすぐに解決できない点が厄介です。ただし、このタイプの後悔は図面段階で防げることが多く、あらかじめ1階に転用可能な部屋と十分な収納計画を用意しておくことで、将来の切り替えが現実的になります。
比較不足で起きやすいのは、夜間動線への配慮が足りないまま判断してしまうことです。図面上では寝室とトイレが近く見えても、実際には廊下の曲がりや扉の開閉が多く、夜間は想像以上に動きづらく感じる場合があります。
特に寝起きで視界が定まらない状況では、わずかな動線の違いが負担になります。
モデルハウス見学の際は、昼間の印象だけでなく「夜ならどう動くか」を意識して確認してみてください。照明の位置や明るさ、階段の見え方、曲がり角の数など、細かな違いが老後の安心感を大きく左右します。
2階で寝てはいけないかよりも、自分の家は、どんな条件なら2階寝室が成り立つかを比べるほうが、判断が具体的になります。住宅会社や間取り案を比較する際は、デザインや価格と同じくらい、夜間の動線と将来の切り替えやすさを見ておきたいところです。
夜間動線を確認する際は、単純な距離よりも途中にどれだけ障害物があるかを見ることが大切です。
曲がり角や段差、扉の開閉、暗がり、手すりのない区間が増えるほど、夜間の移動は不安定になりやすく、転倒リスクも高まります。図面上では問題なく見えても、実際の動作では負担になることがあります。
可能であれば、寝室からトイレまでを夜中に歩く想定で頭の中で動線をたどってみてください。寝起きで視界がはっきりしない状態でも安全に移動できそうか、という感覚で確認すると、生活実感に近い判断がしやすくなります。
1階完結をうたっていても、実際には洗濯物干しが2階ベランダ前提だったり、収納が2階に偏っていたりと、生活の一部が2階依存になっている家も少なくありません。この状態では、将来1階で生活しようとしても負担が残ります。
そのため、名目だけでなく本当に1階だけで日常が回るかを確認することが大切です。具体的には、1階に寝場所の候補があり、トイレや洗面が近く、洗濯から収納までが1階で完結しやすいか。
こうした条件がそろっていると、生活の切り替えも無理なく進めやすくなります。
同じ将来は1階で寝られるようにしたいでも、会社によって提案差が出ます。理由は、標準仕様、設計の自由度、コスト配分の考え方が違うからです。
将来の変更を前提にすると、構造の取り方や設備の仕込みが効いてきます。提案を比較するときは、間取りだけでなくなぜその配置なのか後から変えるときのハードルは何かまで質問してみてください。回答の具体性が、その会社の設計力の差として表れます。
以下は、比較時に整理しやすいようにまとめた簡易表です。
| 観点 | 2階寝室を続ける場合に見る点 | 1階へ切り替える場合に見る点 |
|---|---|---|
| 夜間トイレ | 2階トイレの有無、照明計画 | 寝場所候補からトイレまでの距離 |
| 階段 | 両側手すり、踏面・勾配、踊り場 | そもそも階段を使わず回る動線 |
| 温熱環境 | 2階の暑さ、廊下・階段の冷え | 1階の底冷え、寝室の断熱 |
| 将来の可変性 | 2階で完結できる設備の余地 | 1階個室化、収納の再配置のしやすさ |
どうでしたか?最後までお読みいただき、ありがとうございます。
60歳過ぎたら2階で寝てはいけないという言葉は強く聞こえますが、実際には住まいの条件や暮らし方によってリスクは大きく変わります。
夜間に階段移動が増えやすいこと、季節によって体への負担が変わること、緊急時や災害時に階段が壁になりやすいこと。こうした構造を理解し、備えを重ねていくことが安心につながります。
判断の軸はとてもシンプルです。
- 夜間に階段を使う回数を減らせるか
- 階段の安全性を高められるか
- 使えなくなったときに1階へ切り替えられるか
2階寝室を続けるなら夜間動線の工夫と安全対策を、切り替えを見据えるなら1階に寝られる余地と収納計画を考えておくことが現実的です。
最後に紹介させてください。
ここまで読んで、考え方や判断軸は少し整理できたものの、次に何から始めればいいか迷っている方も多いと思います。今は決断よりも、情報の集め方や比較の仕方を知る段階かもしれません。そんなときに役立つ記事を、あわせて紹介します。
迷ったときほど急いで結論を出さず、条件を比べて安心の根拠を増やしていきましょう。体調や住環境によって答えは変わるため、必要に応じて専門家に相談しながら、あなたに合った選択を重ねていくことが大切です。