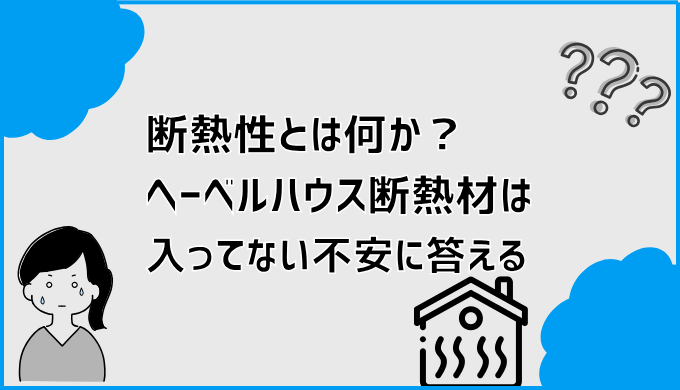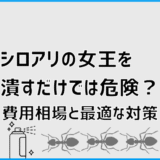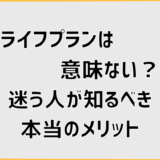この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
家づくりを考えるとき、多くの方が気になるのが断熱材の有無や性能です。特にヘーベルハウスに関しては、断熱材が入ってないのではないかと不安を感じる声を耳にします。
しかし実際には、外壁や屋根、床下にまで複数の断熱層が設けられており、その厚さや構造に工夫が凝らされています。
それでもなぜ入ってないと見えるのか、あるいは床下に断熱材を入れない工法を採用する理由など、疑問は尽きません。
断熱性能を正しく理解するには、断熱性とは何かを整理し、材料ごとの特性や部位ごとの役割を知ることが大切です。
さらに既存住宅で寒さを感じた場合には、窓や隙間を確認し、必要に応じて断熱材を追加するなど、断熱性向上に必要な技術と工夫を取り入れることが有効です。
加えて選ぶべき断熱材の種類と特徴を知っておけば、自分の暮らしに合った最適な解決策を選択できます。
ここでは、断熱材が入ってないと誤解される理由から、厚さと性能の関係、床下断熱の考え方、さらには断熱材の選び方や改善方法まで、安心できる住まいづくりに役立つ知識をわかりやすく解説していきます。
- ヘーベルハウスの断熱材構造と部位ごとの特徴
- 断熱材が入ってないと誤解される理由と背景
- 過去仕様と現在仕様の違いや厚さと性能の関係
- 床下断熱の考え方と快適性を守る仕組み

- ヘーベルハウスの断熱材構造と部位別特徴
- なぜ断熱材が入っていないと誤解されるか
- 過去の仕様と現在の違いについて
- 断熱材の厚さと性能の関係
- 床下に断熱材を入れない理由とは
住宅の断熱性能について調べていると、「ヘーベルハウスには断熱材が入っていないのではないか」という声を見かけることがあります。
しかし、実際には部位ごとに適切な断熱材が組み込まれており、その誤解は設計構造や素材の見え方に由来するものです。
ALC外壁は厚みがあり、その内部に断熱材を重ねる構成となっているため、一見すると断熱材が見えにくいのです。
また、過去の仕様と現在の標準仕様の違い、断熱材の厚さと熱性能の関係、さらには床下断熱の考え方なども誤解を招く要因になっています。
ここでは、ヘーベルハウスの断熱材構造や部位ごとの特徴、なぜ断熱材が入っていないと見られやすいのか、仕様の変遷や厚さと性能の関係、さらに床下断熱の理由について詳しく解説していきます。
ヘーベルハウスは、外壁にALC(軽量気泡コンクリート)パネル「ヘーベル」を採用し、その内側に高性能断熱材を重ねる“二重の断熱構造”を基本としています。
ALCは独立気泡を多く含み、もともと熱を伝えにくい性質を持っています。そのため遮音性や耐火性といった付加価値に加え、断熱性能にも一定の効果を発揮します。
しかし、それだけで十分な断熱性を確保できるわけではなく、壁や屋根にはさらにフェノールフォーム系の断熱材「ネオマフォーム」が加えられます。
ネオマフォームは熱伝導率0.020W/(m・K)という最高水準の性能を誇り、薄くても効果的に熱の出入りを防ぐ特性を持っています。
屋根・外壁・床という主要部位ごとに断熱仕様は工夫されており、特に床下では厚さ60mmのポリスチレンフォーム断熱材と、厚さ100mmのヘーベル床材が組み合わされています。
この構造は床下からの冷気や湿気の侵入を抑え、冬でも安定した室温を保ちやすい環境をつくります。
外壁のALC、壁内のネオマフォーム、床下の複合断熱層といったように、部位ごとに役割が分担されているため、家全体としてバランスの取れた断熱性能が維持されるのです。
一般的なサイディングやモルタル外壁と比較すると、ALCの持つ素材特性と高性能断熱材の組み合わせにより、長期にわたって安定した断熱効果が見込めます。
こうした設計は、快適な室内環境を維持しながら冷暖房の効率を高め、住まい全体の省エネルギー性につながっていると言えるでしょう。
| 部位 | 使用材料 | 厚さ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 外壁 | ネオマフォーム+ALCパネル | ネオマフォーム45mm程度/ALC75mm | 高断熱・耐火・遮音性を両立 |
| 屋根 | ネオマフォーム | 約45mm | 熱の侵入を大幅に抑制 |
| 床下 | ポリスチレンフォーム+ヘーベル床材 | 断熱材60mm+床材100mm | 冷気・湿気を防ぎ室温安定 |
ヘーベルハウスに対して「断熱材が入っていないのでは」といった声が聞かれるのは、外壁材の特性や構造の見え方に大きく影響しています。
外壁に用いられるALCは、軽量でありながら無数の気泡を含むことで熱を伝えにくく、素材そのものがある程度の断熱性能を備えています。
そのため、外壁パネル自体が断熱材の役割を果たしているかのように映り、追加の断熱層が不要だと誤解されがちです。
しかし実際には、壁や屋根、そして床下に至るまで、性能の異なる断熱材が複層的に組み込まれています。
居住者が生活する中で直接目にすることができないため、この「見えない状態」が存在しないという誤解を生んでしまうのです。
また宣伝や説明の場面では、ALC外壁の耐火性や耐久性、さらには断熱性が大きく強調される傾向があります。
その結果、内側に隠れているネオマフォームなどの高性能断熱材が十分に認識されず、外壁材だけが断熱の中心であるかのように受け止められてしまうのです。
このように情報の伝わり方もまた、誤解を広げる一因となっています。
しかしながら、公式仕様を確認するとその実態は明確です。壁や屋根には熱伝導率0.020W/(m・K)という最高ランクに位置づけられるネオマフォームが採用され、床下では厚さ60mmのポリスチレンフォームと100mmのヘーベル床材が組み合わされています。
これらは単なる補助的な層ではなく、快適な室内環境を維持するために欠かせない基盤として設計されています。
見た目には存在が分からなくとも、実際には精密に配置された断熱層が家全体を覆っているのです。
要するに、ヘーベルハウスが「断熱材が入っていない」と誤解される背景には、素材そのものの性能と、断熱材が隠れているという構造的特徴、そして情報の伝わり方の三つの要因が重なっています。
断熱材は確かに組み込まれており、外壁や屋根、床下のあらゆる部位で役割を果たすことで、安心して暮らせる快適な住まいを支えていると言えるのです。
ヘーベルハウスの断熱は、外壁にALC(軽量気泡コンクリート)パネル「ヘーベル」を採用し、その内側に高性能断熱材を重ねる二重構成を基本に発展してきました。
特に大きな変化が見られたのは2017年に導入された「シェルタードダブル断熱構法」であり、この仕様を境に断熱性能は飛躍的に強化されました。
当時の公式発表では、外壁に厚さ75mmのALCの内側へ熱伝導率0.020W/(m・K)級のフェノールフォーム断熱材「ネオマフォーム」を45mm加えることが示されています。
さらに1階床では従来の仕様と比べ、約3倍の厚みを持たせた60mmのポリスチレンフォーム断熱材と100mmのヘーベル床材の組み合わせが採用され、断熱性の底上げが図られました。
この強化により、2階建て住宅では外皮平均熱貫流率(UA値)が0.6以下を目指せる水準となり、省エネ住宅の基準であるZEHの達成を見据えた仕様へと進化しています。
築年数が古い住宅では、外壁の断熱材厚さや床下の仕様にばらつきがあり、断熱性能が十分に確保されていない例もありました。
現在の仕様は「素材」「厚さ」「連続性」を重視した一体的な設計思想に基づいており、各部位の断熱ラインを明確にすることで、冷暖房の効率を高め、室内の温度ムラを抑えやすくしています。
冬場の冷輻射や足元の冷えに配慮した床断熱の強化は、その象徴的な変化といえます。
| 部位 | 旧仕様の傾向 | 現行の代表仕様 | 期待される効果 |
|---|---|---|---|
| 外壁 | ALC+断熱材(厚みにばらつき) | ALC75mm+ネオマフォーム45mm | 外壁断熱の明確化、冷輻射の抑制 |
| 屋根 | 部分的な充填断熱 | ネオマフォーム中心の高性能断熱 | 夏の侵入熱・冬の放熱を低減し、省エネ効果向上 |
| 1階床 | 地域や年代によって厚みに差 | ヘーベル床材100mm+断熱材60mm | 床下からの冷気・湿気を遮断し、足元の快適性強化 |
このように見ていくと、現行の断熱仕様は単に断熱材を厚くするだけでなく、部位ごとに役割を分担させ、全体のバランスを取る設計へと進化してきたことがわかります。
断熱材の性能は、材料の熱伝導率(λ)と厚さ(d)の組み合わせで決まります。
材料単体の熱抵抗(R値)は「R=d/λ」で表され、厚みを増すか、λの小さい高性能な材料を使うほど、熱を通しにくくなります。
建物全体では、屋根・外壁・床・窓といった外皮の熱の通しやすさを面積加重平均したUA値が指標となり、この値が小さいほど省エネ性能に優れた住宅であると評価されます。
例えばR値2.25m²・K/Wを確保する場合、ネオマフォームなら厚さ45mm程度で達成できますが、押出法ポリスチレンフォーム(λ=0.028W/(m・K))では約63mm、グラスウール(λ=0.038W/(m・K))では約86mmが必要となります。
この比較からも、同じ断熱性能を得るために高性能な材料ほど厚みを抑えられることが直感的に理解できます。
| 材料 | 熱伝導率λ [W/(m・K)] | 厚さの目安(R=2.25) |
|---|---|---|
| フェノールフォーム(ネオマフォーム相当) | 0.020 | 約45mm |
| 押出法ポリスチレンフォーム(XPS) | 0.028 | 約63mm |
| グラスウール(一般的設計値例) | 0.038 | 約86mm |
ただし、断熱材の厚さだけで体感の快適さは決まりません。
熱橋(部材の接合部にできる熱の通り道)の回避や気密性、防露設計、そして窓の性能など、外皮全体の調和が居住性能を大きく左右します。
壁の断熱材を厚くしても、窓の断熱性が低ければ足元に冷気が降りる「コールドドラフト」が発生することもあります。
したがって、厚さの増強は有効な手段であるものの、外皮全体を総合的に設計する視点が欠かせません。
住宅の床断熱には「床断熱」と「基礎断熱」という二つの方式があります。床断熱は1階の床面で外気と室内を分ける方式で、床下は屋外相当として換気を確保します。
一方、基礎断熱は基礎周りを断熱し、床下全体を室内空間として取り込む方法で、床下換気口を設けないのが一般的です。
そのため「床下に断熱材が入っていない」と見える場合も、実際には基礎断熱を採用しているだけというケースが少なくありません。
ヘーベルハウスでは標準的に床断熱を採用しており、1階床に厚さ60mmのポリスチレンフォーム断熱材、その上に100mmのヘーベル床材を組み合わせています。
この設計により、床下からの冷気や湿気を防ぎつつ、安定した足元の快適性を実現しています。
また、外壁や屋根がALCとネオマフォームの二重構成で覆われているため、床下だけが断熱の弱点になるわけではありません。
もし床付近で寒さを感じる場合、それは断熱材の欠如ではなく、床下の断熱材の連続性や配管周りの気流止め、窓や気密性の影響が関係している可能性が高いのです。
| 観点 | 床断熱 | 基礎断熱 |
|---|---|---|
| 断熱ライン | 床面で室内と外気を分ける | 基礎周りを断熱し床下全体を室内に含める |
| 床下の扱い | 屋外相当として換気を行う | 室内空間として取り扱い、気密・防露が必須 |
| メリットの例 | 点検が容易で白蟻対策もしやすい | 床温の安定性が高まり、配管の凍結リスクを抑えやすい |
| 注意点の例 | 気流止めや断熱欠損があると性能低下 | 気密不良や湿気処理の不足による結露リスクがある |
つまり「床下に断熱材が入っていない」という見え方は、工法の違いによるもので、断熱が欠如していることを意味しません。
住まいの快適性を保つには、自邸がどちらの方式を採用しているのかを理解したうえで、気密性や開口部性能との組み合わせを見直していくことが大切です。

- 寒さを感じるときの確認ポイント
- 断熱性向上と断熱材追加の技術と工夫
- 他メーカーとの断熱性能比較
- 選ぶべき断熱材の種類と特徴
- よくある質問集と回答まとめ
- まとめ:ヘーベルハウス断熱材は入ってない不安に答える
住まいの中で「思ったより寒い」と感じると、断熱材が入っていないのではと不安になる方も少なくありません。
しかし、多くの場合は断熱材の有無ではなく、窓や床下など特定の部位で熱が逃げていることや、施工精度の差が原因になっています。
ヘーベルハウスをはじめとする住宅メーカーの断熱性能を比較しながら、寒さを感じたときに確認すべきポイントや、追加の断熱改修による改善方法を整理すると、解決策が見えてきます。
さらに、断熱材の種類ごとの特徴や選び方を理解することで、費用対効果の高い対応策を選べるようになります。
ここでは、確認から改修、他メーカーとの比較、断熱材の選定、そしてよくある疑問への答えまで、実際の解決につながる知識をまとめて解説していきます。
家の中で冷えを感じるとき、その要因は単に断熱材の厚さや有無だけでは説明できません。
窓やドアといった開口部の性能、床下や基礎部分の断熱処理、建物全体の気密性、さらには施工精度の良し悪しが複雑に関係しています。特に窓は外気と接する面積が大きいため、外皮性能の中でも熱が逃げやすい部位です。
アルミフレームの単板ガラスに比べ、樹脂サッシや木製サッシ、さらにLow-E複層ガラスを組み合わせる窓では、同じ部屋でも体感温度が大きく変わることがあります。
床付近の冷えも見逃せません。ヘーベルハウスのように床断熱を標準仕様としている住宅でも、施工過程で気流止めが不十分だったり、配管まわりの隙間がそのまま残っていたりすると、冷たい外気が床下から侵入してしまいます。
その結果、足元が常に冷えると感じる状況につながるのです。点検口を開けて断熱材の連続性や欠損の有無を確認するだけでも、原因解明の第一歩になります。
また、施工精度が低いと断熱材が図面通りに収まっていない場合があります。この場合、熱が回り込みやすい部分(熱橋)が生じ、室内の快適性を下げます。
サーモカメラを用いた熱画像診断や、専門業者による簡易気密測定を活用することで、どの部位が弱点になっているのかを把握しやすくなります。
このように、寒さを感じるときは単純に「断熱材が入っていない」と結論づけるのではなく、開口部の性能、床下や基礎部分の断熱処理、施工の精度や気密性などを総合的に確認する姿勢が大切です。
建物全体を順序立てて見ていくことで、原因を明確にし、効果的な改善につなげることができます。
既存住宅で断熱性能を高めるためには、効果の出やすい部位から段階的に改修を進めるのが現実的です。
窓の改修は最も投資対効果が高いとされ、既存の窓に内窓を設置したり、ガラスをLow-E複層ガラスやトリプルガラスへと交換したりすることで、冷気の流入を大幅に抑えることができます。
国土交通省の省エネ基準でも、開口部は断熱性能の底上げに直結する要点として位置づけられています。
次の段階として取り組みやすいのは天井や小屋裏です。屋根からの熱損失は全体に占める割合が大きく、断熱材を増し敷きするだけでも冬の暖房効率が改善されます。
その後、床や壁の補強を行うことで、外皮全体の断熱バランスが整います。特に床は冷えを直接感じやすいため、床下に断熱材を追加したり、既存材の隙間を埋めたりする工夫が有効です。
さらに、追加断熱を行う際には気密と防露計画を同時に考慮する必要があります。
断熱材を厚くすると結露のリスクも高まるため、防湿層の位置や透湿性を適切に設計することが欠かせません。
例えばフェノールフォーム系断熱材は薄くても高い断熱性能を示しますが、防火性能や施工条件も確認しなければなりません。
最新の技術としては、吹付け硬質ウレタンフォームや真空断熱材といった高性能断熱材の活用があります。
これらは限られた厚さでも大きな効果を発揮するため、リフォーム空間の制約が大きい場合にも適用しやすい方法です。
ただし施工品質に性能が左右されやすいため、経験豊富な専門業者に依頼し、施工後には性能確認を行うことが望まれます。
| 部位 | 改修方法 | 効果の目安 |
|---|---|---|
| 窓 | 内窓設置、複層・三層ガラス化 | 冷気流入を大幅に減らし、体感温度を改善 |
| 天井 | 断熱材の厚み増し敷き | 暖房効率の向上、室温の安定 |
| 床 | 床下断熱材の追加や隙間補修 | 足元の冷えを軽減し、冷輻射を緩和 |
| 壁 | リフォーム時の断熱補強 | 外気の影響を減らし、居室全体の快適性を向上 |
このように、断熱改修は「窓→天井→床・壁」と段階を踏むことで効率良く進められます。
追加断熱の際には、厚さや素材の性能値だけでなく、防露や気密の確保も含めた総合設計を意識することで、より確実に快適な住環境を実現できます。
住宅の断熱性能を理解するためには、単純に数値を比較するのではなく、外皮の設計思想や施工の考え方を総合的に把握することが大切です。
ヘーベルハウスはALC外壁材とフェノールフォーム系断熱材を重ねる二重の断熱構造を採用しており、外壁そのものの断熱性に加えて、高性能な材料で熱損失を抑える設計思想が明確に示されています。
一方で積水ハウスは、天井から壁、床までを連続的に断熱材で包み込み、断熱ラインの切れ目を減らすアプローチを取っています。
また、トヨタホームは外張り断熱と充填断熱を併用する「ハイブリッド型構法」で、熱橋を減らしつつ部位ごとの断熱強化を図っています。
断熱性能の指標として広く用いられるUA値(外皮平均熱貫流率)は、小さいほど熱が逃げにくいことを示します。
しかし、この値は建物の地域区分や窓面積、プランによって大きく変わるため、数値そのものをメーカー間で単純比較するのは適切ではありません。
実際の検討では、標準仕様とオプション設定、施工精度、窓やサッシの性能などを総合的に把握する必要があります。
| 観点 | ヘーベルハウス | 積水ハウス | トヨタホーム | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 外皮設計の思想 | ALC+フェノールフォームの二重構成 | 天井・壁・床を連続的に包む | 外張り+充填のハイブリッド | 設計思想の違いが比較の前提 |
| 主な断熱材 | ネオマフォーム(λ=0.020) | 高性能グラスウール等 | XPS+充填材併用 | 部位ごとの適材適所がポイント |
| 窓・サッシ | 樹脂や高性能複合サッシ | SAJサッシなど高断熱仕様 | 仕様選択幅が広い | 窓性能が体感に直結 |
| 到達性能の目安 | ZEH基準クリア(UA値0.6以下事例) | ZEH実績多数 | 地域別に最適化したUA値 | プラン依存で数値は変動 |
このように、断熱性能は「数値の優劣」で判断するのではなく、それぞれのメーカーがどのような素材を選び、どのような構法で全体を組み立てているかを理解したうえで、地域や生活スタイルに適した仕様を見極めることが選択の鍵となります(出典:国土交通省「住宅における外皮性能(UA値等)」 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001443042.pdf )。
断熱材には繊維系と発泡プラスチック系があり、それぞれに適した使い方があります。繊維系の代表であるグラスウールは、施工性とコストのバランスが良く、適切な防湿層設計を組み合わせれば壁や天井の充填に安定して利用できます。
ロックウールは断熱性能に加えて耐火性や高温時の寸法安定性に優れており、防火計画を考慮する部位に適しています。
発泡プラスチック系では、フェノールフォームがλ=0.020W/(m・K)という非常に小さな熱伝導率を持ち、薄くても高い断熱性能を確保できる点が特徴です。
押出法ポリスチレンフォーム(XPS)は吸水性が低いため、床下や外張り断熱に好適です。ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)は寸法安定性や長期性能が示されており、外張り断熱や基礎断熱に広く利用されています。
吹付け硬質ウレタンフォームは現場で発泡させて継ぎ目のない断熱層を作れるため、気密性に寄与しますが、施工品質の管理が性能維持の鍵を握ります。
| 種別 | 主な材料 | 熱伝導率λ(W/m・K) | 特徴 | 適用部位 |
|---|---|---|---|---|
| 繊維系 | グラスウール | 0.035~0.038(高性能品0.032) | 価格・施工性のバランス良好 | 壁・天井の充填断熱 |
| 繊維系 | ロックウール | 0.036~0.038 | 耐火・寸法安定性に優れる | 防火を求める壁や天井 |
| 発泡系 | フェノールフォーム | 0.020 | 高断熱性能、薄く施工可能 | 外張り・屋根・壁 |
| 発泡系 | XPS | 0.028~0.040 | 吸水性が低く耐久性良好 | 床下・基礎周り |
| 発泡系 | EPS | 0.034~0.041 | 寸法安定性・長期性能 | 外張り・基礎断熱 |
| 発泡系 | 硬質ウレタンフォーム | 約0.024~0.028 | 継ぎ目のない施工が可能 | 壁・屋根・床全面 |
断熱材を選ぶ際には、単に熱伝導率の数値を追うだけではなく、防火・透湿の要件や施工性、部位ごとの湿潤条件を併せて考えることが必要です(出典:断熱建材協議会「省エネ基準(仕様基準)断熱材・窓等 製品リスト」 https://dankenkyou.com/energy_saving.html)。
- 断熱材の「不燃」と「難燃」は同じ意味ですか?
- 建築基準法では「不燃」「準不燃」「難燃」といった区分が明確に分けられており、それぞれ性能要件が異なります。製品ごとの認定情報を確認することが求められ、カタログ記載だけで判断するのは避けるべきとされています(出典:国土交通省「構造方法等の認定」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000042.html )。
- 断熱材を厚くすると結露の心配は増えますか?
- 厚みを増すと温度差が大きくなるため、防湿層の位置や透湿抵抗のバランス設計が不可欠です。断熱材の連続性、気密性、換気計画を組み合わせることで内部結露のリスクを抑えることができます。
- 床が冷えるのは断熱材が不足しているからですか?
- 床断熱を採用していても、配管まわりの隙間や気流止めが不十分だと冷気が入り込む場合があります。点検や補修、内窓の併用、放射暖房との組み合わせで改善効果が期待できます。
- 窓を高断熱仕様にすれば、壁の断熱は強化しなくてもよいですか?
- 窓の改善は大きな効果をもたらしますが、外皮全体のバランスを無視すると効果は限定的になります。屋根・壁・床・窓を総合的に見て段階的に改善することが推奨されています。
- どの断熱材が最も優れていますか?
- 一律に「これが最良」とは言えません。部位ごとの条件、防火要件、コスト、施工方法など複数の要因を考慮して適材適所で選ぶことが現実的です。公式仕様や一次情報を確認し、自邸の条件に合わせて選定根拠を残すことが信頼できる判断につながります。
ヘーベルハウスの断熱材については、入っていないのではという誤解が生じやすいものの、実際には外壁や屋根、床下など各部位ごとに適切な断熱材が組み込まれています。
外壁のALCや高性能断熱材のネオマフォーム、床下の複合断熱構造などが一体となることで、見えない部分で住まい全体を快適に保っています。
こうした仕組みを理解することで、安心感を持って暮らせることが分かります。
また、築年数や仕様の違いによって体感が変わることもあります。寒さを感じる場合は、窓や床下の気密、施工精度などを確認し、必要に応じて追加の断熱改修を行うことが有効です。
窓の改善や天井への断熱材追加は投資対効果が高く、優先的に検討できる方法です。さらに、最新の高性能断熱材を活用することで、省エネ性や快適性を大きく高めることも可能です。
断熱性の比較においては、単純な数値ではなく、それぞれのメーカーが採用する設計思想や材料の特性を理解することが欠かせません。
家族のライフスタイルや地域特性に合った断熱仕様を見極めることが、長期的な快適性につながります。
最後に、断熱材の種類や特徴を知っておくことも大切です。繊維系・発泡系それぞれの特性を踏まえ、部位ごとの条件に合うものを選ぶことが、費用対効果の高い住まいづくりに直結します。
要点を整理すると以下のようになります。
- ヘーベルハウスは部位ごとに適切な断熱材を採用し、誤解されやすいが高い断熱性能を備えている
- 寒さを感じたときは、窓や床下などの弱点を確認し、段階的な改修で改善可能
- 他メーカーとの比較では、数値だけでなく設計思想や材料の特性を考慮することが大切
- 断熱材の種類や特徴を理解し、条件に合う選択をすることが長期的な快適性と省エネにつながる
断熱材は見えない存在だからこそ、その役割を正しく理解することが大切です。適切な知識と判断で、快適で安心できる住まいづくりを実現していきましょう。
とはいえ、「自分の家にはどの断熱仕様が合うのか」「他メーカーと比較して本当に安心できるのか」と迷う方も多いはずです。
そんなときは、複数の住宅会社から無料で間取りプランや資金計画を提案してもらえるタウンライフ家づくりを活用するのが便利です。
自宅にいながら複数社のプランを比較でき、断熱性能や仕様の違いもわかりやすく整理できます。
【PR】タウンライフ