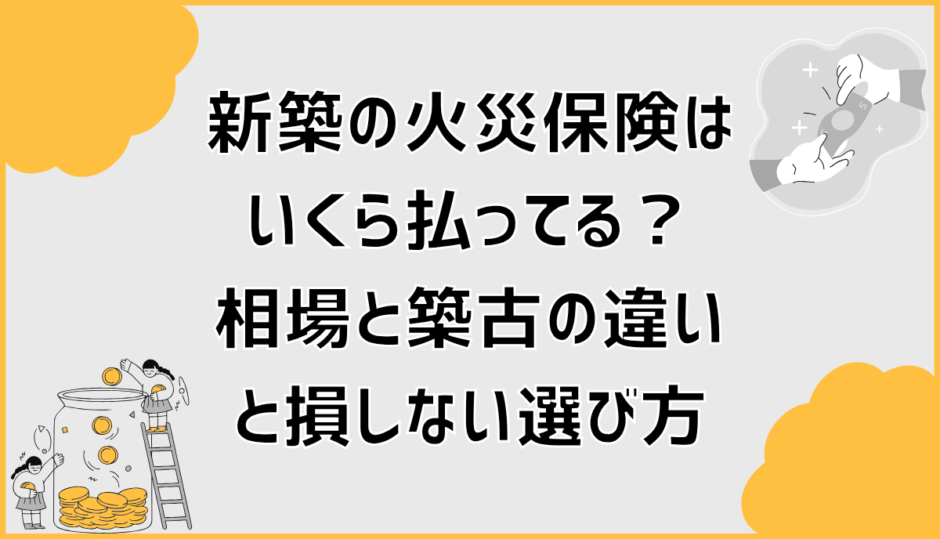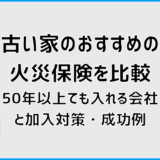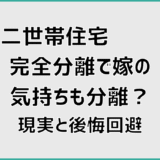この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
家を建てる計画が進むと、多くの方が火災保険について考え始めますが、特に火災保険はいくら払ってる新築の場合どれくらいが普通なのか、相場の基準が分からず不安を感じることがあると思います。
住宅ローンの手続きと同時に準備することが多いため、いつ入るのか、そもそもの必要性、そして正しい選び方が見えにくく、迷ってしまう場面もあるのではないでしょうか。
実際には、火災保険はいくら払ってる新築の金額は、建物の構造や地域の災害リスク、補償内容、さらに築古の住宅との違いなど、さまざまな要素で変わります。
同じ条件でも保険会社によって差が出るため、比較しないまま契約すると、本来必要な補償を逃してしまったり、逆に余計な費用を払ってしまう可能性もあります。
ここでは、火災保険の基本となる必要性や加入のタイミング、築古との違い、そして後悔しないための選び方の理由を、丁寧に整理してお伝えします。
読み進めていただくことで、あなたにとって最適な判断ができるようになり、安心して家づくりを進められるヒントになると思います。一緒に整理していきましょう。
- 新築の火災保険の相場と総額の考え方
- 築古との違いによる保険料や補償内容の変化
- 後悔しない火災保険の選び方と必要な補償の整理方法
- 複数社を比較する際の具体的な見るべきポイント
本記事では、保険会社の公式情報や公的データ、各種レビューサイトや利用者の声を参照し、筆者が独自に整理・構成しています。
口コミは個人の感想であり状況により異なる場合があります。内容は一般的な情報であり、最終判断は専門家へ相談してください。

新築の火災保険って、みんな一体いくら払っているのだろう。家づくり終盤になると多くの方が気になるテーマではないでしょうか。住宅ローンを利用する場合は加入がほぼ必須となり、火災保険は家と暮らしを守る大切な保障になります。
ただし、保険料は建物の構造や地域、補償内容によって大きく変わり、平均額だけでは判断しづらい面もあります。さらに、いつ契約を進めればよいのか迷う場面も多いはずです。
ここでは、実際の相場感や必要性、契約のタイミングまで分かりやすくまとめて解説していきます。
新築の火災保険はいくらになるのかは多くの方が悩む点です。住宅ローン利用時は加入がほぼ必須ですが、保険料は建物の構造や地域、補償内容によって大きく変わります。
目安として、木造100㎡の新築一戸建てで火災保険と地震保険をセットにし、5年契約・建物と家財をバランス良く補償した場合の総額は約10万〜20万円前後とされています。
補償を絞れば10万円を切ることもあり、広く取れば20万円を超えるケースもあります。これらはあくまで一般的な参考値であり、実際の金額は保険会社ごとの料率や割引制度によって変動するため、個別の見積もり確認が欠かせません。
新築の火災保険を考えるときは、「建物」と「家財」、「火災保険」と「地震保険」を分けて整理すると、相場感がつかみやすくなります。
新築の木造一戸建ての場合、建物の保険金額が2,000万円前後、家財が500万〜1,000万円程度に設定されることが多く、この組み合わせで5年契約にすると、火災保険単体で5万〜10万円前後、地震保険を加えると合計10万〜20万円程度というイメージです。
1年契約の場合は、契約期間が短いため割引が少なく、年間あたりの負担が相対的に高くなる傾向があります。
相場をイメージしやすいように、代表的なパターンを簡単に整理すると次のようになります。
| 建物構造・補償 | 期間 | 合計保険料の目安 |
|---|---|---|
| 木造・火災のみ・家財少なめ | 1年 | 約2万〜3万円 |
| 木造・火災+地震・家財あり | 1年 | 約3万〜4.5万円 |
| 耐火構造・火災+地震 | 1年 | 約1.8万〜3万円 |
| 木造・火災のみ・家財少なめ | 5年 | 約8万〜12万円 |
| 木造・火災+地震・家財あり | 5年 | 約10万〜20万円 |
| 耐火構造・火災+地震 | 5年 | 約8万〜15万円 |
いずれも標準的な新築一戸建てを想定した参考値であり、実際の見積もりでは地域の災害リスクや特約、割引条件などにより上下します。
相場はあくまで「スタートライン」の感覚としてとらえ、最終的な金額は必ず個別の見積もりで確認することが欠かせません。正確な情報は各保険会社や公式サイトを確認し、最終的な判断は専門家に相談することをおすすめします。
火災保険料は、建物の構造や所在地の災害リスク、保険金額、家財補償の有無、補償範囲、免責金額、契約年数など複数の要素で決まります。
特に構造による差は大きく、鉄筋コンクリート造(M構造)が最も安く、準耐火(T構造)、一般的な木造(H構造)の順に高くなる傾向があります。同じ条件でも木造は耐火構造より5年で数万円高くなるケースもあります。
また、長期一括払いは年払いや月払いより割安となりやすく、地域の災害リスクによっても大きく変動します。こうした仕組みを理解することで、保険料の根拠が把握しやすくなり、納得して契約できるようになります。
新築の保険料を考える際は、火災保険と地震保険を合計額で比較することが大切です。地震保険は火災保険にセットして加入する仕組みで、保険金額は火災保険の30〜50%の範囲で設定できます。
一般的には地震保険の負担が大きくなる傾向があり、火災保険だけなら5年で約10万円でも、地震保険を含めると20万円を超えるケースがあります。
合計額で見ないと想定以上の負担になることがあるため、5年など期間全体での総額として把握することが大切です。自宅の地震リスクや耐震性、預貯金とのバランスを考えながら保険金額や期間を調整すると、無理のない支払い計画につながります。
新築では間取りや設備選びが優先されやすく、火災保険は後回しになりがちですが、災害時に家計を守る大切な備えです。
火事だけでなく台風や落雷、水害など幅広い損害に備えることで、半壊・全壊などの大規模被害にも対応できます。
修繕費が数百万円から数千万円になる場合もあり、貯蓄だけで賄うのは厳しいケースが多く、生活再建の資金確保として重要な役割を持ちます。
補償内容や金額は住宅状況によって異なるため、契約前に必ず保険会社や専門家に相談しながら適切な補償範囲を検討することが推奨されています。
新築住宅で住宅ローンを利用する場合、多くの金融機関では火災保険への加入を融資条件としています。これは、火災などで建物が失われたとき、担保としての価値がなくなってしまうのを防ぐためです。
仮に保険に加入しておらず、家が全焼してしまった場合でも、ローンの返済義務だけは残ります。
一方で、火災保険に加入していれば、保険金によって建物の再建費用や修繕費用の一部をカバーできるため、ローン返済と再建費用を同時に抱えるリスクを軽減できます。
新築の契約段階では、住宅ローンの審査書類と一緒に火災保険の見積もり提出を求められることもあるため、早めに前提条件や必要な補償範囲を整理しておくと、スムーズに手続きが進みます。
火災保険は火事だけを補償するものではなく、落雷や爆発、台風・暴風、雹災、雪災、水災、盗難、破損など幅広いリスクに対応できる点が特徴です。
どこまでが基本補償で、どこからが特約扱いかは保険会社によって異なり、水災補償や免責金額の設定で保険料が大きく変わります。
地域の災害リスクに応じて水災補償を付けるべきか判断することも重要で、例えば河川沿いでは外すことが大きなリスクになる場合があります。
立地条件やハザードマップを確認し、補償の過不足が出ないよう専門家と相談しながら検討することで、安心感のある契約につながります。
新築の火災保険は、住宅の引き渡しと同じタイミングで補償がスタートするように契約するのが一般的です。そのため、引き渡し日が決まった段階で、逆算して準備を進めることが大切になります。
特に住宅ローンの実行日と引き渡し日が近い場合、金融機関から火災保険の加入証明書の提出を求められることも多く、直前になって慌てて検討する状況はできるだけ避けたいところです。
火災保険は、構造や補償内容によって保険料が大きく変わるため、事前に比較検討する時間を確保しておくと、納得度の高い選択につながりやすくなります。その意味でも、「いつ入るか」を考えることは、「どんな内容で契約するか」と同じくらい重要なポイントです。
火災保険の補償は、契約で決めた保険始期日から有効になります。新築の場合、多くは引き渡し日を保険始期日に設定し、その日から建物と家財に対して補償がかかるようにします。
もし契約が遅れて、引き渡し後に保険が始まるような状態になってしまうと、その空白期間に災害が発生した場合、補償を受けられないおそれがあります。
また、建築中の段階では、工事業者側が加入している工事保険などでカバーされていることが多いものの、引き渡し以降は所有者であるあなた自身の責任となります。
そのため、引き渡し日までに契約内容を固め、証券発行や住宅ローンとの連携も含めて準備しておくことが、安全なスタートにつながります。
見積もりをいつから始めるかについては、引き渡し予定日の1か月前くらいを目安にすると、比較検討の時間を確保しやすくなります。
この時期には、建物の構造区分や延床面積、所在地など、見積もりに必要な情報がほぼ確定していることが多く、複数社から条件をそろえて見積もりを取ることができます。
1か月あれば、インターネットの一括見積もりサービスや保険ショップ、金融機関の紹介など、複数のルートを使って比較することも可能です。
逆に、引き渡し直前の数日で慌ただしく決めようとすると、補償内容を十分に吟味できず、過剰な特約を付けてしまったり、本来必要な補償を外してしまったりするリスクが高まります。
余裕を持って動くことが、結果として保険料の適正化と安心感の両方につながります。

新築の火災保険を選ぶとき、多くの方が「どれを選べば正解なのか」「この金額は妥当なのか」と迷いや不安を感じるようです。実際、火災保険は住宅の状態や築年数によって必要な考え方が違い、築古の住宅では条件が厳しくなる場合もあります。
また、補償内容や保険料のバランスをどう取るかで満足度が大きく変わりますし、同じ条件でも保険会社によって金額が大きく異なることも珍しくありません。
ここでは、新築と築古の違いの理解、後悔しない選び方、そして複数社を比較する必要性について、やさしく整理して解説していきます。納得の保険選びの参考にしていただければ嬉しいです。
火災保険は、新築か築古かによって考え方が大きく変わります。新築の場合は、建物の状態が良く、耐震・耐火性能も現在の基準に合わせて設計されていることが多いため、保険料が比較的抑えられるケースが目立ちます。
一方、築年数の古い住宅では、老朽化や基準の違いから、損害リスクが高いと判断され、保険料が高くなったり、そもそも加入条件が厳しくなったりする場合があります。
これから新築を建てる方にとっても、「将来築古になったとき火災保険がどう変化していくのか」を知っておくことは大切です。更新のタイミングや見直しのポイントがイメージしやすくなり、長期的なランニングコストを考えた家づくりにつながります。
築古住宅の保険料はどれくらい変わるのか、より詳しい相場を知りたい方はこちらの記事でまとめていますので、参考にしてみてください。
火災保険の補償額の考え方には、大きく分けて「再調達価額(新価)」と「時価」があります。新築や築浅の住宅では、同等の建物を新たに建て直すために必要な金額を基準とする再調達価額で契約するケースが一般的です。
一方、築年数が進むと、経年劣化を反映した時価ベースで評価されることがあり、同じ損害が発生しても、受け取れる保険金額が小さくなる場合があります。
例えば、老朽化した屋根が台風で損傷したケースで、損害の一部が経年劣化と判断されると、修理費用の全額が補償されないこともあります。
自宅が再調達価額で評価されているのか、時価で評価されているのかによって、災害時の実際の負担額が変わってくるため、契約内容を確認しておくことが欠かせません。
わからない場合は、保険会社や専門家に評価方法を確認し、必要に応じて見直しを検討していくことが勧められています。
築古住宅では、建物の老朽化や耐震性の不足などから、損害発生リスクが高いと見なされる傾向があります。その結果、新築に比べて火災保険料が高くなる、あるいは一定の条件を満たさないと引き受けを断られるケースも出てきます。
特に、築30年を超える木造住宅などでは、保険会社ごとに引き受け方針が異なり、会社によっては割増保険料や補償範囲の制限が設けられる場合があります。
こうした事情から、築古住宅で火災保険を検討する際には、1社だけでなく複数社から見積もりを取り、条件を比較することが大切になります。
同じ築年数・構造でも、会社によっては耐震診断の有無や改修状況を評価し、割引を適用してくれる場合もあるため、情報を集めて選択肢を広げることが、加入の可能性を高めることにつながります。
築古の住宅では、「老朽化による損傷」と「災害による損傷」の線引きが難しくなることが多く、その結果、補償範囲に制限が設けられることがあります。
例えば、長年の雨風で傷んだ屋根から雨漏りが発生している場合、台風が引き金になっていても、主な原因が経年劣化だと判断されれば、保険金の支払い対象外となる可能性があります。
このようなトラブルを避けるためには、引き渡し時やリフォームのタイミングで建物の状態をしっかり確認し、明らかな不具合は事前に修繕しておくことが望ましいとされています。
また、保険の約款や重要事項説明書には、経年劣化や維持管理不足による損害が補償対象外であることが明記されていることが多いため、加入前に内容をよく読み、疑問点は必ず質問しておくと安心です。
古い家の場合は考え方や保険料が大きく変わります。築年数の影響や比較のポイントをまとめた記事も参考にしてみてください。
火災保険は、一度契約すると5年程度は同じ内容で継続することが多く、「なんとなく選んでしまった」結果が長く続いてしまうこともあります。
後悔を避けるためには、最初に「何を守りたいのか」「どのリスクに重点を置くのか」を整理し、そのうえで保険料とのバランスを取っていくことが大切です。
特に新築の場合は、建物だけでなく、新しく購入した家具や家電などの家財も一度にそろうため、家財補償をどう設定するかがポイントになります。
全てを完璧に守ろうとすると保険料が膨らみますが、補償を削りすぎると、いざというときに十分な保険金を受け取れない可能性があります。
火災保険を選ぶ際には、まず守りたい対象とリスクの優先順位を整理するところから始めると検討しやすくなります。
例えば、「建物の再建資金を最優先にするのか」「家財も含めてトータルで生活再建をカバーしたいのか」「水害や地震など特定のリスクに重点を置きたいのか」といった視点です。
優先順位を明確にすると、必要な補償とそうでない補償が見えやすくなります。
河川から離れた高台の住宅であれば、水災補償の必要性は相対的に低くなるかもしれませんし、逆に河川沿いや低地に建つ住宅では、水災を外すことは大きなリスクにつながります。
ハザードマップなど客観的な情報を確認しながら、家族で優先順位を話し合っておくと、納得度の高い選択につながります。
火災保険の商品によっては、さまざまな特約がセットになっていることがあります。
庭木や門扉、カーポート、携帯品、日常生活賠償など、一見すると心強く感じられますが、すべてが自分たちの生活に必須とは限りません。生活スタイルによっては、ほとんど使う可能性がない補償が保険料を押し上げている場合もあります。
一つひとつの特約について、「自宅の条件や生活スタイルに照らして本当に必要か」を確認し、不要と判断したものは外していくことで、保険料を無理なく抑えられます。
その際、「万が一のときに自己負担できるかどうか」をイメージしながら取捨選択すると、過度に不安にならずに整理しやすくなります。正確な判断が難しい場合は、保険会社や専門家に相談しながら一緒に確認していく方法も有効です。
火災保険では、自己負担額にあたる「免責金額」を設定することで、保険料を調整できる場合があります。
免責金額を高めに設定すると、小さな修繕費用は自己負担になりますが、その分、保険料を抑えやすくなります。例えば、免責0円のプランから免責5万円のプランに切り替えると、年間の保険料が下がるケースがあります。
どの程度の免責金額が適切かは、家計の状況や貯蓄の余裕によって変わります。
数万円程度であれば自己負担できるのか、それともできるだけ自己負担を少なくしたいのかを検討し、複数パターンの見積もりを比較すると、負担感と安心感のバランスが見えやすくなります。
免責金額の設定を含めて、最終的な判断は専門家と相談しながら進めると安心です。
火災保険は、同じような補償内容に見えても、保険会社ごとに保険料や特約、割引制度が大きく異なります。
そのため、一社だけの見積もりで即決してしまうと、本来もっと条件の良いプランを選べた可能性を見落としてしまうことがあります。複数社を比較することで、保険料の相場感だけでなく、各社の特徴や自宅との相性も把握しやすくなります。
特に新築の場合、構造や耐震性能、防犯設備などによって適用される割引が変わることが多く、「ある会社では割引対象になるが、別の会社ではならない」といった違いもあります。こうした差を確認するうえでも、比較は欠かせないプロセスといえます。
ここまで読んで、どの保険会社が自分に合うのか迷ってしまうと感じる方もいるかもしれませんね。新築だからこそ、できれば損をせずに納得感のある選び方をしたいと思う方は多いようです。
複数社の見積もりをまとめて比較できるサービスを使うと、保険料の違いや自宅に合うプランが一目で分かり、時間をかけずに自信を持って決められるようになります。
保険料は、損害保険料率算出機構が公表する参考純率などをもとに、各社が独自の付加保険料や割引制度を加味して決定しています。
そのため、同じ建物構造・所在地・保険金額・補償内容で見積もりを取っても、会社によって数万円単位の差が出ることは珍しくありません。
また、構造区分の判定や耐震等級・省令準耐火構造などに対する割引の扱いが会社によって異なるケースもあります。自宅がどの構造区分にあたるのか、どの割引が使えるのかを確認しながら、複数の見積もりを見比べることで、「なぜこの会社は安いのか・高いのか」を理解しやすくなります。
複数社の火災保険を比較する方法としては、主にインターネットの一括見積もりサイト、保険ショップや乗合代理店、金融機関の紹介窓口、各社の公式サイトからの個別見積もりなどがあります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、どれが自分に合うかは、重視したいポイントによって変わります。
一括見積もりサイトは、同じ条件で複数社の見積もりを一度に取得できるため、相場感をつかむのに向いています。
保険ショップや代理店では、対面やオンラインで相談しながら比較できるため、補償内容の細かな違いを説明してもらえる点が魅力です。
時間に余裕があれば、最初に一括見積もりで全体像をつかみ、そのうえで気になる会社を絞り込んで詳しく相談する流れも検討しやすくなります。
おすすめの比較方法
効率と情報量のバランスを考えると、最初のステップとしては、インターネットの一括見積もりサービスを利用して、複数社の保険料と大まかな補償内容を一覧で確認する方法が利用しやすいと感じる方が多いようです。
建物構造や所在地、希望する補償範囲などを入力するだけで、いくつかの保険会社のプランを比較できるため、「自宅条件だとどの程度の保険料帯になりそうか」を短時間で把握できます。
そのうえで、候補に挙がったプランについて、保険ショップや専門家に相談しながら細部を詰めていくと、補償の重複や不足を避けやすくなります。
実際に見積もりを取らないと本当の適正額は分かりません。複数社を比較して納得して選びたい方は、こちらの記事でまとめていますので、参考にしてください。
どうでしたか?ここまで読んでいただき、本当にありがとうございます。
新築の火災保険はいくら払ってるのかは、多くの方が迷いや不安を感じやすいテーマです。建物の構造や地域、補償内容の違いによって金額が変わるため、誰にとっても正解がひとつではありません。
だからこそ、相場や保険料が決まる理由を理解したうえで、自分の家に合った安心できる契約を選ぶことが大切だと感じます。
この記事では、火災保険の相場や必要性、新築と築古で考え方が変わるポイント、そして後悔しない選び方について整理してきました。すべては、あなたが納得したうえで判断できるようにするためです。
もう一度、この記事で押さえたいポイントをまとめると次のとおりです。
- 新築の火災保険の相場は条件によって大きく変わる
- 火災保険は家と暮らしを守るために必要な備え
- 加入のタイミングは引き渡し前の準備が安心
- 複数社で比較することで納得感のある選択ができる
火災保険はいくら払ってる新築の検討は大きなお金が関わる選択ですが、知識を持てば不安は小さくなります。あなたの家づくりが後悔のないものであるよう、少しでも参考になれば嬉しいです。読んでくださり、ありがとうございました。