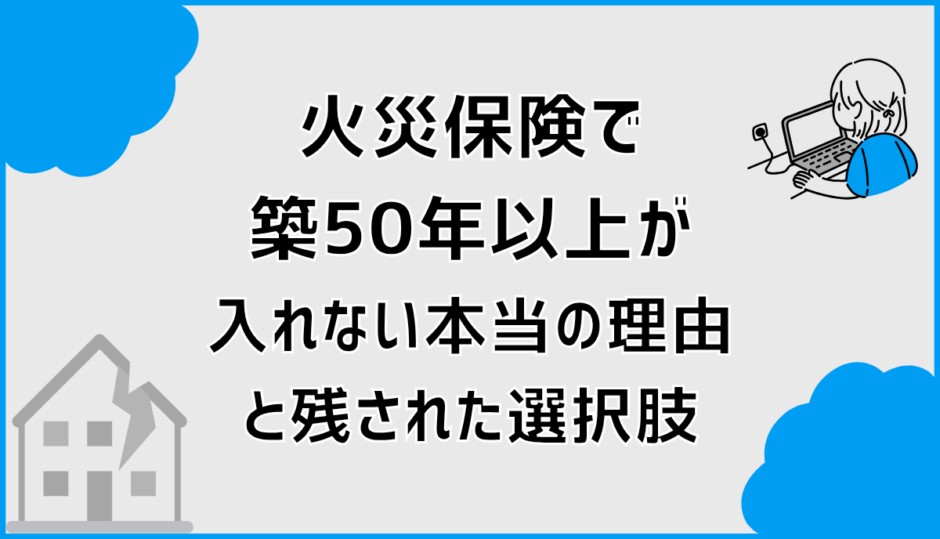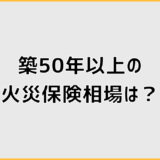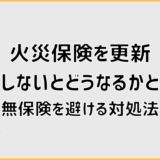この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
築50年以上の家で火災保険の更新や新規加入を進めようとしたとき、火災保険で築50年以上の家は入れないのかと言われて戸惑ったという声をよく耳にします。
申し込みの段階で入れないと告げられたり、更新時に突然加入できないと説明されると、とても不安になりますよね。これまで大切に住んできた家だからこそ、守る手段がなくなるのではと心細くなったり、焦りを感じる方も多いと思います。
ただ、慌てなくて大丈夫です。築50年以上だから絶対に火災保険に入れないわけではありません。
入れないと言われる背景には、老朽化や管理状況、空き家期間など、複数の理由が関係している場合があり、築年数だけで判断されているとは限りません。
審査で重視されるポイントを整理し、適切な対策を取れば、突破方法が見えてくるケースもあります。
ここでは、火災保険で築50年以上の家が入れないと言われる理由をわかりやすく整理し、実際に入れる可能性を広げる現実的な対策や、どうしても厳しい場合に考えたい選択肢まで丁寧にまとめています。
また、同じ悩みを持つ方からのよくある質問にも触れながら、迷わず前に進むためのヒントを共有していきます。
あなたの家を守る方法は、まだ残されています。いっしょに最善の道を探していきましょう。
- 火災保険で築50年以上の家が入れないと言われる主な理由
- 築50年以上でも加入できた実例と突破のための具体的なポイント
- 加入を前提にした現実的な対策と条件調整の方法
- どうしても入れない場合に検討できる選択肢と備え方
本記事では、保険会社の公式情報や公的データ、各種レビューサイトやユーザーの声を参照し、筆者が独自に整理・構成しています。
口コミや体験談は状況により異なります。内容は一般的な情報であり、最終判断は必ず各社公式情報をご確認ください。

築50年以上の家に住んでいると、「火災保険にもう入れないのでは」と心配になる方が多いようです。実際、近年は自然災害の増加や修繕費の高騰により、保険会社の審査が以前より厳しくなり、築古住宅が断られるケースも増えています。
ただ、築50年だからといって必ず加入不可になるわけではありません。建物の状態や管理状況によって評価が変わり、工夫次第で通過できた例もあります。
ここでは、加入が難しくなる背景や断られる理由、突破の方法、さらに保険料が高くなりやすい仕組みまで、順を追って整理していきます。
築50年以上でも火災保険に必ず入れないわけではありません。判断は築年数だけでなく、屋根・外壁・配管・電気設備などの状態、管理状況、空き家期間といった要素を総合的に見て行われます。
近年はネット型保険で機械的に「対象外」と表示される例が増えていますが、これは現地調査がないため入口が厳しいという仕組みによるものです。
ネット型で断られても、代理店型や共済で加入できる可能性があります。断られた際は理由を確認し、複数社へ相談することで選択肢が広がります。複数社に相談すること自体が、築古住宅で火災保険を検討するうえでの基本戦略と言えます。
入れる会社を知るだけでも道が開けます。築古住宅でも契約できた成功パターンを比較した記事をこちらにまとめていますので参考にしてみてください。
築50年以上の住宅でも、日常的に手入れがされ、設備の更新や部分的なリフォームが行われていれば、保険会社から「きちんと管理された建物」と評価される場合があります。
審査の際に見られるのは、単なる築年数だけでなく、屋根や外壁の防水状態、配管・配線の劣化具合、シロアリ被害の有無、耐震性など、事故につながりやすいポイントです。
例えば、屋根の葺き替えや外壁塗装、防水工事、給水管・排水管の更新、分電盤や配線の改修など、リスクの高い部分に手が入っていると、築年数が古くても評価が上がる傾向があります。
過去の工事の契約書や保証書、施工写真などがあれば、審査時の説得力が増します。申し込みの前に、これらの資料を一度整理しておくと話がスムーズです。
一方で、築古住宅で火災保険に入れない、あるいは更新時に条件が厳しくなったという声が増えているのも事実です。背景には、台風や豪雨など自然災害の多発による保険金支払いの増加、建築費の高騰による修理・再建コストの上昇があります。
保険会社から見ると、築年数が大きいほど事故発生時の損害額が膨らみやすく、収支の安定性が揺らぎやすくなります。
特に木造で劣化が進んだ住宅は、火災や漏水のリスクが高いと判断されやすく、保険会社ごとの審査基準も年々シビアになっています。更新のタイミングで「これまで通りの条件では継続できない」「免責金額を上げてほしい」「契約期間は1年のみ」などと言われるケースもあるようです。
安心して備えるためには、現行契約の条件や満期日を早めに確認し、余裕を持って他社の見積もりを取っておくことが欠かせません。
厳しくなっているとはいえ、築50年以上の住宅で加入できている例も多くあります。共通しているのは、保険会社に対して建物の情報を丁寧に伝えている点です。
具体的には、屋根・外壁・配管・電気設備などの写真を複数角度から用意し、いつどのような修繕を行ったかを一覧でまとめたうえで、代理店を通じて審査にかけてもらう方法です。
また、補償範囲を調整することで承認されたケースも見られます。
たとえば、建物と家財のフルセットではなく家財のみの契約にする、風災・水災など特定の補償を外す、自己負担額(免責)を高めに設定するなど、リスクと保険料のバランスを取りながら契約内容を絞り込むやり方です。
情報提供の量と質が増えるほど、築年数が古くても「引き受けられるかもしれない」と判断される余地が生まれます。築年数だけであきらめず、できる準備を一つずつ整えていくことが現実的な一歩になります。
築50年以上の住宅が火災保険で断られやすいのは、単に古いからというよりも、「事故が起きたときに被害が大きくなりやすい」「故障や不具合が見えにくい」といったリスクが重なりやすいからです。
保険会社は、過去の膨大なデータから築年数ごとの事故発生率や支払い額を分析しており、築古ほど損害率が高くなる傾向が強まっています。
さらに、老朽化した建物は小さな不具合が連鎖しやすく、一度トラブルが起きると補修範囲が広がりがちです。木造であれば、屋根や外壁からの雨水侵入、シロアリ被害、古い配線からの出火などが代表的なリスクとなります。
空き家や使用頻度の低い古民家では、日常的な目配りが効きにくく、被害の発見が遅れやすい点も問題になります。
築年数が進むと、配管の腐食による漏水、電気配線の絶縁劣化によるショート、基礎のひび割れや不同沈下による構造不良など、さまざまなトラブルが起きやすくなります。
こうしたトラブルは、火災や水濡れ事故のきっかけとなり、結果として保険金支払いのリスクを押し上げます。また、1981年以前に建てられた旧耐震基準の建物は、地震時の倒壊リスクが高いとされています。
過去に耐震診断を受けている場合や、耐震補強工事を行った履歴があれば、これも審査の評価に影響することがあります。
診断書や工事報告書、補強部分の写真などを揃え、建物がどの程度の耐震性能を持っているのかを説明できるようにしておくと、不安の軽減につながります。
空き家や古民家は、火災保険の引き受け条件が一段と厳しくなる傾向があります。人が住んでいない期間が長いと、日々の換気や清掃が行われにくく、湿気やカビ、シロアリ、ネズミなどの被害が進行しやすくなります。
誰も気づかないうちに配管が破損して水漏れが続いていた、漏電が起きていた、といったケースも想定されます。
昔ながらの木材や紙、藁などをふんだんに使った古民家では、燃え広がりやすさも懸念材料になります。
このため、「居住用として常時使用しているか」「定期的に点検・清掃をしているか」「防犯・防火の対策はどうか」といった管理状況の確認が重視されます。
定期的に訪れて清掃していることがわかる写真や、点検記録を提出できれば、評価が柔らぐ場合もあります。
ネット完結型の火災保険は、申し込みの簡単さや保険料の安さが魅力ですが、築古住宅にとっては入口のハードルが高くなりがちです。
現地調査を行わない分、築年数や構造、所在地などの入力情報から自動的に可否を判定する仕組みになっているため、一定以上の築年数になると一律で「対象外」となる設計が多いからです。
そのため、築50年以上の住宅でネット型を試してみたところ、画面上で早々に申し込み不可になり、「やはりどこも無理なのか」と感じてしまう方もいます。
しかし、現地写真や工事履歴をもとに個別判断してくれる代理店型の保険会社であれば、同じ建物でも検討のテーブルに乗ることがあります。築古住宅では、「まずは相談型の窓口を利用する」というルート選びも、大きなポイントになります。
火災保険に入れないと言われても、選び方次第で道が開けるケースもあります。具体的な成功例と保険選びのコツはこちらの記事にまとめていますで、参考にしてみてください。
築50年以上の住宅でも、火災保険への加入をあきらめる必要はありません。保険会社が知りたいのは、「この家がどれくらい手入れされているのか」「どこまでリスクを減らす工夫がされているのか」という点です。
ここを丁寧に伝えることで、加入の可能性が見えてくる場合があります。
その際、建物の状態説明とあわせて、契約条件の調整も選択肢になります。補償範囲を絞ったり、免責金額を高めに設定したりすることで、保険会社にとってのリスクを抑え、引き受けのハードルを下げる考え方です。
また、リフォームや住宅診断の結果を提出して、安全性が高まっていることを示すと、より前向きな判断が得られやすくなります。
加入できているケースとしては、まず建物の状態が比較的良好なパターンがあります。
屋根の防水性能が保たれている、外壁のひび割れが少ない、配管や電気設備を一定の周期で更新しているなど、事故のきっかけとなりやすい部分の手入れが行き届いている住宅です。
このような住宅では、築50年以上でも審査をクリアしている例があります。
また、補償を限定することで承認されたケースも見られます。
例えば、建物の補償はあきらめて家財のみの契約にする、風災や水災の補償を外して火災中心のプランにする、といった形です。
自宅の立地や生活スタイルによって、「何を守りたいのか」「どのリスクまで備えるのか」は変わります。自分にとって優先度の高い補償を整理し、それに合わせてプランを組み立てることが大切になります。
火災保険は保険会社ごとに引き受け基準や料率が異なります。そのため、ある会社では断られた物件が、別の会社では条件付きであれば受け入れ可能となることもあります。
築古住宅の場合は、特に1社だけで判断せず、最低でも3社程度の見積もりを取り、補償内容と保険料、免責条件を比較することが現実的です。
加入しやすくするための調整としては、自己負担額を一定以上に設定する、契約期間を短期にする、特定の補償を外すなどがあります。
もちろん、補償を削りすぎると「いざというときに足りない」ということになりかねませんので、削る部分と残す部分の線引きが重要です。わからない点は代理店や窓口で質問し、あなたの家に合うバランスを探っていきましょう。
どの保険会社に相談して比較すれば良いか分からないと感じる方も多いと思います。
一括見積もりを活用することで、加入できる可能性を確認しながら、無理なく比較できます。サービスのメリット・デメリットや体験談もまとめていますので、参考にしてみてください。
民間の損害保険会社での加入が難しい場合でも、共済という別ルートが残されている場合があります。
都道府県民共済、こくみん共済coop、JA共済などの相互扶助型の制度は、商品によって築年数への考え方が異なり、比較的築古に寛容なプランも見られます。
ただし、すべての共済が築年数不問というわけではなく、用途や管理状況など独自の条件が設けられている点には注意が必要です。
共済はあくまで組合員どうしの助け合いを前提とした仕組みであり、加入対象者や補償範囲、掛金の考え方も民間保険とは異なります。
検討する際は、パンフレットや公式サイトで補償内容を確認し、わからない点は窓口で質問して整理しておきましょう。
フルリフォームまでは難しくても、リスクの高い箇所だけを優先的に修繕することで、保険会社の評価が変わるケースもあります。
特に効果が大きいとされるのが、屋根・外壁の防水性能回復、雨漏り箇所の修理、古い分電盤や露出配線の更新などです。
火災や水漏れ事故と直結しやすい部分に手を入れることで、「事故の可能性を下げる努力をしている住宅」と評価されやすくなります。
小規模な工事であっても、見積書や領収書、施工後の写真を保管しておき、申し込み時に資料として提出すると説得力が増します。
リフォーム費用の負担とのバランスを見ながら、どこまで手を入れるかを検討していくとよいでしょう。費用面については、最終的な判断をする前に、施工会社や専門家にも相談することをおすすめします。
加入の可能性を高めるために、どこを修繕すべきか、どの順番で動くべきかを知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
築50年以上の住宅で見積もりを取ると、「思っていたより保険料が高い」と驚く方も少なくありません。ここで押さえておきたいのは、「加入の可否」と「保険料がいくらになるか」は別の問題だという点です。
入れるかどうかは審査の話であり、金額が高くなるかどうかは料率の話になります。この二つを分けて考えると、判断がしやすくなります。
火災保険の保険料は、建物の構造、所在地、築年数、補償範囲、保険金額、免責金額などをもとに計算されます。築年数が大きくなると、事故の発生確率や損害額が相対的に高くなるとみなされ、結果的に料率が上がる方向に働きます。
加えて、近年は建築資材や人件費の高騰により、修理や建て替えにかかる費用自体が高くなっている点も、保険料上昇の背景として押さえておきたいところです。
火災保険の料率は、過去の統計データをもとに設定されています。火災、風災、水災、盗難など、さまざまな事故の発生頻度や平均的な支払い額を分析し、地域や構造ごとのリスクに応じて保険料が決まる仕組みです。
築古住宅は、配管・配線トラブルや雨漏りなどの事故が発生しやすく、修繕範囲が広がりやすいことから、全体として損害率が高くなりやすいとされています。
また、再建築費ベースでの評価では、「同じ家を今建て直すといくらかかるか」を基準に保険金額を設定することが一般的です。
建築費が上がっていれば、その分だけ必要な保険金額も増え、保険料も高くなります。こうした仕組みから、築50年以上の住宅では、築浅と比べて保険料が高くなるのは避けにくい傾向にあります。
加入できるかどうかと、いくらになるかは、判断のフェーズが異なります。まずは審査を通過できるかどうかが第一関門であり、その後に複数社の見積もりを比較して保険料や補償内容を検討する、という流れで考えると整理しやすくなります。
保険料が高いからといって、その商品が必ずしも悪いとは限りません。補償範囲が広い、免責金額が低い、オプションが手厚いなどの理由で、結果として保険料が高くなっているケースもあります。
一方で、安さだけを重視して補償を削りすぎると、いざというときに「思っていたより支払われない」ということにもなりかねません。複数社の条件を見比べながら、保険料と補償内容のバランスを確認していくことが欠かせません。
費用に関する情報は、あくまで一般的な目安にすぎません。正確な金額や条件については、各保険会社や共済の公式サイト、パンフレットなどで直接確認し、最終的な判断は専門家にも相談しながら進めてください。
保険料や補償の比較を整理することで、加入判断がとてもスムーズになります。まずは全体像をつかみたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

火災保険の見積もりや更新で「築年数が古いので引き受けできません」と言われると、とても不安になりますよね。特に築50年以上の住宅では、思い入れのある家だからこそ、どうしたら良いのか迷ってしまう方が多いようです。
ですが、断られたからといって、すぐに諦める必要はありません。まずは理由を整理し、次に取れる選択肢を冷静に確認していくことが大切です。
ここでは、断られた際に最初に確認すべきポイント、どうしても入れない場合の現実的な選択肢、そして多く寄せられる疑問への回答をまとめました。行動の順序を知ることで、次に進むヒントが見つかるはずです。
火災保険の申し込みや見積もりで「築年数や建物の状態を理由にお引き受けできません」と言われると、とても不安になります。
ただ、そのまま落ち込んでしまう前に、まずは「なぜ断られたのか」をできるだけ具体的に言語化しておくことが、次の一手につながります。理由が整理できれば、対策を打てる余地も見えてきます。
断られたときは、担当者の説明をよく聞き、可能な範囲でメモを取っておきましょう。
築年数そのものが基準を超えていたのか、屋根や外壁の劣化が指摘されたのか、空き家期間が長いからなのか、あるいは過去の保険金請求歴が影響しているのかなど、理由はいくつかのパターンに分かれます。
感覚的に「古いからダメだった」とまとめてしまうと、具体的な対策が立てにくくなります。
「築年数の上限を超えていた」「屋根からの雨漏りがあり、修繕を条件にしても難しいと言われた」「空き家扱いとなり、専用のプラン以外では引き受けられないと言われた」など、できるだけはっきりした言葉で整理してみてください。
このとき、断られた理由を建物要因、契約要因(補償内容や保険金額)、管理要因(空き家期間や使用状況)などに分けてノートに書き出しておくと、次に相談する保険会社や専門家にも状況を伝えやすくなります。
同じ理由で何社からも断られるのか、それとも会社ごとに指摘されるポイントが違うのかも見えてきます。
建物の状態を客観的に伝えるためには、言葉だけでなく資料の準備が欠かせません。外観や屋根、外壁、基礎、室内の天井や壁、配管まわりなどを撮影した写真があれば、保険会社はイメージしやすくなります。
雨漏り跡やひび割れなど、気になる箇所も正直に写しておいたほうが、後からのトラブルを避けやすくなります。
あわせて、設計図面や間取り図、過去に行ったリフォームや修繕の履歴も整理しておきましょう。
いつ、どこを、どの程度の内容で工事したのかが分かる資料があると、「築年数のわりにきちんと手入れされている住宅」と評価される可能性が高まります。
さまざまな工夫をしても、民間の火災保険や共済への加入がどうしても難しいケースもあります。その場合でも、「もう何もできない」と思い込まずに、リスク整理や資産の使い方を見直すことで、次の選択肢が見えてくることがあります。
まず考えたいのは、火災保険なしで持ち続ける場合に、どれくらいのリスクを背負うことになるのかという点です。
火災や風災、雪害などで大きな損害を受けた場合、修理費や建て替え費用を自己資金だけで賄うことになるため、家計へのインパクトは小さくありません。
一方で、建物の価値がすでに低く、将来的に建て替えや売却を予定している場合は、必要な備え方も変わってきます。
無保険のまま所有を続けるかどうかを考えるときには、「最悪のケースが起きたときにどこまで受け止められるか」を具体的にイメージすることが欠かせません。
たとえば、建物が全焼してしまった場合の再建費用の目安、半焼や一部損壊の修理費の目安、家財の買い替え費用などをざっくりと試算してみる方法があります。
これらの金額はあくまで一般的な目安であり、実際の費用は立地や建物の規模、仕様によって大きく変わります。正確な見積もりが必要な場合は、建築会社や工務店にも相談しながら検討を進めてください。
そのうえで、「どこまで自己負担できるのか」「どこから先は難しいのか」を家計の状況と照らし合わせて整理していきます。
築50年以上の住宅で火災保険に入れないと言われたとき、いきなりリフォームを検討するのではなく、まず状況を整理することが大切です。
どの部分が理由で断られたのか曖昧なままでは、対策の方向性も見えにくく、効果の薄い工事に費用をかけてしまう可能性があります。そこで、現実的な突破口として役立つのが第三者による住宅診断(ホームインスペクション)です。
専門家が建物全体をチェックし、構造や劣化状況、電気配線、基礎の状態などを報告書にまとめてくれるため、保険会社にとっても判断材料として扱いやすくなります。
この診断結果から、保険審査で特に影響の大きい箇所が明確になり、必要最小限のリフォーム計画を立てやすくなります。
火災保険 築50年以上 入れないと悩む方の多くは、リフォームすれば入れるのではと考えがちですが、住宅診断を挟むことで優先すべき対策が見えるようになり、無駄を抑えつつ審査通過の可能性を高める道筋が作れます。
診断後は、再挑戦するか、建て替えや売却を検討するか、あるいは無保険で持ち続けるリスクを整理するか、次の判断も明確になります。
火災保険に入れないことがきっかけとなり、建物の将来について見直しをする方もいます。老朽化が進み、安全面への不安が大きい場合には、建て替えや解体・売却を選ぶケースもあります。
また、空き家として放置するのではなく、小規模な修繕を行ったうえで賃貸や店舗として活用する方法も考えられます。
どの選択肢が適しているかは、立地や周辺環境、家族構成、資金計画によって大きく異なります。
不動産会社や建築会社、空き家活用の専門家など、複数の立場の意見を聞きながら、複数パターンを比較検討していくと、自分たちに合った方向性が見えやすくなります。
築古住宅の扱いは、感情的な部分とも深く結びつきます。思い出のつまった実家である、先祖代々受け継いできた土地である、という事情があると、判断が難しくなる方も多いようです。
だからこそ、一人で抱え込まずに、家族と率直に話し合う時間を取ることが欠かせません。
火災保険に入れないリスクや、必要な修繕費、将来の建て替えや売却の可能性などを共有し、家計全体としてどの選択肢が現実的なのかを一緒に考えていきましょう。
必要に応じて、ファイナンシャルプランナーや専門家の助言を受けながら、長期的な視点で判断していくことをおすすめします。
保険の見直しは、住宅ローンの完済や暮らし方の変化にも深く関係します。判断基準を整理したこちらの記事も参考にしてみてください。
築50年以上の住宅でも火災保険に必ず入れないわけではありません。判断は築年数だけでなく、屋根・外壁・配管・電気設備などの状態や管理状況が重視されます。
近年はネット型で自動的に「対象外」となる例が増えていますが、代理店型や共済なら加入できる可能性があります。断られた際は理由を明確にして複数社へ相談することで、選択肢を広げやすくなります。
リフォームによって火災保険の審査が通りやすくなる場合があります。特に屋根や外壁の防水工事、配管・電気配線の更新、耐震補強は評価に影響しやすいとされています。
ただし必ず加入できるとは限らず総合判断となります。リスクの高い箇所から無理のない範囲で改善し、工事内容は資料として整理しておくと役立ちます。
空き家や古民家でも、管理状況が整っていれば火災保険に加入できる場合があります。定期的な点検や清掃、防火・防犯対策、使用目的の明確化などが求められることがあります。
一方で、長期間手入れされていない空き家や、構造に問題がある古民家は加入が難しいケースもあります。まずは写真や状態を整理し、保険会社や専門家へ相談することが有効です。
ネット型火災保険は、築古住宅にとって不利になりやすい側面がありますが、すべてが完全に不可能というわけではありません。商品によっては、築年数の上限が比較的緩やかだったり、一定条件を満たせば加入できたりするケースもあります。
ただ、築50年以上の場合は画面入力の段階で対象外となることも多いため、その場合は早めに代理店型や共済など、相談ベースの窓口に切り替えるのが現実的です。
築古住宅では、複数社の見積もりを比較することが現実的です。各社で築年数の考え方や補償内容、免責設定が異なるため、1社だけでは判断しづらい場合があります。
最初は2〜3社から始め、必要に応じて候補を増やす方法もあります。比較の際は、保険料だけでなく補償範囲や免責、サポート体制も含め総合的に確認すると選択肢を整理しやすくなります。
どこに相談すればよいか迷う場合は、まず現在加入している保険会社や、これまでに付き合いのある代理店に問い合わせてみるのが一つの方法です。
それと並行して、各社の公式サイトや、金融庁や消費生活センターなど公的機関の情報ページも参考になります。
例えば、金融庁の「お金と暮らし」などでは、保険全般に関する基本的な情報がまとめられています(出典:金融庁「お金と暮らし」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/kurashi.html)。
情報を集める際は、一つのサイトや一人の担当者の意見だけに頼らず、複数の視点を持つことが安心につながります。
最終的な判断に迷う場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家にセカンドオピニオンを求めることも検討してみてください。
どうでしたか?ここまで読んでくださり、ありがとうございます。
築50年以上の家で火災保険に入れないと言われると不安になりますよね。でも、築年数だけで可能性が閉ざされるわけではありません。建物の状態や修繕履歴を示すことで評価が変わり、複数社へ相談すれば道が開ける場合があります。
今回の記事では、入れないと言われる背景、確認すべきポイント、加入の可能性を広げる突破方法、どうしても難しいときの選択肢まで整理しました。
行動の前に押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- 入れないと言われた理由を明確にする
- 建物の状態を示す写真や修繕履歴を揃える
- ネット型・代理店型・共済など複数の相談先を比較する
- 加入が難しい場合はリスク整理と今後の選択肢を検討する
まずは状況を整理し、写真や資料を揃え、相談ルートを広げてみてください。もし加入が難しくても、無保険のリスクや建て替え・活用などの判断材料を持つことで、次に進む選択ができるようになります。
最後に紹介させてください。
火災保険に入れないと言われたとしても、築50年以上の家を守る方法は必ずあります。状況を整理し、選択肢を知ることで、次に進む道が見えてきます。
さらに具体的な検討を進めたい方に向けて、保険の選び方や成功例、相場比較、リフォームによる突破方法などをまとめた記事も用意しています。あなたの状況に合う情報から読み進めてくださいね。
プランの違いが知りたい方へ
続けるか考え方を知りたい方へ
住宅ローン完済後の火災保険は続ける?見直し判断と手続き完全ガイド
加入例や入れる保険を参考にしたい方へ
火災保険で築50年以上の家を守る入れる保険の見つけ方と成功例
通るための改善点などを知りたい方へ
大切な家を守るための行動は、一歩ずつ進めれば大丈夫です。この記事がそのきっかけになればうれしく思います。