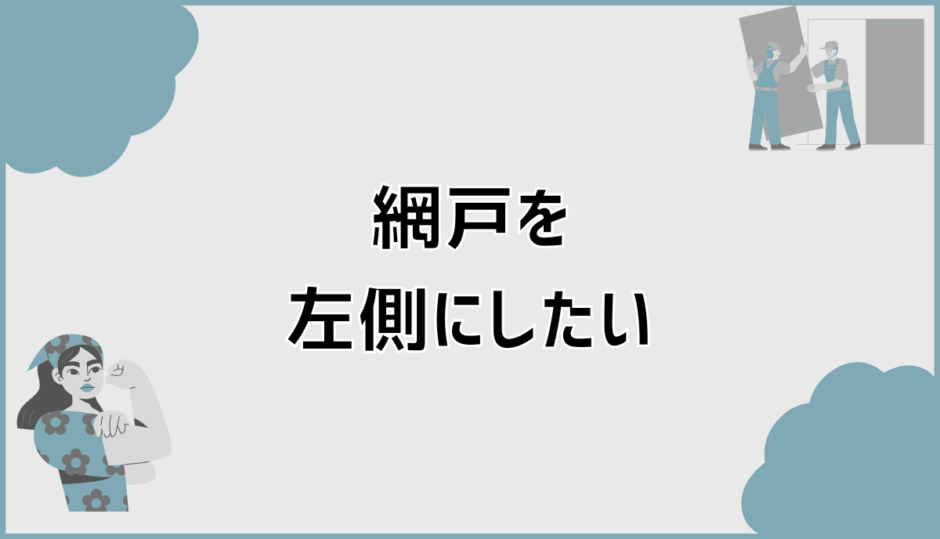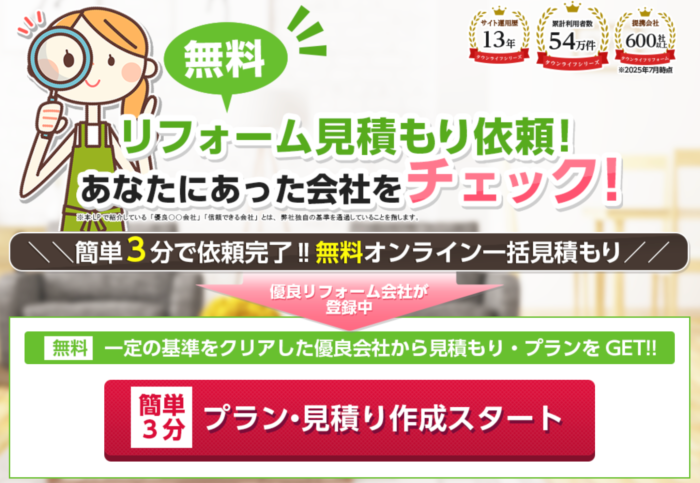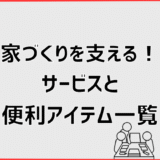この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
網戸を使っていると、右側よりも左のほうが操作しやすいのに、と感じる瞬間はありませんか。窓の近くに家具があったり、ベランダへの出入りが多かったりすると、自然と左側にしたい気持ちが強くなることもありますよね。
ただ、いざ動かそうとすると、どっち側が正解なのか、虫が入らないのはどちらなのか、左にすると隙間対策が必要なのでは、と次々に不安が浮かびやすいのも正直なところだと思います。
網戸は単に動かせばいい設備ではなく、構造や使い方によって快適さが大きく変わります。左に寄せる選択が合う場合もあれば、工夫や注意が必要なケースもありますし、条件次第では無理をしない判断が安心につながることもあります。
ここでは、網戸を左側にしたいと感じる背景を整理しながら、虫が入らない使い方や、左にした場合に起こりやすいポイント、現実的な隙間対策まで順を追って確認していきます。
読み終えたときに、あなたの家では左が合うのか、それとも別の選択がよいのかを、落ち着いて判断できる状態になることを目指しています。一緒に整理していきましょう。
- 網戸を左側にしたいと感じる主な理由と起こりやすい迷い
- 左側にした場合に虫が入りやすくなる条件とその考え方
- 左運用でも快適に使うための現実的な隙間対策のポイント
- 自分の家で左側が合うかどうかを判断するための目安
- どこに頼めばいいか分からない
- 見積金額が妥当か判断できない
- 何社も問い合わせるのが面倒
- 営業電話がしつこそうで不安

こんな不安をありませんか?
見積は「決断」ではなく考えを整理するための材料ですリフォームで迷うのは、決められないのではなく、比べる材料が足りないだけ。
まずは
- 工事範囲の違い
- 仕様に対する考え方
- 価格の幅
を並べて見える化することで、「何を基準に判断すればいいか」が自然と見えてきます。
その整理を、まとめてできる方法があります。
タウンライフリフォームなら、全国660社以上の優良リフォーム会社から、あなたの条件に合った「リフォームプラン+見積もり」を完全無料・一括で受け取れます。
安心して使える理由
- 累計利用者数54万人以上
- 自宅にいながら比較できる
- しつこい営業なし(自分でコントロール可)
※「情報収集だけ」の利用もOKです
※本記事では、メーカー公式情報や取扱説明書、一般的な事例、利用者の声を参考に整理し、筆者の視点で構成しています。口コミや体験談には個人差があるため参考程度とし、最終的な判断はご自身で確認する前提でお読みください。
網戸を左側にしたい理由や注意点

網戸を左側にしたいと感じる場面は、実はそれほど珍しくありません。家具や家電の配置、日々の生活動線、ベランダへの出入り方など、暮らし方によっては右側の網戸が使いにくく感じることもあります。
一方で、網戸は右側が基本とされてきた理由があり、位置を変えることで虫の侵入やすき間が気になるケースも出てきます。ここでは、左側にしたい理由と注意点を整理しながら、判断に迷いやすいポイントを順序立てて見ていきます。
網戸を左側にするのはアリか・条件と注意点
網戸を左側に寄せて使うこと自体は、多くの引き違い窓で実現できます。ただし、動かせることと快適に使えることは別であり、そこを理解せずに位置だけを変えると不具合につながりやすくなります。
多くのサッシは右側設置を前提に、網戸とガラス戸の重なり量、気密ブラシ(モヘア)の向き、下枠レールの排水構造まで含めて設計されています。そのため左側にすると、構造上どうしても密着性が下がりやすい場面が出てきます。

使えるかと快適かは、別で迷う場面ですね
左側運用が比較的安定しやすいのは、網戸側のガラス戸を常に全開にして使う生活スタイルが定着している場合です。
一方で、少しだけ開けて風を入れる半開運用が多い家庭では、網戸とガラス戸の重なりが浅くなり、1〜2mm程度のすき間が生じやすくなります。このわずかなすき間が、コバエや小さな羽虫の侵入経路になることは珍しくありません。
さらに、築年数の経過による戸車の摩耗、建付けのわずかなズレ、レール内部に溜まった砂や泥といった要因が重なると、左側に限らず網戸の性能は大きく低下します。
位置を変える前には、開閉の重さやガタつき、枠の歪みがないかを必ず確認し、少しでも違和感があれば無理をせず専門業者へ相談することが安心です。最終的な可否判断は、メーカーの取扱説明書と専門家の見立てを基準に考えてください。
網戸を左側にしたい人が多い理由
網戸を左側にしたい、という要望は決して珍しいものではありません。設計段階の失敗というより、実際の暮らしが始まってから「右側は思った以上に使いにくい」と気づくケースが多い印象です。
窓は毎日何度も触れる場所だからこそ、手を伸ばしにくい、動線に合わないといった小さな違和感が積み重なり、位置を見直したいと感じるきっかけになりやすいのです。
家具や家電の配置が影響する場合
窓の右側に冷蔵庫・食器棚・収納棚・テレビ台などが配置されていると、腕を伸ばす角度が不自然になり、網戸のつまみを掴むだけでも小さな負担が生じやすくなります。
特に掃き出し窓では、カーテンや家具が重なり合い、「開けたいのに手が入らない」「一度物をどかさないと操作できない」といった状況が起きがちです。
模様替えが現実的でない場合でも、網戸を左側に寄せるだけで開閉動作がシンプルになり、日常的なストレスが軽減されるケースがあります。
生活動線や利き手による使いにくさ
人の動きは、利き手や部屋への出入り方向、日常的な風の取り込み方によって自然と偏りが生まれます。たとえば右手で網戸のつまみを引く動作が、通路の向きや家具配置と干渉すると、体をひねったり一歩下がったりする必要が出てきます。
こうした小さな動作の積み重ねが使いにくさにつながります。生活動線の流れとして「左側を開けてそのまま通りたい」間取りでは、網戸も左側にあるほうが直感的で、無理のない動きになりやすいと感じる家庭も少なくありません。
ベランダや勝手口の位置関係
ベランダ側に物干し金物や室外機、収納ボックスなどが配置されていると、右側の開口が物理的に使いにくくなるケースがあります。
洗濯物の出し入れや室外機まわりの回避動線を考えると、右側を開けるたびに体をひねったり、物を避けたりする必要が出てくることも少なくありません。
室内側だけでなく屋外側の動線まで含めて見た場合、左側に開口を寄せたほうが出入りが直線的になり、日常動作がスムーズになると感じる住まいもあります。
なぜ網戸は右側が基本なのか
多くの引き違い窓で網戸が右側に来るのは、単なる慣習ではなく、構造的に安定しやすい配置だからです。
メーカーは、虫の侵入を抑えることに加え、雨水を効率よく外へ逃がし、長期間使ってもガタつきが出にくいようサッシ全体を設計しています。
その設計思想の中心に右側配置が置かれているケースが多く、結果として標準仕様として定着している、という整理になります。
サッシ構造と気密性の関係
引き違い窓は、室内側と室外側でレールが分かれ、戸車が走る溝や雨水を外へ逃がす排水経路が設けられています。下枠には水が溜まらないよう勾配や水抜き穴があり、実は左右で構造条件が微妙に異なることもあります。
網戸はガラス戸よりも軽く、わずかな段差や歪みの影響を受けやすい部材です。そのため、メーカーが想定した位置に設置するほど枠全体が密着しやすく、すき間やガタつきが起きにくくなる仕組みになっています。
網戸と窓の重なり方の違い
虫の侵入は、網そのものの目よりも、網戸枠と窓枠、あるいは網戸とガラス戸の重なり部分に生じる「枠同士のすき間」から起きることが多いとされています。
右側設置を前提とした場合、ガラス戸を少し開けた状態でも網戸との重なり幅が確保されやすく、結果として連続したすき間が生じにくい構造になりがちです。
一方、左側運用では半開時に重なりが浅くなりやすく、細い縦すき間が発生しやすくなります。この違いを理解しておくことで、左側にする場合に必要な補強や運用上の工夫が明確になります(参考:YKK AP「網戸を替える」 https://www.ykkap.co.jp/consumer/reform/window/screen/ )。
網戸はどっち側が虫が入らないか
虫の侵入をできるだけ避けたい場合、一般的には右側に網戸を設置したほうが有利と考えられています。ただし「左側にすると必ず虫が入る」というわけではありません。
実際には左右の違いそのものよりも、窓の開け方や半開にしない意識、すき間対策がきちんとできているかどうかで、結果は大きく変わってきます。

向きより使い方を見る視点も必要そうですね
右側が虫を防ぎやすい理由
右側は、半開で換気したいときでも網戸とガラス戸の重なりが確保されやすく、連続したすき間が生じにくい傾向があります。引き違い窓の多くは、この状態を前提にサッシ構造が設計されているため、意識せず使っても密着性が保たれやすい点が特徴です。
また、モヘアの向きが設計どおりに働きやすく、風圧がかかった際にも毛が外側へ押し付けられることで、すき間を塞ぐ力が維持されやすくなります。
こうした構造的な理由をもう少し深く知っておくと、「なぜ右側が基本なのか」「どこまでなら左側運用が許容できるのか」の判断がしやすくなります。詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。
左側でも問題ないケース
左側でも、網戸側のガラス戸を全開にして使う、レール清掃と戸車調整ができている、モヘアやすき間テープで補強している、といった条件が揃えば、虫の侵入を抑えられることがあります。
メーカーの取扱説明書でも、清掃時に網戸を左右へ移動させる前提が示されている例があります。左右比較の目安を簡単に整理します。
| 観点 | 右側運用 | 左側運用 |
|---|---|---|
| 半開換気の相性 | 良い傾向 | すき間が出やすい傾向 |
| 全開換気の相性 | 問題になりにくい | 問題になりにくい |
| 補助対策の必要性 | 低め | 高めになりがち |
(参考:LIXIL「網戸 お手入れ・張替え」 https://www.lixil.co.jp/lineup/window/amido/clean/ )
左側に網戸を設置すると虫が入る条件
左側網戸で虫が入りやすくなるのは、いくつかの条件が重なった場合に限られます。半開で使う頻度が高い、すき間対策が不十分、建付けにズレがあるといった要因が重なると影響が出やすくなります。
逆に言えば、こうした条件を意識的に避けることで、左側でも大きなストレスなく使える可能性は十分にあります。
半開状態になりやすい使い方
最も起きやすいのが、ガラス戸を中途半端な位置で止めてしまう使い方です。本人としては「しっかり開けたつもり」でも、実際には網戸とガラス戸の重なりが不足し、縦方向に細いすき間が連続して残ってしまいます。
コバエや小さな羽虫は数mm程度の隙間でも容易に通過できるため、特に虫の活動が活発な夏場は影響が顕著です。換気の回数が多い家庭ほど、無意識に半開状態で止めていないか、一度使い方を見直しておくと安心です。
劣化や建付けによる影響
戸車の摩耗やモヘアのへたり、網戸枠のたわみ、建物のわずかな沈下などが起こると、網戸が本来の位置で支えられず、レールからわずかに浮いてしまうことがあります。
この状態で左側運用をすると、もともと重なりが浅くなりやすい場面でさらにすき間が拡大し、虫の侵入リスクが高まりやすくなります。
左右の問題以前に、「きちんと閉まっているか」「下までしっかり落ちているか」を目視と手応えで確認し、動きが重い・外れやすいと感じた場合は、無理をせず専門業者に相談することが安心です。
網戸を左側にしたいときの対策や選択肢
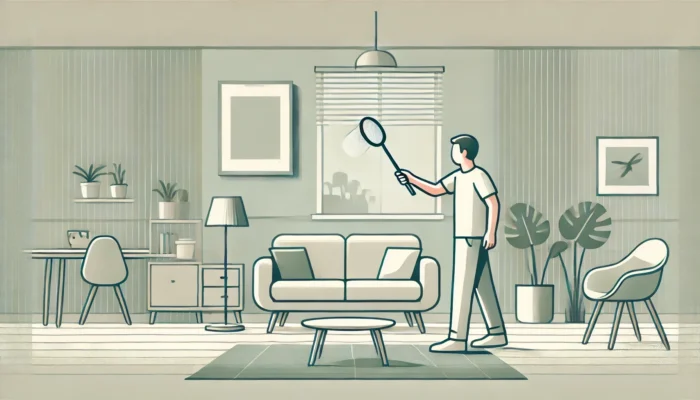
網戸を左側にしたいと決めたあとに気になるのが、「本当に快適に使えるのか」「虫対策はどうすればいいのか」という点ではないでしょうか。
位置を変えるだけでは不安が残るからこそ、運用の工夫やすき間対策、製品選びまで含めて考えることが大切です。
ここでは、左側でも安心して使うための具体的な対策と現実的な選択肢、あわせて知っておきたいメリットや疑問点をまとめて整理していきます。
左側の網戸でも虫を防ぐ工夫
左側に寄せたまま快適に使うには、日々の運用を少し意識することが大きなポイントになります。すき間対策として部材を追加する前に、まずは窓の開け方や閉め方を見直すだけで、虫の侵入や使いにくさが改善するケースも少なくありません。
引き違い窓での正しい開け方
左側に網戸を置く場合は、網戸のある側のガラス戸を全開にする運用を基本として考えることが大切です。中途半端な位置で止めると、重なり不足からすき間が生じやすくなります。
半開で風を入れたいときは、別の窓やドアを少し開けて通風経路を作り、網戸側は必ずしっかり重なる位置まで動かすのがコツです。
また夜間は、室内の光に虫が集まりやすいため、窓付近の照明を控えめにしたり、遮光カーテンで光漏れを抑えたりすると、侵入リスクを下げやすくなります。
家具がある場合の配置調整
家具を大きく動かせない場合でも、窓前を完全に塞がないだけで網戸の操作性は大きく変わります。網戸のつまみ付近に10〜15cmほどの「手を入れる余白」を確保するだけでも、開閉動作が安定しやすくなります。
加えて、カーテンの束ね位置をずらす、家電の電源コードや配線を窓から離して戸に引っかからないようにするなど、小さな調整が積み重なることで使い勝手は向上します。
無理に家具を大移動しなくても、毎回同じ動きで確実に開け閉めできるようになれば、すき間の発生を抑えやすくなり、結果として虫の入り込みも減らしやすくなります。
網戸の左隙間対策で必ずやること
左側運用で特に差が出やすいのが、すき間対策の精度です。すき間は、目で見て分かる大きなものだけとは限りません。触れたときにスースーと空気を感じる、紙が引っかかる、開閉時にガタつきがあるといった小さな違和感も、虫の侵入につながるサインです。日常の操作の中でこうした変化に早めに気づき、放置しないことが快適さを保つポイントになります。
隙間テープやモヘアの使い方
すき間テープは、貼る場所と厚み選びで効果が変わります。基本は、網戸枠とサッシ枠が当たるラインに沿って、屋外対応の耐候タイプを選びます。厚みは、閉めたときに少し押される程度が目安です。厚すぎると動きが重くなり、戸車に負担が出ます。
モヘア(気密ブラシ)は、毛足の向きがポイントです。左右を反転すると向きが逆になり、風圧で毛が寝てすき間が出る場合があります。貼り替えや追加は、既存と同等以上の毛足と密度を選び、貼り付け前にレールや枠の油分・粉じんをしっかり拭き取ってから施工してください。
網戸まわりの隙間対策として、貼るだけで使える防水タイプの隙間テープです。薄手で扱いやすく、窓や網戸の動きを妨げにくい点が特徴です。まずは手軽に試したい場合の選択肢として検討しやすい商品です。
下レールの隙間対策に使いやすいモヘアテープです。毛足が長く、網戸の動きに合わせてしなやかに密着するため、開閉を妨げにくいのが特徴です。摩耗しやすい下部の補助対策として検討しやすい商品です。
隙間が発生しやすい条件
レールに砂が溜まっている、戸車調整がずれている、枠が日射でたわんでいる、築年数が経っている、といった条件では、すき間が再発しやすくなります。対策しても改善しない場合は、網戸そのものが歪んでいることもあるので、部材交換の検討や業者点検が現実的です(参考:三協アルミ「集合住宅用 建材取り扱い説明書(PDF)」 https://alumi.st-grp.co.jp/inquiry/data/STB0203K.pdf )。
左側に網戸を使うための選択肢
左側にしたい、でも失敗は避けたい。そう考える場合は、手段を一気に決めるのではなく、段階的に整理していくと判断しやすくなります。
まずDIYで対応できる範囲なのか、それとも専用製品に置き換えたほうが確実なのか、あるいはリフォームが必要な状態なのかを冷静に切り分けることが大切です。

急いで決めなくても整理からで良さそうですね
網戸を左に動かすDIYの注意点
網戸の脱着は、上枠に押し上げてから下枠を外す手順が一般的ですが、実際の構造はメーカーや製品ごとに異なります。力任せにこじると枠が曲がったり、戸車が外れたりして、かえってすき間やガタつきの原因になりやすくなります。
戸車に調整ネジがある場合は、左右を均等に少しずつ回し、高さと傾きを揃えることがポイントです。作業に不安がある場合や大型の掃き出し窓では、落下やけがのリスクもあるため、無理をせずプロへ相談する判断が安心につながります。
左右どちらも動く網戸製品
左右兼用・両側寄せ対応の網戸や、横引きロール網戸など、窓の使い方に応じた製品も選択肢として考えられます。これらは左右どちらにも寄せられるため、生活動線や家具配置に左右されにくい点が特徴です。
ただし、既存サッシのレール形状や溝の有無、戸当たり側の納まりが取れるかによって設置可否が大きく変わります。購入前には必ずサッシの型番確認と正確な採寸を行い、適合可否を確認することが失敗を防ぐポイントです。
左右を変えるリフォームの目安
サッシ側の構造が片側前提の場合、網戸だけでなく戸車やレール、場合によっては枠部材の加工や交換が必要になることもあります。費用は窓サイズや工事内容で差が出ますが、一般的な目安を把握しておくと判断しやすくなります。
網戸を左右反転させるだけの軽微な調整であれば、部材代と作業費を含めて1万〜3万円程度がひとつの目安です。既存網戸を活かしつつ、戸車調整やモヘア補強を行うケースがこれに該当します。
一方、左右兼用の網戸へ交換する場合や、レール側の納まりを調整する必要がある場合は、2万〜4万円程度が一般的なレンジになります。掃き出し窓などサイズが大きい場合は、これより高くなることもあります。
サッシ構造そのものが右側前提で、レール加工や部材交換を伴う場合は、3万〜5万円前後、条件次第ではそれ以上になることもあります。いずれの場合も、正確な金額は現地調査後の見積もりで判断し、最終的な可否は専門業者と相談することが安心です。
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 | 目安費用 |
|---|---|---|---|
| 位置移動(DIY) | 軽い調整で済みそう | 枠の変形・けがに注意 | 数千円〜1.5万円程度 |
| 対応製品に交換 | 左右運用を確実にしたい | レール適合と採寸が鍵 | 2万〜4万円前後 |
| リフォーム | 根本から使い勝手を変えたい | 工事範囲で費用が変動 | 3万〜5万円前後 |
条件を入力するだけ
判断の整理のために活用ください
契約義務はありません
【PR】
網戸を左寄せにするメリット
左側に寄せることには、使い勝手や空間の感じ方という点で、確かなメリットがあります。代表的なのは「暮らしの動きに網戸が自然に寄り添う」点です。
家具配置や生活動線に合わせて操作がしやすくなると、窓を開ける行為そのものの心理的ハードルが下がり、結果として換気の回数が増えやすくなります。
これは体感的な快適さだけでなく、室内の空気循環という面でもプラスに働く可能性があります。
また、視線の抜け方が変わることで、室内から見たときに網戸の框(枠)が目立ちにくくなり、窓まわりがすっきり感じられるケースもあります。
特にベランダや勝手口の出入りが多い住まいでは、出入口側を広く使えることで、洗濯やゴミ出しといった日常動作がスムーズになることもあります。一方で、こうしたメリットを安定して享受するには、すき間対策と運用ルールが欠かせません。
左側にした場合は「必ず全開にする」「定期的にレールを清掃する」「モヘアの劣化を確認する」といった基本動作を習慣化することが、快適さを維持する鍵になります。
安全面や保証面も含め、メーカー説明書の範囲で運用できるかを確認し、必要に応じて専門家へ相談する姿勢が、後悔のない選択につながります。
よくある質問集
- 左側にすると必ず虫が入りますか?
- 必ず、ではありません。半開で使う頻度が高い、すき間がある、モヘアがへたっている、などの条件が重なると入りやすくなります。全開運用とすき間対策で改善することもあります。
- すき間テープはどれを選べばいいですか?
- 屋外対応の耐候タイプから、閉めたときに軽く押される厚みを選ぶのが目安です。厚すぎると動きが重くなるので注意してください。迷う場合はホームセンターで複数厚みを試すか、専門家に相談すると確実です。
- 網戸が外れやすいのは左側にしたせい?
- 左右以前に、レールの汚れ、戸車の摩耗、枠のゆがみが原因になりやすいです。外れ止め(振れ止め)の位置がずれている場合もあるので、説明書に沿って点検し、改善しない場合は修理依頼をおすすめします。
- 保証はどうなりますか?
- 保証条件はメーカー・施工形態で異なります。位置変更や部材追加が保証対象外になる場合もあるため、正確な情報は各社の公式案内をご確認ください。最終的な判断は専門業者への相談が安心です。
- どうしても不安です。最短で失敗しない方法は?
- 現地での建付け確認と、窓型番に合う提案ができる業者へ相談するのが近道です。小さな違和感を放置すると、虫対策以上に開閉不良や脱輪などのトラブルにつながることがあります。
まとめ:網戸を左側にしたい人
どうでしたか?網戸を左側にしたいと感じる背景には、暮らし方や動線、家具配置など、日常の小さな違和感が積み重なっていることが多いようです。一方で、網戸は構造上の前提や使い方によって快適さが大きく変わる設備でもあります。
左にする選択が合う場合もあれば、工夫や対策が必要なケース、無理をしないほうが安心な場合もあります。この記事では、感覚だけで判断せず、条件や注意点を一つずつ整理してきました。最後に、判断の軸を簡単に振り返ります。
- 左側にしたい理由が生活動線や配置に合っているか
- 半開運用が多く、虫や隙間が気になりやすくないか
- 清掃や調整、隙間対策を続けられそうか
- DIYか製品交換か、相談も含めて無理のない選択か
網戸を左側にしたいかどうかは、正解が一つではありません。
この記事が、あなたの住まいに合った選択を落ち着いて考えるきっかけになれば嬉しいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。