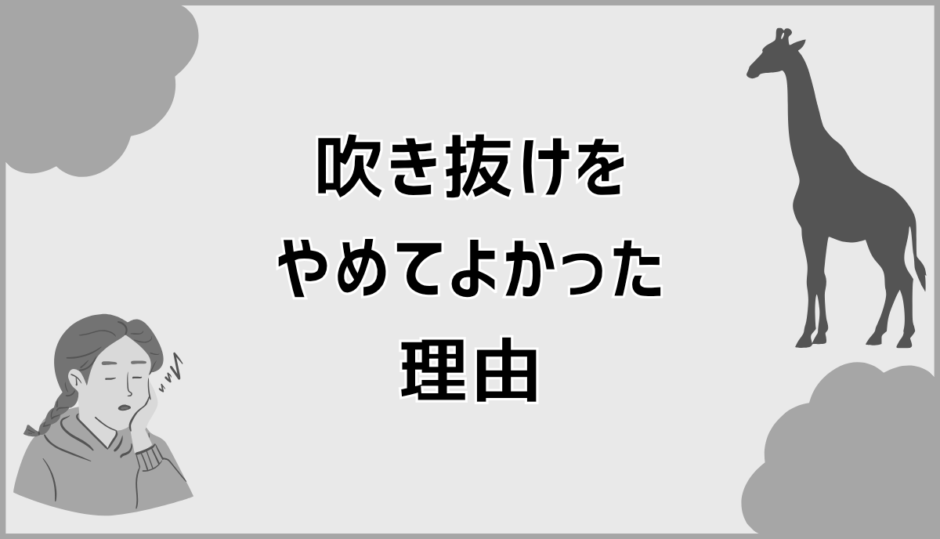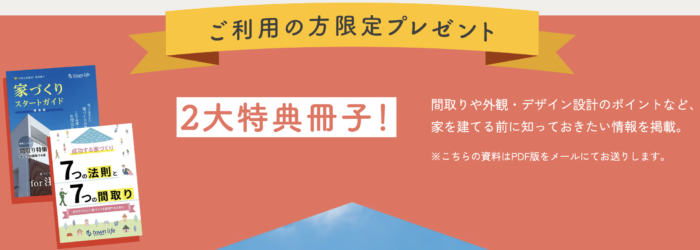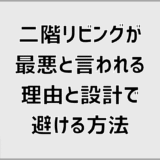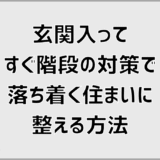この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
家づくりを考え始めたとき、多くの方が一度は吹き抜けに憧れます。明るくて開放的で、おしゃれ。けれど同時に、ネットで後悔という言葉を目にして、不安になった経験はありませんか?
実際には、住み始めてから寒いと感じて後悔や寒い状態になったり、掃除や安全面が想像以上に大変で最悪だと感じたりする体験も少なくありません。ハーフ吹き抜けなら大丈夫だと思ったのに、結果的に後悔したという声もあります。
ここでは、吹き抜けをやめてよかったと感じた人の体験をもとに、やめてよかった理由やメリット、逆に吹き抜けが向いている人の考え方まで整理します。また、メーカーごとの考え方の違いや、将来を見据えた注意点にも触れていきます。
何となく決めて後悔するのではなく、自分たちに合う選択を見つけるための一筋の希望として、この記事があなたの判断材料になればうれしいです。
- 吹き抜けをやめてよかったと感じやすい具体的な理由と後悔につながるポイント
- 冷暖房効率や寒さ、掃除や安全性など実際の暮らしで起こりやすい問題点
- ハーフ吹き抜けを含めた向き不向きと自分に合う判断軸
- メーカー選びや将来を見据えた吹き抜けの注意点と考え方
タウンライフ家づくりとは?
ハウスメーカー選びや資金計画など、家づくりの不安をまとめて解消できる無料の比較サービスです。
間取りや見積もりだけでなく、家づくりの全体像を知るための情報をまとめて確認できます。
今なら家づくりに役立つ特典冊子を無料でもらえる
※本記事は、メーカー公式情報や各種レビューサイト、実際の体験談などを参考にしながら、筆者の視点で整理・構成しています。口コミや体験には個人差があり、感じ方や状況は人それぞれ異なります。なお、記事内で触れている光熱費や安全性、法規の扱いについては、地域や計画内容、審査機関の解釈によって変わる場合があります。最終的な判断は、設計士や施工会社、必要に応じて専門家に相談し、公式情報と個別条件に基づいて進めてください。

モデルハウスや写真で見る吹き抜けは、明るくて開放的で、家づくりの憧れとして心に残りやすい存在です。ただ実際の暮らしを想像し始めると、「本当に自分たちの生活に合うのか」「後から後悔しないか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、吹き抜けをやめた理由とその後の暮らしの変化、そして採用した場合に後悔しやすい実体験を整理し、見た目だけでは分かりにくい現実的な判断材料をお伝えします。

吹き抜けは「開放感」と引き換えに、室内環境・安全性・将来の使い勝手など、日々の暮らしに直結する論点が増えます。
間取り検討の初期はどうしても見た目の印象や非日常感が先に立ちがちですが、プランを具体化するほど、冷暖房効率や音の回り方、掃除や点検の負担といった現実的な課題が浮かび上がってきます。
その結果、「本当にこの家族構成で、10年・20年先までストレスなく回るか」を冷静に見直す場面が増えやすくなります。
設計中に悩みが深くなるポイントは、だいたい3つに集約されます。
ひとつは空調計画です。吹き抜けは上下階の空気が混ざるため、リビング単体で快適にしようとすると、必要能力の見立てが難しくなります。
ふたつめは安全面。2階ホールや階段に面して吹き抜けがある場合、転落防止の納まりや家具配置まで含めて、生活レベルでのリスクを想像する必要があります。
みっつめは将来の可変性です。床がない空間は、後から部屋を増やす・収納を増やすといった変更がしづらく、家族の変化に合わせた「詰め替え」が難しくなることがあります。
この3つは、見た目の好みとは別軸で、暮らしの安定性に効いてきます。吹き抜けに憧れがあっても、設計段階で優先順位を整理すると「無理に採用しなくていい」という判断に落ち着くケースが少なくありません。
吹き抜けをどうするか考え始めたとき間取りだけでなく、実は気が付かずに家づくり全体の流れに迷いが出てくる人もいます。今どこで悩んでいるのかが整理できないまま進めると、判断が揺れやすくなることがあります。
一度立ち位置を見直してみると、考える順番がはっきりしてくるかもしれません。こちらの記事で、全体像が把握できますので、参考にしてみてください。
「吹き抜け=光熱費が必ず上がる」と一概には言えません。電気代は地域の気候条件、断熱・気密性能、窓の性能、換気方式、在宅時間、電力契約単価、空調機器の台数や運転方法によって大きく左右されるためです。
ただし、同じ延床面積(例えば30〜35坪前後)でも、吹き抜けがあると空調対象となる室内容積が約1.2〜1.5倍程度に増えるケースがあり、上下階の温度差を抑える目的でシーリングファンやサーキュレーターを併用する設計が選ばれやすいのは事実です。
そこでここでは、あくまで一般的な住宅条件を想定したモデルケースとして、「差が出やすいポイント」を数値でイメージできる比較を示します。
| 比較項目 | 吹き抜けなし (目安) | 吹き抜けあり (目安) |
|---|---|---|
| 暖房時の体感立ち上がり | 約20〜30分で安定 | 30〜60分かかる場合あり |
| 冬季の暖房運転時間 | 1日6〜8時間程度 | 1日8〜12時間程度 |
| 想定される暖房負荷 | 約4〜5kW相当 | 約5〜7kW相当 |
| 追加対策 | 不要なことが多い | シーリングファン・送風併用 |
| 月の電気代差 (目安) | 基準 | 約2,000〜5,000円増加する例も |
※示した数値はあくまで目安であり、必ず個別の見積もりや専門家の試算とあわせて確認するようにしてください。
ここで示した電気代の差(約2,000〜5,000円/月)は、断熱等性能等級5〜6相当、エアコン暖房、電力単価30円/kWh前後を想定した場合の一例です。高断熱住宅でも、吹き抜けの大きさや間取り、空調の使い方によってはこの範囲に収まらないこともあります。
したがって、最終的な判断では、住宅会社に外皮性能(UA値など)と設備条件を固定したうえで、月別・季節別の冷暖房負荷シミュレーションを作成してもらうことが欠かせません。
後悔として挙がりやすいのは「冬の足元の冷え」です。暖気は上に溜まりやすいので、吹き抜けがあると1階の床付近が冷えやすいと感じる人がいます。
とくに、リビングの一部だけが高天井になっている場合、空間内で温度分布が偏り、ソファ周りは暖かいのにダイニング側は寒い、といったムラが起きやすいと言われます。
もちろん、床暖房や送風で改善することもありますが、それは「対策を前提にした暮らし」になります。家づくりで避けたいのは、日常が常に調整作業になることです。
寒さの感じ方は個人差が大きいので、モデルハウスの短時間体験では分かりにくい点も含め、冬の見学や宿泊体験などで検証できるなら有効です。
吹き抜けのメンテナンスで代表的なのが、照明交換・高窓の清掃・シーリングファンの手入れです。高所作業は脚立の高さが足りないことがあり、無理をすると転倒リスクが上がります。
結果として業者依頼が増え、出張費や高所作業費が積み上がりやすい点が不安材料になります。
吹き抜けを設けない場合、照明や換気の点検が「家庭内で安全に管理できる高さ」に収まりやすく、必要なときにすぐ対応できます。
住まいは一度建てると、10年、20年と維持するものです。設備の寿命や交換を現実的に考えるほど、点検のしやすさは家計にも直結します。
子育て世帯で最も気になるのは転落事故のリスクです。吹き抜け周りの手すりは一定の高さや隙間への配慮が求められますが、実際の生活では「家具を足場にする」「柵の近くで遊ぶ」など予測不能な行動が起こり得ます。
また、転落防止のためにネットや追加柵を後付けすると、意匠性が崩れたり、掃除がしづらくなったりと別のストレスが生まれることもあります。
安全対策は家庭の責任で行う部分も多いので、不安が強い場合は、そもそも危険箇所を作らない設計のほうが精神的に楽です。最終判断は、設計士や施工会社と安全基準・納まりを確認し、家族の性格や生活動線に合う形を選んでください。
吹き抜けで後悔した人の多くは、間取り以前に進め方でつまずいています。なぜ一社だけで家づくりを進めると失敗しやすいのかを知ると、考え方が大きく変わります。こちらにまとめた記事がありますので、参考にしてみてください。

吹き抜けの後悔は、採用直後ではなく「暮らしのルーティンが固まった頃」に表面化しやすい傾向があります。
入居当初は新居の開放感や非日常性に満足していても、毎日の掃除や冷暖房の調整、在宅ワーク中の音環境、子どもの成長に伴う行動範囲の変化などが重なるにつれ、使い勝手への違和感が少しずつ積み重なっていくケースがあります。
来客時や季節の変わり目など、生活の場面が増えるほど、吹き抜けが暮らし全体に与える影響は大きくなります。こうした変化を事前に具体的な生活シーンとして想像するのは、意外と難しいものです。
モデルハウスの吹き抜けは、照明計画や家具配置、空調管理まで計算された状態で演出されているため、非常に魅力的に映ります。しかし、実際の住まいでは日々の暮らしが最優先となり、家具の置きやすさや収納量、掃除や家事動線といった実用面が大きく影響します。
吹き抜けによって壁面が減ると、収納家具や棚の配置が制限され、結果として物が表に出やすくなり、リビングが散らかりやすいと感じる人も少なくありません。
また、開放感を維持するためには常に片付いた状態を保つ必要があり、生活の中で無意識に負担が積み重なることもあります。見た目の印象だけで判断すると、暮らし始めてから「想像以上に管理が大変だった」と感じる要因になりやすい点は押さえておきたいところです。
吹き抜けは上下階が一体となる構造のため、生活音が想像以上に回り込みやすい特徴があります。
テレビや会話の声だけでなく、キッチンでの調理音や食洗機の稼働音、階段の上り下りの足音、子どもが遊ぶ音などが、遮られることなく2階へ伝わりやすく、反対に2階の音が1階に降りてくることも少なくありません。
時間帯によっては、家全体が常にざわついているように感じるケースもあります。とくに在宅ワークやオンライン会議がある家庭では、この「音の回り込み」が集中力や仕事の質に影響することがあります。
マイクに生活音が入りやすかったり、静かな環境を保つために家族が気を遣い続けたりと、日常的なストレスにつながる場合もあります。
吸音材の施工や建具によるゾーニングで軽減できることもありますが、その分コストや間取りの制約が増えがちです。そのため、音環境を重視する家庭では、設計段階から吹き抜けを避ける判断が、結果的にシンプルで負担の少ない選択になることもあります。
「家族の気配が分かる」という点は吹き抜けの代表的なメリットとして語られますが、一方で「常に誰かの気配を感じてしまう」と負担に感じる人もいます。
視線が上下階で抜ける配置の場合、2階ホールや階段での行動が1階から見えやすくなり、声や生活音も届きやすくなります。その結果、無意識に行動を気にしたり、落ち着ける時間が減ったりすることがあります。
特に子どもが成長して思春期に入ると、自室で一人になりたい、静かに過ごしたいと感じる場面が増えていきます。家族関係が良好であっても、空間的な距離が近すぎることで心理的な息苦しさにつながるケースもあります。
将来の年齢変化や生活リズムの違いまで含めて考えたうえで、適度な距離感を保てる間取りかどうかを検討しておくことが、後悔を防ぐポイントになります。
吹き抜けは空気が上下階で循環しやすい構造のため、ホコリや花粉が室内に舞いやすく、なかなか落ち着かないと感じる人がいます。
特に換気扇やエアコンの風向きによっては、1階で舞い上がったホコリや花粉が2階へ移動し、時間差で再び落ちてくるように見えることもあります。
そのため、掃除をしてもすぐに空気中の汚れが目立ち、「きれいになった実感が得にくい」と感じるケースも少なくありません。アレルギー体質の家族がいる家庭では、この空気の動きが体調面の不安につながることがあります。
床材やカーテン、ソファなどをホコリが溜まりにくい素材にすることや、高性能フィルターを備えた空気清浄機を上下階に設置するなど、空気環境を住まい全体の設計要素として考える視点が求められます。
ただし症状や感じ方には個人差があるため、健康面に関わる判断については、必ず医師などの専門家に相談したうえで進めることが大切です。
吹き抜けは高窓や大開口と組み合わされることが多く、日中は明るさを確保しやすい反面、夜間になると室内の様子が外から見えやすいと感じる人もいます。
照明をつけたリビングが外から浮かび上がることで、通行人の視線が気になったり、生活リズムを推測されているような不安を覚えたりするケースもあります。
カーテンやブラインドを閉めれば視線は遮れますが、その分、吹き抜けならではの開放感や明るさが損なわれてしまい、使い方に悩む場面が出てきます。
さらに、窓の数が増えるほど施錠箇所も増えるため、外出時や就寝前の確認が負担になることがあります。家族の生活時間がずれている家庭では「締め忘れがないか」という不安が積み重なり、精神的なストレスにつながることもあります。
防犯面は地域性や立地条件によって求められる対策が異なるため、窓の配置計画、防犯ガラスの採用、センサーライトや防犯カメラの設置なども含め、施工会社と一体となって総合的に検討することが大切です。
強い後悔につながりやすいのは、複数のデメリットが同時に表面化したときです。
例えば「冬場に足元が冷える」「生活音が上下階に響く」「高所の掃除や照明交換が負担になる」といった不満が重なると、本来は開放感を楽しむための吹き抜け空間が、日常的なストレスの原因になってしまうことがあります。
一つひとつは我慢できる範囲でも、毎日の生活の中で積み重なることで、満足度を大きく下げてしまうケースも少なくありません。だからこそ大切なのは、個別の欠点だけを見るのではなく、生活全体の快適性として吹き抜けを評価する視点です。
吹き抜けは空間演出としての効果が高い反面、ライフスタイルに合わなかった場合の反動も大きくなりがちです。長く住み続ける家だからこそ、憧れよりも日々の過ごしやすさを軸に判断しておきたいポイントです。
「全面吹き抜けは不安だからハーフにする」という判断は、一見すると現実的な折衷案に思えます。
しかし、ハーフ吹き抜けであっても、音が上下階に伝わりやすい点や、空間内の温度ムラ、壁面が減ることによる収納・家具配置の制約といった要素が残る場合があります。
思っていたほど室内が明るくならず、「これなら吹き抜けにしなくてもよかったのでは」と感じる声が出ることもあります。また、ハーフにしたことで安心感を持ちやすい反面、寒さや音の問題が中途半端に残り、対策が必要になるケースもあります。
ハーフにすれば安全、ハーフにすれば快適と単純に考えず、何が改善されて何が残るのかを施工会社と具体的にすり合わせたうえで判断することが、後悔を防ぐポイントになります。
吹き抜けで後悔した理由をたどっていくと、間取り以前に情報の集め方で迷っていたケースも少なくありません。
展示場、資料請求、タウンライフなど、家づくりの進め方には違いがあります。それぞれの特徴を整理しておくと、判断の軸が見えやすくなります。こちらの記事にまとめていますので、参考にしてみてください。

吹き抜けをやめるという判断は、必ずしも「妥協」や「後退」ではありません。暮らしやすさや将来の変化を考えた結果として、満足度が高まる選択になることも多くあります。一方で、条件や価値観が合えば、吹き抜けが向いている人がいるのも事実です。
ここでは、吹き抜けをやめて得られた具体的なメリットを整理しつつ、どんな人なら後悔しにくいのか、さらにメーカー選びや将来の視点も含めて判断のヒントをお伝えします。
吹き抜けをやめる判断は「何かを諦める」ではなく、「暮らしに直結する余白を増やす」方向に働くことがあります。床と壁が増えることで、収納・インテリア・採光・将来の可変性など、実用面の選択肢が広がりやすくなります。
空間に余白があると、暮らし方の変化に合わせて使い方を調整しやすくなり、結果として住まいへの不満が溜まりにくくなります。目に見える開放感よりも、日常の扱いやすさや柔軟性を重視した判断が、長期的な満足度につながるケースも少なくありません。
吹き抜けがないと、2階の床面積と壁面を無駄なく確保しやすくなり、その分を収納計画に充てやすくなります。
ファミリークローゼットやパントリー、階段下収納、壁面を活かした造作棚などを組み込みやすく、後から収納家具を買い足さなくても、最初から「しまう場所」を前提にした暮らしが整いやすくなります。
片付けは気合や習慣よりも、動線上に適切な収納があるかどうかが大きく影響します。収納が計画的に配置されている住まいでは、使った物をすぐ戻せるため散らかりにくく、家事の手戻りも減りやすくなります。
共働き世帯や忙しい家庭ほど、この収納力の差が日々の暮らしやすさとして実感されやすい部分です。
吹き抜けがなくても、天井の見せ方や照明計画を工夫することで、十分に雰囲気のある空間はつくれます。
例えば、折り上げ天井や下がり天井を組み合わせて高さに変化を持たせたり、間接照明で天井や壁を照らすことで、実際の天井高以上の広がりを感じさせることができます。
また、壁面にアートや飾り棚を設けたり、テレビ背面をアクセントクロスやエコカラットなどで仕上げたりすることで、視線が集まる「見せ場」を点としてつくることができます。
吹き抜けのように空間全体を面で演出するデザインは開放感が大きい反面、掃除やメンテナンス、模様替えの負担が増えやすい傾向があります。
その点、ポイントを絞ったインテリア演出であれば、日常管理の手間を抑えながら、十分におしゃれな印象を保つことができます。暮らしやすさとデザイン性を両立させたい場合には、吹き抜けに頼らない空間づくりの方が現実的と感じる人も多いでしょう。
採光は必ずしも吹き抜けだけが解決策ではありません。高窓(ハイサイドライト)を用いれば、外部からの視線を遮りながら安定した自然光を取り込むことができますし、窓を一か所に集中させず分散配置することで、室内全体に柔らかく光を回すことも可能です。
さらに、白やベージュなど反射率の高い内装色を採用することで、実際の開口面積以上に明るく感じられる空間をつくることができます。
トップライト(天窓)も有効な選択肢の一つで、条件を満たす場合には建築基準法上の採光計算で壁面の窓より有利に扱われると説明されることがあります(出典:AGC Glass Plaza「15. 光-1 採光と明るさ、季節と窓」 https://www.asahiglassplaza.net/knowledge/rg_knowledge/vol15/ )。
一方で、雨仕舞の精度や夏場の熱取得、将来的な清掃やメンテナンスといった別の検討事項も増えます。採光量だけで判断せず、立地条件や生活スタイルを踏まえたうえで、設計士と十分に条件を整理しながら採用を検討することが大切です。
吹き抜けがない家は、2階床や壁が連続しているため、将来的な間仕切り追加や収納増設といった変更を行いやすい傾向があります。
子どもの成長に合わせて個室を分けたい場合や、在宅ワーク用のスペースを確保したい場合、親との同居を見据えて生活動線を整理したい場合など、「部屋を足す」「空間を区切る」といった選択肢を残しやすい点は大きな安心材料になります。
一方で、リフォームのしやすさは構造形式や耐力壁の位置、配管・配線の通り方、さらには建築基準法や確認申請の扱いによって難易度が大きく変わります。
将来の変更可能性を重視する場合は、構造計画や可変性を前提とした間取りかどうかを施工会社に具体的に確認し、最終的な判断は設計士などの専門家に相談したうえで進めることが大切です。
吹き抜けのような間取りで悩み始めた人は、実は家づくりの進め方でも迷いやすい傾向があります。
展示場や資料請求、タウンライフの違いを知っておくと、なぜ判断がぶれやすくなるのかが見えてきます。こちらの記事にまとめていますので、参考にしてみてください。

吹き抜けを避ける話が多くなりがちですが、条件が揃えば満足につながるケースもあります。大切なのは、雰囲気や憧れだけで判断せず、「なぜ吹き抜けが欲しいのか」を自分たちの言葉で説明できるかどうかです。
その理由に対して、必要な断熱性能や空調計画、掃除や管理の手間、将来的な使い方まで含めて受け入れられるかを冷静に考えることが、後悔を防ぐ分かれ目になります。
ポイントは「吹き抜けが欲しい理由が明確で、そのための性能・運用を納得して選べているか」です。
在宅ワークが多く静音性を重視したい家庭や、共働きで家事・掃除にかけられる時間が限られている家庭では、吹き抜けによる音の回り込みやメンテナンス負担が想像以上にストレスになることがあります。
また、小さな子どもがいる家庭では、安全面への不安から常に気を張る必要が出てくるケースもあります。さらに、収納量をしっかり確保したい場合には、壁面が減ること自体が大きなデメリットになりやすいです。
暮らしの優先順位が「管理のしやすさ」や「部屋数」「将来の使い勝手」にあるなら、吹き抜けは慎重に検討した方が安心につながります。
後悔を減らすには、温熱環境と音環境を設計段階でしっかり整理しておくことが欠かせません。
具体的には、高断熱・高気密仕様を前提に、窓の性能や配置を含めた外皮計画を行い、上下階の温度ムラを抑える空調ゾーニングや送風計画を検討することが求められます。
また、吹き抜けを通じて音が回り込みやすくなるため、階段位置や個室配置など、間取り全体で音の伝わり方を考える視点も重要です。吹き抜け単体で良し悪しを判断するのではなく、住宅性能や暮らし方とセットで考える必要があります。
ただし、性能数値を高めれば必ず快適になるとは限りません。体感は地域の気候条件や間取り、家族構成、住まい方によって変わるため、複数の施工会社の提案を比較し、断熱性能や空調計画の前提となる計算条件を確認したうえで判断することが大切です。
吹き抜けが向いているかどうかは、性能や間取りの前提条件で変わります。文章で理解しても、実際のプランを見ると印象が変わることも少なくありません。条件を伝えたうえで、具体的な間取り案を見比べてみると判断しやすくなります。
ハーフ吹き抜けは、全面的な吹き抜けに比べて床面積を確保しやすく、開放感とのバランスを取りたい人に選ばれやすい手法です。一方で、上下階が部分的につながる構造である以上、音の回り込みや温度ムラといった影響が完全になくなるわけではありません。
そのため、合うのは「ある程度の開放感は欲しいが、全面吹き抜けほどの空調負担や管理の大変さは避けたい」と考える人です。反対に、室内を明るくしたいことを主な目的としている場合は、ハーフ吹き抜けでも期待ほど採光効果を感じられないケースがあります。
その場合は、吹き抜けに頼る前に、高窓の設置や窓配置の見直し、内装材の反射率を高める工夫などで代替できないかを検討する方が、合理的な判断につながりやすくなります。
吹き抜けが欲しい理由が「室内を明るくしたい」のであれば、窓の配置や高さ、方角を工夫することで代替できる場合がありますし、「縦方向の開放感」を求めているのであれば、勾配天井や折り上げ天井によって体感的な広がりを演出できることもあります。
吹き抜けは魅力的な選択肢ではありますが、必ずしも唯一の解決策ではありません。家づくりは、理想の要素を足し算するだけでなく、日々の負担になりやすい要素を減らすことで、結果的に満足度が高まるケースも多く見られます。
判断に迷った場合は、吹き抜けあり・なしの両プランを同じ延床面積や性能条件で見積もり、光熱費やメンテナンス、将来の使い勝手といった運用面まで含めて比較したうえで決めると、納得感のある選択につながりやすくなります。
吹き抜けをやめてよかったかどうかは、メーカーや間取り提案の幅によっても感じ方が大きく変わります。最初から1社に絞って進めてしまうと、気づかないうちに判断基準が偏ってしまうこともあります。
なぜ家づくりで失敗する人ほど1社だけで進めてしまうのか。その構造を知るだけでも、遠回りを防ぐヒントになります。こちらにまとめていますので、参考にしてみてください。

吹き抜けの評価は、メーカーの標準仕様や得意とする温熱設計の考え方、さらに将来の売却や住み替えをどこまで想定するかによっても大きく変わります。
断熱性能や空調提案に強みを持つメーカーであっても、吹き抜けの大きさや間取り次第では追加対策が必要になることがあります。
そのため検討段階では、今の暮らしで感じる満足感だけでなく、10年後・20年後の使い方や選択肢も並べて考えておくことが大切です。そうすることで判断基準が感覚に流されにくくなり、後から迷いが生じにくくなります。
一条工務店は高気密・高断熱のイメージが強く、吹き抜けでも快適に暮らせそう、と期待されやすいメーカーです。
一方で、吹き抜けの規模が大きい場合は、温度ムラ対策や送風計画が必要になることがあり、期待値とのギャップが不満につながるケースがあります。また、外観や内装の意匠は好みの影響が大きく、標準仕様との組み合わせで「思っていた雰囲気と違う」と感じる人もいます。
ここは性能の話と同時に、提案段階でパースやシミュレーションを十分に確認し、暮らし方まで含めて擦り合わせることが大切です。最終的な仕様は公式情報と担当者の説明をもとに確認してください。
吹き抜けは中古市場において評価が分かれやすい要素のひとつです。住宅購入を検討する層の多くは、デザイン性よりも部屋数や光熱費の見通し、日常的なメンテナンス負担、安全性といった実用面を重視する傾向があります。
そのため、吹き抜けがある間取りに対して「冬は寒そう」「掃除や照明交換が大変そう」「使える床面積が少なそう」といった先入観を持たれる可能性があります。
もちろん、吹き抜けがあるから必ず売れにくくなるわけではありません。ただし、好みが分かれやすく、万人受けしにくい特徴であることは理解しておいた方が安心です。
将来の売却も視野に入れるのであれば、構造的に吹き抜け部分を塞げる余地を残しておく、部屋数が不足しないよう間取りを計画するなど、あらかじめ出口戦略を意識しておくことで、将来的な選択肢を狭めにくくなります。
どうでしたか?ここまで読んでいただき、ありがとうございます。吹き抜けは見た目の印象が強い分、家づくりの中で迷いやすい要素のひとつです。
ですが、実際の暮らしを想像しながら整理していくと、吹き抜けをやめてよかったと感じる判断には、きちんと理由があります。
この記事では、冷暖房効率や寒さ、掃除や点検の負担、安全性、将来の使い勝手といった視点から、吹き抜けに関する後悔が生まれやすいポイントを見てきました。
そのうえで、やめてよかったと感じやすい理由や、逆に条件が合えば向いている人の考え方、メーカー選びや将来を見据えた注意点も整理しています。
- 見た目よりも日々の暮らしやすさを重視したい
- 管理やメンテナンスの負担を減らしたい
- 家族構成や生活の変化に柔軟に対応したい
こうした思いがある場合、吹き抜けをやめてよかったと感じる可能性は高まります。一方で、価値観や住まい方によっては吹き抜けが魅力になるケースもあります。大切なのは、憧れだけで決めず、自分たちの暮らしに本当に合うかを考えることです。
ここまで読んで、吹き抜けをどうするかだけでなく、家づくり全体の進め方に少し迷いを感じた方もいるかもしれません。実は多くの人が、自分が今どの段階にいるのか分からないまま判断を重ねています。
今の自分の位置を整理してみると、次に考えるべきことが自然と見えてくることがあります。こちらの記事に家づくりの進め方をまとめていますので、参考にしてみてください。
この情報が、あなたの家づくりを納得のいく形で進めるヒントになればうれしいです。