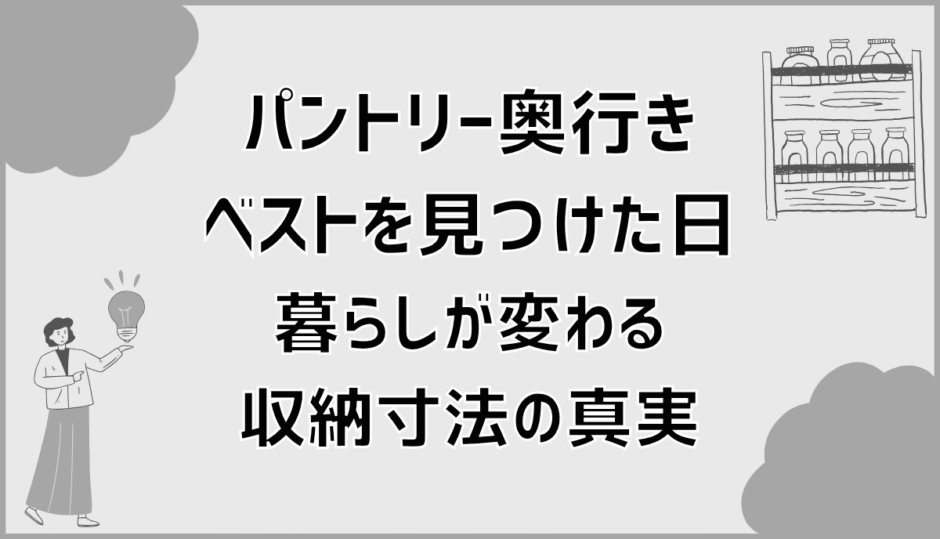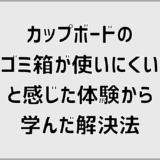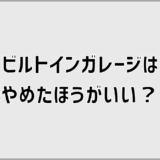この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
家づくりで多くの人が悩むのが、パントリーの奥行きや幅をどのように決めるかという点です。
パントリー奥行きベストをしっかり考えずに設計すると、奥が見えにくく使いづらい、あるいは収納量が足りないといった後悔につながることがあります。
奥行き40・45・60センチ収納の違いや、30センチ収納ボックスを基準にした棚設計、可動棚の活用方法、無印のアイテムを取り入れた整え方などを知ることで、暮らしにぴったり合った収納をつくることができます。
さらに、奥行きのあるパントリー収納アイデアや、90センチ幅の使い方を意識した動線づくりも参考になります。パントリーがなくてもカップボードを上手に取り入れれば、すっきりと心地よい空間を実現することが可能です。
ここでは、使いやすさとデザインの両面からパントリー奥行きベストを導き出し、後悔しない収納づくりのヒントをお届けします。
- 暮らしに合ったパントリー奥行きベストを見極めるための基本的な考え方
- 奥行き40・45・60センチ収納の違いと最適な使い分け方
- 30センチ収納ボックスや可動棚、無印アイテムを活かした実践的な収納設計
- パントリーなしの空間でも後悔しない収納づくりとカップボード活用法

パントリーの奥行きは、収納のしやすさや動線の快適さを左右する大切なポイントです。
奥行きが深すぎると物が埋もれ、浅すぎると収納量が足りず、思うように使えないこともあります。どんな奥行きを選ぶかによって、キッチン全体の印象や作業効率も大きく変わります。
ここでは、奥行きごとの特徴を比較しながら、暮らしに合った最適なバランスを見つけるための考え方を紹介します。
さらに、30cm収納ボックスを基準にした棚設計のコツや、可動棚・無印良品アイテムを活用した実践的な工夫も解説。
奥行きを味方につけて、見た目にも使い勝手にも優れた理想のパントリー収納を実現しましょう。
パントリーの奥行きは、毎日の使い心地を大きく左右する要素の一つです。奥行きが深ければ収納量は増えますが、奥のものが取り出しにくくなり、気づかぬうちに賞味期限を切らしてしまうこともあります。
反対に浅すぎると収納できるサイズが限られ、背の高い調味料や大きめの保存容器が入りにくくなることもあります。
収納量と使いやすさのバランスを考えると、手を伸ばしたときに奥まで自然に届く30〜45cmが、最も使いやすい範囲といえます。
この奥行きが心地よい理由のひとつは、視認性と動作のしやすさにあります。一般的に成人の前腕長は45〜50cmほどとされ、棚の奥行きが45cmを超えると、体をひねったり屈んだりして取り出す動作が増えます。
30cm前後なら、缶詰やレトルト食品、調味料ボトルなどを一列に並べても奥が見えやすく、ラベルを前に向けて整然と管理できます。
45cm付近であれば、2Lペットボトルの短辺向き配置や小型米びつも収まりやすく、収納量と使いやすさを兼ね備えたサイズといえます。
また、30〜45cmの奥行きは空間全体の印象にも影響します。深すぎる棚は圧迫感を生みがちですが、この範囲であれば棚の奥まで自然光が届きやすく、明るく開放的な印象を保てます。
掃除や整理の際にも、奥まで手が届くためメンテナンスが簡単で、清潔な状態を保ちやすい点も見逃せません。
家事動線の面でも、調理スペースから最短距離で手を伸ばせるため、ストレスの少ない動きが可能になります。
したがって、30〜45cmという奥行きは、見やすさ、使いやすさ、収納力、空間の印象という複数の観点からみて、最もバランスの取れたサイズといえます。
キッチンのレイアウトや家族構成によって微調整は必要ですが、この範囲を基準にすれば、多くの家庭で快適なパントリーを実現できます。(出典:国土交通省 住宅性能表示制度 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html)
同じパントリーでも、置くものや使う人の習慣によって最適な奥行きは変わります。40cm、45cm、60cmといった代表的なサイズには、それぞれに特徴と使い方の違いがあります。
| 奥行き | 収納できる主な物 | 視認性・取り出しやすさ | おすすめのパントリータイプ | 向いている家庭像 |
|---|---|---|---|---|
| 40cm | 缶詰、パスタ、調味料ボトル、中型容器、A4ファイルボックス | 一列収納で中身が見えやすく、出し入れがスムーズ | 壁面収納・背面収納 | 買い置きよりも回転率を重視する家庭 |
| 45cm | ペットボトル短辺向き、小型家電、米びつ | 視認性と収納量のバランスが良い | 背面収納・ウォークスルー型 | まとめ買いをする家庭 |
| 60cm | 飲料ケース、大型家電、非常食ストック | 収納量は多いが奥行きが深く死角が生まれやすい | ウォークイン型・コの字型収納 | 大家族や防災備蓄を重視する家庭 |
40cmの棚は奥行きが浅いため、必要なものをすぐに見つけやすく、日常使いの食品や調味料を効率よく管理できます。45cmになると収納量が増え、多少の家電や大きめのボトルも収まりやすくなります。
60cmは広い空間を必要としますが、家電や非常時の備蓄をまとめて収納できる利点があります。動線を意識してスライド棚や引き出しを組み合わせると、深さのデメリットをカバーできます。
I型キッチンの背面収納では、40〜45cmが扱いやすく、調理中の動線を妨げません。L型やアイランドキッチンでは、通路幅を70cm以上確保したうえで片側60cm、もう一方を45cmとする組み合わせが効果的です。
玄関とキッチンをつなぐウォークスルー型パントリーでは、下段を60cm、上段を45cmと段ごとに変える設計が便利です。こうした組み合わせにより、収納と動線の両方を最適化できます。
棚の設計を考えるうえで、収納ボックスのサイズを基準にすることはとても有効です。
市販のボックスは短辺26〜30cm、長辺35〜40cm程度のものが多く、このサイズに合わせて棚を31〜33cm程度に設計すると、見た目にも美しく、引き出すときの動作も自然になります。
手前に少し余裕を持たせることで、ボックスをつまむ際に指がかかりやすくなり、日常の小さな動作が格段にスムーズになります。
段の高さは5cm刻みで可動にしておくと、調味料やペットボトル、粉物のキャニスターなど高さの異なるものに柔軟に対応できます。
季節ごとに収納するものが変わる家庭では、棚板の位置を簡単に変えられる設計が長く快適に使えます。
上段には軽いもの、目線から腰の高さには使用頻度の高い食品、下段には重い飲料や米を配置することで、重心の安定と安全性を確保できます。
また、中段をあえて空けておき、買い物帰りの荷物を仮置きしたり、家電の一時使用スペースにしたりするのもおすすめです。
これにより動線が整理され、使い終わった後の片付けもスムーズになります。奥のボックスを引き出しやすくするために、キャスター付きトレーを敷いたり、後列に透明素材を使ったりする工夫も効果的です。
最後に、棚板の素材にも注目しましょう。木製は温かみがあり、スチール製は耐久性に優れます。湿気の多い場所では、通気性のある素材や防湿加工された板を選ぶと、長く清潔な状態を保てます。
耐荷重を考慮した設計にしておけば、長期間使っても歪みやたわみが生じにくく、安心して利用できます。
可動棚は、季節やライフスタイルの変化に合わせて柔軟に対応できる収納方法として、多くの住宅で採用されています。その最大の魅力は、収納する物の形状や高さに応じて棚板を自在に調整できる点にあります。
瓶詰めや調味料、ストック食材、さらにはキッチン家電まで、多様なアイテムをすっきり収めることができます。
棚板の高さは、一般的に目線から腰の高さまでの範囲を「頻繁に使う帯域」として設定すると、出し入れがスムーズになります。
ピッチは25mmまたは32mm間隔が扱いやすく、食品ストックを詰め込みすぎず、空間に余白を残すことで、見通しの良い収納が実現します。
棚板の奥行きは一律ではなく、上段を浅め、中段を標準、下段をやや深めにすると、全体に軽やかさが生まれます。これは、上を見上げた際の圧迫感を軽減し、動作の自然さを維持する効果があります。
素材面でも、耐荷重や通気性に注目が必要です。厚みのある棚板や補強レールを用いることで、長期使用によるたわみを防げます。
湿気がこもりやすい場所では、通気孔のある棚板を採用すると、食品が湿気に触れにくくなり、保存状態を保ちやすくなります。
また、奥行きのある棚にはLED照明をやわらかく仕込むと、ラベルの視認性が向上し、探し物にかかる時間も短縮できます。
使い勝手をさらに高めるには、棚板を一枚外して作業台として使う方法も有効です。買い物袋の仮置き場や、詰め替え作業の一時スペースとして活用すれば、動線がスムーズになり、整理整頓の意識も自然に続きます。
ローリングストックを意識して、古い食材は手前、新しいものを奥に配置する流れをつくると、在庫の管理も容易です。
| ピッチ設定 | 主な収納アイテム | 特徴と活用ポイント |
|---|---|---|
| 25mm刻み | スパイス瓶・レトルト食品 | 細かい調整でデッドスペースを減らせる |
| 32mm刻み | ペットボトル・缶詰 | 汎用性が高く、季節ごとの入れ替えも容易 |
| 50mm刻み | 家電・保存瓶 | 高さのある物に対応し、収納量を確保できる |
無印良品の収納アイテムは、見た目の統一感と機能性の高さでパントリー収納にぴったりです。色味を白や半透明、木目調に統一することで、棚全体の印象が柔らかく整い、空間に穏やかなリズムが生まれます。
特に人気なのがファイルボックスとポリプロピレンケースの組み合わせです。ファイルボックスは袋入りの食品や調味料を立てて収納するのに最適で、中身を立体的に見せることで無駄が減ります。
ポリプロピレンケースは透明度が高く、中身が一目で確認できるため、使い忘れを防げます。やわらかポリエチレンケースは、軽量で手触りも柔らかく、子どものお菓子や小物類の整理にも向いています。
棚の奥行きに合わせてアイテムを選ぶと、収納効率が大きく変わります。浅めの棚にはファイルボックス、中間の棚にはポリプロピレンケース、深めの棚にはキャスター付きトレーを組み合わせることで、前後の動きが滑らかになり、奥の物もストレスなく取り出せます。
紙ラベルはシンプルなフォントで統一し、位置をそろえるだけで整った印象になります。素材の組み合わせも、木・白・ステンレスの3色に抑えると、全体が静かで温かみのある雰囲気になります。
| 棚奥行き | 適したアイテム | 活用のコツ |
|---|---|---|
| 約30〜33cm | ファイルボックス・やわらかポリエチレンケース | 手前に2〜3cmの余白を確保すると操作がしやすい |
| 約40〜45cm | PP引き出し・ワイヤーバスケット | ラベルを統一して視線の流れを整える |
| 約60cm | キャスター付トレー・ワゴン | 奥行きを活かし、引き出して使える設計にする |
奥行きのあるパントリーは収納力が高い一方で、奥に物が埋もれやすくなります。そのため、奥行きを味方にする設計が求められます。
下段にはキャスター付きの収納ボックスを配置し、重い飲料や米袋を前へ引き出せるようにしておくと便利です。こうした移動式収納を採用することで、掃除や模様替えの際にも手軽に動かせ、床面の衛生も保ちやすくなります。
また、ボックスの材質をポリプロピレンやスチール製にするかで、耐久性や滑りやすさが異なるため、重量や用途に合わせた選定が大切です。
中段には引き出し式トレーを導入し、頻繁に使う食品を手前に、予備のストックを奥に分けて配置すると、効率的に管理できます。
引き出しの高さや深さを食品の種類に合わせて変えることで、取り出しやすさが格段に向上します。たとえば缶詰や瓶類は浅め、乾物や調味料の詰め替え袋は深めに分けると、並びが乱れにくくなります。
さらに、トレー底に滑り止めマットを敷くと、引き出し操作時の振動を抑え、静かな動作が実現します。
スライドラックを導入すれば、棚を丸ごと引き出せるため、奥のスペースを有効活用できます。棚下にレールを設置するタイプや、上面を支える吊り下げ型など、住宅の構造に合わせて選べる製品が増えています。
既存の棚にも後付け可能なレール式トレーがあり、DIY感覚で導入できる点も魅力です。扉付きのパントリーでは、引き出し時に扉と干渉しないよう、開口幅とレールの長さを事前に確認しておくと安心です。
照明を手前上部に設置すれば、奥まで明るくなり、探す動作が軽減されます。特にセンサーライトを採用すると、扉を開けた瞬間に自動で点灯し、夜間でも快適に使用できます。
深いパントリーでは、在庫管理を視覚的に行う仕組みも役立ちます。期限の近い物を手前に置き、補充は奥から行うローリングストック方式を取り入れると、無駄が減り、食品ロスの防止にもつながります。
加えて、ラベルに購入日と使用期限を明記しておくと、入れ替え作業の精度が高まります。棚内に小さなホワイトボードを設け、在庫数を簡単にメモできるようにしておくと、家族全員が共有しやすくなります。
消費者庁でも、家庭での備蓄は普段使いながら補充する循環型が推奨されています(出典:消費者庁 食品ロスにしない備蓄のすすめhttps://www.no-foodloss.caa.go.jp/topic_mar.html)。
深さのある棚は、見せ方としまい方のバランスも大切です。すべてを隠すのではなく、手に取りやすい定位置を残すことで、戻す動きが自然と続きます。
さらに、季節や行事に応じて棚の配置を少し変えると、飽きずに整理を保ちやすくなります。季節の変わり目に一度見直しを行うだけでも、パントリー全体の空気が入れ替わり、心地よい空間が保たれます。
照明や香りを加えると、毎日の家事が少し特別に感じられるようになります。

パントリーは、単に収納する場所ではなく、暮らしの流れを整える大切な空間です。奥行きや幅、通路の取り方ひとつで、毎日の使いやすさが驚くほど変わります。
動線がスムーズであれば、調理や片付けが自然と効率的になり、家事のストレスも軽減されます。この章では、90cm幅を活かしたレイアウトや、奥行き設計で失敗しないためのポイントを解説します。
また、パントリーがない住まいでも、カップボードや収納棚を工夫して同じ機能を実現する方法を紹介。動線とバランスを意識すれば、限られたスペースでも心地よく使えるパントリーがつくれます。
90cmという寸法は、暮らしの中で非常にバランスの取れた幅です。人が通り抜ける余白と、しっかりとした収納力を両立しやすいため、小さなスペースでも計画が立てやすくなります。
壁面に沿った一直線の棚構成はもちろん、L字やコの字のように囲う形にしても、無理のない動きが生まれます。
特に90cm前後で設計すると、手の届く範囲と視界のバランスがよく、動作が流れるようにつながるのが特徴です。
棚を配置する際は、単に並べるだけでなく、使う頻度や重さを意識してゾーニングを行うと整います。
目線から腰の高さは、毎日使う調味料や保存食、上段には軽くて安全なストック品、下段には飲料水や米など重いものを置くと、自然と作業の流れが整います。
奥行きを35cm〜45cmに抑えると、物の把握がしやすく、無駄な買い足しを防ぐことができます。さらに、奥行きの異なる棚を組み合わせることで、通路幅に余裕を残しながら収納量を増やすこともできます。
動線計画では、扉の開閉方向やレイアウトの干渉に注意しましょう。開き扉の場合は、扉を開けたときに通路が圧迫されないように、90cm幅を確保しておくとスムーズに出入りができます。
引き戸やロールスクリーンを採用すると、動きがより軽やかになります。収納動作を一歩で完結できるように設計することが、整った暮らしを維持する大きな助けになります。
また、90cm幅では、通路と収納のリズムをつくることがポイントです。
棚の手前に2〜3cmの指がかかる余白を残しておくと、ケースを引き出しやすくなり、作業がより滑らかに。ラベルの位置を棚下端から一定の高さにそろえることで、見た目の統一感と視認性が高まります。
こうした小さな積み重ねが、動きやすく美しい収納につながります。
| 幅90cmのレイアウト | 棚奥行きの目安 | 通路の目安 | 特徴と向いている使い方 |
|---|---|---|---|
| 片側壁面棚+通路 | 30〜45cm | 45〜60cm | 壁面に沿って一直線。料理中に振り返って取りやすい配置に向く |
| コの字(短辺90cm) | 30cm+30cm | 30〜40cm | 三方向から手が届く。細かな食品や小物の定位置管理に向く |
| L字(長辺90cm) | 45cm | 45cm | コーナーを活かして家電や米びつを収めやすい |
このように、90cmという寸法は住まいのリズムを崩さず、家事を穏やかに支えてくれる頼もしい設計寸法です。限られたスペースでも工夫次第で、動きやすく心地よいキッチン空間が実現します。
パントリーの奥行きは、見た目以上に使い勝手を左右します。深すぎる棚は奥の物が埋もれ、浅すぎる棚は収納しきれずに他の場所へ分散する原因になります。
理想的な奥行きは、収納したい物の大きさを基準に考えるとよいでしょう。ペットボトルや保存瓶が多い場合は40〜45cm、缶詰や乾物が中心なら30cm前後でも十分です。
60cmを超える奥行きを設ける場合は、引き出しトレーやスライドラックを取り入れて、奥の物も取り出しやすくする工夫が欠かせません。
照明計画も、使い心地を左右する大切な要素です。棚の奥まで明るさが届かないと、探す手間が増えてしまいます。天井照明に頼らず、手前上部に小型のLEDライトを取り付けると、奥までやわらかい光が届きます。
センサー式の照明を採用すれば、扉を開けるだけで自動的に点灯し、夜間の使用も快適になります。光の色は昼白色を選ぶと、食品の色が自然に見え、ラベルの文字も判別しやすくなります。
通気性の確保も忘れてはいけません。通気孔付きの棚板やワイヤーバスケットを組み合わせると、空気が滞らず、湿気による劣化を防ぐことができます。
特に湿度の高い季節には、棚の下部に除湿剤を設けるか、定期的に換気を行うことで、カビやにおいの発生を防げます。収納の快適さは、こうした小さな積み重ねから生まれます。
また、家庭での備蓄を管理する際は、消費期限の近い物を手前に、補充は奥から行うローリングストックを意識すると無駄が減ります。
これは消費者庁も推奨しており、普段使いながら備える仕組みとして、食品ロス防止にもつながります(出典:消費者庁 家庭での備蓄を考えよう )。
このように、奥行きの設計には、使う人の動作・照明・空気の流れを見据えた配慮が大切です。奥まで見える、取りやすい、心地よい空間を意識することで、後悔のないパントリーが生まれます。
専用のパントリーがない場合でも、カップボードや可動棚を工夫すれば、機能的で心地よい収納がつくれます。特に、背面カウンターを中心に配置を整えると、家事の流れが美しくまとまります。
調理と片付けの動線を短くし、必要な物が手の届く範囲にあることで、家事の負担が軽くなります。
カップボードのカウンター上は、調理家電を並べるだけでなく、配膳の一時置きにも活用できます。すぐ上に吊り戸棚を設ければ、使用頻度の高い食器や保存容器を取り出しやすくなります。
奥行き45〜65cmのカウンターがあれば、家電を一列に並べてもゆとりが生まれ、見た目もすっきりします。
収納の工夫としては、浅い引き出しにはカトラリーや調味料、深い引き出しにはストック食品やキッチンペーパーなどを分けると、整理が長続きします。
さらに、ラベルや容器の色を揃えることで、視覚的なノイズが減り、空間に統一感が生まれます。30cmほどの浅いオープン棚を壁面に足すと、スパイスやマグカップなど、毎日使う物の定位置として便利です。
| レイアウト | 推奨寸法の目安 | 使い方のポイント |
|---|---|---|
| 背面カップボード一体型 | 奥行き45〜65cm・高さ85cm前後 | 家電を横並びに配置し、真上に器と保存容器。配線は背面に余白を確保 |
| 吊り戸棚+カウンター | 奥行き30〜35cm・手が届く高さ | 軽い食器と乾物を上段に。踏み台なしで届く範囲に配置 |
| 壁面オープン棚追加 | 奥行き25〜30cm | 毎日使う物をすぐ取れる位置に設置し、明るく開放的な印象に |
小さなスペースでも、配置と工夫次第で十分な収納力を発揮できます。暮らしのリズムに寄り添う収納をつくることが、心地よいキッチンを保つ秘訣です。
パントリーがなくても、動線とゾーニングを意識すれば快適な収納計画を立てることができます。まずは、買い物から調理、片付けまでの一連の流れを可視化し、それぞれの動作がスムーズにつながるように配置を考えましょう。
玄関からキッチンへ入る途中に荷物の一時置き場を設けると、帰宅後の動きが自然になります。
ゾーニングでは、使用頻度や重さを基準に収納場所を決めることが大切です。よく使う軽い物は腰から目線の高さに、使用頻度の低い物は上段や下段に配置します。
家族構成に合わせた高さ調整も有効で、子どもが取りやすい位置には軽いお菓子やお手伝い道具を、大人だけが扱う調理器具は上段にまとめると安全です。全員が共通のルールで使える空間をつくると、片付けが自然に続きます。
ストック量は、収納容量の70%程度で運用するのが理想的です。余白を残すことで、買い物の増減や季節の入れ替えにも柔軟に対応できます。
過剰に詰め込みすぎると、奥の物を見落としがちになり、同じ商品を重複して購入する原因になります。ローリングストックの考え方を取り入れ、手前から使い、奥に補充するサイクルを意識すると、賞味期限切れを防げます。
そして、見た目の心地よさも収納計画には欠かせません。ラベルや容器の統一、光の入り方、照明の色温度を整えることで、穏やかな印象が生まれます。
朝の自然光と夜の照明が違和感なくつながるように設計すると、時間帯を問わず快適に過ごせます。季節ごとに棚を見直す習慣を取り入れると、空間が呼吸し、家事のモチベーションも保ちやすくなります。
パントリーの奥行きや幅を正しく計画することは、日々の家事をスムーズにし、暮らしの質を大きく高める鍵になります。
深すぎても浅すぎても使いづらく、ちょうど良いバランスを見つけることが後悔のない収納づくりの第一歩です。
本記事を通して見えてきたのは、見た目だけでなく、動線・照明・通気性など多面的な視点から空間を整えることの大切さです。
まず、パントリーの奥行きは30〜45cmを基準に考えると、取り出しやすさと収納力の両立がしやすくなります。
また、奥行き40・45・60cm収納の特徴を理解しておくと、自分の生活スタイルに合ったベストな寸法を判断しやすくなります。
30cm収納ボックスを基準にした棚設計や可動棚を活用することで、柔軟に変化する暮らしにも対応できます。
さらに、無印アイテムなどシンプルで機能的な収納グッズを取り入れることで、見た目にも穏やかで統一感のある空間が生まれます。
パントリーがある家も、ない家も大切なのは「暮らしに合った動線」をつくることです
。90cm幅を基準にしたレイアウトや、通路とのバランスを意識した配置を整えることで、家事の流れが驚くほどスムーズになります。
もしパントリーがなくても、カップボードを上手に活用すれば同じ機能を果たす収納を実現できます。
- 奥行きと動線を両立させた使いやすい収納を計画する
- 可動棚や収納ボックスを活かして変化に強い空間にする
- 照明・通気性・配置を見直して後悔のない設計に整える
- パントリーなしでも工夫次第で快適な収納を実現する
最後に大切なのは、設計図の上だけで考えず、実際の動作や暮らし方を思い浮かべながら形にすることです。
自分や家族の生活に寄り添うパントリー設計こそが、日々の小さなストレスを減らし、心地よい暮らしを支える最良の答えになります。
新築を考えているなら、理想のパントリー設計は間取りの段階で決めることが大切です。奥行きや棚の寸法をあとから調整するのは意外と難しく、動線や収納量に後悔が残るケースも少なくありません。
タウンライフ家づくりなら、あなたの希望をもとに無料で間取りプランと収納提案を受け取れます。実際の生活動作をもとに、プロが奥行きや通路幅まで考えた最適なパントリー配置を提案してくれるから安心です。
「自分の家ならどんな間取りになるんだろう?」と思った今がチャンスです。3分で入力できて、複数のハウスメーカーの提案をまとめて比較できます。
間取りを見て後悔ゼロへ
【PR】タウンライフ