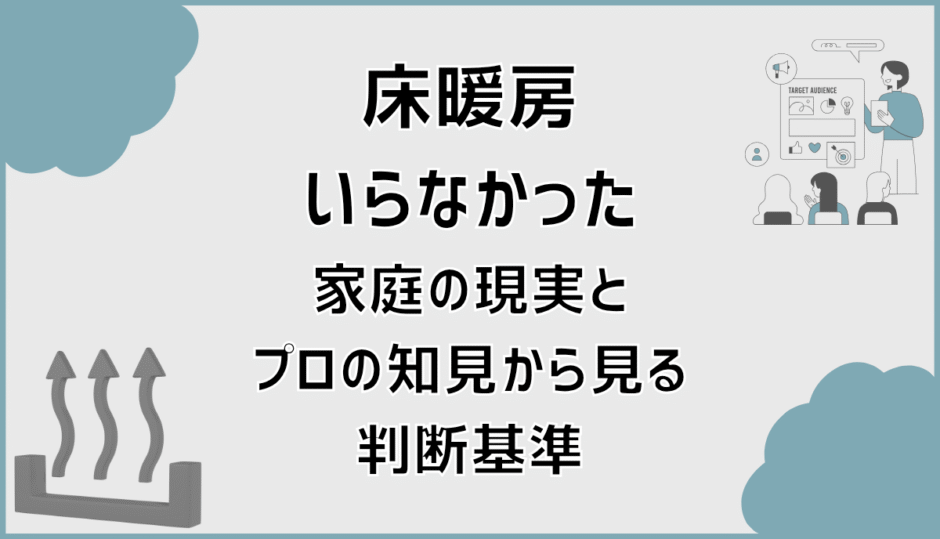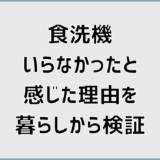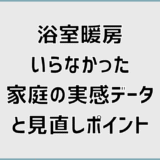この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
床暖房いらなかったという声を耳にすると、「本当に必要なのかな?」と迷う方も多いと思います。
快適そうだけれどコストやメンテナンスが気になる、そんな疑問を抱えながら家づくりを進めている方もいるのではないでしょうか。
実際、一条工務店のように高気密高断熱の住宅では、床暖房いらないと感じるケースも増えています。
では、使わないとどうなるのか、そして後悔しないためにはどんな判断が必要なのでしょうか。
ここでは、床暖房つけなくて後悔した人の実例や、つけてないのに暖かい家を実現した工夫をもとに、快適な冬の過ごし方をわかりやすく解説します。
また、10年後に見えてくるコストや劣化の現実、夏はどうするのかという視点、さらには意外と知られていないゴキブリ対策との関係性まで、実生活に寄り添った情報をまとめました。
暖かさの感じ方は人それぞれですが、家の性能や地域によって「ちょうどいい暖房の形」は変わります。
この記事を通して、あなたの住まいに合った最適な選択を見つけるきっかけになれば嬉しいです。設備を増やすことだけが快適な家づくりではありません。
後悔のない判断をするためのヒントを、実例とデータの両面からお届けします。
- 床暖房いらなかったと感じる家庭の特徴と、快適に暮らせる家の条件
- 床暖房を使わない場合の注意点や、つけなくて後悔した事例から学ぶ判断基準
- つけてないのに暖かい家づくりの工夫と、10年後に差が出るコストの考え方
- 夏の快適対策やゴキブリ対策など、床暖房なしでも快適に暮らすための実践ポイント
※この記事は「新築いらない設備まとめ|体験と傾向から学ぶ必要・不要の見極め方」(まとめ記事はこちら)の関連コンテンツです。

家づくりで迷いやすいのが、床暖房を本当に付けるべきかどうかです。快適そうだけれど費用や使い勝手が気になる、という方は多いですよね。
ここでは、いらなかったと感じやすい条件や判断の物差しを、実例と注意点から整理します。一条工務店で床暖房いらないと言われる家の特徴を押さえ、床暖房いらなかった人が語るリアルな理由をひも解きます。
さらに、使わない場合に起こりがちなポイント、そしてつけなくて後悔したケースまで具体的に解説し、あなたの最適解を見つける道筋を示します。
一条工務店のように高気密・高断熱性能を標準仕様としている住宅では、同じ外気温でも室温の低下がゆるやかで、わずかな熱量で十分な快適さを維持できます。
そのため、エアコンを計画的に運転し、換気システムとバランスよく連動させるだけで冬場の室内環境を安定的に保てる場合が多く、床暖房の必要性を感じない家庭も少なくありません。
ここでは、床暖房を設けなくても快適と判断される典型的な条件を詳しく見ていきます。
まず注目すべきは、外皮性能のレベルです。断熱等性能等級や外皮平均熱貫流率(UA値)、気密性能(C値)が一定基準以上に整っていれば、室内の熱は逃げにくく、床面の温度も極端に下がりません。
たとえばUA値0.4W/㎡K前後、C値0.5cm²/m²以下の住宅であれば、エアコンのみでも20℃前後を維持できるケースが多いとされています(出典:国土交通省 省エネルギー基準資料 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shoenehou.html)。
ただし、これらの数値はあくまで目安であり、実際の快適性は設計者が算出する熱損失計算や地域気候の条件によって異なります。
さらに、間取りと熱の循環も影響します。吹き抜けやリビング階段のある住まいでは、サーキュレーターやシーリングファンを活用して上下の温度ムラを整えることが重要です。
空気の流れを計画的に作ることで、床付近の冷気が滞留しにくくなり、床暖房なしでも足元の快適性を維持しやすくなります。
ドアの開閉頻度、階段の位置、間仕切りの配置など、設計段階での配慮が体感に直結します。
地域の気候条件も判断に大きく関わります。南関東や瀬戸内沿岸など、冬でも氷点下が少ない地域では、朝の冷え込みをエアコンでカバーするだけで十分暖かいと感じる人が多いようです。
逆に寒冷地であっても、日射取得をうまく取り入れた設計や、高断熱窓を採用した住宅では、床暖房を使わなくても安定した室温が確保されています。
窓の性能と換気方式の相性も見逃せません。断熱性の高い窓(熱貫流率の低いもの)を選ぶことで、コールドドラフトと呼ばれる冷気の流れを抑制でき、床際の寒さを感じにくくなります。
さらに、第一種熱交換換気システムを採用することで、外気を取り込む際の温度差を軽減し、冷え込みを和らげる効果が期待できます。
こうした細部の計画が積み重なることで、床暖房の有無による体感差は小さくなるのです。
このように、外皮性能・窓仕様・換気計画・空気循環の4要素がバランスよく設計された住宅では、床暖房を設けなくても十分な快適性を得られることが多いと考えられます。
正確な性能評価やコストの比較を行う際は、公式資料を確認し、最終的な判断は設計者や専門家へ相談することをおすすめします。
床暖房を採用しない選択だけでなく、エアコンを主暖房とし、補助的に小規模な床暖房やパネルヒーターを組み合わせる方法も効果的です。
これにより、初期投資を抑えつつ、必要なときに必要な場所だけを温める柔軟な暖房計画が可能になります。過剰な設備導入を避け、運用の工夫で快適性を高める考え方が、これからの省エネ住宅の鍵となります。
床暖房を導入したものの、思ったほど使用しなかったと感じる背景には、いくつかの共通点があります。
代表的なのは、初期投資の大きさに対して稼働時間が短いこと、ランニングコストの上昇、立ち上がりの遅さ、床材やデザインの制約、そして家族の体感温度の違いです。
これらの要素が重なり、結果的に「いらなかった」との声につながる傾向が見られます。
まず多く挙げられるのが光熱費です。床暖房は広い範囲を長時間温めるため、運転時間が増えるほど電気代やガス代の負担が大きくなりがちです。
特に最近では、ヒートポンプ式エアコンの省エネ性能が高く、同じ温度帯を維持する場合にはエアコン暖房のほうが効率的だとされるケースもあります。
こうした経済的側面から、設置しても使用頻度が減る家庭が少なくありません。費用はあくまで一般的な目安であり、実際の数値は地域や使用条件によって大きく異なります。
次に注目すべきは即暖性です。床暖房は輻射と伝導によってゆっくりと温める仕組みのため、電源を入れてすぐに暖かくなるわけではありません。
寒い朝や帰宅直後など、すぐに快適さを得たい場面では、結局エアコンやファンヒーターを併用する家庭が多いのが実情です。その結果、床暖房をメイン暖房として活用する機会が減り、稼働率が低下していきます。
また、床暖房対応の床材には制約があります。一般的な無垢フローリングでは熱による伸縮や割れが起こりやすく、専用の対応製品を選ぶ必要が出てきます。
その分コストが上がることや、インテリアデザインの自由度が狭まることを懸念する声もあります。デザインを重視する住宅では、床暖房を設けない方がかえって空間づくりを自由に行える場合もあります。
家族の温度感覚の違いも軽視できません。例えば暑がりな家族がいると温度設定が低めになり、結果として使用しなくなるケースがあります。
さらに、使用シーズンが限定的で、春や秋には全く稼働しないため、設備としての存在感が薄れていくことも珍しくありません。
これらのことから、床暖房は住宅性能やライフスタイルに合わないと満足度が下がりやすい設備だと整理できます。設備投資を無駄にしないためにも、住宅性能や地域の気候条件をふまえて総合的に判断することが大切です。
正確な費用や性能については、メーカーや施工会社の公式資料を必ず確認し、最終的な判断は専門家に相談してください。
| 項目 | 床暖房 | エアコン (ヒートポンプ) | こたつ・ホットカーペット |
|---|---|---|---|
| 初期費用 (目安の傾向) | 高め | 中程度 | 低め |
| 立ち上がり | 穏やかで時間がかかる | 即暖性が高い | 即暖性が高い |
| ランニングコスト (傾向) | 使用面積と時間に比例 | 高効率で抑えやすい | 局所使用で低コスト |
| 体感 | 足元からじんわり温まる | 風で素早く暖める | 局所的に直接暖かい |
| 乾燥・埃 | 空気を動かさないため少ない | 乾燥しやすいが対策可能 | 比較的少ない |
| 安全性・意匠 | 機器が露出せずすっきり | 室内機が露出 | 機器の出し入れが必要 |
上記は一般的な傾向であり、実際のコストや性能は製品仕様や設置条件によって異なります。
最新のデータや詳細はメーカー公式サイトなどで確認し、疑問があれば専門家への相談をおすすめします。
床暖房を長期間使わずに放置しておくと、設備の種類によっては不具合のリスクが高まる場合があります。
特に温水式では、配管内の水質が悪化したり、不凍液が劣化して粘度が変わったり、循環ポンプが固着するケースがあるといわれています。
一方、電気式でも長期間通電しないままだと、発熱体やコントローラに不具合が起きていても気づきにくく、いざ使おうとしたときにトラブルが発覚することがあります。
ここでは、使わない期間が長いときに意識しておきたい注意点を整理しておきましょう。
まず大切なのは、季節の変わり目に定期的な点検を行うことです。暖房シーズンが始まる前に短時間だけ試運転をして、温度の上がり方や異音・異臭、エラー表示の有無を確認するだけでも、故障の早期発見につながります。
温水式では、系統内の圧力や循環状態をチェックし、気になる点があれば施工会社やメーカーの点検を受けましょう。メーカーが推奨する点検サイクルや消耗品交換の目安はあくまで一般的な基準とされています。
正確な内容は公式資料を確認し、必要に応じて専門家に相談するのが安心です。
次に意識したいのが湿気とカビ対策です。使用していない期間でも、床下や機器周辺に湿気がこもると、配管や部品の腐食、カビの発生などを招くおそれがあります。
特に梅雨の時期は湿度が上がりやすいため、除湿器を使ったり、通風を確保したりして環境を整えることが大切です。
床材の膨張や収縮は湿度変化の影響を受けやすいため、極端な乾燥や過湿を避けることで、設備と床の両方を長持ちさせられます。
温水式の場合は、不凍液の状態にも注意が必要です。交換の目安や費用はメーカーや仕様によって異なり、一般的には5〜10年ごとに交換が推奨される場合がありますが、これはあくまで目安です。
使用環境や地域の気候によって適切なタイミングは変わるため、専門業者に相談して判断するのが安全です。不凍液の交換や廃液の処理は安全管理の観点からも業者依頼が望ましいとされています。
電気式の床暖房でも、サーモスタットや温度センサーの動作確認を毎シーズン行うことで、トラブルの予防につながります。
とくに長期間使用していない場合は、いきなり本格運転をするのではなく、短時間ずつ稼働させて様子を見ると安心です。
つまり、床暖房を「使わない」と決めたとしても、年に一度の試運転と環境チェックを欠かさなければ、劣化やトラブルのリスクは最小限に抑えられます。
正確なメンテナンス手順はメーカーの取扱説明書や施工会社の案内を必ず確認し、不安がある場合は専門家への相談をおすすめします。
床暖房を採用しなかった結果、冬の体感が思っていたよりも厳しく、あとから「やはり設けておけばよかった」と感じるケースも少なくありません。
その背景を掘り下げてみると、窓性能の過小評価や日射取得の不足、動線設計の盲点、冷気が溜まりやすいレイアウト、そして地域の気候条件の想定不足など、複数の要因が重なっていることが多いようです。
中でも特に影響が大きいのが、窓の仕様です。北面や大開口の窓から熱が逃げやすいと、足元に冷気が流れ込み、室温計の数字以上に寒く感じてしまいます。
床暖房があれば輻射熱によってこの体感差を和らげられますが、設けていない場合はラグを敷いたり、内窓やロールスクリーンを活用したりして局所的に冷気を抑える工夫が必要になります。
窓断熱の重要性を軽く見積もったことが、後悔の引き金になるケースは非常に多いといえます。
また、寒冷地では暖房の立ち上がりが暮らしの質に直結します。
朝の短い時間で一気に室温を上げるには、床暖房単体よりもエアコンや温水ファンヒーターなどの即暖性の高い熱源を併用する設計が望ましいのですが、床暖房を設けない前提でその計画を十分に立てていないと、朝晩の冷え込みが厳しく感じられることがあります。
特に、エアコンの能力選定や吹き出し方向、サーキュレーターの配置が適切でない場合、床際の冷気が溜まりやすく、寒さを強く感じやすくなります。
さらに、家族構成やライフスタイルの変化も見落としがちなポイントです。
設計当初は必要ないと判断しても、将来的に在宅時間が増えたり、乳幼児や高齢者がいる生活に変わったりすると、足元からの暖かさの恩恵が大きくなります。
特に冷え性の方や小さな子どもがいるご家庭では、床暖房の有無が快適性に大きく影響する場合もあります。
これらを踏まえると、床暖房を設けない判断をする際には、窓性能と日射計画、エアコン能力と配置、空気の流れ、そして将来のライフステージの変化までを含めて慎重に検討することが欠かせません。
迷うときは、冬季のモデルハウスや入居者宅を複数回体験し、実際の体感と温度データを確認してみると安心です。
最終的な判断を下す際は、設計者や専門家に相談し、正確な情報は必ずメーカーや公的機関の公式資料を参照してください。

家を建てたあとで「床暖房をつけなくてもよかった」と感じる人がいる一方で、「やっぱり付ければよかった」と後悔するケースもあります。
ここでは、そうした後悔を防ぐために知っておきたい知識と対策をわかりやすく整理します。床暖房の10年後に見えてくるコストや劣化の実態を踏まえ、つけていなくても暖かい家づくりのポイントを詳しく紹介。
さらに、夏の快適性や湿気対策、意外と見落とされがちなゴキブリ対策との関係まで掘り下げます。長く快適に暮らすためには、導入の有無だけでなく、家全体の性能と住まい方のバランスを考えることが大切です。
専門家の意見も参考にしながら、あなたの家に本当に合った選択を見つけていきましょう。
新築当初は快適さを期待して導入される床暖房ですが、設備は年月の経過とともに必ず劣化していきます。
特に温水式床暖房は、熱源機や配管、不凍液、コントローラなど複数の部材から構成されており、それぞれに寿命があります。
おおよそ10年を過ぎた頃から点検や部品交換を検討する時期を迎えると考えておくと安心です。
メーカーによっては、熱源機の設計上の標準使用期間を10年と定めており、修理部品の供給期限もそれに合わせて設定されています(出典:リンナイ ガス給湯暖房熱源機の設計上の標準使用期間 10年 https://www.rinnai.co.jp/safety/system/info/ground/h_warm/)。
さらに、温水循環に使われる不凍液(暖房水)は、時間の経過とともに熱伝導性や防錆性能が低下していきます。メーカーによると、一般的に2〜3年程度で性能が落ち始め、3年を目安に入れ替えが推奨されています。
暖房水の劣化を放置すると、配管内部の腐食や凍結リスクが高まり、最終的には修理費用の増加につながることがあります。
特に温度変化が激しい地域では劣化スピードが早まる傾向があるため、定期的な点検と専門業者による交換が欠かせません。
交換作業では、配管内の洗浄やエア抜きも併せて行われるのが一般的で、これにより暖房効率の低下を防ぎ、長期的な安定運転を維持することができます。
床暖房にかかる費用は、住まいの構造や地域、導入するシステムの種類によって大きく変わります。初期費用だけでなく、10年、20年と使い続ける中で発生するメンテナンスや交換のコストも想定しておくことが大切です。
以下の表は、一般的な温水式床暖房における維持費や交換の目安をまとめたものです。金額や時期はあくまで参考であり、実際にはメーカーや施工方法によって異なる場合があります。
最新情報や具体的な見積もりは必ず専門業者に確認してください。
| 項目 | 発生時期の目安 | 内容・ポイント | 参考情報 |
|---|---|---|---|
| 熱源機の点検・交換 | 約10年前後 | 使用年数が増えると燃焼効率が落ち、エラー発生率が上昇。修理より交換を選ぶケースも多い | リンナイ 設計上の標準使用期間10年 |
| 不凍液(暖房水)の入替 | 約2〜3年ごと | 劣化により伝熱性能が低下。放置すると配管腐食の恐れ | ノーリツ FAQ「3年程度で入替推奨」 |
| 端末や配管まわりの補修 | 使用環境により異なる | エア噛み・漏れ・弁の不具合などの小修理 | メーカーの点検要領・定期点検基準 |
床暖房は長時間運転することが多く、光熱費は運転方法によって大きく変動します。
特に温水式は立ち上がりに時間がかかるため、連続運転を選ぶ方も多いですが、外気温や在宅時間帯に合わせて運転パターンを調整することで、無駄なエネルギー消費を防ぐことができます。
例えば、省エネ型の熱源機や室温センサーを活用すると、室温が安定しやすくなり、電気代やガス代の削減につながります。
また、資源エネルギー庁の資料によると、家庭全体のエネルギー消費の中で暖房の占める割合は非常に大きく、省エネ対策を行う上で最も効果的な分野とされています(出典:資源エネルギー庁 冬の省エネメニュー(家庭)https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/government/shouene_torikumi.html)。
これらを踏まえると、床暖房を導入する際は、設備費だけでなく光熱費やメンテナンスを含めた「ライフサイクルコスト(初期費用のほかに不凍液の交換や熱源機の更新、電気やガス代など)」で比較検討することがポイントになります。
数値はすべて一般的な目安であり、正確な条件は公式サイトや専門家に確認し、最終判断は専門家の助言をもとに行ってください。
床暖房がなくても、設計を工夫すれば冬も十分に暖かく過ごせます。ポイントは断熱・気密・日射取得・空調のバランスを取ることです。
断熱では、屋根から床まで断熱ラインを切らさず、玄関やバルコニーなど冷えやすい部分も丁寧に処理します。UA値を意識して地域に合った断熱性能を選ぶと効率的です。
気密は、隙間を気密テープや発泡材でしっかり塞ぐことで暖気を逃さず、省エネ性を高められます。
日射取得では、南面の窓を活かして太陽光を取り込み、東西面は庇や外付けブラインドで直射を遮ります。これにより、冬は自然な暖かさを得ながら、夏は過剰な熱を防ぐことができます。
空調は高効率エアコンをメインに、サーキュレーターやシーリングファンを併用して空気を循環させると室温差が少なく快適です。
床下エアコンを採用すれば、設備コストを抑えつつ足元の暖かさを感じられます。
| テーマ | 設計・仕様のポイント | 運用のコツ |
|---|---|---|
| 断熱・気密 | 断熱ラインを連続させ、熱橋を防ぐ | 季節ごとに隙間やパッキンを点検 |
| 日射取得 | 南面で採光、東西面で遮蔽 | 日中に光を取り込み、夜はカーテンで保温 |
| 空調計画 | エアコン+循環気流で温度ムラを抑える | 暖房立ち上げ後は温度を控えめに |
これらを組み合わせることで、床暖房がなくても快適で省エネな住まいが実現できます。数値はあくまで一般的な目安であり、詳細は公式資料を確認し、最終的な判断は専門家にご相談ください。
夏場は熱のこもりや湿気が不快感の原因になります。冬を快適に過ごすだけではなく、夏の快適性も意識した住まいにするためには、通風・日射遮蔽・除湿の3つをバランスよく計画することが大切です。
これらを設計段階から組み込むことで、エアコンに頼りすぎずに過ごせる快適な環境をつくれます。
まず、通風の工夫です。風の通り道をデザインすることで、自然の力を上手に利用できます。風上と風下を意識して窓を配置し、室内の空気が滞留しないようにするのがポイントです。
高窓や吹き抜け上部に排気用の窓を設けると、室内にたまった熱気を逃がしやすくなります。特に夏の夕方は屋根裏や天井付近の温度が上がりやすいため、スタック効果(上昇気流)を利用して熱を抜くと体感温度が下がります。
扉を少し開けておくだけでも風の流れが生まれるため、日常の工夫でも効果を感じやすいでしょう。
次に、日射遮蔽です。日射は室温上昇の大きな要因となるため、できるだけ建物の外側で遮ることが重要です。庇や軒を深く取るほか、外付けブラインドやすだれ、植栽などを組み合わせると、直射日光による輻射熱を効果的に抑えられます。
特に東西方向からの低い日差しは、短時間でも大きな熱負荷になるため、外側でしっかりカットするのがおすすめです。
また、庇の長さや角度を季節ごとに調整する設計も有効で、冬は光を取り込み、夏は遮ることができます。
最後に、除湿の管理です。湿度が高いと、気温が同じでも蒸し暑く感じやすくなります。エアコンのドライ運転や再熱除湿を活用して、湿度を50%前後に保つと快適です。
梅雨の時期や湿度の高い日には、除湿機やサーキュレーターを併用すると効果的です。室内の家具の配置にも注意し、壁際に空気が滞留しないようにするとカビ対策にもつながります。
特に寝室やクローゼットなど、湿気がこもりやすい場所は換気を意識しましょう。
| 対策 | ねらい | 設計・運用のポイント |
|---|---|---|
| 通風計画 | 室内の熱気を逃がす | 風上と風下の開口を意識し、高窓や排気ファンで熱を排出する。室内ドアの通気確保も有効 |
| 日射遮蔽 | 輻射熱の侵入を防ぐ | 軒・庇・外付けブラインド・植栽などを活用。東西面は特に入念に遮る |
| 除湿制御 | 蒸し暑さを軽減する | 湿度50%前後を維持。ドライ運転や除湿機を併用して快適性を保つ |
これらを上手に組み合わせることで、夏でもエアコンに頼りすぎず快適に過ごせる家になります。数値はあくまで一般的な目安であり、建物の構造や地域によって最適な方法は異なります。
正確な情報は公式資料をご確認のうえ、最終的な判断は専門家にご相談ください。
床暖房のある空間は、足元からじんわりと温まり、快適に感じる一方で、室内の湿度が上がりやすくなる傾向があります。これは、床面の温度上昇によって空気中の水分が保持されやすくなるためです。
こうした暖かく湿った環境は、ゴキブリやダニなどの衛生害虫が活発になりやすい条件でもあるため、暖房期であっても衛生管理を意識することが大切です。
日頃から清掃・乾燥・換気・密閉保管を徹底することで、住まいの清潔さを保ちやすくなります。
特に注意したいのが、台所や洗面所、浴室まわりといった「水と食べ物が交わる場所」です。キッチンの巾木や冷蔵庫の背面、配管まわりは、わずかな食べカスや水滴が残ることで害虫の温床になりやすい場所です。
これらの部分は定期的に掃除を行い、油汚れや食渣をためないようにしましょう。食品は必ず密閉容器に入れ、使わなくなった段ボールや紙袋は早めに処分するのがおすすめです。
また、床を水拭きしたあとは乾いた布で仕上げ拭きをして、湿気を残さないように意識しましょう。調理や入浴の後には、数分間でも強制換気を回すことで湿気を外に逃がせます。
さらに、床材の選び方も清潔な環境づくりに大きく影響します。目地の多い床材や凹凸のある仕上げは、どうしても埃や水分が溜まりやすく、清掃の手間が増える傾向があります。
床暖房対応の複合フローリングや、継ぎ目が少なく表面がフラットな素材を選ぶと、汚れがつきにくく掃除もしやすくなります。
特に最近は、抗菌・防カビ仕様の床材も多く、衛生管理のしやすさを重視する方に適しています。
湿度の管理も欠かせません。冬場でも加湿のしすぎは避け、室内の相対湿度をおおよそ50%前後に保つのが目安です。
湿度が高すぎると結露やカビの発生リスクが高まり、逆に低すぎると喉や肌の乾燥につながるため、快適性と衛生面のバランスを取ることが大切です。
湿度計を活用しながら、加湿器と換気を上手に組み合わせるとよいでしょう。これらの数値はあくまで一般的な目安であり、住宅の構造や地域の気候によって適正範囲は異なります。
正確な情報は公的機関やメーカーの資料を確認し、最終的な判断は専門家にご相談ください。
この記事を通して伝えたいのは、床暖房が本当に必要かどうかを「感覚」ではなく、住まいの性能やライフスタイルから考える大切さです。
床暖房いらなかったと感じる人も、つけなくて後悔した人も、それぞれの背景には明確な理由があります。重要なのは、どちらが正しいかではなく、あなたの家に合った選択を見つけることです。
床暖房を設けるか迷ったときは、次のポイントを整理してみましょう。
- 家の断熱・気密性能、窓や換気の計画を見直す
- 家族構成や将来のライフスタイル変化を想定する
- 設備費・光熱費・メンテナンスを含めたライフサイクルコストで比較する
- 夏の快適性や湿気、ゴキブリ対策まで視野に入れる
これらをバランスよく検討することで、必要な設備を見極め、過剰な投資を防ぐことができます。特に一条工務店のような高断熱住宅では、設計段階の工夫や運用次第で床暖房いらないと感じるケースも少なくありません。
その一方で、寒冷地や体質によっては、床暖房の恩恵を強く感じる人もいます。
家づくりに正解はありません。どんな選択も、知識と理解の上で決めることができれば、それがあなたにとっての最良の家づくりになります。
もし「新築を建てたいけれど、どんな家にするかまだイメージがつかめない」「床暖房を入れるべきか、もっと情報を集めて考えたい」と感じているなら、LIFULL HOME’Sの注文住宅資料請求を活用してみてください。
早い段階から複数のハウスメーカーや工務店の資料を比較できるので、家づくりの方向性をつかむ第一歩として最適です。
住宅性能やデザインの違いを知ることで、自分に合った快適な家の形が見えてきます。
比べて分かる家の違い