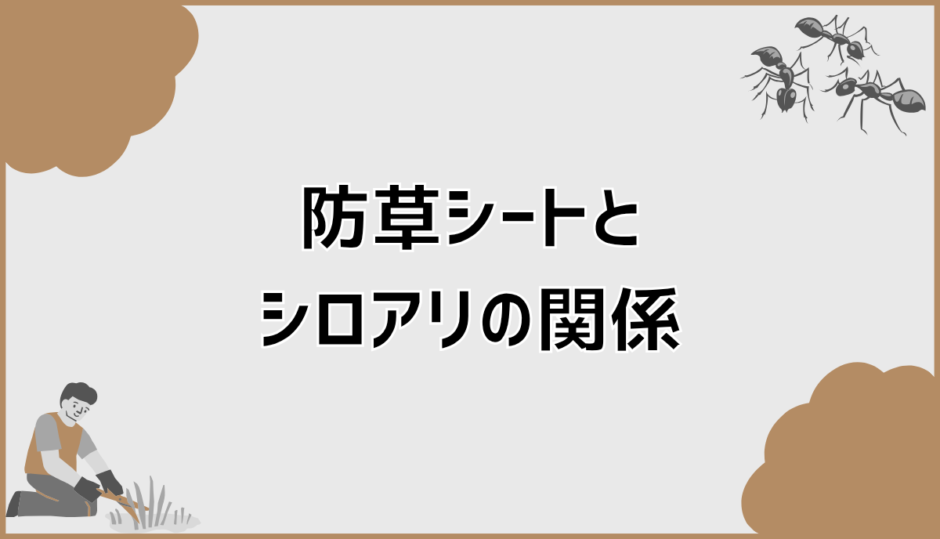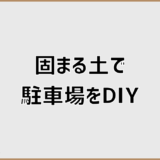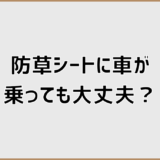この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
新築後しばらくして庭や犬走りを整えようとしたとき、防草シートを敷けば手入れが楽になると感じる一方で、シロアリが出やすくなるのではないか、ゴキブリやムカデまで増えたら困る、と立ち止まってしまう方も多いようです。
虫よけになると聞いたことがある反面、逆効果だったという話も目にすると、どれを信じていいのか分からなくなりますよね。
防草シートとシロアリの関係は、実はとても誤解されやすいテーマです。シートそのものが原因なのか、それとも施工や環境の問題なのか。この整理がつかないまま進めてしまうと、安心したくて敷いたはずなのに、不安だけが残る場合もあります。
この記事では、防草シートがなぜシロアリや他の虫と結び付けられやすいのか、その背景を一つずつ確認しながら、選び方や施工、使う場所によって何が変わるのかを共有します。
結論を急ぐ必要はありません。防草シートとシロアリの関係を正しく理解すれば、どこまで気にして、どこは気にしすぎなくていいのかが見えてきます。あなたの家に合った判断軸を、一緒に整えていきましょう。
- 防草シートがシロアリの直接原因にならない理由
- 防草シートと虫が結び付けられやすい誤解の正体
- シロアリやゴキブリ、ムカデを招きやすい施工や環境
- 防草シートで失敗しにくくする選び方と考え方
※本記事では、メーカー公式情報や公的機関の資料、一般的な事例や口コミなどを参照し、内容を整理して構成しています。体験談や感じ方には個人差があるため、判断の参考として読み進めていただき、最終的な確認は専門家へご相談ください。
防草シートとシロアリの基礎知識

防草シートとシロアリの関係は、ネットや口コミで情報が錯綜しやすく、不安だけが先に立ちがちです。防草シートを敷くと本当にシロアリが増えるのか、なぜそう言われるのか、他の虫との関係はどうなのか。
ここでは、防草シートが原因と誤解されやすい背景や、実際の被害例の考え方を整理しながら、判断の軸を落ち着いて確認していきます。
防草シートでシロアリは発生するのか
防草シートを敷くと「シロアリが寄ってくるのでは?」と不安になる方は多いです。家づくりの文脈で見ると、この心配は半分当たりで半分誤解です。
というのも、防草シートそのものは木材ではなく、シロアリの餌にはなりません。一般的な不織布・織布(ポリプロピレンなど)やポリエステル系シートが、直接シロアリを増やす仕組みは考えにくいです。
一方で、シロアリは湿気や暗さ、そして餌になる木材・有機物があると活動しやすくなります。
防草シートを敷く工程や、その後の環境が「湿気がこもる」「落ち葉や木片が残る」「通気が悪い」状態になってしまうと、結果としてシロアリが好む条件が整う場合があります。
つまり、問題の本体はシートではなく、敷設面のコンディションと周辺環境です。また「防草シートを敷いた後に羽アリを見た=シートが原因」と短絡しやすい点も、誤解が広がる理由です。
羽アリの発生は季節・気温・湿度の影響も受け、発生源が必ずしもシート下とは限りません。気になるときは、まずは床下・基礎周り・庭の木材残渣の有無といったシロアリの好条件を点検し、原因を切り分けるのが現実的です。
なお、シロアリ対策は住宅の耐久性や資産価値に直結します。ここは一般的な考え方の整理であり、異常が疑われる場合の最終判断は、シロアリ防除の専門業者や住宅の点検担当者に相談してください。
防草シートがシロアリの原因と誤解される理由
防草シートは「雑草を抑えるために地面を覆う」ものなので、見た目として地面が暗くなります。

見た目の印象だけで原因と結び付けやすい部分ですね
この暗く覆われた状態が、シロアリと結び付けられやすいのが第一の背景です。さらに、施工の仕方によっては水分が抜けにくくなり、湿気が残ることがあります。結果として「シートの下=虫の温床」という印象が先行しやすいんですね。
湿気と暗さがシロアリを招く
シロアリは乾燥に弱く、湿気が多い環境で活動が活発になるとされています。防草シートの下でも、整地不足による水たまりや、湿った土のまま施工することで湿気がこもる場合があります。
さらに落ち葉や刈草などの有機物が残ると、シロアリの餌と環境が同時に整ってしまいます。防草シート自体が原因ではなく、湿気と有機物をためない下地づくりが対策のポイントになります。
施工不良と素材選びの失敗
誤解を招きやすいのが施工不良です。シートの重ね不足や固定の甘さで隙間ができると、雑草だけでなく虫も出入りしやすくなります。また、排水しにくい素材や重い物を置いて通気を妨げる施工は、局所的に湿気が溜まる原因になります。
住宅の基礎周りでは、耐久性と透水性のバランスを意識し、湿気をためない丁寧な施工が欠かせません。
防草シートと虫の関係
防草シートは、シロアリ以外の虫の発生にも関係します。

虫が出た=失敗と即断しなくてよさそうです
ただし期待すべきは虫よけ効果ではなく、虫が棲みにくい環境を作れるかどうかです。雑草を抑えることで餌や隠れ場所は減りますが、下地処理が甘く湿気が残ると逆効果になることもあります。この点を理解して使い分けることが大切です。
ゴキブリやムカデは増えるのか
ゴキブリやムカデは暗くて湿った場所を好むため、条件が揃うと増えたように感じることがあります。特に、シートの下に落ち葉や枯草が残っていると、ゴキブリの餌や他の小虫が増え、結果としてムカデの餌場にもなります。
逆に、下地処理を徹底し、乾いた土で水はけを確保し、シートに隙間を作らず、上に砂利や砕石を敷いて通気と排水を助けると、虫の発生が目立ちにくくなる場合もあります。つまり「増える/減る」は施工品質と環境条件で変わります。
防草シートに虫よけ効果はあるのか
防草シート自体に忌避成分があるわけではないので、虫よけ剤のような即効性を期待するとズレが出ます。防草シートができるのは、あくまで生息条件の調整です。
- 有機物や雑草を減らし、虫の餌を作らない
- 草むらや物陰をなくし、隠れ場所を減らす
- 排水と通気を確保し、湿気を溜めない構造にする
この3点ができて初めて、結果として虫が減ったと感じやすくなります。虫が気になる方ほど、素材選びより前に「下地処理」と「排水・乾燥」を優先して考えるのが近道です。
防草シートでシロアリ被害が出た例はあるのか
「防草シートを敷いたらシロアリが出た」という声は確かにあります。
ただ多くの場合、防草シートそのものが原因というより、もともと湿気が多い、木材や有機物が残っていたなど、シロアリが侵入しやすい条件が重なっていたケースが目立ちます。
防草シートはきっかけとして疑われやすいものの、背景を整理して見ることが欠かせません。
原因は防草シートではないケースが多い
シロアリは土中を移動できるため、地表を防草シートで覆っても、湿気や木材などの餌があれば床下や基礎周りへ侵入する可能性があります。防草シート下で虫を見つけると原因を誤認しがちですが、侵入経路は複数あります。
被害が疑われる場合は、防草シートだけに注目せず、床下点検や周辺環境も含めて総合的に確認することが大切です。
被害が起きやすい条件と対策
被害が起きやすい条件には共通点があります。目安として、次のような状態が重なると注意が必要です。
- 基礎周りが常に湿っている(雨水が溜まりやすい、日陰が多い)
- 木片、切り株、落ち葉が溜まりやすい
- 犬走りや物置周りが密閉気味で通気がない
対策はシンプルで、湿気と餌を減らす方向に寄せます。施工前に土を乾かし、落ち葉・刈草・木片を撤去し、整地で水の逃げ道をつくる。
すでに敷いている場合は、局所的にめくって清掃し、必要に応じて砂利・砕石で排水を改善します。被害が疑われるときは、自己判断で薬剤散布を繰り返すより、専門家の点検を優先してください。
防草シートとシロアリ対策の考え方

防草シートをシロアリ対策として考えるときは、「敷けば安心」「高いものを選べば大丈夫」といった単純な話ではありません。シートの種類や素材だけでなく、施工の仕方や使う場所、そしてその後の管理まで含めて考える必要があります。
ここでは、防草シート選びと施工で押さえたい視点を整理しつつ、用途別の考え方や、よくある疑問への向き合い方までをまとめていきます。判断に迷ったときの基準を持つための土台として読み進めてみてください。
シロアリ対策になる防草シートの選び方
防草シートは種類によって性質が異なります。シロアリ対策では、耐久性だけでなく、湿気を溜めにくい構造かどうかが重要です。
加えて、長期間使っても破れや劣化で隙間ができにくい製品を選ぶことで、湿気や虫の侵入リスクを抑えやすくなります。
素材と厚みと透水性の見方
防草シートは織布と不織布に分かれ、不織布は透水性・通気性に配慮された製品が多く、住宅周りで扱いやすい傾向があります。
選ぶ際は透水性や耐候性、厚みを確認し、極端に薄いものは避けたいところです。薄手のシートは劣化や破れで隙間が生じやすく、湿気や有機物が溜まりやすくなる点に注意が必要です。
住宅周りで避けたい防草シート
住宅の基礎周りで避けたいのは、次の特徴を持つものです。
- 極端に薄く、安価で耐候性が弱い(短期で破れやすい)
- 透水性が不明、または水が抜けにくい構造
- 生分解性を優先し、長期の形状安定が期待しにくい
基礎周りは、見た目よりも管理のしやすさが優先です。シートが劣化して破れると、補修のたびに端部が乱れ、そこから雑草と虫の両方が入りやすくなります。
最終的な判断は、敷地の排水状況と日当たり、建物の基礎仕様(換気の取り方など)を踏まえて、施工業者や点検担当者と相談するのが確実です。
施工で差が出るシロアリ対策のポイント
同じ防草シートを使っても、施工の仕方次第で結果は大きく変わります。
シロアリ対策として意識したいのは、下地で湿気を断つこと、隙間を作らないこと、そして基礎周りの通気を妨げないことです。この3点を押さえるだけでも、リスクの感じ方は大きく変わってきます。
下地処理と湿気対策
施工前は、雑草を根まで除去し、刈草や落ち葉を残さないことが基本です。残渣があると、シート下で有機物が分解され、湿気が長く残りやすくなります。整地では凹凸をなくし、水が溜まる皿を作らないことが肝になります。
湿気は気候にも左右されます。気象庁の解説でも、梅雨時期(6〜7月)は湿度が高い状態が続きやすいことが示されています(出典:気象庁「平均相対湿度の長期変化傾向」https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr/himr_2-1.html )。この時期に施工するなら、晴天が続くタイミングを選び、地面をしっかり乾かしてから敷くほうが安心です。
基礎周りと犬走りの注意点
基礎周り(犬走り含む)は、住宅の耐久性に直結するエリアです。ここでありがちな失敗は、シートで基礎の周囲を密閉してしまうこと。
通気が落ちると、床下側の湿気が抜けにくくなる場合があります。設計や工法で条件は異なるため、一律の断定はできませんが、少なくとも次は意識しておきたいです。
- 基礎の換気経路を塞がない
- 雨水が基礎に向かって流れない勾配にする
- 物置や荷物を基礎に密着させない
犬走りは、砂利・砕石と組み合わせて排水を取りやすくすると管理が楽になります。施工後も、落ち葉が溜まる季節はこまめに掃除し、湿気と有機物を溜めない状態を維持しましょう。
防草シートは用途別に考える
防草シートは、庭の見た目を整えるためのアイテムである一方、敷地内の水の流れや空気の通り道にも影響を与えます。

場所ごとに同じ考え方でよいか迷うところですね
使う場所や用途によって重視すべきポイントは異なるため、あらかじめ何を優先するかを整理しておくと、シート選びや施工方法で迷いにくくなります。
庭や犬走りなど人が歩く場所
歩行がある場所は、破れにくさと安全性がポイントです。シートが薄いと、踏圧や砂利の角で傷みやすく、破れから雑草が出るだけでなく、隙間ができて湿気とゴミが溜まりやすくなります。
加えて、表面材(砂利、平板など)の安定性も大切です。歩くたびに沈む・ズレる状態は、端部のめくれや水溜まりにつながります。
犬走りは基礎に近いため、シート選びよりも排水の設計が効きます。雨どいの排水が近くに落ちる場合は、排水経路を先に整理し、必要なら雨水枡や砕石層で水を逃がす考え方が合います。
物を置くなど重さがかかる場所
物置、室外機、自転車ラックなど、荷重がかかる場所は通気が落ちやすいのが難点です。ブロックや平板で点支持すると、その下が暗く湿りやすく、虫の隠れ家になりがちです。
できれば面で荷重を受けるように下地を整え、隙間に落ち葉が溜まらない配置にします。あわせて、木材パレットや端材を地面に直置きするのは避けたいところです。
湿度が高い状態が続くと、カビや微生物が発生しやすくなり、結果としてシロアリのリスクが高まる可能性があります(出典:林野庁「新たな用途(床下調湿用)」 https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/mokutan/youto.html )。「置く物の素材」も含めて、湿気と有機物を増やさない運用が大切です。
なお、車が乗る場所のように大きな荷重がかかるケースでは、防草シートの選び方や下地構造で考え方が変わります。こちらの記事で、車に乗っても大丈夫か詳しく解説していますので、気になる方は参考にしてみてください。
防草シートとシロアリのよくある質問
ここでは、読者の方から特に多い疑問を短く整理します。住宅の状態や地域差で答えが変わる部分もあるため、あくまで一般的な目安として読んでください。異変がある場合の最終判断は専門家に相談しましょう。
- 防草シートでシロアリ被害は増えるのか
- 防草シート自体が原因になることは少なく、湿気や木片の放置が重なるとリスクが高まります。
- 防草シートに虫よけ効果はあるのか
- 防草シートは虫よけではなく、乾燥した環境を作り虫を寄せにくくします。
- ゴキブリやムカデ対策になるのか
- 下地処理と排水が適切なら虫は減りやすく、湿ったまま覆うと増えたように感じることがあります。
- 防草シートなしで砂利だけ敷くのは有効か
-
砂利だけの施工には注意点も多く、条件次第では雑草や虫の原因になります。詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。
あわせて読んでほしい
- DIY施工でも問題ないのか
- DIY施工は可能ですが、下地や端部処理が仕上がりを左右します。不安があれば専門家に確認すると安心です。
用途まで考えて失敗を防ぐために
防草シートとシロアリの関係は、シート単体の性能よりも「湿気と有機物を溜めない運用」を作れるかで決まります。
シロアリ対策として失敗しにくい流れは次の通りです。まず、敷く場所を用途で分けます。基礎周り・犬走りのように住宅に近い場所は、排水と通気を最優先に考え、薄手のシートや短期劣化しやすいものは避けます。
庭の奥など住宅から距離がある場所は、メンテナンス頻度と見た目のバランスで選びやすいです。次に、施工前の段取りです。雑草除去、落ち葉・木片の撤去、整地で水溜まりをなくす。
この下地が甘いと、どんな高耐久シートでも不安が残ります。施工後は、季節ごとに点検して、端部のめくれや破れ、落ち葉の堆積を早めに潰します。最後に、迷ったときの判断軸を置いておきます。
- 基礎周りは乾燥と排水を優先する
- 木材や有機物を地面に残さず、置かない
- 羽アリ、床のたわみ、カビ臭などの異変があれば早めに点検する
シロアリ対策は、家の安全性や費用に関わるテーマです。この記事は一般的な考え方の整理なので、地域特性や住宅仕様に合わせた最終判断は、専門業者や住宅の管理者に相談したうえで進めてください。
まとめ:防草シートとシロアリの誤解
どうでしたか?防草シートとシロアリの関係は、思っていたより単純ではなかったと感じた方もいるかもしれません。
防草シートそのものが原因になるケースは少なく、実際には湿気や有機物、施工や使い方が重なって誤解が生まれやすいテーマです。大切なのは、怖がりすぎず、仕組みを理解したうえで判断することだと思います。
この記事では、防草シートとシロアリを巡る不安を整理し、考え方の軸を共有してきました。ポイントを振り返ると、次の点が判断の助けになります。
- 防草シートは湿気と有機物を管理できるかが鍵
- シロアリや虫の発生は施工や環境で差が出る
- 使う場所や用途によって選び方は変わる
防草シートとシロアリ対策は、正解を急ぐより、自分の家に合った選択を積み重ねることが安心につながります。
最後に紹介をさせてください。
防草シートに車が乗る場合の考え方や、防草シートなしで砂利を敷く際の注意点をあらかじめ整理しておくことで、施工後の後悔や不安を減らしやすくなりますので、こちらの記事を参考にしてみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。これからの家づくりや住まいの管理を考える際の、ひとつの参考になればうれしいです。