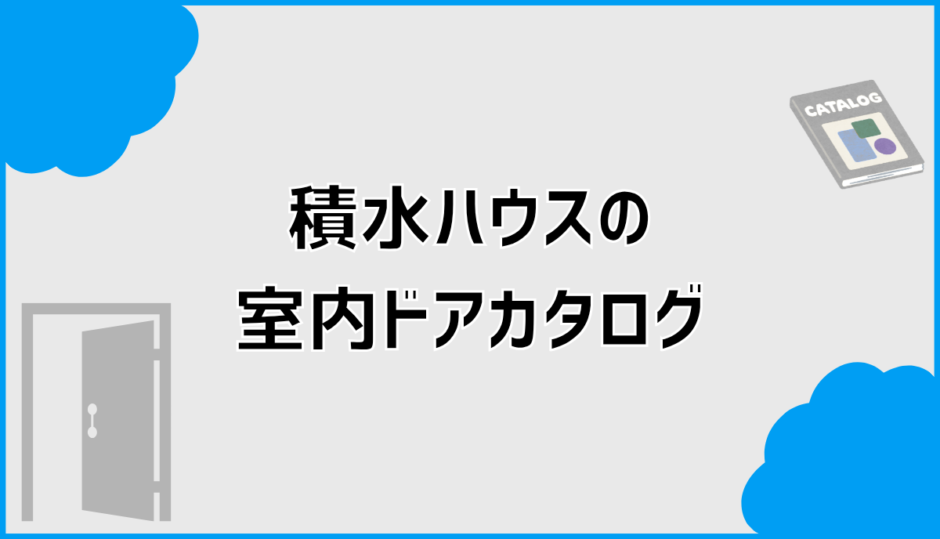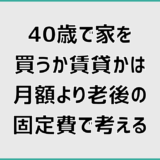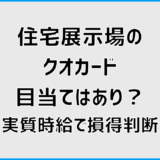この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
家づくりを考え始めたばかりの頃は、まずは土地や間取り、予算のことが気になって、室内ドアまで具体的に意識していない方がほとんどだと思います。
ところが、住宅会社の資料や展示場を見ているうちに、室内ドアのカタログを手にする場面が出てきて、「こんなに種類があるんだ」と少し戸惑うこともありますよね。
積水ハウスの室内ドアは全体的に整った印象があり、どれを選んでも大きな失敗はなさそうに見える一方で、違いが分かりにくく、判断の基準が持てないまま不安になることもあるかもしれません。
家づくりの初期段階では、細かい仕様まで決める必要はありません。ただ、室内ドアは後からまとめて考えようとすると、間取りや動線との関係が見えにくくなり、迷いが増えやすい部分でもあります。
カタログは便利ですが、何が分かって、何がまだ決めなくていいのかを整理しておかないと、情報に振り回されてしまいます。
ここでは、家づくりを始めたばかりの段階で、積水ハウスの室内ドアカタログをどう受け止めればいいのかを、分かりやすく整理していきます。
今すぐ決めること、まだ保留でいいこと、その境界を知っておくだけでも、これからの打ち合わせがずっと楽になります。まずは全体像をつかむところから、一緒に考えていきましょう。
- 積水ハウスの室内ドアカタログで分かることと分からないこと
- 室内ドアを早い段階で意識すべき理由と判断の目安
- 開き戸や引き戸など種類ごとの考え方と注意点
- 打ち合わせ前に知っておくと迷いにくくなる整理視点
※本記事では、積水ハウスの公式情報や公開資料、一般的な事例を参照し、内容を独自に整理して構成しています。口コミや体験談は感じ方に差があるため参考程度とし、最終的な判断は公式情報や担当者への確認を前提にお読みください。
積水ハウスの室内ドアカタログの基礎

室内ドアは、毎日触れる設備でありながら、空間の印象や暮らしやすさに直結します。積水ハウスの場合、ドア単体のデザインだけでなく、床・巾木・枠・収納などの建具一式として「住まい全体の整合」を重視する設計思想がベースです。
そのため、カタログは単なる型番表ではなく、空間提案として読むほど理解が進みます。ここでは、カタログの入手経路、読み取れる範囲と限界、代表的な種類や色の傾向までを整理し、打ち合わせ前に迷いを減らすための土台をつくります。
積水ハウスの室内ドアの特徴
積水ハウスの室内ドアは、建具単体の派手さや個性を前面に出すというより、床・巾木・枠・収納まで含めて「住まい全体の調和」を取りやすい点が特徴です。
色や質感がシリーズとして整理されているため、建具だけが浮きにくく、廊下から各室へ視線が抜けた際も空間に一体感が生まれやすい設計になっています。
完成後に落ち着いた印象になりやすく、長く使っても違和感が出にくい点は大きなメリットです。
標準仕様の中にも意匠や仕様の違いがあり、縦スリット入りのタイプ(TS建具など)と、スリットのないシンプルなタイプ(SP建具など)では、同じサイズでも価格差が生じることがあります。
室内ドアは枚数が多くなりやすいため、リビングなど見せ場だけ意匠性を高め、個室や収納は抑えると、全体のバランスを取りやすくなります。
また、ハンドルや丁番などの金物類も標準範囲で選択肢があり、一部にKAWAJUN系デザインが含まれることもあります。金物は使用頻度が高いため、見せ場のみ変更し、他は標準で揃えると統一感を保ちやすいです。
木造住宅では湿度変化による建付け調整が必要になる場合がありますが、メーカー標準建具であれば相談窓口が一本化されやすく、メンテナンス面でも安心感があります。見た目だけでなく、動線や調整のしやすさまで含めて検討することが満足度につながります。
室内ドアのカタログの入手方法
積水ハウスの室内ドアに関する情報は、公式の紙・デジタル資料、展示場や担当者からの配布資料、ネット上の写真・解説など、複数の入口があります。ただし、入手経路によって「情報の粒度」が大きく異なります。
初期は空間提案としてのカタログで方向性を決め、検討が進んだら仕様表や見積に落とし込み、最終は担当者の最新資料で型番・採用条件を確定する、という流れが最もスムーズです。
公式カタログと会員向け資料
公式カタログは、ドア単体の型番一覧よりも、内装の世界観を伝える構成が中心です。床・壁・建具の組み合わせ写真を見比べることで「自分の好みの方向性」を掴みやすく、打ち合わせでの共有が楽になります。
My STAGEなどの会員向けデジタルカタログは、スマホで見返せるので候補整理に便利です。紙カタログは色味の印象が掴みやすい反面、版が古いと廃番や仕様変更に気づきにくいので、改訂年月の確認は必須です。
展示場や担当者からの資料
展示場や担当者の資料は、地域仕様や商品系列ごとの条件が反映されやすく、見積内容と直接紐づく具体的な情報を確認できる点が大きな強みです。
公式カタログでは把握しにくい、色の可否や選択できる面材の範囲、ハイドア設定の有無、ガラス採光の種類、引き込み戸が採用できるかどうかといった「実際に採用できるかどうか」の判断材料を、比較的早い段階で把握できます。
検討が進んでから条件に合わないことが分かると手戻りが大きくなるため、展示場や担当者の資料で現実的な選択肢を整理しておくことは、打ち合わせ全体をスムーズに進めるうえで役立ちます。
ネット情報を見る際の注意点
ネットの写真や体験談は、完成イメージを膨らませる材料としては有効ですが、情報の扱い方には注意が必要です。
同じ呼び名の室内ドアでも、採用された年代や商品系列の違いによって、面材の仕様やガラスの種類、選べる色、標準かオプションかの扱いが変わることがあります。
地域仕様やキャンペーン条件による差もあるため、ネット情報だけで「標準で入る」「この仕様は選べる」と判断すると、打ち合わせ段階で認識のズレが生じやすくなります。
あくまで参考情報として捉え、最終的には担当者から提示される最新の仕様書や見積資料で照合する前提で読み進めると、後悔や手戻りを防ぎやすくなります。
カタログで分かることと分からないこと
室内ドアのカタログは、検討の迷いを減らすための強い味方です。
ただし、カタログは「候補を絞る道具」であって、採用可否や費用まで確定させる資料ではありません。ここを押さえると、写真のイメージと実物のギャップ、打ち合わせでの認識ズレを減らせます。

カタログだけで決め切らなくても大丈夫です
カタログで分かる内容
カタログで把握しやすいのは、デザインの方向性、面材のテイスト(木目・単色など)、ガラス採光の入り方、枠や床との相性イメージです。
写真を通して、明るめ・落ち着き重視といった空間の方向性を比較できるため、好みを整理する段階では非常に役立ちます。開き戸・引き戸・引き込み戸といった形式の違いも、具体的な使い分けイメージとして概念的に理解できます。
また、天井高がある空間でハイドアを採用したときの縦の伸びや、ガラススリットによって廊下や玄関側へ光を落とす演出など、完成後の「空間の見え方」を掴む材料としても有効です。
実際の採用可否は別途確認が必要ですが、全体像をイメージするための資料として、カタログは重要な役割を果たします。
カタログでは分からない内容
一方で、地域ごとの標準範囲や商品系列による採用条件、壁厚や下地の制約、引き込み戸に必要な壁内スペースなどの納まりは、カタログだけでは判断できず、図面と仕様書での確認が欠かせません。
特に引き込み戸やハイドアは、構造条件によって採用可否が左右されることがあり、見た目の好みだけで決めてしまうと後から調整が必要になる場合があります。
費用面でも、同じデザインに見えても高さの違い、ガラス採光の有無、金物やソフトクローズ機構の設定によって金額が変わるため、カタログから一意に判断することはできません。
まずはカタログで「好きな方向性」を固め、そのうえで仕様表で採用条件を照合し、見積で差額の根拠を確認する、という順番で進めると認識のズレを防ぎやすくなります。最終的な判断は、必ず公式資料と担当者の説明をもとに行ってください。
積水ハウスの室内ドアの種類
ドアの種類は、見た目以上に「使い勝手」を左右します。特に、開閉スペース、動線への干渉、掃除のしやすさは暮らし始めてから効きます。
積水ハウスの室内ドアも、開き戸・引き戸・引き違い戸・引き込み戸などをベースに、空間の役割に合わせて選べる構成です。
開き戸の特徴と使われ方
開き戸は構造がシンプルで、気密や遮音を確保しやすい傾向があります。そのため、寝室や書斎、子ども部屋など「音や視線をしっかり区切りたい」空間と相性が良く、落ち着いた環境をつくりやすい点が特徴です。
一方で、開く方向によっては家具の配置や廊下の動線と干渉しやすく、使い勝手に影響が出る場合があります。たとえば、ドアを開けた状態で収納扉が開けられなくなる、通路幅が一時的に狭くなるといったケースは珍しくありません。
そのため、間取り図だけで判断せず、図面上で実際の開閉軌跡を確認し、日常動線や家具配置を想定したうえで内開き・外開きを検討しておくと、入居後のストレスを減らしやすくなります。
引き戸と引き違い戸の特徴
引き戸は前後の開閉スペースが不要なため、洗面室や廊下、LDK周りなど、日常的に人の出入りが多く回遊性を高めたい場所に向きます。扉を開け放しても通路を塞ぎにくく、動線がスムーズになる点は大きなメリットです。
引き違い戸は左右に扉が動く構造のため、大きな開口を取りやすく、通風や採光を重視したい空間でも使いやすい形式と言えます。一方で、床にレールがあるタイプは、ホコリや髪の毛などが溜まりやすく、掃除の手間が気になることがあります。
見た目や動線の良さだけでなく、日々の掃除やメンテナンスのしやすさまで含めて検討すると、暮らし始めてからの納得感につながります。
ガラス入りドアの特徴
ガラス入りは、暗くなりがちな廊下や玄関ホール側へ光を落とす目的で採用されやすい形式です。全面ガラスは開放感が出る反面、指紋汚れや室内の見え方が気になることがあります。
外からの視線が通りやすい間取りなら、縦スリット程度に留めると、採光とプライバシーのバランスを取りやすくなります。形式の比較は、以下の表で整理すると判断しやすくなります。
| 形式 | 使い勝手の特徴 | 注意点 | コスト傾向 (目安) |
|---|---|---|---|
| 開き戸 | 遮音・ 気密を取りやすい | 開閉スペース、 干渉確認が必須 | 抑えやすい |
| 片引き戸 | 動線がスムーズ | レール掃除、 壁面の取り合い | 中程度 |
| 引き違い戸 | 大きな開口を 確保 | 壁量確保、 納まり確認 | 中程度 |
| 引き込み戸 | 見た目が すっきり | 壁内スペースが 前提 | やや 上がりやすい |
費用は工事条件や仕様で変動します。最終判断は担当者と見積で確認してください。
室内ドアのデザインと色の傾向
室内ドアは床や壁と隣り合う面積の大きな要素であるため、色の選び方によって家全体の印象が大きく左右されます。
積水ハウスの住宅では、白や明るい木目を基調にした軽やかな配色提案が多く、建具色を揃えて空間全体の統一感をつくる設計が比較的扱いやすい傾向です。
建具の色が揃うことで視線が分断されにくく、廊下から各部屋を見たときにも落ち着いた印象になりやすくなります。一方で、部屋ごとにドア色を変えすぎると、廊下から見た際に色の情報量が増え、空間が雑多に感じられる場合があります。

他の家の正解より、自宅の見え方を優先したい
色決めの手順としては、床→壁→建具の順に、面積が大きいものから決めていくのが基本です。
建具はドア本体だけでなく、枠・巾木・窓枠とも連動して見えるため、ドアだけ異なる色を選ぶと点で強調され、意図しないちぐはぐ感が生まれやすくなります。
まずは建具全体を同系色で揃え、変化をつけたい場合はリビングドアなど一部に限定する考え方が、全体バランスを崩しにくい方法です。
採光の考え方も色選びと密接に関係します。全面ガラスのドアは開放感がありますが、玄関からリビングが一直線に見える間取りでは、視線が抜けすぎて落ち着かないと感じることがあります。
縦スリット程度のガラス採光であれば、廊下や玄関側の暗さを和らげつつ、室内の見え方をコントロールしやすくなります。
また、昼と夜では自然光と照明の条件が大きく異なるため、色や質感の見え方も変わります。最終判断では、自然光と照明下の両方でサンプルを確認し、カタログ写真の印象だけに頼らないことが、後悔を減らすポイントです。
積水ハウスの室内ドアカタログの確認ポイント

カタログで候補を絞ったら、次は「採用条件の確認」に進みます。ここで押さえたいのは、標準かオプションか、打ち合わせ前に見落としやすいポイント、最終仕様を確定させる手順です。
室内ドアは枚数が多く、1つの差額が小さくても合計では無視できない金額になりがちです。また、開閉方向や引き込みスペースの有無など、後から変えにくい要素も含まれます。
カタログの雰囲気だけで決めず、図面・仕様書・見積の3点で整合を取ることが、納得感のある選び方につながります。
室内ドアは標準仕様かオプションか
室内ドアが標準かオプションかは、多くの方が気になるポイントですが、商品系列、地域仕様、プラン条件、採用する高さやガラス仕様、金物のグレードによって扱いが変わります。
たとえば、同じ見た目に近いドアでも、縦スリットの有無(TS建具系/SP建具系のような扱い)、ハイドア指定、ソフトクローズ機構の有無、ガラス採光の量などが重なると、差額が発生するケースがあります。
カタログ写真だけでは違いが分かりにくいため、仕様の内訳まで確認する姿勢が大切です。
目安としては、個室や収納などは標準範囲に収めやすく、リビングドアや来客の目に入りやすい場所は、意匠性や採光の優先度が上がり、結果として差額が出やすい傾向があります。
ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、すべてのケースに当てはまるわけではありません。費用については条件による差が大きいため、推測だけで判断しない姿勢が欠かせません。
見積書に記載される建具名(シリーズ名や記号)を起点に、どこまでが標準に含まれ、どこからが差額なのかを担当者に確認してください。
仕様書の記載内容と見積の内訳を一致させておくことで、後からの行き違いや認識違いを防ぎやすくなります。最終的な条件は、必ず公式資料をもとに確認するようにしましょう。
打ち合わせ前に知っておきたい注意点
打ち合わせで迷いが増える原因は、室内ドアを「デザイン」だけで判断してしまうことにあります。
実際には、開閉方向、周囲との干渉、床に敷くマットやラグの厚み、将来の家具配置まで含めて影響するため、見た目以上に検討要素が多い設備です。開き戸の場合、内開きか外開きかで使い勝手は大きく変わります。
たとえば、ドアを開けた瞬間に収納扉が使えなくなる、廊下で人とすれ違いにくくなるなど、図面上では見落としやすい小さな不便が、暮らし始めてから積み重なることがあります。
そのため、平面図だけでなく、開閉軌跡を書き込んだ図面で動きを確認し、必要に応じて家具の置き場まで想定しておくと安心です。
引き戸は前後の開閉スペースが不要で動線がスムーズになる一方、床レール部分にゴミが溜まりやすい点や、戸車の調整が必要になる場合がある点も把握しておきたいポイントです。
段差の有無は掃除のしやすさや将来のバリアフリー性にも関わります。引き込み戸は見た目がすっきりし、開け放したときの一体感が魅力ですが、壁内に扉を収納するスペースが必要なため、採用できる場所は限られます。
希望がある場合は、間取りが固まる前の段階で設計へ伝えておくと、無理のない調整がしやすくなります。
防音を重視する場合は、遮音性能の考え方を知っておくと打ち合わせでの質問が具体化します。建具の遮音等級(T等級)は、JIS A 4702(ドアセット)で扱われる枠組みに基づく指標の一つで、数値が高いほど音を通しにくい傾向があります。
等級の意味を理解したうえで確認すると、寝室や書斎など用途に応じた判断がしやすくなります。(出典:一般社団法人 日本建設業連合会「用語 T等級」 https://www.nikkenren.com/kenchiku/sound/pdf/glossary/en-0100.pdf )。
最終仕様を確認する際のポイント
最終段階では、カタログよりも「仕様書と図面」が主役になります。ここで確認すべき軸は、開閉形式、開く方向、サイズ(高さ・幅)、ガラス採光の有無、枠・巾木との色合わせ、金物(ハンドル、丁番、クローザー等)と多岐にわたります。
カタログで描いていたイメージが、実際の間取りや仕様条件でどのように反映されるのかを、一つずつ現実に落とし込む工程だと考えると分かりやすいです。
特に、天井高がある空間でのハイドアは、縦方向の伸びが強調され空間演出としては効果的ですが、その分、費用、扉の重量感、搬入経路、施工精度への影響が出やすくなります。
そのため、全室を高尺にするのではなく、リビングや玄関ホールなど「見せ場」に限定し、その他は標準高さにするなど、メリハリを付けた選択が現実的です。

迷ったら図面と見積を同じ条件で揃えましょう
確認作業は「図面→仕様書→見積」の順で揃えると整理しやすくなります。まず図面で設置場所と開閉方向、干渉の有無を確認し、次に仕様書で建具名・色・ガラス仕様・金物を確定させ、最後に見積で差額の根拠をチェックします。
この流れを踏まず、口頭説明やイメージだけで進めてしまうと、「その仕様は標準外だった」「選べると思っていた色が対象外だった」といった認識のズレが起こりやすくなります。
また、玄関からリビングが見通せる間取りでは、リビングドアのガラス量がプライバシーや落ち着きに直結します。
採光を確保したい場合でも、全面ガラス一択にせず、縦スリットや部分ガラスなど段階のある選択肢を検討すると、明るさと視線コントロールのバランスが取りやすくなります。
最終的な判断は、必ず担当者が提示する最新の公式資料をベースに行い、不明点や判断理由はその場で確認し、記録として残しておくことをおすすめします。
よくある質問
室内ドアは日常的に触れる設備なので、検討が進むほど疑問が具体的になります。ここでは、カタログを見ながら特に出やすい質問を整理します。
採用可否や費用は条件で変動するため、断定は避け、最終的な判断は担当者の説明と公式資料でご確認ください。
- 室内ドアのデザインはどこまで選べるか
- 選択肢は標準ライン内で色・面材・ガラス・金物を組み合わせる形が基本です。カタログで方向性を絞り、写真を共有すると打ち合わせが進めやすくなります。建具色は揃え、変化は一部に留めるとバランスを保ちやすいです。
- 後からドアの変更や交換は可能か
- 金物類は後から交換できる場合がありますが、開閉方式の変更は壁工事を伴い大掛かりになりやすいです。費用は条件差が大きいため、必要に応じて現地確認と見積で判断すると安心です。
- 他メーカーのドアは選べるか
- 他メーカー製はデザインの幅が広がりますが、納まり調整や保証の整理が難しくなる場合があります。価格は本体だけでなく付帯工事を含めた総額で比較し、図面段階で条件を確認しておくと安心です。
- ガラス入りドアはどの場所に向いているか
- ガラス入りドアは、廊下や玄関ホールなど暗くなりやすい場所に光を取り込みたい場合に向いています。ただし、玄関からリビングが直線で見える間取りでは視線が抜けすぎることもあるため、縦スリットなど控えめな採光を選ぶとバランスを取りやすくなります。
自分の地域の標準仕様の確認方法を知る方法
積水ハウスの室内ドアは、商品系列や建築時期、地域の仕様によって、選べる内容や標準の範囲が異なる場合があります。カタログやネットの情報だけでは、自分の計画条件にそのまま当てはまるか判断しにくいと感じることもあります。
そうしたときは、公式カタログや資料を取り寄せて、最新の情報を手元で確認するのが一つの近道です。
LIFULL HOME’Sを利用すれば、積水ハウスを含む複数のハウスメーカーのカタログをまとめて請求できるため、仕様の考え方や方向性を比較しながら整理しやすくなります。カタログ請求は無料で、検討の初期段階でも利用できます。
まずは資料を見ながら、自分の地域や条件でどこまでが標準に含まれるのかを把握し、そのうえで担当者との打ち合わせに進むと、認識のズレを減らしやすくなります。
次に、カタログ請求の流れを簡単に整理していきます。数分あれば確認できる内容です。
カタログを請求する手順
公式サイトにアクセスして建築予定エリアで住所を選択。

まとめ:積水ハウスの室内ドアカタログ
どうでしたか?最後まで読んでいただき、ありがとうございます。積水ハウスの室内ドアカタログは、見た目を選ぶための資料というより、住まい全体の整合や暮らし方を考えるためのヒント集のような存在です。
最初から細部まで決め切ろうとせず、どこまで分かり、どこから確認が必要なのかを整理するだけでも、家づくりの負担はぐっと軽くなります。
この記事では、カタログの役割や注意点を軸に、判断がぶれやすいポイントを一つずつ見てきました。特に意識しておきたいのは、次のような点です。
- カタログは方向性を掴むための資料であること
- 標準仕様かどうかは条件で変わること
- 開閉方式や高さは後から変えにくいこと
- 図面と見積を同じ条件で確認すること
積水ハウスの室内ドアカタログを正しく使えば、迷いを減らしながら納得感のある選択がしやすくなります。
焦らず、自分たちの暮らしに合うかどうかを軸に、ひとつずつ確認していくことが、後悔を減らす近道です。これからの打ち合わせが、少しでも落ち着いた時間になることを願っています。