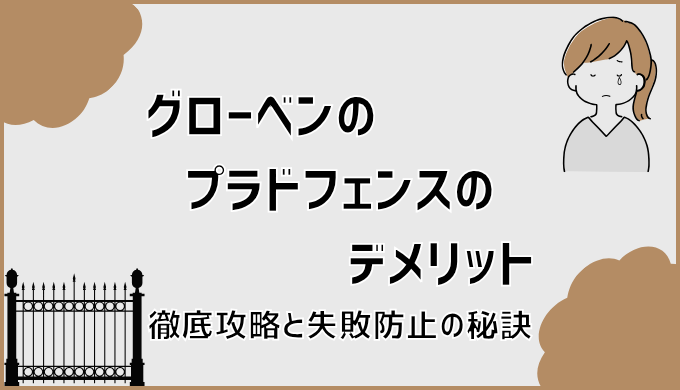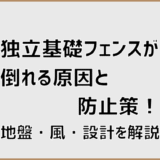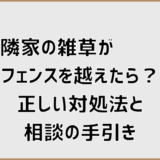この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
家づくりや庭づくりを考えるとき、外構の印象を大きく左右するのがフェンスです。
中でもグローベンのプラドシリーズは、天然木のような美しさと樹脂ならではの耐久性を兼ね備え、多くの住宅で採用されています。
ただし、どんな製品にも魅力と同時に注意すべき点があり、プラドフェンスにもデメリットは存在します。
例えば、設置する高さによって風の影響を受けやすくなったり、DIY施工で細部を誤ると強度に不安が出たりすることがあります。
その一方で、実際の口コミにはデザイン性やメンテナンスのしやすさを評価する声も多く、費用面でもシリーズごとの幅広い選択肢が用意されています。
ここでは、プラドフェンスの特徴や高さの選び方、考えられるデメリット、さらにそれを補う工夫までを丁寧に解説していきます。
読んでいただくことで、失敗や後悔を避け、安心して理想の外構づくりを進めるための視点を得られるはずです。
- プラドフェンスの特徴や高さの選び方と設置基準について理解できる
- 実際に多いデメリットと注意点を把握できる
- デメリットを補う工夫や活用方法を知ることができる
- 費用や口コミを含めた総合的な判断材料を得られる

- グローベンプラドフェンスの特徴
- プラドフェンスの高さと選び方
- プラドフェンスの主なデメリット
- デメリットを補う活用方法と工夫
グローベンが展開するプラドフェンスは、樹脂と木粉を組み合わせた人工木素材を採用し、天然木のような温かみのある見た目と高い耐久性を兼ね備えています。
外構をスタイリッシュに演出できる一方で、選ぶ高さや設置条件によっては風圧の影響を受けやすくなるなどの注意点も存在します。
ここではプラドフェンスの特徴や高さの選び方、考えられるデメリットとそれを補う工夫について詳しく解説し、設置前に知っておきたいポイントを整理していきます。
グローベンが展開するプラドフェンスは、自然な木目調と樹脂製ならではの耐候性を兼ね備えた外構資材として、多くの住まいに採用されています。
芯材には木粉を混ぜた再生樹脂を採用し、その外側を高密度ポリエチレンで覆うという多層構造を持っています。
この設計により、天然木のような温かみのある風合いを保ちながらも、樹脂ならではの耐久性を高めています。
長期間使用しても腐食やシロアリ被害の心配が少なく、屋外環境に強いのが特徴です。
また、一枚ごとに木目の模様が異なり、工業製品のような均一さではなく、自然に近い揺らぎを感じさせるデザインを実現しています。
そのため、モダンな住宅にもナチュラルテイストの住まいにも、幅広く調和しやすい点が魅力です。
シリーズごとに特性が異なり、目的に応じた選択が可能です。エントリーモデルのoneはコストパフォーマンスに優れ、5色のカラーバリエーションで住まいに合わせやすい柔軟さがあります。
中位モデルのrichは板厚を22mmにまで厚くしたことで、従来モデルに比べて剛性が大幅に向上しました。
見た目にも重厚感があり、デッキフェンスとしての利用にも適している点が評価されています。
さらに上位モデルのplusでは、柱スパンを2000mmまで広げることができ、施工効率が大きく改善されています。
補強材を裏面に組み込んだ仕様のため、強風地域や広い敷地でも安心して設置できるのが特長です。
施工のしやすさにも配慮されており、公式の取扱説明書には温度変化に伴う膨張収縮を見越したビス打ちやクリアランスの確保、日常的なお手入れの方法が丁寧に記載されています。
これに従うことで長期的に美観と耐久性を維持することができます。塗装や防腐処理の必要がなく、水洗いや中性洗剤での清掃で十分な点も、手間を減らしたい方にとって大きな利点です。
このようにプラドフェンスは、デザイン性と機能性の両面で多様なニーズに対応し、使いやすさと美しさを両立させた外構資材として支持されています。
フェンスの高さは見た目だけでなく、快適性や安全性に直結する要素です。たとえば、地上設置の場合はH1800までは60角柱、さらにH2200までは75角柱を使用することが推奨されています。
ブロック上設置の場合はH1200を上限とするのが望ましく、敷地条件や既存基礎との組み合わせを考えながら計画する必要があります。これらの基準を守ることで、安定した設置が可能となります。
視線を遮る目的であれば、1700〜2000mmの高さが効果的とされています。歩道や隣地との境界部分ではH1800クラスの高さが多く選ばれます。
一方で、リビング前の腰高窓やデッキ部分などでは、H1200程度の高さでも十分にプライバシーを守ることができます。
このように設置場所によって高さを調整することで、遮蔽性と採光・通風を両立することが可能です。また、敷地全体で高さに変化を持たせると、単調さを避け、外観に奥行きやリズムを加える効果も期待できます。
さらにシリーズごとに設置基準が異なります。richは柱ピッチを1000mm以内に抑える必要がありますが、plusは2000mmまで広げられるため、柱本数や基礎数を抑えることができます。
ただし、高尺仕様を選択する場合は基礎の強度や柱断面、埋め込み深さなどの条件が厳しくなり、強風や地盤の性質も考慮した設計が求められます。
強風地域や地盤が弱い場所では、控え柱や補強材を取り入れることが推奨されます。こうした基準を守ることが、長期的に安心して利用するための鍵となります。
要するに、プラドフェンスの高さを決める際には「どの場所でどんな目的で使うのか」を明確にし、シリーズごとの施工基準と現場条件を照らし合わせながら選ぶことが大切です。
適切な高さを選べば、外構全体の完成度を大きく高めることができます。
フェンスの高さはデザイン性だけでなく、隣地境界や道路に面する位置によって制限が設けられています。具体的な制限内容については、国土交通省が公開している建築基準法関連ページを参考にすると安心です(出典:国土交通省「建築基準法」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/index.html)。
プラドフェンスには優れた点が多くある一方で、樹脂製品ならではの弱点も存在します。
まず、外気温による伸縮の影響を受けやすい点です。板端部に隙間を設けずに施工すると、膨張や収縮によって反りや目地の乱れが生じる場合があります。
メーカーの施工要領では、固定ビスの位置や余裕穴の確保を必須としており、これを守らないと不具合の原因になるとされています。
樹脂という素材の性質上、施工時点でこうした性質を考慮することが不可欠です。
また、薄板仕様では剛性が不足する場合があり、強い衝撃や押圧でたわみが生じる可能性があります。
実際に「押すと板がしなる」といった利用者の声も確認されており、衝撃を受けやすい場所では注意が必要です。
メーカーも説明書の中で、板材に過度な荷重や一点的な衝撃を加える行為を禁止しています。利用環境によっては、剛性の高いシリーズや補強材の導入を検討することが推奨されます。
コスト面でも課題があります。従来工法のプラドフェンスは柱ピッチを1000mm以内とする必要があり、その分柱や基礎の数が多くなる傾向があります。
同じ延長距離を設置する場合でも、アルミ製フェンスに比べて施工の手間や費用がかさむ点は理解しておくべきです。
近年では2000mmピッチに対応した上位シリーズも登場しましたが、これは特殊な裏面補強がある場合に限られます。
さらに、板塀構造のため風の影響を受けやすいのも特徴です。強風地域や地盤の弱い場所では、控え柱や基礎強度の強化が必要とされ、設計上の自由度は実際には環境条件によって制約を受けます。
無理に高さを優先したり基礎を簡略化したりすると、倒伏のリスクが増す点に注意が必要です。
このように、プラドフェンスはコスト・デザイン・施工性のバランスに優れる反面、施工条件や環境によって性能が左右されやすい面を持っています。
設計段階から環境要因を考慮し、基準に沿った施工を行うことが安心して利用するための前提になります。
弱点を理解した上で適切に対応することで、プラドフェンスはさらに長く快適に使うことができます。
まず温度変化への対応としては、施工時に隙間や余裕穴を確保し、固定方法を工夫することが基本です。
これにより膨張や収縮に追従できる柔軟な構造となり、反りや音鳴りを防ぐことができます。
設置後も定期的に点検を行い、ビスの緩みなどを調整することで、安定した状態を保つことができます。
衝撃やたわみへの備えとしては、剛性の高いシリーズを選んだり、裏面補強のある仕様を導入する方法があります。
特にplusシリーズは柱ピッチを2000mmまで広げられるため、基礎や柱の数を減らしつつ外観の美しさを保ちやすい構造です。
また、敷地環境によっては、植栽や低木を組み合わせて一次的に衝撃を和らげる工夫も有効です。こうした設計上の工夫は、見た目の柔らかさや自然との調和を高める点でも役立ちます。
風への対応も軽視できません。設置する高さを欲張らず、基礎や柱を余裕のある仕様にすること、強風地域では控え柱や補強材を併用することが大切です。
さらに、水抜き処理や凍結対策など、見えない部分の施工品質も長期的な耐久性に直結します。
メーカーの推奨する施工基準を守りつつ現場条件に合わせて工夫することで、安全性と意匠性の両立が可能になります。
つまり、プラドフェンスは弱点を理解し、施工時の工夫や設置環境への配慮を加えることで、本来持つ魅力を最大限に活かすことができる製品です。
デザイン性と機能性をバランスよく取り入れたい方にとって、工夫次第でより価値ある選択肢になるといえます。

- 施工条件と強風地域での注意点
- プラドフェンスのDIY施工ポイント
- プラドフェンスの費用と相場比較
- 他シリーズや他社フェンスとの比較
- プラドフェンスの口コミまとめ
- プラドフェンスに関するよくある質問集
- まとめ:グローベンのプラドフェンスのデメリット徹底攻略と失敗防止の秘訣
グローベンのプラドフェンスはデザイン性と耐久性の両立で注目される製品ですが、設置環境や施工方法によっては思わぬデメリットが表れる場合があります。
特に強風地域での施工条件やDIYでの取り組み方は慎重な判断が必要です。また、費用相場や他社製品との比較を通じてコストと性能のバランスを見極めることも大切になります。
ここでは施工上の注意点からDIYのコツ、価格帯や口コミ、よくある質問までを詳しく整理し、安心してプラドフェンスを導入するための総合的な視点をお届けします。
プラドフェンスを安全に長期間使うためには、設置場所の条件や気候の影響をしっかり考慮することが大切です。
特に強風地域では、板塀形状のフェンスが風を大きく受けやすいため、メーカーが示している施工基準を丁寧に守る姿勢が欠かせません。
たとえば、プラド/richは柱の芯々間隔を1000mm以内とし、H1800までは60角柱、H2200までは75角柱を使う設計が推奨されています。
また、ブロック上設置では1200mm程度が上限とされており、基準を超える計画は不具合の原因となりやすいのです。
さらに、プラド/plusは裏面補強材を併用する仕様によって2000mmピッチまで許容されていますが、いずれの場合も高さが増すほど柱断面や埋め込み深さに余裕を持たせる必要があります。
一般的には300~500mmの埋め込みが推奨され、地盤の状態に応じてさらに深く、あるいは幅を広げて施工することが望ましいとされています。
とくに軟弱地盤では砕石を厚く敷いたり、地盤改良材を加えたりする補強策が効果的です。これらの施工条件を守ることで、強風下でも倒壊リスクを抑え、安定した使用が可能となります。
また、施工現場で忘れられがちな要素として、排水処理や凍結対策があります。水抜き穴や透水性の砕石を用いた施工は、基礎周辺の水分滞留を防ぎ、凍結や劣化を抑える効果が期待できます。
特に寒冷地では、基礎が凍上により押し上げられる現象を防ぐための工夫が不可欠です。
メーカー資料でも「高さを欲張らない」「スパンを基準内に収める」「基礎寸法を現場条件に応じて増やす」という三原則が強調されており、これらを守ることが施工品質と長寿命化に直結するとされています。
DIYでの設置を検討する方も多いですが、成功の鍵は正しい手順と素材特性の理解にあります。プラドフェンスは木粉混合樹脂で作られており、温度差による伸縮が避けられません。
そのため、ビス穴に余裕を設けたり板端にクリアランスを確保したりする工夫が必要です。固定ビスを強く締めすぎると、伸縮が阻害され反りや割れの原因となるため注意が必要です。
施工の流れは、通り芯の設定→穴掘り→柱の垂直確認→コンクリート固定→硬化後に板材設置という順序が基本です。
特に柱を立てる際は水準器で何度も確認し、わずかな傾きも修正することが重要です。硬化不十分な状態で板材を取り付けると耐久性が損なわれるため、しっかりと養生期間を設ける必要があります。
さらに、プラド/plusのような上位シリーズでは、中間補強アルミの挿入が求められるケースもあり、これを怠ると振動やたわみが発生しやすくなります。
初心者が陥りやすい失敗としては、基礎に急結剤を使う、アルミ支柱内部にモルタルを流し込む、水抜き処理を行わないといった事例が挙げられます。
これらはメーカーが明確に禁止事項としているため、注意が必要です。また、施工精度のわずかな誤差が全体の仕上がりや耐久性に影響するため、DIYでも業者施工と同等の慎重さが求められます。
もし不安を感じる場合には、基礎工事のみ専門業者に依頼するなど、部分的に外注を活用する方法も有効です。
費用を考える際には、本体価格だけでなく、柱・基礎・金物・施工費を含めた総額を把握することが重要です。
公開されている参考価格例によると、プラド/oneは1mあたり約1.3万円から、プラド/richは約2.5万円から、さらにプラド/plusは仕様によって幅広く、可動ルーバー仕様では1mあたり約6.9万円からの事例が確認されています。
これらは工事費込みの目安であり、コーナー加工や運搬養生の条件で変動することも考慮する必要があります。
以下に、各シリーズの相場を整理します。
| シリーズ | 特徴 | 参考価格(1mあたり・工事費込み) |
|---|---|---|
| one | エントリーモデル、5色展開 | 約13,000〜20,000円 |
| rich | 板厚22mmで剛性強化 | 約25,000〜30,000円 |
| rich+ | richに補強構造を追加 | 約25,000円〜 |
| plus | 柱スパン2000mm対応、補強構造 | 約35,000〜69,000円 |
DIY施工を選べば工事費分を抑えられる一方で、基礎精度や風対策を誤ると修繕費がかさむ可能性もあります。
逆に、業者施工では安定性が確保されやすく、保証制度が付く場合もあるため、費用対効果を考えると必ずしも高額とは限りません。
まとめると、プラドフェンスの費用はシリーズや仕様、高さによって幅広く変動しますが、適切な選択と施工を組み合わせることで、コストと品質の両立が可能になります。
プラドフェンスは、天然木のような木目調デザインと樹脂製ならではの耐久性を組み合わせた製品であり、その特徴は他のシリーズや他社フェンスと比較することでより明確に理解できます。
例えば、同社のアルミフェンスは軽量で施工が容易という利点を持ちますが、どうしても無機質でクールな印象になりやすい傾向があります。
それに比べてプラドフェンスは、木目の再現度が高く、住まい全体に温かみを与える点で優れています。
天然木フェンスは自然素材ならではの風合いが魅力ですが、経年劣化による腐食やシロアリの被害といった問題が避けられず、定期的なメンテナンスが不可欠です。
その点、プラドフェンスは樹脂素材を基盤としているため、防腐処理や塗装の必要がなく、清掃だけで長期的に美しさを維持できるとされています。
また、他社の人工木フェンスは木粉と樹脂を混合した構造である場合が多いですが、プラドフェンスは裏面補強や多層構造を備えたシリーズがあり、風荷重への耐性が強く、施工条件に応じた柔軟な対応力が評価されています。
特に「plus」や「rich+」シリーズでは、柱のピッチを最大2000mmまで広げられる設計が導入されており、見た目のシンプルさを保ちつつ施工手間やコストを抑える工夫もなされています。
以下に代表的な比較をまとめます。
| 製品名 | 特徴 | 耐久性 | コスト感 |
|---|---|---|---|
| プラドフェンス | 木目調樹脂、裏面補強あり、シリーズ展開豊富 | 高い | 中程度〜やや高め |
| アルミフェンス | 軽量、施工容易、錆に強い | 高い | 中程度 |
| 天然木フェンス | 自然素材の風合い | 低い(腐食・メンテ要) | 中〜低 |
| 他社人工木フェンス | 木粉樹脂が主体、意匠性は製品ごとに差 | 中〜高 | 中程度 |
この比較からも分かるように、プラドフェンスは最安値帯ではありませんが、意匠性と耐久性を両立できる点で全体的なバランスが優れた製品だと評価されています。
価格だけでなく、住まいに与える調和や長期的な安心感まで考慮することで、その価値がより際立ちます。
プラドフェンスに関する利用者の口コミでは、まずデザイン性への満足度が非常に高い点が特徴的です。
「天然木のように見えるため庭の雰囲気が柔らかくなった」「住宅外観との一体感があり、上品な印象になった」という声が多く寄せられています。
また、樹脂素材ならではの強みとして、腐食やシロアリ被害の心配がほとんどないことから、メンテナンスの手間が少なく済む点も高く評価されています。
数年使用しているユーザーからは「色あせが目立ちにくく、施工直後の状態を長く維持できている」という具体的な感想も確認されています。
一方で、懸念点として「夏場は多少の伸縮がある」「強い衝撃を受けると板がたわむことがある」といった口コミもあります。
これは素材特性に起因するため、設置環境によって影響を受ける可能性があります。ただし、施工基準に従い柱間隔や控え柱の配置を守ることで、問題を大幅に軽減できるとされています。
さらに、「完成後は想像以上に高級感があり、外構全体の雰囲気が明るくなった」という意見も見られ、住宅デザインにおいてプラスの影響を与える存在であることがうかがえます。
総合的には、デザインと機能を両立した満足度の高いフェンスとして評価されており、特に「自然な質感を求めつつ、メンテナンスの手間を抑えたい」と考える方に適していると考えられます。
- メンテナンスは必要ですか?
- プラドフェンスは塗装や防腐処理を必要とせず、基本的には水洗いや中性洗剤での清掃だけで維持できるとされています。強い溶剤や研磨剤は表面を傷める可能性があるため、使用は避けることが推奨されています。
- 強風地域でも設置できますか?
- メーカーの施工基準では、柱のサイズやピッチ、控え柱の有無を適切に守ることで強風地域でも設置可能とされています。例えば「rich+」や「plus」シリーズは裏面補強があるため、2000mmピッチでの設置も認められており、剛性確保の工夫が施されています。
- 費用はどのくらいですか?
- シリーズや仕様によって幅がありますが、公開されている工事費込みの目安では、1mあたり「one」が約1.3万円から、「rich」が2.5万円程度から、「plus」や「rich+」では仕様によって5.7万円〜6.9万円程度とされています。延長や高さ、基礎条件によって変動するため、見積もりの際は条件を揃えて比較することが重要です。
- カラーやデザインの選択肢は豊富ですか?
- プラドフェンスは複数色展開がされており、住宅外観に合わせてナチュラルな木調から落ち着いたモダンな色合いまで幅広く選択できるとされています。シリーズごとにカラーバリエーションが異なるため、事前にカタログで確認することが勧められます。
- 保証制度やアフターサポートはありますか?
- 製品によってはメーカー保証が付帯しており、一定期間内の不具合や欠陥に対応してもらえるとされています。購入先や工事店によって保証内容が変わる場合もあるため、契約時に保証条件を必ず確認しておくことが安心につながります。
これらの質問は、購入前に多く寄せられる内容であり、施工や費用面での不安を解消する上でも役立ちます。
正しい情報を把握しておくことで、設置後のトラブルを防ぎ、安心して長期的に利用できる選択につながります。
グローベンのプラドフェンスは、天然木のような質感を持ちながらも樹脂素材による耐久性を兼ね備えた外構資材です。
施工のしやすさや豊富なデザイン性から多くの住宅で選ばれていますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。
例えば、温度変化による伸縮や強風地域での安定性、さらには費用面でのコスト感などは、購入や設置前に十分な理解が必要です。
ただし、これらの注意点は適切な施工や工夫によって解決できる部分が多く、製品の特性を理解したうえで正しく対応することで、長期間安心して使うことができます。
とくに強風地域では施工基準を守り、補強材や控え柱を適切に導入すること、DIY施工を考える場合は正しい手順と余裕を持った設計を心がけることが大切です。
また、プラドフェンスの魅力はデザイン性や機能性だけでなく、シリーズごとの幅広い選択肢にあります。
目的に合わせて高さや仕様を選び、口コミや費用相場も参考にすることで、より納得感のある導入が可能です。以下の点を押さえておくと安心です。
- 設置環境や高さに応じた適切なシリーズを選ぶ
- 強風や地盤の条件に合わせた施工基準を守る
- DIYか業者施工かを慎重に判断する
- 費用相場と比較しながらコストと性能のバランスを取る
要するに、プラドフェンスはデメリットを正しく理解し、それに応じた対策をとることで、住まいに長く調和する価値ある選択肢となります。
家づくりや庭づくりを計画する方にとって、安心と美しさを両立できるフェンスとして検討に値するといえるでしょう。
とはいえ、「自分の家に合うシリーズや施工方法が分からない」「費用や業者選びで失敗したくない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そんなときに便利なのが、外構・エクステリアパートナーズです。専門のエクステリアプランナーが無料で最大3社の優良業者を紹介してくれるため、デザインや施工内容を比較しながら納得のいくプランを選べます。
外構工事を安心して進めたい方は、一度相談してみるのがおすすめです。