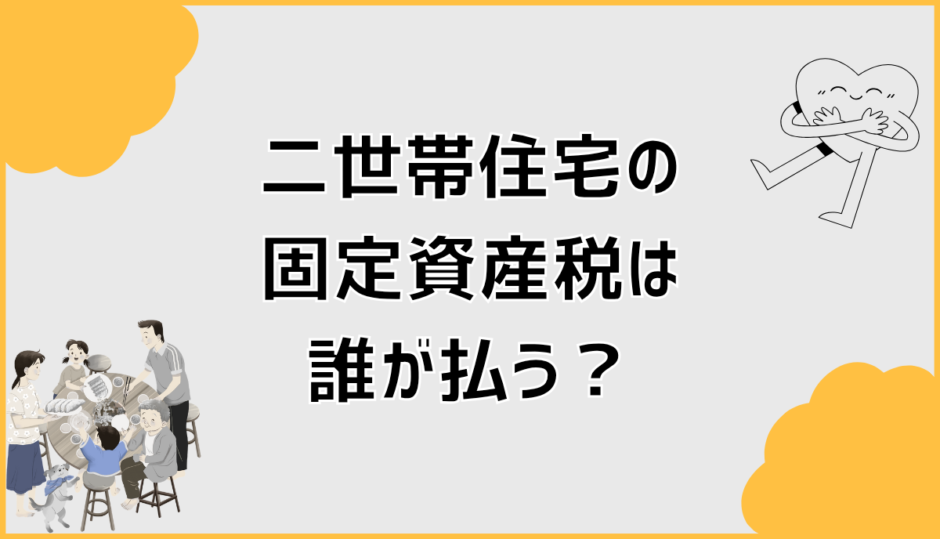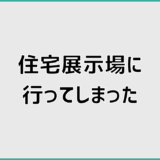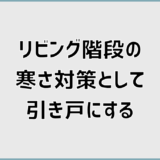この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
二世帯住宅の話が具体的に進み始めると、間取りや費用のこと以上に、あとから気になってくるのが固定資産税の扱いではないでしょうか。
親と子で一緒に住むことは決まっているものの、固定資産税は誰が払うのか、どこまでが自分の負担になるのかは、意外と曖昧なまま話が進みがちです。
玄関を共有するのか、それともキッチンを2つ設けるのかといった住まいの形によって、税金の考え方や軽減の効き方が変わることもありますし、平均的な負担感が分からず不安になる方もいるかもしれませんね。
ここでは、二世帯住宅における固定資産税の基本から、判断に迷いやすいポイント、将来を見据えた対策までを順に整理していきます。
誰か一人が抱え込まず、家族全体で納得できる形を考えるための材料として、落ち着いて読み進めていただけたらと思います。
- 二世帯住宅の固定資産税は誰が払うのかという基本的な考え方
- 住宅の形や共有の有無で税金の扱いがどう変わるか
- 親子で負担を分ける際に注意したいポイント
- 固定資産税の平均や軽減を踏まえた判断の整理
※本記事では、公的機関の案内や制度資料、一般的な事例などを参照し、内容を整理して構成しています。体験談や口コミには個人差があるため参考情報として捉え、具体的な判断はご自身で専門家へ確認する前提でお読みください。
二世帯住宅の固定資産税は誰が払うのか

二世帯住宅を検討し始めると、「固定資産税は誰が払うのか」という疑問にぶつかる方は少なくありません。親が土地を持っている場合、子が建築費を出す場合、名義をどうするかによって、税金の考え方は少しずつ変わってきます。
さらに、住宅の形が一世帯扱いか二世帯扱いか、共有名義にするのかによっても、負担の見え方は異なります。
ここでは、二世帯住宅ならではの固定資産税の基本的な考え方を整理しながら、よくある迷いや注意点を順に解説していきます。建てる前に知っておきたい全体像を、ここで一度落ち着いて確認していきましょう。
二世帯住宅の固定資産税は誰が払う
二世帯住宅の固定資産税でいちばん混乱しやすいのが、「実際にお金を出した人」と「税金を払う義務がある人」が一致しないことです。
固定資産税(土地・家屋)は、毎年1月1日(賦課期日)時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者になります。東京都主税局の案内でも、賦課期日現在の所有者が納税義務者と示されています(出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/real_estate/o )。
つまり、建築費を親が負担していても、登記名義が子であれば子が納税義務者です。逆に、子が援助して建てたとしても、登記名義が親なら親に納税通知書が届きます。
現実の負担は家族内で分担できますが、自治体に対しては名義人が責任を負う、という整理が基本ですね。

名義と負担のズレ、整理が必要かもしれません
また、年の途中で売買や贈与があっても、その年の税の請求先は原則として1月1日時点の名義人です。実務上は、売買契約で日割り精算することが多いものの、契約と課税は別物です。
お金の出し手と名義がズレる場合は、後から「なぜ自分に請求が来るのか」と揉めがちです。
まずは、納税義務者は登記(台帳)上の所有者という原則を軸に、家族内の負担ルールを別で決めておくのが安心です。最終的な扱いは自治体の案内や専門家の助言で確認してください。
二世帯住宅の形で変わる固定資産税
二世帯住宅は、生活の分け方によって「1戸扱いか、2戸扱いか」が論点になります。
固定資産税そのものは土地・家屋の評価額と税率で決まりますが、住宅用地特例や新築住宅の減額は「1戸あたり」の考え方が絡むため、結果として税負担の差が出やすいです。
とくに注意したいのが、完全分離型で区分登記できるケースです。区分登記になると、建物が2戸の住宅として扱われ、軽減措置が2戸分適用される可能性があります。
一方、同じ二世帯でも共有部分が多いと1戸扱いになりやすく、軽減の「枠」は1戸分で進むことが一般的です。ここでのイメージを整理するために、代表的な見え方を表にまとめます。
| 住まいの分け方 | 生活設備 の独立性 | 登記のイメージ | 税の見え方 (一般論) |
|---|---|---|---|
| 完全同居型 | 低い (ほぼ共有) | 単独・共有 | 1戸扱いになりやすい |
| 部分共有型 | 中 (玄関など一部共有) | 単独・共有が多い | 1戸扱いになりやすい |
| 完全分離型 | 高い (玄関・水回り独立) | 区分登記が検討対象 | 2戸扱いになり得る |
玄関共有の場合
玄関を共有していると、外から見た住まいの独立性が弱くなるため、1戸として扱われるケースが多くなります。
固定資産税の通知もまとめて届くため、「親世帯分」「子世帯分」と区切って請求されるわけではありません。家計負担は、光熱費と同じようにルール化しておくとスムーズです。
キッチン2つの場合
キッチンが2つあっても、それだけで必ず2戸扱いになるとは限りません。
玄関が共通で内部で行き来できる間取りだと、1戸扱いのまま進む自治体もあります。2戸扱いを狙うなら、間取りの独立性と登記可否を、設計段階で自治体や専門家に確認しておくと確実です。
共有名義だと誰が固定資産税を払う
親子で共有名義にする二世帯住宅は少なくありません。共有にすると「持分割合に応じて負担する」と考えがちですが、固定資産税の世界では少し見え方が異なります。
自治体からの請求は、名義人全員に対して連帯して課税される形になることが多く、誰か一人が納付すれば、滞納としては解消されます。とはいえ、家族内の公平感を保つには、持分割合や家計状況に合わせて分担を設計するのが現実的です。
よくあるのは、土地は親の持分が大きいので親が多め、建物は子がローンを返しているので子が多め、といった調整ですね。ただし、共有名義は税金だけでなく将来の手続きにも影響します。
相続が発生すると、相続人が増えて共有者が増えることがあり、意思決定が難しくなるリスクがあります。固定資産税も、納付書が届く人と実負担者が増えていくと管理が煩雑になります。
実務では、代表者がまとめて払い、家族内で精算する形が多いです。その際は、口頭ではなく、簡単でよいので「誰が、いつ、いくら負担するか」をメモに残しておくと安心です。
税務上の扱い(贈与にならないか等)も絡むため、心配な場合は税理士や司法書士に確認しながら進めてください。
親や子が全額払う場合の注意点
二世帯住宅では、納税通知書が届く名義人ではなく、親または子が固定資産税を全額負担しているケースもあります。家族の助け合いとしては自然ですが、税務上は「他人の税金を肩代わりした」と見られる余地がある点に注意が必要です。
とくに、名義が子なのに親が毎年支払っている場合、状況によっては子への経済的利益の提供と解釈される可能性があります。
逆に、名義が親なのに子が全額負担している場合も同様です。すべてが直ちに問題になるわけではありませんが、長期にわたり継続すると説明が必要になる場面が出てきます。

毎年の支払い、贈与扱いが気になるところです
対策としては、支払いの根拠を整理することが鍵になります。
たとえば、同居に伴う生活費の一部として負担している、親が子から家賃相当の受領をしていて実質的に精算されている、など、家計の流れとして整合が取れていれば説明しやすくなります。
また、支払い方法も工夫できます。名義人がいったん納付し、後日分担分を振込で受け取る、家計簿や通帳にメモを残す、などはシンプルですが効果的です。
税金の判断は個別事情で変わります。固定資産税を誰かが多めに負担する設計にするなら、贈与税の基礎控除(年間110万円など)も含め、最終判断は税理士など専門家に相談することをおすすめします。
二世帯住宅の固定資産税の平均額
固定資産税の「平均額」を一言で示すのは難しいですが、二世帯住宅でよく見られる価格帯を想定すると、ある程度のイメージはつかめます。
建物にかかる固定資産税の目安
一般的な二世帯住宅では、建物の延床面積が50〜60坪前後になることが多く、建物の固定資産税評価額は1,500万円〜2,500万円程度になるケースが一つの目安です。
この場合、標準税率1.4%で計算すると、建物だけで年間およそ21万円〜35万円前後がベースになります。
ここに新築住宅の軽減措置が適用されると、一定期間は税額が2分の1となり、建物分の固定資産税は年間10万円台前半〜後半に収まることもあります。
ただし、軽減期間が終了すると本来の税額に戻るため、数年後に負担が増える点は事前に把握しておきたいところです。
土地にかかる固定資産税の目安
土地については、住宅用地特例が適用されるため、課税標準は大きく圧縮されます。たとえば評価額3,000万円の土地でも、小規模住宅用地の特例が効けば、課税標準はその6分の1相当まで下がります。
ただし、地価が高いエリアや敷地が広い二世帯住宅では、特例後でも年間10万円前後の税額になることは珍しくありません。
合計するとどのくらいになるか
これらを合算すると、二世帯住宅の固定資産税は、軽減措置がある時期で年間15万〜25万円前後、軽減終了後は30万円前後から40万円程度になるケースが一つの目安と考えられます。
もちろん、これはあくまで一般的な想定であり、立地や建物仕様によって上下します。
より現実的な数字を知りたい場合は、建築予定地の公示価格や、同規模住宅の固定資産税評価額を不動産会社や自治体で確認し、事前に概算を出しておくと安心です。
実際の税額は自治体の決定によるため、最終的な判断は必ず自治体の公式情報や専門家の助言をもとに行ってください。
二世帯住宅の固定資産税が高い理由
二世帯住宅の固定資産税が高く感じられる背景は、仕組みを分解すると見えてきます。ポイントは大きく2つで、延床面積が増えやすいことと、設備グレードが評価に反映されやすいことです。
まず延床面積です。親世帯と子世帯の生活を分けようとすると、LDKや水回りが増え、結果として床面積が大きくなりがちです。建物の評価は床面積や構造、仕上げなどを総合して算定されるため、面積が増えると評価額も上がりやすくなります。
次に設備です。キッチンが2つ、浴室が2つ、トイレが複数など、二世帯住宅は設備が充実する傾向があります。設備の種類や仕様は評価に影響しうるため、同じ床面積でも設備が豪華なほど評価額が上がる可能性があります。
さらに、完全分離型で2戸扱いになると、軽減措置が2戸分使える余地がある一方、都市計画税の課税対象や将来の管理コストも含め、総合コストの見え方が変わります。固定資産税だけを切り取って最適化すると、相続や売却時に別の負担が出ることもあります。
税額が高いかどうかは、住まいの快適性や家族の助け合いとトレードオフになる面もあります。税の仕組みを理解したうえで、間取りと名義をセットで設計することが後悔を減らす近道です。
二世帯住宅の固定資産税を誰が払うかの注意点

二世帯住宅の固定資産税は、誰が払うかだけでなく、どこまでが対象になり、どんな点に注意が必要かを理解しておくことが大切です。
建物の軽減措置が使えるのか、土地の特例がどう効くのか、都市計画税は別に考える必要があるのかなど、知らないまま進めると後から戸惑う場面も出てきます。
ここでは、税額を左右しやすいポイントや、事前に整理しておきたい注意点を中心に解説していきます。トラブルを防ぐためにも、ここで一度、全体の注意点を確認しておきましょう。
二世帯住宅で使える固定資産税軽減
二世帯住宅でも、要件を満たせば固定資産税(家屋)の軽減措置を受けられます。
新築住宅に係る固定資産税の減額制度
代表的なのが新築住宅に係る減額制度で、新築住宅の固定資産税を原則3年間(国土交通省の整理では「マンション等の場合は5年間」)、2分の1に減額するものです。
あわせて、認定長期優良住宅については、5年間(マンション等の場合は7年間)2分の1に減額する特例があることも示されています(出典:国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000021.html )。
減額が適用される床面積と二世帯住宅の考え方
減額の対象は、居住部分の床面積120㎡相当分までが基本で、床面積が一定範囲(例:50㎡以上280㎡以下)に収まることなど、いくつかの要件があります。
二世帯住宅で2戸扱い(区分登記)になる場合は、各戸ごとに要件判定や減額枠が動く可能性があるため、設計内容によって税負担に差が出ることがあります。
申告手続きは必要か
手続きについては、「必ず申告が必要」と一律に考えない方が安全です。
新築住宅の減額は、家屋調査などを通じて自治体が把握し、自動的に適用されることも多い一方、自治体や住宅の種類(とくに認定長期優良住宅など)によっては申告書や添付書類の提出が求められる場合があります。
必要書類や期限には地域差があるため、引き渡し後は早めに自治体へ確認しておくと安心です。
増改築・リフォームとの違いに注意
二世帯住宅では将来的に増改築やリフォームを行うケースもありますが、耐震改修やバリアフリー改修などの減額制度は、新築住宅の減額とは別制度です。
要件や適用期間も異なるため、新築時の軽減と混同すると、思ったほど税額が下がらないことがあります。
軽減措置を取りこぼさないためには、設計段階で「1戸扱いか2戸扱いか」を整理したうえで、「どの軽減制度が対象になり、申告が必要か」を自治体に確認し、引き渡し後の手続きをあらかじめスケジュールに組み込んでおくのが現実的です。
土地にかかる固定資産税の注意点
二世帯住宅は建物に目が行きがちですが、土地の固定資産税も家計に効きます。土地には住宅用地特例があり、1戸あたり200㎡までの部分(小規模住宅用地)は固定資産税の課税標準が6分の1、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。
この仕組みは多くの自治体で共通に運用されます。二世帯住宅でポイントになるのは「戸数認定」です。区分登記で2戸として認められれば、200㎡の枠が2戸分動く可能性があり、結果として土地の軽減が広く効くことがあります。
逆に1戸扱いのままだと、敷地が広いほど一般住宅用地の部分が増え、税の伸びが目立ちやすいです。また、住宅用地特例は、住宅が建っていることが前提です。建て替えで一時的に更地になると、条件を満たさず税が跳ねることがあります。
工期のタイミングで年度をまたぐ場合は、自治体に確認しておくと安心です。さらに、二世帯で将来売却や賃貸活用を想定するなら、土地の権利関係(共有持分、地目、接道など)も長期的な税負担に影響します。
土地の税は、立地と戸数認定で印象が大きく変わります。建物の計画と同時に、敷地の特例がどう効くかを確認し、正確な取り扱いは自治体の案内や専門家に相談してください。
都市計画税は誰が払うのか
固定資産税と一緒に届くことが多いのが都市計画税です。名前は聞いたことがあっても、仕組みを把握していない方は意外と多いかもしれません。
都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内の土地・家屋に課される目的税で、税率や対象は自治体ごとに定められます。納税義務者は固定資産税と同じで、賦課期日(1月1日)時点の所有者として台帳に登録されている人です。
東京都主税局の案内でも、都市計画税の納税義務者は賦課期日現在の所有者とされています(出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/real_estate/o )。
二世帯住宅だから都市計画税が特別に増える、というわけではありません。
ただし、土地の住宅用地特例は都市計画税にも連動し、小規模住宅用地は課税標準が3分の1、一般住宅用地は3分の2など、軽減の仕組みが固定資産税と異なる点は押さえておきたいところです。
「固定資産税だけ見ていたら、都市計画税もあって合計が想定より高かった」というのはよくある落とし穴です。住む場所が市街化区域かどうか、税率が何%かは自治体で変わるため、正確な情報は自治体の公式情報で確認してください。
二世帯住宅でできる税金対策
二世帯住宅の税金対策は、住み始めてからよりも、建てる前に整理した方が効きやすいです。固定資産税は毎年の支払いなので、名義と負担の設計がそのまま家計の安定につながります。

税だけでなく相続も並べて見たいですね
名義の決め方
名義は、誰が資金を出すか、将来の相続をどうするか、ローンを誰が組むかをセットで考える必要があります。単独名義は管理がシンプルですが、出資割合と名義がズレると贈与と見られるリスクが出ます。
共有名義は出資割合に合わせやすい一方、相続で共有者が増えると意思決定が難しくなることがあります。
完全分離型で区分登記が可能なら、固定資産税の軽減が広がる可能性がある反面、相続の特例との関係で別の検討が必要になる場面もあります。
支払いルールの決め方
納税通知書が誰に届くか、誰が引き落とすか、世帯間でどう精算するかを、最初に決めておくのがトラブル予防になります。口座引き落としにするなら、名義人の口座から落とし、分担分を月々で受け取る形にすると管理しやすいです。
将来同居解消や介護など生活が変わる可能性も踏まえ、見直し前提のルールにしておくと現実的です。税金対策は、固定資産税だけでなく贈与・相続・住宅ローン控除などと連動します。
最終判断は、自治体の案内と、税理士・司法書士など専門家の助言を踏まえて行ってください。
固定資産税で起きやすいトラブル
二世帯住宅の固定資産税トラブルは、「知らなかった」「聞いていない」が原因になりがちです。
よくあるのは、名義は子なのに親が払うつもりでいた、共有名義なのに通知書の宛先だけで負担を決めてしまった、同居が解消したのに支払いルールが更新されていない、といったケースです。
もう一つ多いのが、納期限を過ぎてしまうことです。分割納付の期ごとに資金繰りが必要で、うっかりすると延滞金が発生します。
延滞金の利率は年ごとに見直されるため、国税庁の公表資料などで最新の割合を確認するのが無難です(出典:国税庁「延滞税の割合」https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm )。
自治体税の延滞金も同様に利率が設定されており、長引くほど負担が増える点は共通です。
相続が絡むとさらに複雑になります。名義人が亡くなった直後は、相続登記が完了するまでの間、相続人が納付対応を求められることがあります。
誰が代表して払うのか、住み続ける人がいるのか、売却するのかで、家族内の合意形成が必要になります。
トラブルを避けるには、名義、支払い担当、精算方法、相続時の方針を、最低限メモに残して共有することが効きます。曖昧なまま進めず、必要に応じて専門家へ相談してください。
二世帯住宅の固定資産税で押さえておきたいポイント
ここでは、二世帯住宅の固定資産税について、とくに見落としやすい要点を整理します。家づくりや同居を進める前に、次のポイントを一度確認しておくと安心です。
- 固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点で登記(台帳)上の所有者として登録されている人です。建築費の負担者や実際の居住者とは必ずしも一致しません。
- 二世帯住宅は、間取りや独立性によって1戸扱いか2戸扱いかが判断されます。玄関や動線を共有する場合は1戸扱いになりやすく、完全分離型で区分登記が可能な場合は2戸扱いの検討対象になります。
- 1戸扱いか2戸扱いかによって、土地の住宅用地特例や新築住宅の固定資産税軽減の効き方が変わる可能性があります。設計段階での確認が負担差につながります。
- 共有名義は支払い分担を調整しやすい一方、相続時に権利関係や管理が複雑になりやすい点に注意が必要です。
- 親または子が固定資産税を全額負担する場合は、継続状況によって贈与と見られないよう、家計の流れや精算関係を整理しておくと安心です。
- 税額の見通しは、評価額と税率をベースに、固定資産税と都市計画税、各種軽減措置を含めて合計で考えると現実に近づきます。
最終的な税額や制度の適用可否は自治体ごとに判断されるため、正確な情報は自治体の公式サイトや窓口で確認し、不安がある場合は税理士や司法書士など専門家に相談してください。
まとめ:二世帯住宅の固定資産税は誰が払う?
どうでしたか?二世帯住宅の固定資産税は、誰が払うのかという点だけでなく、名義や住まいの形、将来のことまで関わってくるテーマです。
最初に整理しておかないと、住み始めてから「こんなはずではなかった」と感じてしまう場面も出てきます。この記事では、基本的な仕組みから注意点までを一つずつ確認してきました。
- 固定資産税は原則として名義人が納税義務者になる
- 住宅の形や共有の有無で税金の扱いが変わる
- 全額負担や共有名義は将来のトラブルにつながりやすい
- 平均額や軽減を含めて全体で考えることが大切
家づくりは、建てる前の話し合いがとても重要です。
二世帯住宅だからこそ、税金のことも家族で共有し、納得できる形を選んでいきたいですね。ここまで読んでいただき、ありがとうございました。