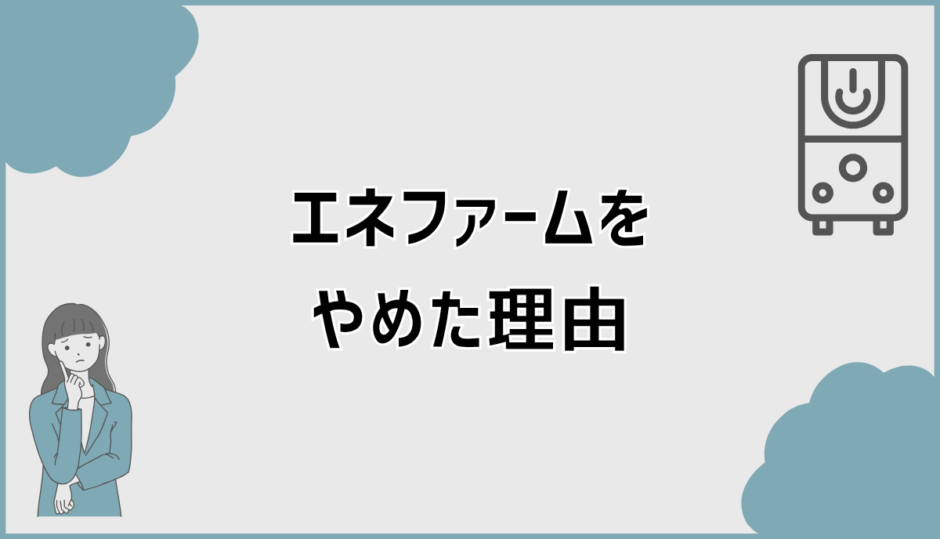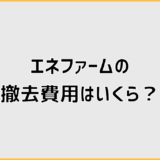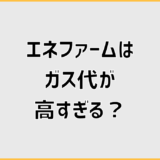この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
ある日、点検案内のハガキや光熱費の明細を見て、「エネファーム、そろそろやめた方がいいのかな」と立ち止まった経験はありませんか。時代遅れなのでは、という不安と、これまで感じてきたメリット、そして気になり始めたデメリット。
その狭間で、家計への影響や維持管理にかかる費用、給湯機器としての今後の使い道まで、頭の中が整理できずに迷ってしまう方も多いように感じます。
実際、エネファームをやめた人の理由を聞くと、光熱費の変化や修理費の負担など、想像以上に現実的な悩みが並びます。
ここでは、そうした声をもとに、やめた背景や判断の分かれ目を分かりやすく整理しながら、後悔しにくい選択肢を一緒に考えていきます。読み終える頃には、あなたの暮らしに合った答えの輪郭が、きっと見えてくるはずです。
- エネファームをやめた主な理由と実際の体験談の整理
- 光熱費や家計に起きやすい変化と注意点の把握
- 撤去費用や補助金、保証に関する具体的な注意点
- 後悔しにくい給湯機器選びと判断基準の考え方
タウンライフリフォームとは?
タウンライフリフォームは、リフォーム会社選びや費用の不安を「決める前」に整理できる無料サービスです。
複数社に一社ずつ問い合わせなくても、あなたの条件に合ったリフォームプラン+見積もりをまとめて受け取れます。
見積は考えの整理手段
完全無料・契約義務なし
※本記事では、メーカー公式情報や公的資料、各種レビュー、実際の体験談などを参照し、内容を精査したうえで独自に整理・構成しています。口コミや事例には個人差があるため参考情報として捉え、最終的な判断はご自身で関係各所へ確認することを前提にご覧ください。
エネファームをやめた理由と費用の実態

エネファームは省エネ性や非常時の安心感から注目されてきましたが、実際に使い続ける中で「思っていたほど光熱費が下がらない」「維持費や更新費が不安」と感じ、やめる選択をする家庭も増えています。
一方で、使い方や条件によっては、今も満足して使い続けている方がいるのも事実です。
ここでは、やめた理由や実際の声を整理しながら、どんな家庭が撤去を検討しやすいのか、逆に続けた方が向いているのはどんなケースなのかを、判断材料として分かりやすくまとめていきます。
エネファームをやめた主な理由
エネファームは「発電しながらお湯をつくる」家庭用燃料電池として登場し、省エネや災害時の安心感で注目されました。一方で、導入から年数が経つほど「想定と違った」と感じる論点が増えやすい設備でもあります。
背景にあるのは、電気料金・ガス料金の変動、住宅の断熱性能、家族構成の変化、そして10年以降に現れやすい維持費の増加です。ここでは、やめた人が口にしやすい理由を整理します。
時代遅れと感じた
登場当初は「家で電気をつくる」という発想自体が新しく、大きな注目を集めましたが、現在では太陽光発電や家庭用蓄電池、V2Hなど選択肢が大きく広がっています。
その中で、エネファームの発電量は数百W規模にとどまり、家庭全体のピーク電力をカバーできるわけではありません。
また、自家消費を優先して稼働する特性から、「昼は太陽光、夜は蓄電池」という運用を目指す家庭では役割が重なり、設備構成が複雑に感じられることもあります。
結果として、より分かりやすく、管理しやすいシンプルな構成へ見直す流れが強まっています。
メリットとデメリットを比較した結果
メリットは、発電と給湯を同時に行え、災害時の最低限の電力確保や床暖房との相性が良い点です。一方、二筐体で設置場所を取り、更新・撤去の手間や将来の維持費が読みづらいという弱点もあります。
導入時の試算は理想条件を前提にしがちで、在宅時間や給湯量、暖房の使い方が想定と異なると、長期の費用対効果に差が生じやすくなります。
光熱費が下がらず家計負担が増えた
エネファームは買電を減らせる一方で、発電に必要なガス使用量が増えるため、家計への影響は「電気代の減少分」と「ガス代の増加分」のバランスで決まります。
電気料金が高騰している時期には有利に感じやすいものの、ガス単価や燃料費調整額の影響を受けると、想定ほどの節約効果が得られない場合もあります。
特に給湯や暖房の使用量が少ない家庭では排熱を十分に活かせず、結果として光熱費が下がらないことが不満につながりやすい傾向があります。
現在プロパンガスをご利用中の戸建住宅で、ガス代が高いと感じている場合は、無料診断だけで毎月数千円負担が軽くなるケースもあります。
維持管理費用が高すぎた
多くのプランでは「10年までは無償メンテナンス」とされていますが、保証が切れるタイミングから有償点検が現実的な負担としてのしかかります。
点検費用は契約内容や機種によって差があるものの、総点検で数万円から10万円前後、さらに部品交換や不具合対応が重なると出費は一気に膨らみます。
これらが数年おきに発生する可能性を考えると、家計への影響は決して小さくありません。長期のランニングコストに点検・修理費を含めて試算すると、より維持費の読みやすい給湯方式へ更新した方が合理的だと感じる家庭も増えています。
故障リスクと寿命が不安だった
燃料電池ユニットは安全上の配慮から、通電開始から一定年数で発電機能が停止する設計が一般的です。停止後も給湯器としては使用できますが、「発電しないなら別方式で十分」と考える家庭も少なくありません。
加えて、使用年数が進むほど故障リスクや高額修理の不安が高まり、突然お湯が使えなくなる事態は生活への影響も大きくなります。
そのため、トラブルを未然に防ぐ目的で、早めに交換や撤去を検討する流れが生まれやすい傾向があります。判断に迷う場合は、機器の状態を点検したうえで、メーカーやガス会社、施工店など専門家に相談し、総合的に決めることが安心につながります。
実際にやめた人の体験談と口コミ
口コミで多いのは「良かった点はあるけれど、長く使うほど負担が見えた」という温度感です。導入直後は、発電で買電が減ることや、床暖房の快適さ、停電時の安心感を評価する声が目立ちます。
一方で、10年に近づく頃から話題が変わり、「点検費が思ったより重い」「更新時にまとまった出費になる」「発電メリットを感じづらい」といった現実的な論点が増えます。

その声が自宅に当てはまるか整理したいですね
特に多いのが、期待の置き方のズレです。例えば「電気代が大きく下がる」と思っていたのに、実際はガス使用量が増えて相殺され、家計としては横ばいに見えるケースがあります。
エネファームは給湯需要があるほど排熱を活かせるため、単身〜少人数世帯、日中不在が多い家庭では効果を体感しにくいという声につながりやすいです。
また「維持管理の説明が分かりづらかった」という口コミも見かけます。無償期間が終わると、点検や修理の費用が自己負担になり、しかも1回で終わらず一定周期で発生する可能性があります。
ここを導入時にイメージできていないと、家計の予定が崩れたように感じやすいでしょう。
一方で、やめた人の中にも「停電時に助かった経験がある」「冬の給湯・床暖房の快適性は高かった」という評価は残る傾向があります。
つまり、設備として悪いというより、生活条件とコスト構造の相性が合わなくなったことが決め手になりやすい、という整理が現実的です。
口コミは個別事情の集合なので、そのまま自宅に当てはめるのは危険です。次のように、自宅の前提を置いて読み替えるのがコツです。
- 家族人数と在宅時間(給湯や暖房の使用量がどれくらいあるか)
- 床暖房や浴室暖房など、温水機器の使用状況
- 太陽光発電・蓄電池の有無と、売電より自家消費を重視するかどうか
- 今後10年間にかかる更新費用や点検費用を家計に組み込めるか
費用や制度は年度で変わるため、正確な条件は公式サイトの最新情報を確認し、見積もりは複数社で比較したうえで、最終判断は専門家に相談することをおすすめします。
やめた方が得な人と続けた方が得な人
エネファームは、家庭ごとに最適解が変わる設備です。判断の軸は、実際の光熱費削減がどれほど出ているか、そして10年以降に発生する点検・修理・更新費を無理なく受け止められるか。
家族人数、在宅時間、給湯・暖房の使い方、将来計画を重ねて考えると、続けるか、やめるかの方向性が自然と整理できます。詳しい判断基準は別記事で解説しています。

続ける損得は明細で確認しておきたいですね
やめた方がいい人の特徴
まず、光熱費の削減効果を実感できていない家庭です。給湯需要が少ない、日中の在宅時間が短い、床暖房など温水設備の利用頻度が低い場合、発電時の排熱を十分に活かせず、期待していた節約効果が得られにくい傾向があります。
次に、10年以降に必要となる点検や修理費の負担が重い家庭です。数年おきにまとまった出費が発生すると、家計管理のストレスが大きくなりがちです。
さらに、太陽光発電や蓄電池など別の自家消費策を強化したい家庭では、設備の役割が重複しやすく、構成を整理する目的で撤去や更新を選ぶケースも少なくありません。
続けた方がいい人の特徴
一方で、ガス料金が相対的に有利で、給湯・暖房需要が大きく、発電の稼働時間を確保できている家庭は、導入メリットを維持しやすいです。
停電時の最低限電力を「確実に残したい」という目的が強い場合も、発電設備を残す価値があると考える方がいます。さらに、機器状態が良好で、保守契約や点検計画が納得できる形で整っているなら、急いで替える必要がないケースもあります。
判断のために、家計と設備を同じ尺度で見てみると整理しやすいです。例えば、次の3つを1枚にまとめると比較が楽になります。
| 見るべき項目 | 確認方法 | 見え方 |
|---|---|---|
| 月々の電気・ ガス合計 | 直近12か月の明細 | 期待より横ばい/増加なら要注意 |
| 今後の維持費 | 点検案内・契約書・見積 | 10年以降の出費を織り込めるか |
| 更新の総額 | 撤去+新設の相見積 | 乗り換え先で家計が安定するか |
ここまで整理すると、「続けることで得られる価値」と「やめることで減る負担」を比較できます。数値は地域・契約・設備状態で変わるため、最終判断は必ず公式情報の確認と、専門家への相談を前提に進めてください。
エネファームをこのまま使い続けるか、それともやめるかで迷ったときは、10年後まで見据えた判断軸を整理しておくと、後悔のない選択につながりやすくなりますので、こちらの記事を参考にしてみてください。
エネファームをやめた人の体験と注意点

エネファームをやめると決めた後は、次にどの給湯機器を選ぶか、そして撤去や交換にどれくらいの費用がかかるのかが大きな関心事になります。
さらに、補助金の条件や保証の扱い、契約上の注意点を知らずに進めてしまうと、思わぬ出費やトラブルにつながることもあります。
ここでは、実際によく選ばれている設備の傾向や、撤去費用の目安、制度面での注意点を整理しながら、後悔しにくい現実的な選択肢を分かりやすくまとめていきます。
やめた後に選ばれた給湯機器
エネファームをやめた後は、「発電」よりも「給湯の安定・維持費の読みやすさ・家計の最適化」を優先して選び直す流れが目立ちます。
候補としてはエコキュート、高効率ガス給湯器(エコジョーズなど)、そしてオール電化+太陽光(必要に応じて蓄電池)です。選定では、初期費用だけでなく、10年単位の更新・修理・点検の見込みまで含めた総額で考えると後悔が減ります。
エコキュートを選ぶ人が多い理由
エコキュートは、ヒートポンプ技術によって空気中の熱を効率よく集め、お湯を沸かす省エネ性の高い給湯システムです。
電気を直接加熱に使う方式と比べ、消費電力量を大きく抑えられる点が特長で、深夜電力の活用や太陽光の余剰電力での沸き上げ運用ができれば、月々のランニングコストを安定して抑えやすくなります。
また、発電設備を持たない分、構造が比較的シンプルで、故障リスクや点検項目が少なく、長期的な維持管理の見通しを立てやすい点も、多くの家庭に選ばれている理由です。
オール電化と太陽光の組み合わせ
自家消費を重視する家庭では、太陽光発電とエコキュートを組み合わせ、必要に応じて蓄電池を追加する構成にすることで、昼間に発電した電気をお湯や家庭内の電力として無駄なく活用しやすくなります。
さらに、防災面を意識する場合は「停電時にどの家電を使いたいか」を基準に、蓄電池やV2Hの導入を検討する流れが一般的です。
ただし、設備を増やすほど初期費用は高額になりやすいため、光熱費削減を優先するのか、災害対策を重視するのか、あるいは両立を目指すのか、家庭ごとの目的を明確にしたうえで選択することが大切です。
ガス給湯器に戻すケース
「更新費を抑えたい」「機器構成をできるだけシンプルにしたい」家庭では、高効率ガス給湯器へ戻す選択も有力です。既存のガス配管や温水暖房設備をそのまま活かせるケースが多く、大掛かりな工事を避けやすい点がメリットといえます。
初期費用を抑えつつ、使い慣れたガス給湯に戻せるため、生活の変化が少ない点も安心材料です。
ただし、ガス単価や契約プラン、床暖房の使用頻度によって家計への影響は変わるため、導入前に光熱費シミュレーションを行い、長期的な負担を確認しておくと納得感の高い選択につながります。
比較の目安を、家計目線でコンパクトに整理します(費用は地域・機種・工事条件で変動するため、方向性の参考としてご覧ください)。
| 乗り換え先 | こんな家庭に向く | ランニングコストの傾向 | つまずきやすい注意点 |
|---|---|---|---|
| エコキュート | 光熱費を安定させたい 太陽光の余剰電力を活かしたい | うまく運用できると 抑えやすい | 設置スペース、寒冷地仕様の要否、 電気容量(分電盤・契約)の確認 |
| オール電化+太陽光 (+蓄電池) | 自家消費重視 停電対策も強化したい | 条件が合えば大きく 改善しやすい | 初期費用が大きくなりやすい (目的を絞らないと過剰投資になりがち) |
| 高効率ガス給湯器 (エコジョーズ等) | 初期費用を抑えたい ガス暖房を継続したい | 読みやすいが 単価次第 | ガス単価・料金改定リスク、 暖房配管の扱い(残す・撤去) |
選ぶときは、(1)今の明細(電気・ガス)を12か月分そろえる、(2)撤去+新設の総額見積もりを並べる、(3)停電時に何を動かしたいかを決める、の3点があると判断が早くなります。
補助制度は年度で更新され、受付終了も起こり得ます。最新条件は公式発表を確認してください(出典:経済産業省 資源エネルギー庁『給湯省エネ2026事業』 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/kyutokidonyu/kyutodonyuhojo2025.html)。
給湯機器の選び直しは、「うちの場合はいくらかかるのか」「本当に元が取れるのか」が一番気になりますよね。
条件によって金額も工事内容も大きく変わるため、一般的な目安だけで判断すると、後から想定外の出費に戸惑うことも少なくありません。
私のことかも、と感じた方は、今の住まいに合った見積もりを一度取ってみると、選択肢が一気に整理できます。
入力時はリフォーム内容で「水回り」を選ぶと、給湯器交換の相談内容を伝えやすくなります。複数社の工事内容と金額をまとめて比較できるタウンライフリフォームを活用すると、無理なく納得できる判断がしやすくなります。
複数社の費用を一括比較
相場を知らずに決めると損
【PR】
エネファーム撤去費用と処分費の相場
やめると決めたときに気になるのが、撤去・処分と、次の給湯機器の設置を含めた総額です。
エネファームは発電ユニットと貯湯ユニットの二筐体構成が多く、一般的な給湯器と比べて搬出や処分の手間がかかりやすいため、設置環境によって費用差が生じやすい特徴があります。
目安としては、撤去のみで数万円〜10万円前後になるケースが多いものの、搬出経路が狭い住宅やクレーン作業が必要な場合、基礎の撤去・復旧を伴う場合などは、これを上回ることもあります。

撤去だけで判断せず総額で見たいところです
また、撤去と同時にエコキュートやガス給湯器へ交換する場合は、本体価格や新設工事費が加わるため、想定以上に総額が膨らむケースもあります。
工事内容や住宅条件によって費用差が出やすいため、事前に全体像をつかんでおくことが大切です。
撤去費用の考え方や、更新時に失敗しやすいポイント、具体的な金額イメージについては、別記事で詳しく整理していますので、あわせて参考にしてみてください。
補助金と保証と違約金の注意点
撤去・交換の場面でトラブルになりやすいのが、補助金の条件、保証の扱い、そして契約上の縛りです。ここを先に整理しておくと、後から「知らなかった」を減らせます。
まず補助金です。国の補助は年度ごとに制度が変わり、予算上限に達すると受付が終了します。実際に「給湯省エネ2025事業」は補助金申請額が予算上限に達したため、交付申請の受付終了が案内されています(出典:給湯省エネ2025事業 公式サイト『交付申請の受付を終了しました』 https://kyutou-shoene2025.meti.go.jp/news/2025122301.html )。
これから交換を考える場合は、対象機器、申請タイミング(工事前申請が必要なケースが多い)、撤去加算の有無などを、必ず最新の公式情報で確認してください。自治体補助も併用できる場合がありますが、要件や期限が異なるので要注意です。
次に保証です。メーカー保証やガス会社の保守契約には、対象範囲と期間があります。10年を境に有償になる項目が増えることが多く、ここから先の費用感が変わります。
保証の延長や保守契約の内容は会社・機種で違うため、現在の契約書・保証書を見ながら確認するのが確実です。最後に違約金や返還です。
補助金を受けている場合、一定期間の継続使用が条件になっていると、途中撤去で返還が必要になる可能性があります。また、リース・割賦・サービス契約(メンテナンス契約を含む)を組んでいる場合、解約条件が設定されていることがあります。
撤去工事の段取りを組む前に、次の3点をチェックしておくと安全です。
- 過去に利用した補助金の名称、交付条件、使用期間の縛り
- 現在の保証期間、無償・有償の範囲、点検義務の有無
- 契約形態(購入・リース・割賦・サービス契約)と解約条項
制度や契約は個別性が高い領域です。正確な情報は必ず公式サイトと契約書類で確認し、判断に迷う場合は販売店・ガス会社・施工店など専門家に相談してください。
やめて後悔しない最適な選択肢
やめるか続けるかで迷うときは、「今の不満」を埋めるだけでなく、次の10年をどう過ごしたいかを軸に選ぶと後悔が減ります。設備の比較は、初期費用だけでなく、維持費・更新費・使い勝手・災害時の備えを同じテーブルに乗せることが大切です。
まず現実的なのは、10年目前後で状態確認をして、総点検・修理の見込みが大きいなら、更新先の候補(エコキュート・高効率ガス給湯器・オール電化+太陽光)を同時に相見積もりする進め方です。
エネファームは発電停止後も給湯器として使える機種があるため、「発電は止めて給湯だけにする」という運用が成立する場合もあります。
ただし、安全面や機器状態は個体差があるので、自己判断で運転変更せず、必ずメーカー・ガス会社・施工店の指示に従ってください。次に、後悔が起きやすい落とし穴を先に潰します。
補助金を使うなら申請時期と要件、撤去費の内訳、電気容量や設置スペース、寒冷地仕様の要否、床暖房を残すかどうか。
このあたりは、工事後に取り返しがつきにくい論点です。見積書の段階で「何が含まれ、何が別料金か」を確認し、説明が曖昧な会社は避けるのが無難です。
最後に、情報の鮮度も押さえておきたいところです。給湯器補助は年度で更新され、受付終了も起こり得ます。制度面は公式発表を確認し、地域の自治体補助も含めて整理すると、同じ工事でも実質負担が変わる場合があります。
迷ったときの優先順位はシンプルにして構いません。
- お湯の安定(生活インフラの確保)
- 10年単位での家計の見通し
- 防災(停電時に何を動かしたいか)
この3つを満たす組み合わせが、その家にとっての最適解になりやすいです。正確な費用や制度条件は必ず公式サイトで確認し、最終的な判断は専門家に相談したうえで進めてください。
まとめ:エネファームをやめたこと
どうでしたか?最後までお読みいただき、ありがとうございます。エネファームをやめた背景には、光熱費や家計への影響、維持管理や更新にかかる費用、そして暮らし方の変化など、さまざまな要素が重なっています。
大切なのは、良い・悪いで単純に判断するのではなく、ご自身の生活に合っているかを冷静に整理することだと思います。この記事が、迷いを整理するヒントになれば嬉しいです。最後に、判断の軸をもう一度まとめておきます。
- 今の光熱費と家計負担が納得できているか
- 維持管理や更新費用を無理なく見込めるか
- 今後10年の暮らし方に合った給湯機器か
ここまで読んで、「自分の家の場合はどうなるのだろう」と感じた方もいるかもしれませんね。エネファームをやめた後の給湯機器選びや撤去費用は、住宅条件や地域、工事内容によって大きく変わります。
一般的な目安だけで決めてしまうと、後から想定外の出費に戸惑うこともあります。今の住まいに合った金額や工事内容を把握するためにも、複数社の見積もりを一度比較してみると、無理のない予算感と現実的な工事内容が見えてきます。
複数社の費用と工事を比較
知らずに決めると後悔
【PR】
給湯器の交換相談は、リフォーム内容で水回りを選択すると入力がスムーズです。
あなたの選択が、これからの住まいをより心地よいものにしてくれることを願っています。