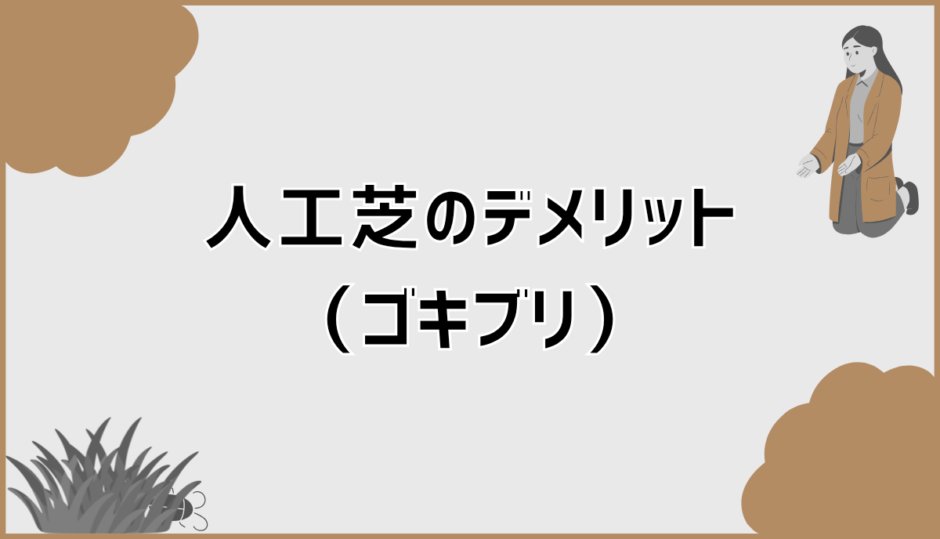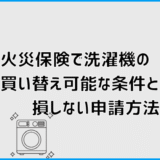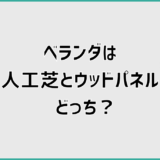この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。ここから家づくりの、ここからです。
ベランダに人工芝を敷いたら、見た目は良くなりそうだけど、ゴキブリが出たらどうしよう。雨のあと、人工芝の下が湿っていたら虫やカビが増えるのでは。そんな不安が頭をよぎって、なかなか決断できずにいる方もいるかもしれませんね。
実際、人工芝にはメリットだけでなくデメリットもあり、設置の仕方やベランダの環境次第では後悔につながるケースがあるのも事実です。
ただ、その不安が人工芝そのものの問題なのか、それとも使い方や管理の前提を知らないことから来ているのかで、選択は大きく変わってきます。
ゴキブリや虫が気になる理由、カビが発生しやすい条件、そしてどんなベランダだと失敗しやすいのかを整理できれば、必要以上に怖がる必要はなくなります。
ここでは、人工芝のデメリットをゴキブリの視点から丁寧にひも解きつつ、後悔しやすいパターンと避けるための考え方をまとめています。
読み終える頃には、あなたのベランダに人工芝が合うのかどうかを、感覚ではなく判断軸で考えられるようになるはずです。一緒に整理しながら、納得できる選択を探していきましょう。
- 人工芝でゴキブリが不安になりやすいベランダの条件が分かる
- 人工芝のデメリットと虫やカビが発生しやすい理由を整理できる
- 後悔しやすい設置パターンと避けるための判断軸を理解できる
- 自分のベランダに人工芝が合うか見極める考え方を持てる
※本記事は、人工芝メーカーの公式情報や公的機関の資料、一般的なレビューや体験談などを参考にしつつ、内容を独自に整理・構成しています。口コミや使用感には個人差があるため、最終的な判断はご自身の環境に合わせて行ってください。
人工芝のデメリットとゴキブリの実態

ベランダに人工芝を敷こうと考えたとき、「ゴキブリが出やすくなるのでは?」と不安に感じる方は少なくありません。見た目は良さそうでも、虫や湿気、後悔の声を聞くと迷ってしまいますよね。
ただ、その不安は人工芝そのものが原因なのか、設置環境や使い方によるものなのかで、見え方が大きく変わります。ここでは、ゴキブリの実態や人工芝のデメリットを整理しつつ、どんなケースで後悔しやすいのかを分かりやすく見ていきます。
人工芝にするとゴキブリが出やすいって本当か
「人工芝を敷くとゴキブリが増える」と聞くと、不安に感じる方は多いかもしれません。ただ、人工芝そのものがゴキブリを引き寄せる餌や発生源になるわけではありません。
問題になりやすいのは、人工芝を敷いたことでベランダの環境が変わり、結果としてゴキブリが好む条件に近づいてしまうケースです。ゴキブリは暗く、暖かく、湿度の高い場所を好む生き物だとされています(出典:国立感染症研究所「ゴキブリ類」 https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/60200_ref.html )。
また、府営住宅のガイドブックでも、ゴキブリは家具や壁の縁など狭いところを好み、夜行性でうす暗いところを好むと説明されています(出典:大阪府都市整備部住宅建築局「府営住宅ガイドブック」)。
人工芝を敷くことで、床面に日光が当たりにくくなり、風通しも弱まると、雨の後や湿度の高い時期に水分が残りやすくなります。さらに、落ち葉や砂、ゴミが人工芝の下に入り込むと、それらが湿気を含み、乾きにくい状態が続くこともあります。

原因が人工芝自体か環境か、迷う場面ですね
一方で、ベランダ本来の排水勾配がきちんと機能していて、水が溜まらずに流れる環境が保たれていれば、人工芝を敷いたからといってゴキブリが増えるとは限りません。
裏面に透水穴のある屋外用人工芝を選び、ゴミを溜め込まない使い方ができていれば、過度に心配する必要はないでしょう。
要するに、「人工芝=ゴキブリ」ではなく、「湿気と汚れが溜まりやすい設置や管理になっていないか」を冷静に確認することが判断のポイントになります。
実際にベランダの人工芝でゴキブリは出るのか
理屈だけではなく、実際に「出た」「出なかった」の差がどうして生まれるのかは、多くの方が気になるポイントだと思います。
口コミや体験談を見ていくと、発生の有無は人工芝そのものの種類よりも、ベランダの環境条件や日常的な管理状況に左右される傾向が強いようです。
ゴキブリが出たとされるケースで目立つのは、人工芝を敷いたまま長期間めくらず、裏側に落ち葉・砂・髪の毛・食べこぼしなどが蓄積していたパターンです。
こうしたゴミは湿気を含みやすく、暗くて狭い空間を作るため、害虫の隠れ場所になりやすいと考えられます。
加えて、ベランダの排水口(ドレン)周辺に汚れが溜まっていたり、プランターの水やりによって常に湿った土が近くにあると、人工芝以外の要因も重なって寄りつきやすくなる場合があります。
一方で、ゴキブリが出ていないケースでは、水が溜まらずに流れる排水環境が保たれていること、定期的に掃除や点検が行われていること、人工芝の裏面が通気・排水しやすい構造になっていることが共通点として挙げられます。
ベランダはもともと排水勾配が設けられている場合が多いため、その勾配を活かした敷き方ができているかどうかも差になりやすいポイントです。
なお、口コミはそれぞれの住環境や生活スタイルに強く左右され、同じ商品でも結果が異なることは珍しくありません。
最終的には、ベランダの向きや日当たり、風通しといった立地条件に加え、飲食の有無や植木鉢の配置といった生活動線が、現実的な発生傾向を左右すると捉えておくと理解しやすいでしょう。
人工芝のデメリットとして知るべきポイント
人工芝は見た目が整いやすく、ベランダに出たときの冷たさを和らげてくれるなど、暮らしを快適にする面があります。
一方で、導入前に理解しておきたいデメリットは複数あり、文章だけで読むよりも整理して把握した方が判断しやすい部分でもあります。ここでは、ベランダで人工芝を使う際に知っておきたい主なデメリットを表にまとめます。
| デメリットの内容 | 起こりやすい理由・背景 | 注意したいポイント |
|---|---|---|
| 湿気がこもりやすい | 床面に日光が届きにくく、 風通しが弱まる | 排水勾配を潰さない敷き方、 雨後の乾き具合を確認 |
| カビ・臭いが 出やすい | 水分が残りやすく 乾燥に時間がかかる | 定期的にめくって 裏側を点検・換気 |
| ゴミや汚れが 溜まりやすい | 繊維に砂・ホコリ・ 落ち葉が絡む | 表面だけでなく 裏側の掃除も前提にする |
| 静電気でホコリ を呼びやすい | 素材や乾燥環境の影響 | 掃除頻度が増える 可能性を想定 |
| 夏場に表面が 熱くなる | 直射日光で温度が上昇 | 色・設置場所・ 使用時間に注意 |
| 経年劣化 が起きる | 紫外線や雨風の影響 | 将来的な交換を前提に考える |

メリットと手間をどう受け止めるか悩みやすいですね
このように見ると、人工芝は「敷けば終わり」の床材ではなく、一定の掃除や点検、将来的な交換まで含めて管理していく前提で選ぶ必要があることが分かります。
湿気対策の目安としては、東京都保健医療局の「健康・快適居住環境の指針」で湿度の目安を40~60%としています(出典:東京都保健医療局「健康・快適居住環境の指針」 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/jukankyo/indoor/kenko/kenkai_bunyatosisin )。
ベランダは室内と条件が異なるものの、湿気を溜めない発想そのものは共通するため、掃除と換気、排水をセットで考えると不安を減らしやすくなります。
導入前に、自分の生活スタイルでこれらの管理が現実的かどうかを想像しておくことが、後悔を防ぐための大切な視点になります。人工芝のデメリットを見ていくと、他の床材と比べてどうなのかも気になってきますよね。
人工芝とウッドパネルを並べて考えることで、ベランダに合う選択肢が整理しやすくなります。こちらの記事を参考にしてみてください。
ベランダの人工芝で後悔する人が多いケース
人工芝で後悔しやすいのは、商品そのものの良し悪しというよりも、「ベランダの環境」と「使い方」が噛み合っていなかったケースが多い点です。
特に、日陰が多く直射日光が当たりにくい、風が抜けず湿気がこもりやすい、排水口がゴミで詰まりやすいといった条件が重なると、人工芝の下に湿気が残りやすくなります。
その結果、乾きにくい状態が続き、カビや虫の不安につながりやすくなるため、設置前に環境を冷静に見極めることが大切です。
湿気がこもりカビや虫が発生しやすい環境
北向きや隣家の壁に囲まれて日が当たりにくいベランダは、もともと雨のあとに乾くまで時間がかかりやすい環境です。カビは高温・多湿を好むとされており(出典:大阪府都市整備部住宅建築局「府営住宅ガイドブック」 https://www.osakafueijutaku.jp/for-residents/pdf/bookmark-of-house-10-511.pdf )、湿気が逃げにくい条件では人工芝との相性が悪くなりがちです。
こうした場所に人工芝を全面敷きすると、床面に残った水分が蒸発しにくくなり、湿気がこもりやすくなります。その結果、人工芝の裏側や床との隙間でカビが発生したり、虫が隠れやすい状態になったりすることがあります。
さらに、排水口の近くに落ち葉や砂、ゴミが集まりやすい構造だと、湿ったゴミが溜まりやすくなり、害虫の温床になりやすい点にも注意が必要です。
敷きっぱなしで掃除や点検ができていない場合
人工芝は「一度敷いたら終わり」と考えてしまいやすい点が、後悔につながる落とし穴です。表面を軽く掃くだけでは、人工芝の裏側に入り込んだ砂や落ち葉、細かなゴミまでは取り除けません。
さらに、ジョイント部分や継ぎ目にわずかな隙間があると、そこにゴミが溜まりやすくなり、雑草が生えたり虫が潜みやすくなったりします。こうした状態を放置すると、掃除や対処の手間が徐々に増えていきます。
月に1回でも部分的に人工芝をめくり、床面の汚れや湿気を確認できない生活スタイルの場合、気づいたときには管理が負担に感じられることがあります。
以上を踏まえると、湿気が逃げにくいベランダで、点検しない前提の設置は、後悔につながりやすい組み合わせです。
人工芝のデメリットやゴキブリを避ける判断

人工芝のデメリットやゴキブリの不安を知ったうえで、「それでも使うべきか」「別の選択肢にするべきか」と迷う方も多いと思います。
大切なのは、人工芝が良いか悪いかを決めつけることではなく、自分のベランダ環境や暮らし方に合っているかを冷静に見極めることです。
ここでは、後悔を減らすための具体的な対策や床材選びの考え方、人工芝が合わないと感じた場合の次の選択肢まで、判断の整理に役立つ視点をまとめていきます。
それでも人工芝で後悔しないための対策
人工芝を選ぶなら、最初から「湿気を溜めない設計」と「日常的に管理できるルール」をセットで考えておくことが現実的です。
特別に難しい対策をすべて行う必要はありませんが、排水や掃除といった基本を外してしまうと、ゴキブリや虫、カビへの不安が残りやすくなります。事前に無理なく続けられる管理方法を想定しておくことが、後悔を防ぐポイントになります。
ゴキブリや虫やカビを防ぐために必要な対策
対策の基本は、ベランダに水分を溜めない排水性の確保です。人工芝は必ず裏面に水抜き穴(透水穴)がある屋外用を選び、もともと備わっているベランダの排水勾配を潰さないように敷くことが大切です。
あわせて、排水口の周囲に落ち葉や砂、ゴミが溜まらないよう定期的に掃除し、雨の後には水たまりができていないかを目視で確認すると安心感が高まります。
また、プランターを置く場合は受け皿に水を溜めっぱなしにしないことや、土が人工芝の上にこぼれないようにするなど、日常的な小さな工夫が湿気や虫対策として効果を発揮します。
後悔しにくい人工芝の選び方と設置の考え方
人工芝は、吸水性の高い素材を避け、屋外使用を前提とした透水穴付きの商品を選ぶことが基本になります。水分が抜けにくい素材を選ぶと、湿気がこもりやすくなり、カビや虫の不安につながりやすいため注意が必要です。
また、全面を固定して敷くよりも、一部をめくって床面を点検できる設置にしておくと、掃除や確認の手間を抑えやすくなります。継ぎ目はできるだけ少なくし、隙間を作らない施工を意識することで、ゴミや虫の入り込みを防ぎやすくなります。
防虫剤などの薬剤を使用する場合は、必ず使用場所や対象を確認し、ベランダ利用が問題ないか注意事項を守ることが前提です。
不安がある場合は無理に自己判断せず、施工業者や住環境の専門家、マンションであれば管理会社に相談したうえで判断することが安心につながります。
ベランダの床材選びで見落としがちな点
床材はどうしても見た目や雰囲気で選びがちですが、ベランダではまず「排水」「清掃」「重さ」「近隣への影響」といった実用面を確認しておく方が失敗しにくいです。
特に見落とされやすいのが排水口までの水の流れで、床材を敷くことで水が思わぬ方向へ回り込み、排水が遅くなることがあります。
雨の日に水たまりができる状態が続くと、汚れやカビの原因になるだけでなく、滑りやすくなり安全面の不安にもつながります。
次に意識したいのが掃除のしやすさです。人工芝はゴミや砂が繊維に絡みやすく、表面だけ掃除しても奥に汚れが残ることがあります。
一方、デッキパネルやタイル系の床材は、隙間に砂やホコリが落ちやすく、放置すると黒ずみや詰まりの原因になります。
どの床材にも一長一短があるため、自分がどのくらいの頻度で掃除できるのか、使う掃除道具が現実的かを事前に想像しておくことが大切です。
さらに、床材の重さや固定方法も重要な視点です。軽すぎると強風で飛ばされる恐れがあり、重すぎると排水やメンテナンスの際に持ち上げる負担が大きくなります。
マンションの場合は、管理規約で設置物の重量や固定方法が制限されているケースもあるため、事前確認は欠かせません。
ベランダの床材は「見た目」だけでなく、「水がきちんと流れるか」「無理なく掃除できるか」「安全に固定できるか」という視点で選ぶことで、使い始めてからの後悔を減らしやすくなります。
人工芝が合わないと感じた人の次の考え方
人工芝を試してみて「思ったより手入れが大変だった」「湿気がこもって不安を感じる」といった違和感を覚える方も少なくありません。
その場合、無理に人工芝を使い続ける必要はなく、いったん立ち止まって目的を整理し、別の方法に置き換える方が結果的に満足度が高くなることがあります。そもそも人工芝を敷いた理由は人によって異なります。
「ベランダの見た目を整えたい」「裸足で出られる空間にしたい」「子どもが座れる柔らかさが欲しい」など、目的を細かく分解して考えてみることが大切です。
たとえば見た目重視であれば、全面敷きにこだわらず、部分的に人工芝を使って点検しやすくする方法や、屋外用のデッキパネル・タイルマットに切り替える選択肢も現実的です。
また、クッション性を求めている場合は、屋外用ラグやクッションマットを必要な範囲だけ敷くことで、排水や掃除の負担を抑えつつ目的を満たせることがあります。
全面を覆わないだけでも、湿気がこもりにくくなり、管理の手間が大きく変わるケースは多いです。
さらに「虫が不安」という理由で人工芝が合わないと感じた場合、原因は床材そのものではなく、ベランダ周りの環境にあることも少なくありません。
段ボールや使っていない植木鉢、落ち葉が溜まった状態を整理するだけでも、隠れ場所が減り、不安が軽減される場合があります。
合わないと感じた時は、床材の良し悪しで判断するのではなく、「自分が何を求めていて、その目的と管理のしやすさが合っているか」という視点で見直すことが、次の選択を前向きにするためのヒントになります。
人工芝が少し合わないかもと感じたとき、別の床材を知っておくと選択肢が広がります。ウッドパネルとの違いを知ることで、後悔しにくい考え方が見えてきます。こちらの記事を参考にしてみてください。
ベランダは人工芝で後悔しないか迷った時の判断
迷っている段階では、メリット・デメリットを並べるだけだと決めきれません。
判断を楽にするには、ベランダの条件をチェックリストのように整理して、人工芝が相性の良い環境かを先に見ます。以下は目安としての比較です。自宅のベランダに当てはめてみてください。
| 観点 | 相性が良い傾向 | 注意が必要な傾向 |
|---|---|---|
| 日当たり・ 風通し | 日が当たり乾きやすい | 日陰が多く乾きにくい |
| 排水 | 水が溜まらず流れる | 排水口が詰まりやすい |
| 使い方 | こまめに掃除できる | 敷きっぱなしになりがち |
| 周辺要因 | プランター少なめ | 土・落ち葉が多い |

今すぐ決めなくても良いと感じる方もいそうですね
この表で右側が多い場合は、人工芝を選ぶなら部分敷きや、めくれる設置を前提にした方が安全です。逆に左側が多ければ、人工芝でも後悔しにくい可能性があります。
なお、マンションは規約や防災上の制限があることもあるため、最終的には管理規約や管理会社の案内を確認し、必要なら専門家へ相談してください。
まとめ:人工芝のデメリットのゴキブリ
どうでしたか?ここまで読んでいただき、ありがとうございます。人工芝のデメリットやゴキブリへの不安は、実は人工芝そのものより、ベランダの環境や使い方によって左右される場面が多いと感じた方もいるかもしれませんね。
排水や湿気、掃除のしやすさを考えずに敷いてしまうと、後悔につながりやすい一方で、条件が合えば必要以上に怖がる必要はありません。
- 人工芝は湿気や汚れが溜まると虫やカビの不安が出やすい
- ゴキブリが気になる原因は設置環境や管理不足が重なるケースが多い
- 敷きっぱなしにせず点検や掃除を前提に考えることが大切
- ベランダの条件次第では部分敷きや別の床材も選択肢になる
家づくりや住まいの工夫は、正解を探すというより、自分の暮らしに合うかを見極めることが大切です。
最後に紹介をさせてください。
人工芝にするか迷っている段階では、他の床材と比較した視点を持つことが判断の助けになります。人工芝とウッドパネルを冷静に比べることで、あなたのベランダに合う選択がしやすくなります。こちらの記事を参考にしてみてください。
人工芝のデメリットやゴキブリの不安も含めて整理したうえで、あなたにとって納得できる選択につながればうれしいです。