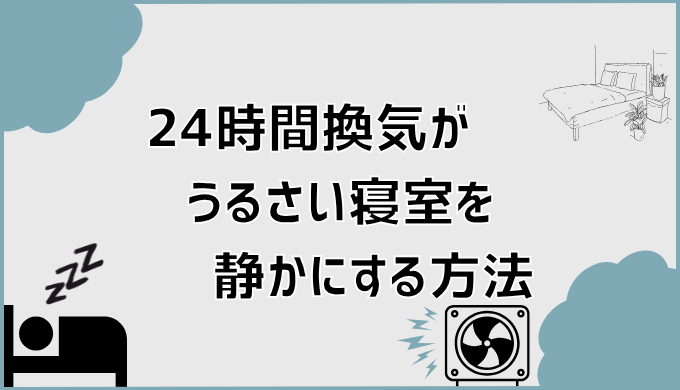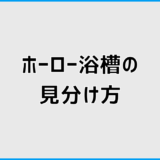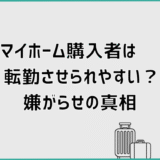この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
夜、寝室に入ったときに「ゴーッ…」と低い音が響いてきて、なんだか眠れない。そんな経験、ありませんか?それ、もしかしたら24時間換気の音かもしれません。
空気の入れ替えが自動でできて便利なはずの24時間換気。でも、いざ住み始めてみると「うるさい…」「寝室だけ音が気になる…」とストレスに感じている方は意外と多いんです。とくに家を建てたばかりの方や、これからマイホームを考えている方にとっては、「こういう音が出るものなの?」「止めてもいいの?」と、不安になってしまうことも。
ここでは、そんな疑問に寄り添いながら、寝室で24時間換気がうるさくなる理由と、その音を静かにするための具体策を詳しくご紹介します。ポイントは、自分の家が「第一種換気」なのか「第三種換気」なのかを見極めること。実は、この方式の違いによって、音の出方も対策の方向性もまったく変わってくるんです。
ここでは、風量設定・ダクト構造・フィルターの汚れなどの基本チェックはもちろん、
- ユニットの設置場所による振動の伝わり方
- 防音フードや吸音材の工夫
- “夜だけ止める”という選択肢のリスクと対応法
など、実際に多くの家庭で試されている現実的な解決策を、住まいのプロの視点で解説しています。
「寝室の空気はきれいに保ちたいけど、うるさいのは嫌」そんなわがまま、ちゃんと両立できます。あなたの家も、「静かな24時間換気」に変えて、ぐっすり眠れる寝室を手に入れませんか?
- 寝室で24時間換気がうるさく感じる主な5つの原因
- 第一種・第三種換気それぞれの静音対策が違う!
- 就寝時でもできる!いますぐ実践したい静音化の工夫
- 「夜だけ止めたい」時のリスクと代替案を提示

- 寝室で換気音が気になる原因はどこにある?
- あなたの家の換気方式はどっち?確認と違い
- 第一種換気がうるさいときの対処法と選び方
- 第三種換気で「風の音」がうるさい場合の工夫
- フィルターや設定ミスが音の原因かもしれない
「夜、寝室に入ると…ゴーッという低い音が気になる」そんな経験、ありませんか?24時間換気は家の空気を清潔に保つために必要不可欠。でも、その換気音がストレスになってしまっては本末転倒です。
ここでは、寝室で換気音がうるさく感じる理由を構造的に紐解きながら、第一種・第三種換気の違いに応じた静音対策を、より実践的に深掘りしていきます。
寝室で換気音が特に気になる理由は、「静かすぎる空間」と「遮音性の高さ」にあります。わずかな構造的・機械的な音でも、耳に残ってしまうのです。ここでは、主な原因を5つに分類して具体的に解説します。
換気システムの風速が強いと、それだけで「ゴーッ」「ブーン」といった風切り音やファンの唸りが発生します。特に風速が4m/sを超えると、空気音が顕著になります。また、経年劣化によりファンの軸に歪みが生じたり、羽根のバランスが崩れると、「ジジジ」「カタカタ」といった異音の原因に。
給気口がベッドの近くや耳の高さにあると、空気が身体に当たって冷たく感じるだけでなく、風音が直に伝わります。床近くにあると特に体感的な不快感が増し、1,600〜1,800mm程度の高さが理想的な設置位置です。また、給気口と排気口が近すぎると、局所的な高風速=ショートサーキットが発生し、騒音が増す原因になります。
ダクトが長かったり、曲がりが多い・径の変化が急だったりすると、内部の空気流が乱れて騒音が発生しやすくなります。また、ダクトやユニットの接続部が緩んでいたり、建物の構造体と接していると、振動が共鳴して「ゴーン」「カラカラ」といった音が室内に響くことも。
給気・排気口のフィルターが目詰まりしていると、空気がうまく通らずに風切り音が強まったり、ファンに余計な負荷がかかってモーターが異音を出す原因になります。年1回以上の清掃・点検が理想です。
夜間の寝室は遮音性が高いため、他の部屋では気にならないレベルの音でも際立って聞こえます。換気ユニットが壁や天井に直付けされている場合、振動が構造体を伝って大きく響くことがあり、防振ゴムや浮かせた設置が重要になります。
換気音の対策を考えるには、まず自宅の換気方式を知ることが第一歩。見分け方と、それぞれの特徴・音の出やすいポイントを比較して紹介します。
- 【特徴】
給気・排気ともにファンで管理され、熱交換器付きユニットが主流。高気密住宅に多く採用されます。 - 【音の出やすい場所】
ファン、熱交換器ユニット、ダクトの曲がり部分や共鳴部 - 【対策例】
運転モードを「弱」に設定(それでも0.5回/h以上の換気量を確保できる設計が一般的)
フィルター清掃や熱交換素子の定期洗浄
消音ダクトやサイレンサーの設置
ユニットの防振架台設置や吊り施工
- 【特徴】
トイレ・浴室などの排気ファンで室内の空気を外に出し、給気は壁のガラリなどから自然に取り入れる方式。 - 【音の出やすい場所】
外部風の強さによって生じる給気口の風切り音や逆流音 - 【対策例】
防音フード・スクウェアベントキャップへの交換
レジスター内部に吸音材を設置
サイレンサーの追加(ダクト内に挿入型の静音パーツ)
給気口の位置を寝室の枕元から離す、足元側や風下面への配置見直し
第一種換気は「給気も排気も機械で制御できる」高性能な換気方式。温度管理や空気の質が安定するメリットがある一方で、24時間稼働することで発生する「機械音」や「風切り音」、「振動」などが寝室などの静かな空間では気になりやすいというデメリットも。
第一種換気で音が気になるときの具体的な対処法と、選定時に注目すべき静音ポイントを、設置構造や運用の工夫とあわせて掘り下げます。
- 運転モードを「弱」に切り替える
多くの住宅では、強運転にしなくても必要な換気量(0.5回/h)は十分確保できます。特に就寝時は「弱」モードで運転することで、体感音がぐっと下がります。 - フィルターと熱交換素子の掃除
フィルターが詰まると、風の流れが悪くなりファンが高回転になって音が大きくなります。半年に1回の清掃を習慣化しましょう。熱交換素子の内部にホコリが蓄積していると、風切り音が強くなることも。 - ダクトに吸音材や消音部材を追加
曲がりの多いダクトや長尺ダクトは風の乱れが起きやすく、音が増幅しがちです。断熱材付きダクトやグラスウール巻きの消音型に交換することで、室内への音の伝わり方が変わります。 - ユニットの設置位置を見直す
天井裏やクローゼットの上などに設置されているユニットが、寝室の真上だった場合は要注意。機械音が天井から直に伝わってしまうことがあります。配置変更が難しい場合は、吸音材を天井裏に敷き詰めたり、吊り施工で構造体から浮かせる工夫が有効です。 - ユニットの防振施工
吊りバンドに防振ゴムを噛ませる、床置きなら防振パッドを敷くなど、振動源と建物構造の間に“クッション”を挟むだけで共鳴音が大幅に軽減されます。
- 騒音値(dB)を確認
メーカーの仕様書には「定格運転時の音圧レベル(dB)」が記載されています。寝室付近で使うなら20dB以下が理想。夜間の無音空間ではこの数値の違いがはっきり体感に表れます。 - モーターの種類(DCモーターが優秀)
回転の滑らかさや低騒音性能を考えると、ACモーターよりもDCモーターの方が有利。変速制御にも強く、効率よく静かに回ります。 - サイレンサーや静音筐体の有無
高性能な機種は、ファンの前後に専用のサイレンサーを内蔵していたり、ユニット自体が静音構造で設計されています。 - 設置場所の自由度
屋外設置型や配管延長が可能なタイプなら、寝室から物理的に離して配置できるため、構造的に音の影響を受けにくくなります。 - メンテナンス性(掃除のしやすさ)
工具不要で分解できる構造のものは、清掃の頻度が上がりやすく、長期的にも静音性を維持しやすくなります。
第三種換気は「排気はファンで、給気は自然に任せる」シンプルな仕組み。だからこそ、外からの風が強く吹き込んだときや、給気口の位置が悪いと、耳障りな風切り音・侵入音が発生しやすいという弱点があります。
ここではその風の音を抑えるための構造的な工夫や、後からでも取り入れやすい部材による対策を紹介します。
- 給気口の位置を見直す
給気口が風の直撃を受ける場所(北面・高台など)や、寝室の枕元に設置されていると風切り音がダイレクトに届きます。風下になる南面・低層面への移設や、足元付近に位置変更するだけで劇的に改善するケースもあります。 - 防音フードや深形フードの導入
「深形ベントキャップ」「スクウェアベントキャップ」は、外部風の乱流を抑え、給気口内部への風の侵入音を物理的にカットしてくれる効果があります。 - 吸気口に吸音材を仕込む
吸気グリルの内部に、通気性を損なわないレンコン状の吸音材を挿入すると、風音の直進性を緩和できます。簡単に取り付け可能なDIY商品も多数出ています。 - ダクト内にサイレンサーを設置
屋外からの給気ラインにサイレンサーをかませると、室内への音の伝達が大きく減衰。静音型の金属ダクトと組み合わせれば、効果はより高まります。 - 建物形状と風向の影響を考慮した設計
高台・角地・ビル風が強い場所では、建物の陰側に吸気口を設ける、あるいは地面に近い位置に変更するなど、風の当たり方を考えた設計がポイントです。
「うるさいから高級な機種に交換したい…」と思う前に、まずは簡単にチェックできる“初歩的な見落とし”から確認を。
実は、こうした小さなメンテナンス不足や設定ミスが、不要な音の原因になっているケースも多いのです。
- 風量設定が強すぎる
初期設定のまま最大風量になっていませんか?夜間は「中」または「弱」運転に切り替えるだけで体感騒音が半減することも。 - フィルターが目詰まりしている
吸気・排気ともにフィルターが汚れていると、空気がスムーズに流れず、ファンが異常回転して「ブーン」「ジジジ」といった音が出やすくなります。 - 吸気・排気口が塞がっている
室内側では家具が接触していたり、屋外では落ち葉や虫ネットの詰まりが音を増幅させている場合も。 - モーターや羽根の劣化
使用年数が5〜10年を超えると、経年劣化によりファン軸のブレや潤滑油の劣化で異音が出やすくなります。 - 風量調整ダイヤルのズレ
特に第三種換気でよくあるのが、給気口の風量調整ダイヤルが中途半端な位置にあることで、風が乱れて音が出るパターン。
- 半年に1回のフィルター掃除をルーチン化
- 年1回の風量設定と騒音チェックを推奨
- 音が気になる「時間帯・部屋」を記録しておく(業者相談がスムーズになります)

- 24時間換気を「夜だけ止めたい」はアリ?
- よくある質問Q&A|換気の音と寝室の悩み
- まとめ:24時間換気がうるさい寝室を静かにする方法
寝室で24時間換気の音が気になると、眠れなかったりストレスが溜まったり…。それでも止めてしまっていいのか、どこまで工夫すればいいのか迷う方も多いはずです。
ここでは「夜だけ止めていい?」「赤ちゃんがいる場合は?」「音の正体は?」といったよくある疑問を解決しながら、寝室でも快適に24時間換気を使うための具体策を紹介します。
結論から言うと、「止めないのが理想」ですが、一時的な停止はやむを得ない場合もあるというのが現実的な考え方です。
24時間換気は、家の中の湿気・CO₂・化学物質(ホルムアルデヒドなど)を排出するための設備。とくに高気密住宅では、空気が逃げにくいため、換気を止めると以下のようなリスクがあります。
- CO₂濃度の上昇により眠りが浅くなったり、頭痛を感じることがある
- 冬場の室内外温度差によって、壁や窓で結露が発生しやすくなる
- 建材や家具から放散される化学物質が室内にこもりやすくなる
とくに、築浅の住宅や気密性が高い家では「少しの無換気」でも空気の質が一気に落ちやすくなります。
「音が気になって寝られない」という深刻なケースでは、短時間だけ止める選択も視野に入れながら、以下のような代替策でバランスを取ることが大切です。
- 起床後に必ず換気を再開することを習慣化する
- 日中の風量をやや強めに設定して換気総量を確保する
- 寝室以外の部屋で強制換気を継続する(特に脱衣所やリビングなど)
止めるのではなく、“静かに使い続ける”工夫もあります。以下は、就寝時の静音対策として実際に効果のある方法です。
- 就寝時だけ「弱」運転に切り替える(機種によっては風量設定可能)
- 風速を抑えるよう吸排気口の風量バランスを調整する
- 音が響きやすいダクトや機械の周囲に吸音材を追加する
- 音源が寝室に近い場合、ユニットを寝室から離す/吊り施工に変える
たとえば、換気本体のモーター音が直接天井裏から響いている場合、振動伝播を抑えるために、吊りバンドに防振ゴムを噛ませたり、防音シートで覆ったりといった施工も有効です。
- Q. 新築したばかりなのに換気音が気になる…これって初期不良?
- 多くの場合、機器そのものに問題があるわけではなく、風量設定が強すぎる・ダクト長や曲がりが多い・本体の設置位置が悪いといった施工上の要因が絡んでいます。メーカーや施工会社による再調整で改善されるケースもあるので、まずは相談を。
- 赤ちゃんの寝室に換気設備があるけど、止めた方がいい?
- 止めないで使い続けるのが基本です。赤ちゃんは体温調節や免疫機能が未熟で、空気環境の影響を受けやすいため、きれいな空気を保つことは重要です。音が気になる場合は、風が赤ちゃんに直接当たらないようグリルの向きを調整、運転モードを夜間のみ弱運転に切り替え、ベビーベッドの位置を少しだけずらすといった工夫を。
- 音の大きさが時間帯によって変わるのはなぜ?
- 昼と夜とで音の聞こえ方が変わるのは、周囲の「環境音」が関係しています。夜は住宅地全体が静かになるため、わずかな機械音でも耳につきやすくなるのです。また、外気温や風速の変化により、給気口から入る風速・風切り音が日中と夜間で変わることも。
- 音が気になってストレスを感じる…。生活改善の工夫は?
- 音を遮る吸音パネルや厚手のカーテンを使う、サーキュレーターやホワイトノイズ機器で「音の対比」を緩和する、音源のある部屋の扉をしっかり閉める、ストレス軽減のための就寝前ルーティン(読書、アロマなど)を取り入れるような方法で音に対するストレスを緩和できます。
- 換気音の相談はどこにすればいい?修理とまではいかないときは?
- 「気になるけど壊れてはいない」状態でも、相談先はあります。
・住宅を建てた施工会社(工務店・HMなど):設計意図や施工方法に詳しい
・換気機器メーカー:静音パーツや風量設定の具体的な方法を案内可能
・住宅診断士や建築士:家全体のバランスを見ながらの改善提案が可能
「寝室の24時間換気がうるさくて眠れない…」そんな悩みを持つ方は、実は少なくありません。換気は家の空気環境を保つために欠かせないものですが、静かな寝室ではその音がストレスになりやすいのも事実です。
ここでは、構造・機械・設置場所・使い方の4つの視点から、音の原因と対策を詳しく解説してきました。大切なのは「止める」のではなく、「静かに使い続ける」工夫をすることです。
改めて、音の原因と対策を振り返ると……
- 風量設定の見直し
夜間は「弱」に切り替えるだけでも効果的 - フィルター清掃
半年に1回は清掃して風切り音を予防 - 設置場所や機種の工夫
寝室から離したり、静音型機種を選ぶ - サイレンサーや吸音材の導入
ダクト内や給気口で音を抑える - 音の感じ方への対策
ホワイトノイズや厚手のカーテンも有効
「静かな寝室を手に入れたい」「でも健康的な空気環境も守りたい」。その両立は、決して難しいことではありません。
まずは、今の環境でできる小さな工夫から始めてみてください。音の感じ方が変わるだけで、睡眠の質や生活の快適さが大きく変わるかもしれません。
無理なく続けられる方法で、24時間換気と心地よい睡眠を両立させましょう。